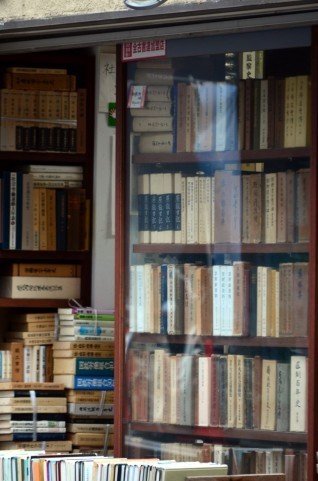
- 運営しているクリエイター
2023年1月の記事一覧
「一人前の分前」があるから「取引、交易、交換」が成り立つ
「国富論」の中でアダム・スミスは
「分業と言うものは、・・・(中略)・・・人間の本性上のある性向、すなわち、ある物を他の物と取引し、交易し、交換しようとする性向」と述べています。
そして、
「この性向はすべての人間に共通なもので、他のどんな動物にも見出されないものである」
と言っています。
例えば、
「同じ兎を追う二匹のグレイハウンド犬は一種の協同作業をしているようなかたちを取ることがある
雑草やハーブによる猛寒波対策の可能性
10年に一度の猛寒波。
結局、最低気温は-7.1℃にまで低下したようです。
アメダスのグラフは、午前6:10、6:20ともに-6.5℃になっているとしています。この間に-7.1℃になったようです。
畑の野菜たちはけっこう元気でした。
ニンジンは動画のように葉が一部霜枯れしたものの、けっこう青々していました。
やはり、草が地面に生えていることが放射冷却現象を防ぎ、保温効果を発揮しているようです。
萬葉集冒頭歌、「掘り具」の意味はこれだったのか?
見沼菜園クラブ・たんぽぽ農園近くの土手で自生しているカラシ菜を採っている人に会いました。
漬物にするのだそうです。
株ごと抜いて、カッターで根を切り、葉の部分だけにしています。
萬葉集冒頭歌「御籠よ、御籠もちよ、御串よ、御串もちよ、この岡に菜摘ます子(籠と掘り具をもって、この岡に菜を摘みに来た娘)」
になぜ御串(掘り具)が出てくるのか、謎でした。
今回、土手でのカラシ菜収穫をみて、その疑
民衆が自ら「百姓」と名乗りだした時代
「日本中世の歴史1・中世社会の成り立ち(木村茂光)」に12世紀頃から荘園の住人と言う呼称に代わり「百姓」と言う呼称が多くなってくることが述べられています。
民衆が要求をする際、「住民等解」、「百姓等解」、「百姓等申状」等の文書を出したようです。
その文書の表題が時代によって変化するとのこと。
同書は、「平安時代後期が『住民等解』の時代であることに対比して言うならば、鎌倉時代・南北朝時代は『百姓等















