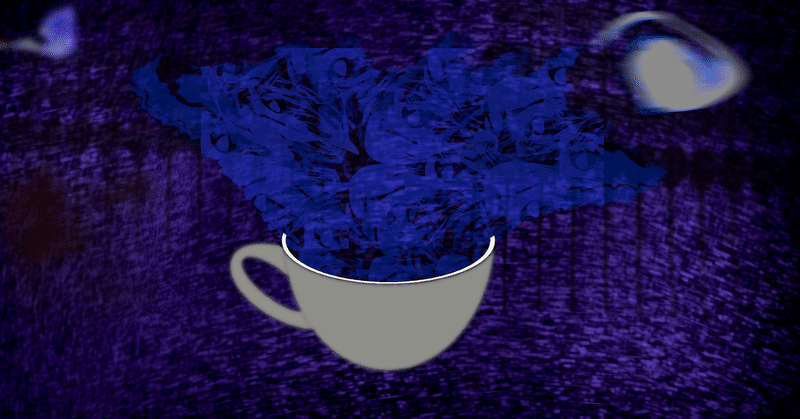
イマジン(コーヒー・タイム)
一口含むと危険な熱さを感じる。コーヒーカップを遠ざけて、背もたれにすがる。コーヒーを飲むということは、一息になせるものではない。一つの仕草はゆっくりとしていて、とても小さい。近づいたと思えば離れなければならない。否応なしに間が生まれ、そこにあなたが現れる。
「いいねを待っておるのか?」
「いや別に」
「それで一喜一憂か。落ち着かない奴よの」
「普通じゃないかな」
「普通が聞いてあきれるわ」
「はあ?」
「近頃の者は何でも普通で片づけたがるが」
声がだんだん小さくなってあなたは消えてしまう。
私はコーヒーカップに手を伸ばし。口元へと持って行く。一口含む間だけカップに触れている。やっぱり熱い。コーヒーカップをゆっくりと遠ざけて、テーブルの上に置く。苦みが口の中に広がっていく。胸の真ん中で手を合わせて、液体が浸透していくのを待つ。待っている間に、あなたは現れる。
「バスを待っておるのか?」
「いや別に」
「ではコーヒーが冷めるのを待っているのだろう」
「まあそうかもしれないね」
「自信がないのか」
「そうだね」
「自信がなければ不安だろう」
「まあ時にはね」
「皆そういうものだ」
「そうかな」
「不安も必要だろう」
「どうして?」
「ミルクは不安の上に浮かぶのだから」
いい加減なことを言って、あなたはテーブルの下に沈んでいく。次に現れるのはあなたか、あなたではないあなたか。はっきりと顔を見せないあなたは境界線を持たないが、常に私の上に立っているようでもある。
熱いコーヒーは恐る恐る口をつけなければならない。危険を冒して受け取るご褒美、それは生きた贈り物と言えるだろう。この一口に感謝の気持ちを捧げたい。一息に飲み込むことはできない。けれども、それはなぜかうれしくもある。苦くて飲み込み難い時が、空白のテーブルを作り出す。コーヒーカップを遠ざけた刹那、あなたが顔を出す。
「おにぎりのことを思ってたの?」
「いや別に」
「おにぎりが最強だと?」
「まあ、合理的ではあるね」
「おにぎりはお弁当とは違う」
「うん」
「箱を必要としないのよ」
「確かにそうだ」
「だから直接手に渡すことができるわ」
「ああ、やっぱりすごいね」
「おにぎりは手に始まり手に続くのよ」
「おにぎりは強いね」
「それも片手で足りるの」
「うん」
「片手におにぎり、もう一方にあなたは何を?」
「そうだな。パンかな」
「あなた変ね。確かにここはパン屋さんね」
「そう。ずっとパンの香りがしてるよ」
「だけど形が一定しないわ」
「パンには色々あるからね」
「だからあなたはペンを取りなさい」
「やっぱりそうか」
「同じことばかり書くのが嫌?」
「まあそうかもしれないな」
「同じと思うからいけないのよ」
「思いたくはないんだけどね」
「どうせ同じには書けないんだから」
「そうだろうか」
「コーヒーカップが回るようには書けないのよ」
「わからないな」
「みんなただ生きているだけなんだから」
「よくわからないな」
「次の瞬間あなたはいないんだから」
「えっ?」
そう言って消えていくのは、あなたの方だろう。答えを持たず消えていけるのは、気楽なものだ。苦みが抜けていく頃、次の一口を求めて指がコーヒーカップに近づいていく。慎重に取っ手に指をかけて持ち上げる。器がすれる微かな音がする。もう最初の頃のように熱くはない。けれども、まだ底に近づいてはいない。一口の小ささが一定の時間を約束してくれる。胸の真ん中に手を置いて、浸透していく時を感じる。ああ、今ゆっくりと広がっていく。
「占ってやろうか」
「いいえ結構」
「嫌でも占って進ぜよう」
「人に頼りたくはない」
「涙はどこから出ると?」
「うーん、苦さからかな」
「涙はあくびから、涙は玉ねぎから、涙はかなしみから、涙は笑いから、涙はあとからあとからあふれ出てくる」
「まあそうかもね」
「ならば占ってやろう」
「いいえ結構」
「ビルの間から無理難題が湧いて出るであろう」
「はあ」
「お題の隙間から新たな敵が出現するであろう」
「お題?」
「それは味方にもなり得る敵じゃ」
「複雑ですね」
「年の終わりに12月がくるであろう」
「まあ普通はね」
「普通のワニの尾にくっついてクリスマスがくる」
「トナカイじゃないかな」
「のんべんだらりとした生活のあとに黒猫が訪れるが、お前は幸運をつかめずに敵に囲まれてしまう」
「敵も味方になるのでしょう」
「恐れるがよい、安心するがよい」
「どちらかにしてほしいね」
「お前は望むほどに空っぽにはなれぬ。悲しいほどに満たされる」
「はあ。そういうものですか」
「それを知っておけ。知は不安に打ち勝つことができる」
あなたの言うことは筋道が通っていない。星から涙、夏を飛ばしてクリスマス、トナカイの角をつかんで投げかける。不親切な謎々に似ている。けれども、正解だらけのクイズよりは私の心を和らげてくれるようだ。終着が約束されていないほど、考えることができる。
手を合わせた胸の真ん中を、コーヒーが落ちて行く。私はゆっくりとあたたかい人に変わって行く。コーヒーは時の使いだ。私はコーヒーを止められない。私はいつでも時間と共にある。
もうすぐ底を見つけるだろう。
「お正月を待っているのか」
「いや別に」
「では私を?」
「いえいえ」
「モチーフを持ってくるのを待っているのか」
「何かあるの?」
「何かを書き出すのが恐れているな」
「まあ躊躇いはするけど」
「何を」
「ちょっとしたことだから」
「書かなくてもいいと?」
「そうかもしれない」
「そう言って言葉を呑む君は昔からそうだ」
「わかるの?」
「話してみなければわからないだろう。何が返ってくるか、どう膨らむか」
「だから?」
「書くということも同じだ。自分の中の他人に任せてみることもできる」
「そんなんでいいのかな」
空っぽになりたいのは私かもしれない。あなたは完全には放置しない。コーヒーと私が交わらぬ隙をうかがって私の前に現れ、関心を引こうとする。気づけば多くの時間、あなたと話している。人生は想像の中にあるようだ。あなたの声に含まれるヒントは小さい。小さくて簡単に見過ごしてしまう。その切れ端が生きる力に変わることもあるのだけれど。
「完全なる者はすべてを見通して書くだろう。少なくとも、それは君ではないのだ」
「そうでしょうとも」
「書いて見つかる不在もあれば、書く内に現れるものもある」
「あるいはね」
「自分の中に何がどれほど眠っていると思う?」
「わからない」
「だから書いてみるのだよ」
「何か頼りないな。心細いやり方みたい」
「物語を必要とするのは作者だけじゃない」
「作者しかいないと思える時もあるけどね」
「読者の存在を信じられないと?」
「見失うことも多いから」
「完璧であろうとすることは無意味だ」
「どうせ無理だしね」
「解釈もまた1つの創造ではないのか?」
「ああ。きっとそうだろう」
「ならば読者も作者なのでは?」
突然、すべてが空っぽに見え、自分がどうしようもなくちっぽけな存在に思われる時がある。その時は夕べの夢が、ハリウッド映画より劣って見える。虚無と満ちあふれるものは背中合わせに存在するから、ある瞬間にはターンして、大きな花火が打ち上がる。空っぽであることは、まだ終わりではない。
「人生の楽しみは一杯のコーヒーであるべきだ」
「それは欲張るなという意味?」
「一杯あればいい。閃きは熟考に勝るということさ」
「ふふっ」
それはいい。
私は最後の一口を飲み干して、深く息を吐き出した。
もうあなたは現れない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
