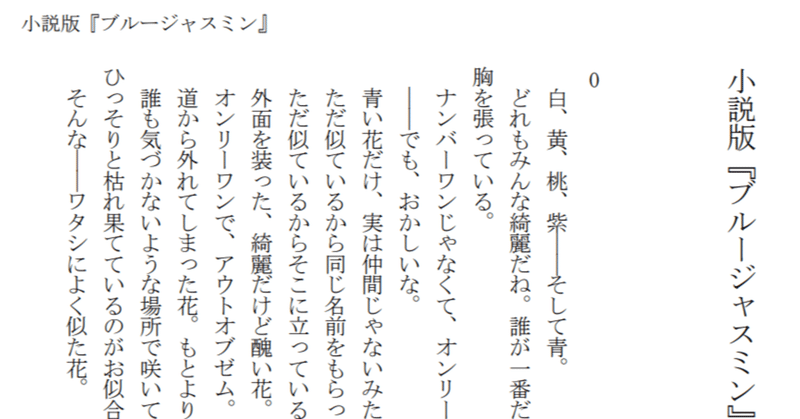
【短編小説】小説版『ブルージャスミン』【+feat.可不】
端書
※本作品は以下の楽曲をもとに、原作者ギンクル氏監修の上で執筆された公式二次創作小説です。
楽曲と小説、どちらを先にご覧になってもお楽しみいただけます。
小説版『ブルージャスミン』
原作:ギンクル
著:レファル
縦書きレイアウトはこちらから。
0
白、黄、桃、紫──そして青。
どれもみんな綺麗だね。
誰が一番だなんて争わず、しゃんと胸を張っている。
ナンバーワンじゃなくて、オンリーワン。
──でも、おかしいな。
青い花だけ、実は仲間じゃないみたい。
ただ似ているから同じ名前をもらって。
ただ似ているからそこに立っている。
外面を装った、綺麗だけど醜い花。
オンリーワンで、アウトオブゼム。
道から外れてしまった花。
もとより「みんな」ではない花。
誰も気づかないような場所で咲いているのなら、そのままひっそりと枯れ果てているのがお似合いだ。
そんな──ワタシによく似た花。
1
この世界は醜く歪んでいる。
「──先生、鶴崎先生!」
「あ、はい!」
ワタシは慌てて作成途中のテスト問題から視線を外し、声の主へと意識を向ける。
「全く。仕事熱心なのはいいですけど、呼ばれたら一度で返事をしてください。それくらい生徒だって当たり前にできますよ」
「は、はい……すみません」
半ばうなだれるように頭を下げる。
この嫌味たらしい女はこの学校の教頭。
つまりワタシの上司にあたり、嫌いな人間のうちの一人。
「それで、ワタシに何か……?」
「何か? じゃなくて、分かるでしょ? お願いしてた書類、どうなってます?」
「あっ……」
「あなたねえ……」
はああぁ、とわざとらしくため息を吐かれる。
「今日までにやっておいてって言いましたよね? 困るんですよそういう態度で仕事されたら。生徒の課題じゃないんですから、期日はちゃんと守ってもらわないと」
「す、すみません! 必ず今日中に終わらせます!」
すぐさまデスクに向き直り、やりかけのデータを上書き保存してフォルダの中を漁る。
「当たり前です。私だって暇じゃないんですから、本当しっかりしてください」
「すみません!」
テストだって今週末に控えているのに。
今日も遅くまで残業だなと途方に暮れる。
しかし、教頭の小言はとどまるところを知らなかった。
「はあ……鶴崎先生ももういい歳なんだから、いい加減いい人探して結婚したらどうなんです? そんなんじゃ一生独り身で寂しい人生ですよ?」
ぴた、と手が止まる。
「…………今、それ関係なくないですか」
「は? 今なんて?」
「……すみません」
そして、また作業へと戻る。
その間も二言、三言と業務に関係のない悪口が、昼下がりの職員室に響き渡っていた。
2
「本当、あのクソ教師……!」
抑えきれない怒りを何とか表に出さぬよう努めつつ、目元を拭って誰もいない廊下を急ぎ足で進む。
大学を出て、この高校に赴任してから数年が経つ。
仕事にもようやく慣れ、副担任ではなく担任としてクラスを受け持つようになった今でも教頭のパワハラは続いていた。
聞くところによると、この学校に赴任してきた新人教員全員に似たようなことをしているらしく、それで仕事を辞めていく者が後を絶たないらしい。
校長は見て見ぬふりだし、教育委員会はアテにならない。
味方をしてくれる先生もいるけど、そんな彼らも教頭には頭が上がらない有様。
正直、ワタシもできることならすぐにでもこんな職場辞めてしまいたい。
でも、そうしない理由が──できない理由が、ワタシにはあった。
それは、
「……はい、ホームルーム始めるよー」
引き戸を開け、三年C組の教室に入る。
まだ社会の汚さを知らないキラキラしたたくさんの目がこちらを見つめる。
その中でも一際輝いているそれが、ワタシがここに居続けるたった一つの理由だった。
美園カスミ。
容姿端麗、成績優秀、スポーツ万能。
生徒だけでなく教師陣からも非常に信頼が厚く、裏表を感じさせない性格の絵に描いたような優等生。
その人気の高さから毎年クラス委員を務め、それと並行して二年連続生徒会長も勤め上げ、今年の夏に大勢の生徒から惜しまれつつの引退。
その後もこのクラスのまとめ役として大いに貢献してくれている。
一言で表すなら、高嶺の花。
そんな誰もが振り向くほどの、誰もが恋してしまうほどの、穢れの知らない綺麗な花に──ワタシは恋していた。
教師が、自らの教え子に。
禁断の恋だった。
──初恋だった。
3
定期考査期間中ということもあり、ホームルームは連絡事項だけ伝えて終わり。
そのまま生徒の大多数は下校していく。
そしてその多数派から漏れ、ちらほらと教室に残る生徒の中に美園カスミはいた。
「会長、これ集めておいた物理のノート!」
「こっちはこの前のプリントね」
「ごめん会長! 昨日出し忘れてた現国のノート、一緒に先生のところに届けてくれない?」
生徒会を引退した後も「会長」の呼び名で親しまれている彼女には、クラス委員として提出物を職員室に持っていく仕事が残っていた。
しかし、今日に限ってその量は膨大で、とても一度に一人で抱えきれるものではなくなっている。
それを助ける者はいない。
だからといって皆が揃って薄情というわけでもない。
彼女なら、何でもできる彼女ならばきっと自分の助けなんてなくても一人でこなせるだろう。
言わば期待の表れなのだ。
そして、実際彼女はそんな期待に応え続けてきた。
だからこその信頼だ。
だけど、できるからといって負担を感じないわけではない。
それをワタシは、よく知っていた。
「手伝うよ、美園さん」
「あ、先生!」
とうとうワタシと彼女の二人きりになった教室で、その端正な顔立ちがワタシに向く。
穢れを知らないつぶらな瞳が、ワタシだけに向いている。
そのことに至上の優越感すら覚える。
「あっ、でも……」
申し訳なさそうに表情を曇らせる彼女。
人のよさを隠し切れていないその仕草に愛しさが溢れる。
「大丈夫、先生も職員室に行くところだったし。ついでだよ」
「……そう? じゃあ、お願いしようかな!」
ぱあっと笑みを咲かせて。
それだけで日々の疲れが癒えていくようだった。
彼女の荷物を半分持ち、教室を後にする。
放課後の廊下にはもう誰もいない。
二人きりの空間を並んで歩く。
この時間が一生続けばいいのにと思う。
このまま、あの最悪な職場に辿り着かなければどれほど良いことか。
「……先生?」
少し後ろから鈴の音のような声が響いた。
振り返ると彼女が足を止めてこちらを見ている。
「どうしたの、美園さん?」
「それは私のセリフ。職員室、こっちでしょ?」
階段を示す。
職員室はここより階下に位置している。
つまり階段を下りる必要があるのだが、どうやら気づかぬ内に通り過ぎてしまっていたようだ。
「ご、ごめんね」
慌てて彼女のもとへと引き返す。
「先生……大丈夫? 最近ぼんやりしていること多いけど、何か悩み事? 私でよければ話聞くよ?」
見事に心理を突いてきた。
だがパワハラのことも、当然この秘めたる想いも明かすわけにはいかない。
「……大丈夫、ちょっとテスト問題作るのに難航してて。どうしようかなーって」
「えっ、日本史のテストってもう明後日でしょ? 間に合うの?」
「無理にでも間に合わすから平気。ありがとね」
言いながら、一緒に階段を下りていく。
美園カスミという花は、昔のワタシによく似ている。
ワタシも学生時代は成績優秀で、仲間からも教師からも信頼されていた。
正直人気も高かったと思う。
異性からは引く手数多だったし、だからすぐに運命の人と巡り合って、結婚して幸せに暮らすと信じてやまなかった。
でも、そうはならなかった。
高校を卒業し、大学を卒業し、社会に出てもなおワタシは恋を知らない子供のままだった。
どころか、次々と周りが大人の階段を上っていく中で一人取り残される焦りから好きでもない男に初めてを捧げてしまい、その傷を今でもずっと引きずっている。
穢れた花。
自ら穢れることを選んだ、醜い花。
もうあの頃には決して戻れない。
取り返しのつかない過ちをワタシは犯してしまった。
ちらと、横目で美園カスミを見る。
こちらに気づき、にこりと笑みを返してくれた。
それだけで胸が高鳴る。
──この学校に来て、ある年の入学式。
そこでワタシは彼女に出会った。
凛とした顔立ちで新入生代表スピーチを読む美園カスミに。
一目惚れだった。
これが恋なのだと知った。
運命があるのなら、きっとこれなのだと思った。
彼女がいるから過酷な業務も頑張れた。
彼女がいるから理不尽な困難も乗り越えられた。
そして今年、ワタシはついに彼女のいるクラスを受け持つことができた。
神様はちゃんといて、ワタシのことを見てくれているんだと強く思った。
ワタシは幸せだった。
この幸せが一生続けばいいと思った。
でも、そうはならないことをワタシは知っている。
彼女もいつか、ワタシのように穢れを知る日が来るのだろうか。
できることなら、一生綺麗なままでいてほしい。
この醜い世界でそれがいかに難しい事なのか、分からないわけじゃないけれど。
職員室が視界に入った。
終わりはすぐそこだった。
4
年々季節が過ぎ去るのを早く感じていたが、この一年は本当にあっという間だった。
三月の初週。
卒業式。
やっと担任を受け持てたあの日の高揚がつい昨日のことのように思い出される。
過ぎ去った日々が走馬灯のように瞼の裏を駆け巡る。
ここが学校で、相手が生徒である以上、この日が来ることは分かっていたし、それなりに覚悟だってできていたはずだった。
それでも、胸の痛みが治まらない。
意を決する。
最後に一言だけでもと、ワタシは卒業証書の入った筒を片手に泣き合っている集団へと歩みを進めた。
担任なんだし、こんな日くらい、これくらいのワガママは許してほしい。
「……美園さん」
「あっ、先生!」
ワタシは良い担任でいられただろうか、と今更になって思う。
彼女と一緒にいた他の生徒たちも泣き笑いでワタシを囲んでくれていることを今は前向きに捉えよう。
「卒業おめでとう」
「ふふっ、ありがと!」
「鶴崎センセー、あたしたちはー?」
「そうやって会長ばっかりヒイキするんだから」
「はいはい、みんなも卒業おめでとうね」
やいのやいのと騒ぎ立てるのをあしらいながら、再び彼女へと視線を戻す。
「……本当に卒業しちゃうんだね」
ワタシの言葉を受け、優しく微笑んで彼女は返す。
「先生、初めての担任クラスだったもんね」
違う。
この感情はそんな容易いものではない。
本当は胸が張り裂けそうなくらい苦しいし、できることならこのまま彼女を連れ去ってどこか遠くへ行ってしまいたい。
でも、それが誰の幸せにもならないことくらい分かっているから。
そんな分別ができてしまう醜い大人になってしまったから。
だから、こうして平静を装って、無い愛嬌を振りまいているのだ。
「そんな悲しい顔しないでよ」
「えっ?」
しかし、彼女はそんな心情すら、まるで見透かしたように。
「大丈夫だよ」
まるで元気づけるように笑って。
「別にもう一生会えないってわけじゃないんだから」
花のような綺麗な笑みで、彼女は言った。
「いつか、またどこかで」
「……うっ、ううっ」
ぼろぼろと。
「センセー?」
「ご、ごめんね……抑えきれなくなっちゃって」
気が付くと、大粒の涙がとめどなく溢れ出していた。
「ちょっとセンセーが一番泣いてんじゃん!」
「ごめんね、あたしたちが卒業して悲しいよね? よしよし」
優しく頭を撫でてくれる愛すべき生徒たち。
でも、違う。
違うんだ。
これは──
「…………」
「……会長?」
俯き、ハンカチで涙を拭っていると、こちらに近づく気配を感じてワタシは顔を上げた。
「先生」
「み、美園さん……?」
その表情はこの場に似つかわしくないほどに真剣で。
テスト期間のあの日、そしてこの一年間で幾度となく向けてくれた、心の底から人を思いやるその眼差しを、このときワタシは感じた。
「ごめんねみんな、ちょっと先行ってて。私、先生と話したいことがあるから」
「えっ……?」
彼女は聖母のように優しく頬を緩ませ、静かに言った。
「一緒に来て」
5
卒業式、校舎裏。
そこに呼び出される意味くらい知っているし、実際呼び出されたこともある。
でも、今から始まるのがそんな甘酸っぱい思い出になるような何かではないことくらいは容易に想像がついていた。
「……ごめんね美園さん、みっともない姿見せちゃったね。せっかくの卒業式なのに、ごめんね」
正直彼女が先ほど見せた表情の意味も、わざわざここへ連れてきた真意もワタシには分からない。
ただ、本来なら今頃友達とファミレスにでも行って、高校生活最後の思い出として雑談に興じているはずなのだ。
そんなささやかな幸せを邪魔してしまい、担任としても大人としても失格で。
そして、こうして友達よりもワタシを優先してくれたことに喜びを感じてしまっている時点で、人間としても失格なのだろう。
やがて、彼女は口を開いた。
「先生、さっき何で泣いてたの?」
「えっ……」
一体どこまで気づいているのだろうか。
不安に駆り立てられながらも、恐る恐る答える。
「それは……みんなが卒業しちゃうのが、悲しくて」
「本当に?」
思わず目を逸らしながらも、ゆっくりと頷く。
「……私だけは、先生に信頼されてるって思ってたんだけどなあ」
「……え?」
表情を緩め、校舎にもたれかかる姿勢で彼女は続ける。
「ほら、先生って割と平気で嘘吐くから」
「嘘なんて……」
「隠さなくていいよ。本当は一人でずっとしんどい思いしてるのに、私たちが心配しないようにって強がってくれてたんでしょ? ……ごめんね、本当は知らないフリしたまま卒業しようと思ってたんだけど──私知ってるんだ、先生がたまにここに来て、一人でこっそり泣いてるの」
「…………そう、なんだ」
まさかそんなところを見られていたなんて。
恥ずかしさが胸の内から込み上げる。
「もちろん誰にも言ってないよ! っていうか、結局最後まで先生のこと助けてあげられなかったし」
「助けられなかったって、ワタシは美園さんがいてくれればそれで──」
はっ、と我に返って慌てて口を止める。
危ない、言ってはいけないことまで口走ってしまうところだった。
「えへへ、ありがと。先生って優しいね」
「こんなの……普通だよ」
好きな人がいてくれるだけで頑張れるのなんて。
「……ほんとはね。私、学校に来るのが嫌いだったんだ」
「え……?」
「さっきの子たち、別に友達なんかじゃないし」
「な、何言って……」
あまりにも唐突な話の流れについていけなくなる。
構わず彼女は続ける。
「実は私、裏で嫌われてるんだよね。自分で言うのもアレだけど、私って何でもできちゃうから。自分たちがどんなに頑張っても取れない点数や成績を私が何の努力も無しに取っちゃうからって、僻んでるんだよ」
本当に何もしてないワケねーだろってカンジだよね、と空虚に笑う。
「今だから、先生だから言うんだけどね、この学校滑り止めだったんだ。本当はもっと頭いいとこ狙ってて、でも直前に詰め込み過ぎて試験当日に熱出しちゃってさ。だから周りより勉強できるのは正直当たり前だし、大学受験こそはって日頃から周りより必死に勉強してるのも当たり前なんだよね」
事実、彼女は歴代でも類を見ないほどの好成績で高偏差値を誇る都内の有名大学に合格してみせた。
「……でも、美園さんの魅力はそれだけじゃない。運動だってできるし、それにクラス委員や生徒会長だって……!」
「えへ、ありがと」
そう力なく笑ってから、
「……家が厳しくてさあ。子供のころに習い事をいくつもさせられたの。その中にテニスとか水泳とかあったから、スポーツができるのはその名残。だから漫画やゲームの話についていけなくて……」
見たことないような虚ろな顔で、滔々と続ける。
「クラス委員や生徒会長なんて、それこそ面倒な仕事をできる奴に押し付けてるだけ。でも、それでさらに先生から信頼されるようになるってとこまでは考えてなかったんだろうね。急に手の平返したように私に擦り寄ってきてさ。私と一緒にいれば自分たちも先生からよく見られるからって。笑っちゃうよね」
へらへらと。
そんなくだらない場所に通わなくちゃいけないのは苦痛で仕方なかったと、笑った。
「でも、今年一年は違った。やっぱりクラスメイトは私の上辺しか見てないし、自分たちのことしか考えてないし。でも、ちゃんと私のことを見て、手を差し伸べてくれる人がいた」
「……素敵な人に出会えたんだね」
「先生のことだよ?」
「えっ?」
心臓が射抜かれたような気がした。
一瞬息を忘れるような瞳と言葉で、彼女はワタシの心を貫いた。
「で、でもワタシ、美園さんが周りからそんな風に思われてたなんて、知らなかったし……」
「知らなくても、助けてくれたでしょ? ほら、私が持ちきれない荷物を半分持ってくれたりさ!」
「そ、そんなこと……誰でもするでしょ?」
「私には先生しかしてくれなかったよ。言ったでしょ、嫌われてるって」
「……どうして、それをワタシに?」
率直な気持ちだった。
どうしてその事実を今、このタイミングで彼女は打ち明けたのか。
「先生の秘密を知っちゃったんだから、そのお詫び。私も何か秘密を教えなきゃ不公平でしょ?」
そう答える彼女は、いつもの優しい笑みに戻っていた。
「ねえ、何かあったの? ……さっきの泣き方、何だか普通じゃなかったように見えたんだけど。何ていうか、ただ『卒業しちゃって悲しい』って感じじゃなかったよ」
「……やっぱり、美園さんには敵わないな」
きっと、それを答えさせるための暴露でもあったんだろう。
彼女はこれでイーブンのようなことを言ったけれど、さすがにこの流れでシラを切るのは不可能だ。
いっそのこと、この気持ちにも気づいてくれれば楽なのに。
それできっぱりと拒絶してくれれば、全部諦めもつくのに。
優しくしてくれるから、いつまでも期待してしまう。
彼女が誰にでもこうして手を差し伸べる子だっていうのは分かっているはずなのに。
「……ワタシね、確かに担任を持つのは今年が初めてだったんだけど、それまでは副担任として何度も卒業生を見送っていったの」
「うん」
「それで、卒業式のたびに決まって言われるセリフがあって」
「うん」
「『いつかまたどこかで』って、みんな気軽に口にするの」
「そうだね」
「でも、それで本当に再会したことなんてただの一度もなくて。ここに来てからだけじゃない。大学時代の教育実習でも、ワタシが高校生のときの卒業式だってみんな当たり前みたいに言うのに、それから会えたことなんて一度も……!」
「そうなんだ」
「別に、そのこと自体が問題じゃない。そこまで思い入れの深い人たちじゃなかったし、きっとこちらから連絡すればみんな会ってくれると思う。でも、あなたたちは違うでしょ? ワタシは先生で、あなたたちは生徒で……用も無いのにこちらから連絡して会うなんて、そんなこととても……」
「別に連絡してくれていいのに」
「よくない! よくないの……!」
学校に登録されている個人情報を私利私欲で利用することが許されないことくらい理解している。
ましてやそれが邪な感情に支配されたものであるなら尚更。
直接生徒自身にプライベートな連絡先を訊くなんてもってのほかだ。
もう生徒ではなくなったからなんてそんなものは言い訳にすらならない。
ワタシが教師、つまり聖職者であることは変わらないし、それ以前にワタシが大人で、彼女が子供であることも変わらない。
年の差がどうとかそれ以前の問題として、ワタシは彼女に人として幸せに生きる道を教え導かなければならない立場にある。
そして彼女を真に幸せにできるのは、ワタシのような醜い花ではないのだ。
せめて、これがただの「信頼関係」であるなら連絡先の交換くらいはできたかもしれないのに。
ワタシはいつのまにか心の叫びを吐き出していた。
「だから、だから……! せめて、思い出だけは綺麗なままでいさせてよ……目の前からいなくなるならせめて、何も言わずにひっそりといなくなってよ! 『いつかまたどこかで』なんて期待させるような──ありきたりな嘘言わないで!」
大の大人が子供相手に何を泣きわめいているのだろうか。
分かっていても、口から溢れる思いを止めることはもうできなくなっていた。
「──あっ、先生!」
ワタシはまたもや涙を流しながら、それを拭いもせずに走り出す。
もう、合わせる顔なんて無いから。
きっと彼女の中でワタシは訳の分からない大人として、その高校生活最後の思い出に泥を塗りたくっていることだろう。
好きな人に対する仕打ちとしてここまで最低なこともない。
これなら、まだワタシを抱いたもう顔も思い出せないあの男の方が幾分ワタシに対して優しかったと思う。
でも、穢れた花の醜い初恋の最期としては、お似合いなのかもしれなかった。
そんなことをつらつらと考えていた──そのときだった。
「待って!」
強く手首を掴まれ、引き止められた。
「っ!?」
驚いて振り向くと、そこには軽く息を切らした彼女。
まさか、追いかけてきたのか。
「はぁ、はぁ……」
「……離して」
「離さない」
「……っ、どうして……」
「……ごめん。私、先生の言ってることよく分かんない」
「…………だったら」
「だって、そんなに言うなら嘘じゃなくすればいいじゃん」
「……え?」
意表を突いたその一言の意味を即座には測りかねていると、彼女は補足するようにこう続けた。
「今度、一緒に遊びに行こうよ。そうすれば嘘じゃなくなる」
ほら、携帯出して、と彼女は制服のポケットからスマートフォンを取り出してワタシの反応を窺う。
またもや展開についていけず固まってしまうワタシに対し、彼女は少しだけイジワルな表情で、
「何してるの? 連絡先、交換しようよ」
と、まるで友達にでも言うような言葉を投げかけてくるのだった。
「……いいの?」
「ダメだったとしても、無理にでも奪い取ってゲットするから。こう見えて私、今、キレてるんだよ?」
「キレてるって……」
「先生をこんなにも追い詰めている直接の原因は分かんないけど、それに対してもキレてるし、それを今日まで言ってくれなかった先生にも、やっぱり気づいてあげられていなかった私にもキレてる。だから、絶対先生のこと助けるから。じゃなきゃ私の気が済まないから」
先生のこと、絶対楽しませてあげるから。
そう言ってワタシに見せた屈託のないその笑みは、やっぱりいつかの自分によく似ていて。
失いたくないと、強く思った。
6
ランドマークとなっている大時計の下で一人待つ。
日曜日の午前ということもあり、辺りを見渡すと同じように待ち合わせに来ているらしき私服姿の人たちで溢れている。
その大多数はキラキラした若者が占めていて、自分だけ浮いているような気がして居心地が悪い。
「流石に早く来すぎたかな……」
まるでものすごく気合を入れているみたいだ。
あながち間違いではないのだが。
時計を見ると、到着してから二十分が経過していた。
体感的にはもう一時間近く待ったような気がしているのに、どうしてこうも誰かを待つ時間というのは長く感じてしまうのか。
相手が好きな人ともなれば尚のこと。
「あっ、おーい! せんせーい!」
待ち望んだ声が聞こえ、すぐさま顔を上げる。
目が合うと同時、嬉しそうな顔でこちらへ駆けてくる人影。
「ごめんね先生。待ち合わせの時間より結構早く来たはずなんだけど……待った?」
「ううん、ワタシも今来たところだから」
なんてありきたりなセリフを口にする。
「それ、美園さんの私服?」
「え? そうだけど……ヘンかな? 一応いつも通りのを着てきたつもりだけど」
きょろきょろと自分の姿を見回す彼女。
ストリート系というのだろうか。
黒を基調としたシックな色合いでまとめており、パンクな雰囲気がいつもの優等生なイメージを良い意味で壊していて、そのギャップにキュンとする。
「ううん、かっこいいと思うよ」
率直な感想だった。
「えへ、ありがと。これスカートも短いし『そんな不良みたいな恰好やめなさい』って言われたらどうしようかとちょっと不安だったんだ。でも……勇気出してよかった。せっかくなら、先生にはいつもの私を見せたかったから」
そう言ってはにかむ仕草も非常に愛らしい。
確かにスカート丈はちょっと気になるけど。
「そういう先生も私服かわいい! すごく似合ってる」
「ほ、本当? これ着るの数年ぶりとかなんだけど、大丈夫かな……無理してる感じ出てない?」
「先生まだまだ若いんだから、そんなこと気にしなくたっていいんだよ。大丈夫、ちゃんとかわいいよ?」
励ますように笑う彼女。
そう何度も「かわいい」と口にされると照れてしまう。
「それじゃあ、早速行こっか」
「うん。今日はよろしくね、美園さん」
リードされる形で、ワタシたちは大時計を後にした。
そう、今日ここに集まるのはワタシと彼女の二人だけ。
だから、これはデートなのだ。
自然と気合だって入ってしまう。
今日一日をどうか素敵に。
それだけを胸に、ワタシは先を行く彼女の背中を追った。
7
今日のデートプラン──もとい、スケジュールはすべて彼女が組んでくれた。
「私が先生を楽しませるんだから、これくらい当然」とのこと。
どこまでも頼りになるその姿勢につい甘えたくなってしまうが、それで負担まで抱え込んでしまうのもまた彼女の性質であることを、よく似たワタシはよく知っている。
要らないところで無理させてないか、思わず彼女のことばかりを見てしまう。
「──先生、ちゃんと映画観てた? なーんかちらちら視線感じたんだけど」
近くのレストランで昼食を取る間、直前に観ていた映画の感想を語り合う流れで鋭い指摘が入った。
「み、観てたよもちろん。面白かったよね」
「うーん、正直私はあんまりだったかなあ」
オムライスをスプーンで切り崩しながら彼女は続ける。
「テレビであれだけ『衝撃の結末!』って煽ってた割には、オチもなんだかありきたりだったし」
「そうなんだ。ワタシ、あまりテレビ観ないから……」
この会話の展開は意外だった。
「美園さん、結構ずばずば言うんだね」
「あっ……ごめん。クラスの子からもそれやめた方がいいって言われてたんだった。気、悪くした?」
「だっ、大丈夫! ワタシも正直あのオチはどうなんだろうって思ってたから」
咄嗟に話を合わせながら、かつて綺麗だった自分と照らし合わせる。
当然彼女はこれがデートだなんて思っていないだろうけど、それでも同じように自分が誘い、自分が選んだ映画が自分の好みに合わなかったとき、同じように正直に「つまらなかった」と言えただろうか。
美園カスミはワタシとよく似た花だ。
よく似ていて、明確に異なる。
だからワタシは強く惹かれた。
これはきっとその違いの一つに過ぎないのだろう。
自分にはない、芯の通った強さのようなものに。
──レストランで小腹を満たした後は、引き続き彼女のエスコートのもとショッピングを楽しんだ。
服を選び合ったり、雑貨屋を巡ったり。
二人して両手に大量の買い物袋を抱え、最後に何となく立ち寄った店で、彼女が興奮したように声を上げた。
「ねえ見て! このネックレスかわいいー!」
「もう、そんなに大声出したら周りに迷惑でしょ」
言いつつ、ショーケースにべったり張り付くほどの近さで見つめる彼女の横顔を盗み見る。
その表情は本当に綺麗で、純粋な瞳に吸い込まれそうになる。
艶やかな小さな唇が小さく言葉を紡ぐ。
「……いいなあ」
「買ってあげようか?」
「いいの!?」
ばっとキラキラした両目がこちらに向き、一瞬目が眩む。
「あっ、でもさすがに先生にそこまでさせるのは悪いし……」
「お昼だって奢ってるし今更でしょ。それに、今日一日楽しませてもらったし。卒業祝いだと思って」
「えー、でもやっぱり悪いよ。これ結構高いよ?」
「でもそれ、自分で買える?」
「うぅ……」
しばらく葛藤と共に視線を彷徨わせた後、
「あっ」
ある一点で止めて、彼女は言った。
「じゃああれ! あれにする!」
「うん?」
彼女が示す先にあったのは、猫のチャームが付いた二本で一セットのペアネックレス。
値段的には彼女がのめり込んで見ていたものより確かに安いが、
「いいの? こっちが欲しかったんでしょ?」
「いいの。せっかく二人で来てるんだし、お揃いのやつ買おうよ」
「お揃い……?」
その思わぬ単語に一瞬だけ面食らう。
「……いいの?」
「何でそんなに驚いてるの? あっ……もしかして嫌だったり?」
「ま、まさかそんな! すごく嬉しい!」
ついかぶりを振ってオーバーリアクションを取ってしまう。
まさか、彼女の方からそんな嬉しい申し出をしてくるなんて。
しかも元々欲しかったものを我慢してまでだ。
お揃い。
その単語だけで、今夜は嬉しさで眠れなさそう。
「……じゃあ、これで」
ワタシは店員を呼び、猫のペアネックレスを購入した。
「先生、うれしそう」
店を出るなり、すぐさま彼女が言う。
「えっ、そう?」
「うん。先生分かりやすいから」
「それは……ちょっと違うかな」
「え?」
きょとんとする彼女に、ワタシは答える。
「美園さんがよく気づいてくれてるんだよ。それだけ相手のことをちゃんと見ているってこと」
事実、ワタシが追い詰められていたことも、卒業式で流した涙の意味がほかとは違うことにも気づいて声を掛けてくれたのは彼女だけだった。
「……えへへ、何だか褒められちゃった」
「美園さんは……どうかそのままでいてね」
「?」
小首を傾げる。
意味は分からなくていい。
きっとその方が、幸せだから。
「この後どうしよっか?」
代わりにそう尋ねた。
荷物も多くなってしまったし、彼女も歩き疲れているはず。
できることならもっとデートを続けていたいけど、彼女のことを思うならこの辺りでお開きにすべきだろう。
そう考えていたのだが、
「実はね、この先にクラスで話題のパンケーキ屋さんがあるんだ。私まだ行ってなくて。最後にそこだけ寄ってもいい? ネックレスのお礼もしたいし!」
「お礼だなんてそんな……」
むしろワタシがすべきことなのに。
でも、まだデートを続けられる。
その嬉しさでまた胸が一杯になった。
「いいよ、ちょうど先生も何か甘いものが食べたかったし」
「やった!」
事前に場所を調べていたのだろう。
行ったことがないと言いつつも彼女は迷わずワタシをその店へと連れていった。
日曜日の夕方ごろ。
それも話題となっているだけあり、店の前には行列ができていた。
ワタシたちはたわいのない話に花を咲かせて順番を待ち、通された窓際の席に腰を下ろした。
「ラッキー。いい席座れたね」
彼女は微笑み、ワタシは「そうだね」と同調する。
外からの視線が気になって正直落ち着かなかったけど。
注文を決め、料理の到着を待つ。
先に切り出したのはワタシだった。
「美園さん、今日はありがとう。すごく楽しかった」
「本当? よかった! 途中から私ばっかり楽しんでないかなって実は不安だったんだ」
「大丈夫。ちゃんと楽しかったから」
きっと、彼女と一緒ならどこでも同じ気持ちになるのだろうけど。
恋って不思議だ。
まるで魔法にでも掛けられたように、一緒にいるだけで気分が軽くなる。
胸の内が熱くなるような気がして、幸せな気持ちが溢れてくる。
「そう言ってもらえてよかった。これで『先生を楽しませる』って目的は達成かな?」
「…………」
「先生?」
そして恋は、ワタシを少しだけ欲張りにさせる。
「……ねえ、外でも『先生』って言うのやめない?」
「え、どうして?」
「だって……ほかの人に聞かれたら、変に思われちゃうから」
咄嗟に口を突いて出た理由だったが、あながち嘘でもなかった。
今日一日、傍から見てワタシたちがどう思われているか、少なくともワタシはずっと気になっていた。
しかし彼女はあっけらかんと答える。
「別にいいじゃん女の子同士なんだし。変じゃないって」
「……お願い」
ワタシのその言葉を受け、やはり何かに気づいたのだろう。
少し気まずそうな顔をしてから、
「じゃあ……鶴崎さん?」
探るように。
「マツリって呼んで」
下の名前。
穢れてしまった花の名。
「えー、じゃあ私のこともカスミって呼んで。えっと……マツリちゃん?」
「もちろんだよ、カスミさん」
即答する。
想像の中で何百回と口にした名だ。
「……そっちはさん付けなのずるくない?」
「ずるくない」
ふっ、と彼女が噴き出し、やがて二人して笑い合った。
休日に会って、下の名前で呼び合う二人。
「あ、そうだ。ねえマツリちゃん」
「なに、カスミさん?」
「さっき買ったネックレス、せっかくだし着けてみようよ」
そう言って彼女はアクセサリーを取り出し、
「はい、マツリちゃん」
両手を伸ばす。
首を差し出すと、そのまま腕を回してワタシの首に着けてくれた。
胸元で金色の猫が光を反射して光っている。
「思った通り。よく似合ってるよ、マツリちゃん」
「ありがとう。じゃあ次はカスミさんの番ね」
じゃれ合って、また笑い合う。
まるで恋人のよう。
でも、本当にそうはなれないことをワタシは知っていた。
まるで子供のごっこ遊び。
どんなに頑張っても、本物にはなれない。
よく似ていて、偽物だ。
それでも、ワタシは幸せだった。
この瞬間だけはきっと、世界中のほかの誰よりも。
「今日のマツリちゃん、すごくかわいい」
「ありがとう。カスミさんこそ綺麗だよ」
「ねえ、また誘ってもいい?」
「もちろん。待ってる」
──幸せだった。
8
「──ああああああああああぁぁああああああああああ‼」
何かが折れる音がする。
美園カスミと別れたその日の晩、ワタシは一人暮らしの狭い一室で片っ端から物を壊して回っていた。
そうでもしないと、先に心が壊れてしまいそうだったから。
いや、もしかしたらとうの昔に壊れてしまっていたのかもしれない。
自分の物が自分の手によってその機能を失っていく様は、見ていてどこか滑稽だった。
「ああああああ! ああああああああぁぁぁぁああああああああああああああああああ!」
掴んで、もぎ取って、振り回して、投げつける。
どこかで電球が割れてしまったらしい。
気づけば辺りは真っ暗になっていたが、お構いなしに手あたり次第手に取ったものを壊していく。
あの後、特に何かがあったわけじゃない。
むしろデートは滞りなく終わり、それは最後まで幸せな時間だった。
今までの人生で体験したことのないくらい、それはそれは幸せなひとときだった。
──そんな幸せな時間は、終わってしまったのだ。
幸せな瞬間を経験してしまったからこそ、もう二度とそんな時間は訪れないという事実が胸を切り裂く。
「また誘う」なんて台詞がただの社交辞令であることくらい、分かっていた。
彼女が高校生なのは今だけ。
新たな生活が始まれば、新たな出会いを迎えれば、ワタシのことなんてすぐに忘れてしまう。
彼女にとってワタシは所詮、ただの担任教師でしかないのだから。
美園カスミは本物だ。
だからこそ、ワタシには無い強さを持っていた。
常にびくびくと顔色を窺い、歩調を合わせることだけに全力を尽くし、本物を装うことばかりを目的とするあまりあらゆるものが歪み、ねじ曲がり、やがてすべてを見失ってしまった偽物とは違う。
彼女は本物だから。
ワタシとは違うから。
だから素直に自分をさらけ出せるし、そのことに躊躇いが無い。
彼女が「かわいい」と褒めたあの服は別にワタシの趣味じゃない。
彼女が選んだからつまらない映画も「面白かった」と言ったし、本当は甘いものも嫌いだ。
でも、世間じゃそれが普通だから。
それが本物だから。
だから、ワタシはそれに合わせて生きていくしかなくて。
だから、それでもちゃんと自分を表現できる彼女が羨ましかった。
彼女はきっとこの先、ワタシよりも遥かに素敵な人に出会って、恋に落ちて、そして本物の幸せを掴むのだろう。
その幸せなストーリーにワタシはいない。
ただの高校教師Aとして、エンドロールに名前もクレジットされないまま忘れ去られていく。
ワタシは何一つ忘れられないまま、もがき苦しむしかないというのに。
──別にいいじゃん女の子同士なんだし。変じゃないって。
彼女の何気ない一言が頭の中でループする。
女の子同士だから変じゃない。
じゃあ、ワタシが男だったら変だった?
意識してくれた?
つまり、ワタシのことはそういう目では見ていないということで。
分かっていた。
期待なんてしていなかった。
でも、そんな優しい笑みでその現実を突きつけないでほしかった。
もっと夢を見させてほしかった。
期待させるなとか言った癖に、心のどこかでワタシは期待していたかったのだ。
そんな破綻した自己矛盾すら彼女はその輝きで明るみに出してしまった。
瞬間、じわじわと毒が回るように心が蝕まれた。
それでもワタシは、笑みを取り繕っていた。
「ぁぁあああああ! あああああああああぁぁぁあ……!」
そこでまた泣き出せばよかった?
欲望のままに唇でも奪って、ホテルに連れ込めばよかった?
知らない誰かに穢されるくらいなら、いっそワタシが。
──そんなこと、今日に至るまで何百回と考えてきた。
そして、同じ数だけ諦めてきた。
そんなことできるわけがない。
これは立場とか周りの目とか世間体とか、そんな次元の話じゃない。
だって、好きなんだから。
恋に落ちてしまったのだから。
好きな人には誰よりも幸せになって欲しいから。
だから、そんな目先の快感に溺れて傷つけるなんてこと、できるわけがなかった。
キズモノはワタシだけで十分。
だからせめて、醒めない魔法を掛けたなら、解いてからいなくなってほしかった。
ワタシはこの先、どうやって目覚めればいいのだろう。
「ああああああぁ…………うっ、うわぁああああ……」
彼女の言葉が耳の中でこだまする。
──でも、ちゃんと私のことを見て、手を差し伸べてくれる人がいた。
違う。
──知らなくても、助けてくれたでしょ? ほら、私が持ちきれない荷物を半分持ってくれたりさ!
違う。
──先生のことだよ?
違う‼
違うんだ、そうじゃないんだ。
結局ワタシは彼女の綺麗な部分しか見ていなかった。
勝手に理想を思い描いて、勝手にそれを現実の彼女に当てはめて全部分かった気になって。
ワタシにはない強さ?
本物だから自分をさらけ出せる?
適当なことを言うのも大概にしろ。
理想と違ったショックから目を背けるな。
ワタシの恋した『美園カスミ』はいなかった。
ワタシが憧れた綺麗な花なんてものは最初からそこにはなかった。
だから、諦めろ。
どうせ彼女はワタシのことなんてすぐに忘れるんだから、ワタシも彼女のことなんて忘れてしまえ。
それが、ワタシを救う唯一の出口なのは分かっているのに。
──荒れ切った部屋の中。
もはや原型を留めている物の方が少ない中で。
最後に手にしたそれだけは、いくら腕を振り上げたところで手放すことができなかった。
「ううっ、うぐっ……ひぐっ……」
金色の猫が、窓から差す月明りを受けて光っている。
楽しかった。
今日のデートも、この一年間も。
例えそこに咲いていたのがワタシの望むような花じゃなかったとしても、その事実は変わらない。
どうしたってワタシは彼女のことが好きなままで。
きっとこの先も囚われちゃうんだな。
──夜が更けていく。
ワタシによく似たあの花が咲くことはない。
ねえ、ブルージャスミン。
後書
ここまでお読みいただきありがとうございました。
本作品は当記事書き下ろしですが、
原作楽曲は2022年4月24日(日)に開催のM3-2022春にて頒布される
ギンクル1stフルアルバム『#甘酸っぱくなきゃキスじゃないっ』にて
収録されています。
私、レファルもボイスドラマ脚本で参加しています。
さらに会場限定特典として、
季節を彩るボイスドラマ4編をさらに深く楽しめる特別掌編(全8編)や、
全作詞曲・プロデュースを行ったギンクル氏によるセルフライナーノーツが
収録されたブックレットもついてきます(数量限定)。
現在、ボイスドラマ、特別掌編の一部を特別に公開しています。
是非ともお買い求めください。
購入方法等詳細は以下リンクから。
感想もお待ちしています。
レファル
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
