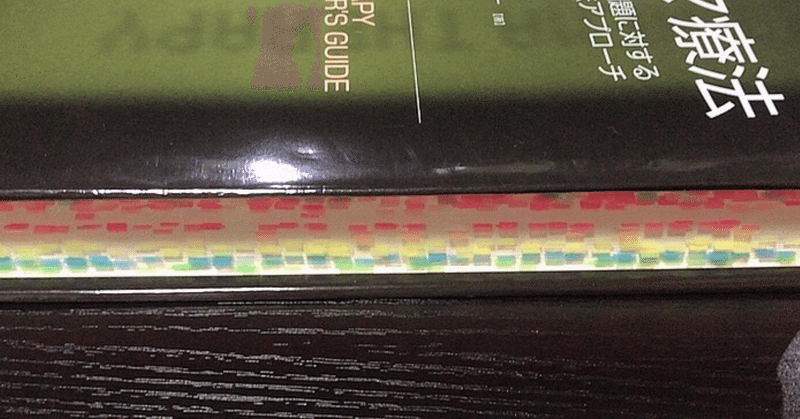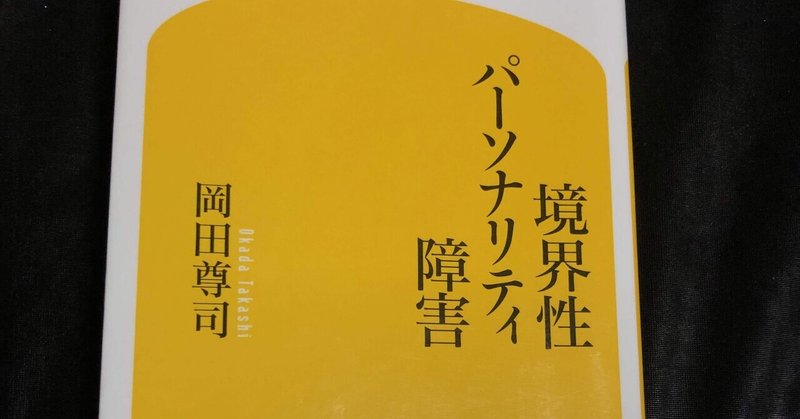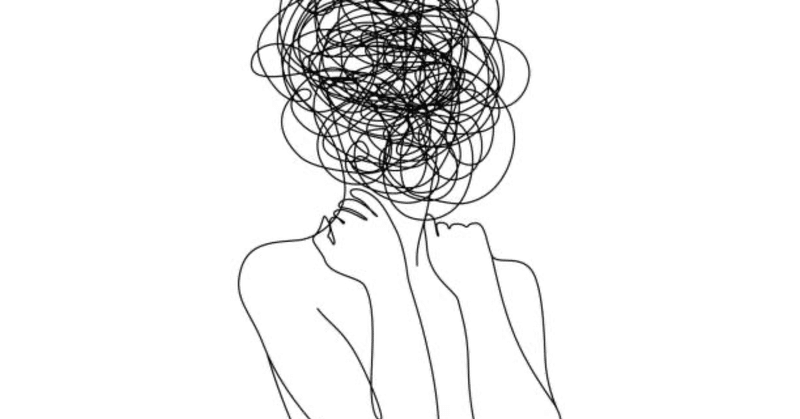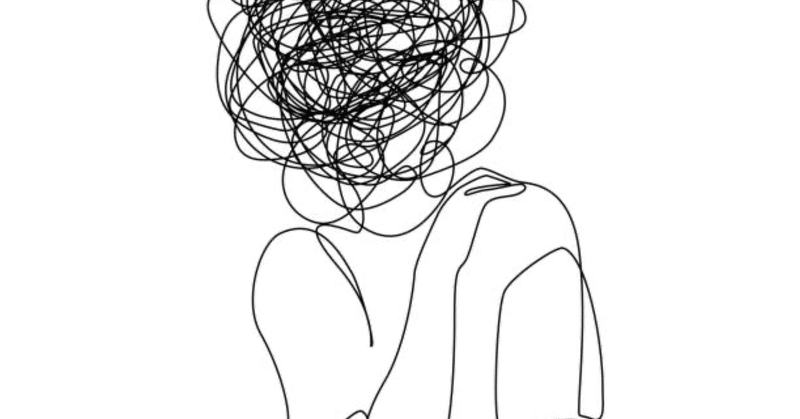#最近の学び
相談の結果、知ったこと:消去バーストと自殺潜在能力
昨日は通院日だった。
今回は以下の2点を相談したい、と考えていた。
いずれに対しても私にとっては新たな情報が得られたので、忘れないうちに記録しておきたい。
①について:なぜ動けなくなるのか
負の条件づけにより反応が悪い方に固定されてしまっている。いわゆる「凍りつき反応」が生じているのでは?という見立て。
おそらくは幼少期に行われた喜ばしくない学習が脳に染みついている。
恐怖を感じるような
(メモ)未解決の復讐衝動
マスターソン著『自己愛と境界例』のまとめがようやく終わろうとしている。
いつかの記事で境界障害トライアドの話をしたがここにきて、その重要性がぼんやり分かったような。
おそらく説明は不十分すぎると思うが、いま閃いたことをメモ程度にまとめておきたい。
マスターソンの説によれば「分離-個体化の失敗が見捨てられ抑うつを誘発し、さらにそれが防衛を誘発する」。
・分離-個体化の失敗