
「生きるとは、捻じ曲げられたものを捻り返して真っ直ぐにすること」と、その人は言った
私は、ずっと「表現」ができなかった。自分みたいな人が、何かを「作りたい」と思うことすら恥ずかしいような気がしていた。鼻で笑われるのが怖かった。
誰にも見せないものすら無理だった。頭の中の自分が、みっともないと言うから。
けれど、今思えば、私は、ずっと’ことば’でいっぱいだった。どうしようもないモヤモヤとしたエネルギーは、ずっと出口を求めていた。
*
2020年、コロナ禍の中、橘川幸夫さんは、小説という表現方法の可能性について目を向ける。
世界的な状況の変化の中で、内面世界に目を向ける人がたくさん生まれるだろう、それが表現する手段と結びついたら、今までとは違った「何か」が生まれるだろう。
それが彼が直感的に思ったことだ。
彼が、伝説の投稿雑誌「ポンプ」を創刊したのは1978年。それは、インターネットの先がけのようなものだった。
「素人」が集まり自由に遊ぶことができる誌上(プラットフォーム)であり、投稿者は住所や名前を公開でき、呼びかけて待ち合わせをしたりサークル活動も積極的に行われた。
そのようなたくさんの「素人」の中に、まだ無名の高校生、岡崎京子がいた。彼女の絵は、あっという間に多くの人の心を掴みポンプ内にファンクラブまでできた。
その高校生が、のちに時代の寵児のマンガ家となるとは、この時に応援した人たちも予想していなかっただろう。
コロナ禍の中で「小説」の創作を呼びかける橘川さんは、「素人」の中から何かが生まれることを期待していた。
橘川さんは、その人の一作目が読みたい、と言う。プロが発注されて書いたエンターテイメントでなく、その人が、どうしても必要があって書くもの。そこには何かが宿るだろう、と。
私は、’ジミー’をすでに書き終えていて、橘川さんの考えに共感していた。
それで、原稿を送った。
*
後で聞いたのだけれど、'ジミー' を読んだ橘川さんは、すぐさま「メタブレーン」社長の太田さんに原稿を送った。夜中だったけど、彼女も一気読みしたという。
「これは」と思った二人は、すぐさま「ジミーについて話がしたい」とメディア・クリエイターの平野友康さんたちにメッセージを送る。早朝4時。
その日の夕方、緊急ミーティングが開かれた。(私は呼ばれなかったので、後で聞いた話だ)
*
Zoom上に現れた橘川さんは、目を輝かせ、待ちきれないように言った。
「あのさ、俺は、小説を書き始めるやつの中から、新しい才能が出てくると絶対、思ってたんだよ。
ポンプから岡崎京子が出たようにな。2−3年後と思ってたのにな」
そう言って、嬉しそうに笑った。
「困ったな。もう、きちゃったよ」
*
その様子を後で聞いた私は、お二人の反応も嬉しかったけれど、「岡崎京子」の名前が出てきたことに、心臓がばくばくとし、いても立ってもいられなくなった。
自分が彼女の才能を持つと言われたわけでは全くないのに(そうでなく、例えば、いう話だ)、「信じられない」と部屋をぴょんぴょん飛び回った。
「リバーズ・エッジ」「チワワちゃん」「ハッピィ・ハウス」...
時代の感覚を表し、多くの表現に影響を与えた尊敬されるアーティスト。
私の思う岡崎京子は、ポンポンとハッピーな画面や軽い言葉を使いながら、孤独と悲しみとどうしようもなさと若さと絶望を、深くえぐるように描いた人だ。
*
二回目のミーティングには、私も呼ばれた。
緊張する私に、社長の太田さんは言いにくそうに口を開いた。
「エイミーさん、私が言ったことはもう聞いてると思いますが、’ジミー’は素晴らしい作品と思いました。
あのクオリティーなら、大手出版から出すことも可能だと思います。
だから、迷いもあるんです。
うちみたいに小さなところで出すと、大きな広告費はないし地方の書店に置くこともできません。エイミーさんにとって、それでいいのかなって..」
なるほど、とうなづいた。メタブレーンは、橘川さんが「仲間が本を出せるための出版社」として立ち上げたもの。儲けは目的でないから、大きな流通経路はないし使える宣伝費もない。必要がなかったのだ。
橘川さんが後を引き取った。
「俺も、’ジミー’は、クオリティーのある作品だと思うんだ。中だるみも全くなくて最後まで読んでしまう。映像が見えてくる。アニメにも向いてるんじゃないかな、、。文章も、音楽があるんだよね」
そういうと腕を組み、少しの間沈黙した。
「エイミーさん次第だと思うんですよ。大手で広告費をかけてやってもらうのがいいなら、文芸系の出版社に紹介することも可能です」
私も口ごもった。どう返事をしていいかわからなかった。
確かに、橘川さんの参加型社会の考え方には共感していたし、だから原稿を読んでもらおうと思った。
けれど、「大手出版社に紹介」とか「アニメ化」だなんて、、。
「大手出版だなんて望んでません」とその場で言えたら、かっこよかっただろう。橘川さんの「参加型社会」は「今までとは違うもの」を目指したムーブメントだし、それを理解してるつもりだったから。
だけど、実際には、私は何も言えずポカンとしていた。
また、あたかもそうであったかのように「すぐに断りました」とここに書くこともできるだろう。
その方が、ここで読んでくれている人も、私を応援する気持ちになりやすいだろうか。
だけど、それは事実でない。私は、そんなに落ち着いた人でないのだ。
恥ずかしいけれど、本当のことを言う。
*
正直言って、私は、「大手からの出版」という言葉にすっかり煩悩を刺激されてしまっていた。ふわふわと地に足がつかなかった。
だって、私は、人に言えるような取り柄がない。人から何か特別とされることは今までなかった。
それが「大手出版から本を出す」って?
うまくいくかは誰も保証しないし、文体だとか内容を変えることを要求されるかもしれない。
だけど、、、
'ジミー’が、、。
平積みになったり、新聞の広告に出るの?
アニメ?
*
私は思うのだけど、作家と名乗れたらすごく嬉しい。人が私を見る目が変わるかもしれない、とは思う。だいたい、私は、いろんなことを上手にできなくて、「ちゃんとしてない」自分に劣等感があるのだ。
ただ、だとしても、「私が」作家となるかというのは、一番大事なことではない。私にとって、もっと嬉しいのは、'ジミー’がたくさんの人に「読みたい」と思われて手に取られること。
多くの人が、いろんなことを想いながら、夢中になってそのページをめくること。
表現するのを恐れていた私が、それでもどうしようもなく、書くことがやめられず筆を進めたものだ。
'ジミー’が広がるチャンスが、本当にあるとしたら...。
「大手出版社に紹介してください」と言えば、それが起こるかもしれない?そうしたら、本が、平積みにされる?
そこから何日も、ほわんほわんといろんなことを夢想した。
今思えば、この時の私は、橘川さんという人を、本当にはわかっていなかった。面白いアイデアを持ち、時代を見つめ、様々な活動をして影響力のある人だとは知っていた。
だけど、その内面は、まだ知らなかった。
出会っていなかった。

*
ふわふわとした気持ちで落ち着かず、数日後、私は「ロッキング・オンの時代」(橘川幸夫・著)を手にとった。以前に購入していたけれど、まだ読んでいなかったのだ。
ロッキング・オンができるまで、みたいな本かと気軽に読み始めたら、実は、一人の繊細な文学青年の話でぐんぐんと引き込まれた。
9章「ロックからのテイクオフ」で、岡崎京子の名前が出てきた。
橘川さんは、「思い出すと辛い気持ちになるので、あまり触らないようにしてきた」とnoteで書いているから、この本以外ではあまり扱っていないかもしれない。
*
「僕は、時代を生きる人が好きなんだ。
時代で有名になった人ではなく、有名になる前のかたまりだけの、無名の、普通の、時代の空気を吸い込んで、思いっきり吐き出そうとしている人が」と橘川さんはいう。
「ポンプ」に投稿していた頃の岡崎京子は、無名の高校生だった。授業中に描いたのだろうか、たくさんの絵を封筒に詰め編集部に送っていた。
橘川さんは、彼女の絵に「技術ではなく、自分の気持ちや石を、そのまま紙にぶつけたような、あふれかえるエネルギー」と「一目見て、すぐに京子の絵だと分かる個性」を感じた。
*
それからしばらくすぎて、90年代の岡崎京子はシンボリックな存在となっていた。人気マンガ家というだけでなく、多くの人の尊敬と憧れの対象で、その作品はすでに広範囲のアーティストに影響を与えていた。(もちろんその後もだ)
96年に不幸な事故が起こる。
それは、「京子が一番大事にしていた「絵を描く喜び」を奪ってしまった」と橘川さんは書く。
「90年代の岡崎京子のことは僕はあまり分からない。70年代後期の、可能性だけの時代の京子のことだけを思い出す」と彼は言う。
「可能性だけの時代の京子」とは、「自分の気持ちや石を、そのまま紙にぶつけたような、あふれかえるエネルギー」を、絵にして送ってきていた無名の女の子だ。
やみくもなエネルギーをそのまま絵にし、誰からも頼まれてもいないのに、お金になるわけでもないのに、やめられないように描き続ける「京子ちゃん」のこと。
「時代の空気を吸い込んで、思いっきり吐き出そうと」必死に絵を描いて封筒にまとめて送ってきていた、可能性に溢れるのびのびとした高校生の子。
その彼女の、一番大事にしていた「絵を描くこと」が、奪われた、と。
*
橘川さんは事故後の彼女ことを、こう記す。
「京子は、素晴らしい家族に囲まれて、元気に生きている。以前に訪問した時、テレビでボクシングの試合を観ていた。ワイルド」
橘川さんにとって、「京子ちゃん」は、表現に向かうやみくもなエネルギーの持ち主だった。その美しさにうたれていたのではないか。
だから「元気に生きている」と彼は言うのではないか。
それは、結局のところ「生きる」ことだから。
彼女が受けただろう、大きな心の痛みに思いを馳せながらも、それを越えて素晴らしい家族に囲まれ元気に生きる彼女の「生命」に目を向ける。
それは、エネルギーを持ち続ける彼女への尊敬であり、同時代を生きる「仲間」であるという認識でもあるだろう。
そして、生きるということへの畏怖。
同時代を生きさせているのは、「生命」だから。
「生命」
橘川さんは言う。
「生命はたくさんの素晴らしいものを与えてくれるが、時には、大切なものを奪い去ることもある。
でも生命がある限り、僕らは、一緒にこの時代を生きていくことが出来る。
僕らは、岡崎京子といつまでも、同時代を生きる」
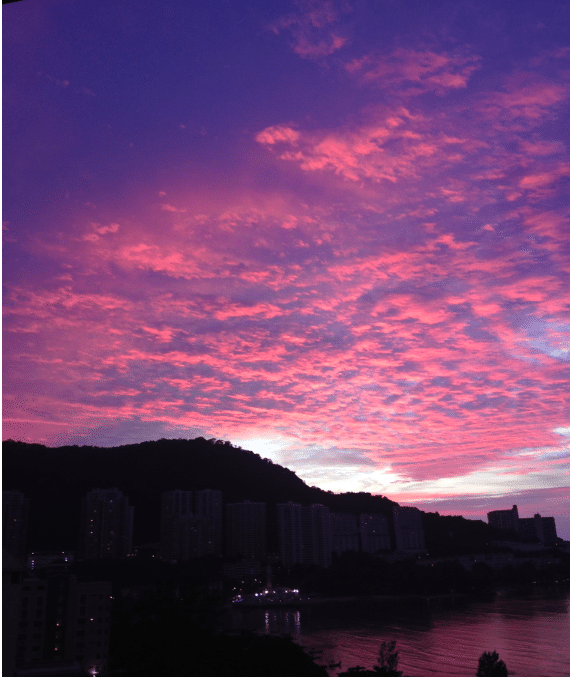
*
私は、目を閉じた。
高校生の「京子ちゃん」のこと。たくさんの人に影響を与え続ける岡崎京子が、同時代を生きていること。
そして、これを書いた橘川さんの想い。
出会うこと。
今という時間を共にすること、それは、生命に他ならないこと
私の受け取ったことが、本当に、橘川さんの想いなのかは分からない。だけど、私は、そう思った。
私は、橘川さんという人と、出会った。
*
「僕は、時代を生きる人が好きなんだ。
時代で有名になった人ではなく、有名になる前のかたまりだけの、無名の、普通の、時代の空気を吸い込んで、思いっきり吐き出そうとしている人が」
私は、本を膝に置き、息をつく。
そうだ。思いっきり吐き出そうとしている人は、私だ。
自分の想いを分かってくれる人がいるなんて、思っていなかった。そんな人がいると思わなかった。
私は、いつもいつも「表現」から逃げていた。何かを書きたいだなんて、みっともない。「何にもならないのに」と頭の中の自分が言っていた。
怖くて、できなかった。
だけど、いつだって、私は、思いっきり吐き出したかったのだ。
ずっとずっと、そうしたかったのだ。
表現することは、生きることだったと、今、思い出す。
私は、同時代を生きる。
怖がらずに、生きる。
<終わり>
ーーーー
「ロッキング・オンの時代」(橘川幸夫著)から多く引用しています
「生きるとは、捻じ曲げられたものを捻り返して真っ直ぐにすること」(「深呼吸する言葉」橘川幸夫)
いつもありがとうございます。いま、クンダリーニヨガのトライアルを無料でお受けしているのでよかったらご検討ください。
