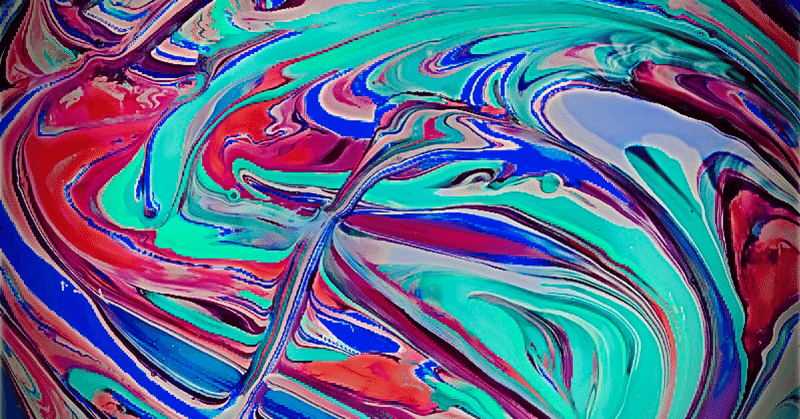
にがうりの人 #56 (禍々しい色)
子供は大人が思っている以上に残酷で狡猾である。成熟した理性が備わっていない分、コミュニティの中で時にそれが正義となり得るのだ。
何不自由ない生活の中で逃げ場を探す。それが私にとって「生きる」事になっていた。そしてその手段に自殺も考えるようになった。矛盾した行為だが、もはやそれくらいしか手立てが無かった。
追い詰められ、気がついた時には病院のベッドの上だった。どこで覚えたのか自室のドアノブにロープをかけ自殺を図ったと聞かされた時、まるでテレビのニュースを見ているような感覚に陥った。
✴︎
そうして私は不登校となった。受けていたイジメの代償は大きく、そして私の心と家族に深い爪痕を残した。
何も出来ない。とにかく幼い時分から「生きる」「死ぬ」という事について考えすぎていたのだろう。私はその存在を肯定する事も否定する事も拒否するようになっていた。
いわば思考停止である。
抜け出せない暗闇。その例えは稚拙でも安易でもなくその通りだった。希望や未来などは口にする事すら許されない漆黒の世界へ私は一人放り込まれたのだ。いや、今から思えば自ら飛び込んだのかもしれない。
最初のうちは両親も甲斐甲斐しく私を慰めていたが、いつまでも表情のない私を徐々に持て余すようになっていた。
しかし、時間はかかったがその暗闇も徐々に明るくなっていく。私は部屋の中で読む本や聴く音楽、観る映画などでいつしか忘却の波に飲まれ、顔色を戻していった。
とは言え、完全に傷が癒えるわけもなく、古傷は何かある度に悪夢を見せ、起きていてもフラッシュバックによるパニックを起こさせた。
私の人生はこの部屋で完結すると本気で思っていた。カウンセリングも受け、学校に行ける身体を養う試みもしたが、うまくはいかなかった。
どうにもならない自分の気持ちをちょうど運悪く巡ってきた反抗期も重なり私は母親にあたる事でなんとか立っていられた。母親にとってみればこの上なく悲しかったに違いない。
当時の私はとてつもなく卑屈で何の希望も持てなく、今思えばただ単純にそれを直視したくなかったのだろう。それはくだらないプライドであったり、身勝手な現実逃避によるものだったのかもしれない。
その頃に出会ったのが、担任教師の津田沼である。私が小学六年生の当時、両親は私の扱いに困り疲弊と諦めを繰り返す日々を送るしかなくなっていた。尽くしても尽くしても我が子の未来が見えないまるで無間地獄にもはや手を合わせて祈る事しか出来ないでいたのだ。
私は私で部屋に閉じこもり、ひたすら与えられたテレビゲームに噛りついていた。何かに夢中になっていないと、現実の世界に連れ戻されそうで心がぐらついていたのだ。
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
