
◆読書日記.《町田健『コトバの謎解き ソシュール入門』》
<2023年5月21日>
町田健『コトバの謎解き ソシュール入門』読了。
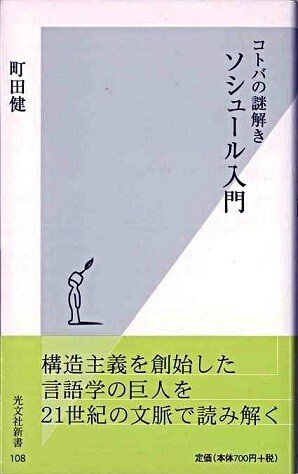
ソシュール学説やフランス語の研究を行う言語学者によるソシュール学説の入門書。
以前から言っているように、ぼくは自分の今年の課題書をソシュールの『一般言語学講義』と決めていて、現在はその準備段階として言語学の入門書やソシュール学説の入門書を呼んでいる所である。
前回までで言語学の入門書を2~3冊読んだ所で、次の段階としてソシュールの入門書を読もうと考え、その第一弾として手にしたのが本書という訳である。
しかし、内容については以前読んだで言語学の入門書(特に丸山圭三郎『言葉とは何か』)と被る部分が多かった。
例えば、どの言語学の入門書でも「言語学の通史」として説明されている「三つの段階」というのは、ソシュールが『一般言語学講義』で提示した言語学の歴史観の枠組みが、だいたいそのまま利用されている。
また、ソシュールが自分以前の言語学が扱ってきた内容を否定し、その考えを一新しなければならないとして提示した、言語学が新たに扱うべき対象として挙げているものについても、だいたいどの入門書でも同じように書いている。
また、そうやってソシュールが否定した過去の言語学にまつわる固定概念についても同じである。
ぼくが最近読んでいる言語学の本で実感したのは、ソシュールが単に「言語について考えた思想家」といったいち思想家ではなく、言語学の研究方法を一変させ、現代言語学の研究方法を決定づけた、その巨大な転換点に位置する重要な人物であるという事だった。
どの言語学の解説書についても、古典的な言語学が「近~現代言語学」に変わる際にはどうしても外して語る事の出来ないほどの存在として、ソシュールという人物がいるのである。
つまり、ソシュールを語るという事は、そのまま「近現代言語学はどうやって成立したのか」という事を語る事でもある。それほどの人物なのである。
それだけでなく、思想的にも「構造主義」の祖として西洋思想界に大きな影響を与え、「記号学」という一つの学問分野を成立させるきっかけとなる人物として、ソシュールという存在があるのだ。
ソシュールを学ぶという事は、近代言語学を学ぶと同時に西洋思想の一時代をも学ぶ事なのだ、という事が理解できる。そんな事を実感する読書体験であった。
◆◆◆
以前の記事でも説明して来た通り、近現代言語学は、研究対象としての言葉について「書き言葉」よりも「話し言葉」を重要視する。
それどころか「書き言葉」を重要視していた古典的言語学を否定する所から、ソシュールの言語学が始まったと言ってもいい。
「話し言葉」が言語学の研究対象になった事で、やっと言語学は学問としての「科学性」を手に入れる事ができたのだ――とまで言われるほどに現代言語学における「話し言葉」の重要性は明確になっている。
しかし、われわれは学校で「文法」を学ぶ時は、音声としての「話し言葉」の内容を学んでいるわけではない。
教科書に書かれている例文に対して主語はどこにあたり述語がどこにあたり……といった形で文章というものを学んでいく。
小学校でも、日本語の読み書きは、教科書に書かれた「文章」が対象になる。また、ノートにひらがなや漢字を書いていく事で、言葉というものを学んでいくのが学校教育の方法であっただろう。
このように考えてみれば、学校教育では一貫して「書き言葉」のほうを重要視しているとは言えないだろうか。
「日本語はどのように発音されているのか?」といった事を、一度でも学校教育で意識させられた事があるだろうか? ないだろう。
つまり、われわれはいつの間にか学校教育の方針によって、「言葉」については「書き言葉」のほうを重要視するという習慣を身につけさせられているのではないだろうか。
しかし「言語」というもののを本質を研究しなければならない言語学にとって、あくまで重要なのは「話し言葉」であって、「書き言葉」ではないのである。
だから、言語学の入門書を読み始めて最初に驚かされたのは、言語学を学ぶ際に「音声学」は必須であるという事であった。
音声学というのは言語の音声的手段を研究する言語学の一部門である。一部門といってもすべての言語はその表現手段として音声を用いているので非常に重要な一部門であり、筆者の考えでは言語の研究者がプロであるか、アマであるかのメルクマールが音声学の知識である。プロである限り音声学の知識は不可欠であり、アマであっても音声学の知識のあるなしで、言語研究の領域は狭くなってくるうえ、正しい理解のための一つの基盤が失われることになる。
いま地球上にある言語は1万種類ほどもあると言われていて、その中で現在も「文字」のない言語というのも非常に多くある。
そもそも、文字のない民族は多数あれど、発話でコミュニケーションしない民族はいないだろう。
本来「言語」というものは、文字でやりとりされるべきものではなかったのだ。――その実感を痛烈に感じていたのは初期のアメリカ言語学者たちであった。
欧州のヨーロッパ人たちにとって言語を研究する際、既に古代ギリシアの昔から文字を何かに書き記し、その中で文法を研究する方法が発生していた。
古代から現代に至るまでの豊富な文字資料の中にあって、学者らは安楽椅子に座ったまま言語について思索を巡らせていれば良いのであった。
金属板でも粘土板でもパピルスでも、書きつけられた「書き言葉」という、逃げも隠れもしない「コトバ」を見て研究すれば良かったのである。
しかし、新大陸へ移り住んだヨーロッパ人の学者たちにとって「言語を研究する」という事は、多くの種族が文字を持たない、言語とは本来「オト」なのであるという単純な事実に直面しなければならないという事であった。
アメリカの新大陸で土着の民俗を研究するという事は、まず何よりも彼らの使っている「オト」の解析をしなければならないという事だったのである。
そこに住んでいる種族の言語を理解しようにも、辞書も文献資料も翻訳文も研究資料も何もない。口から発せばすぐに空中に消えて行ってしまう不定形な「オト」だけ。
そこにあるのは、まったく聞きなれない異質な「オト」の世界だったのである。
細かい意志の通じない相手が口から発しているのは、自分たちが今まで全く接して来なかったコトバであり、聞きなれない発音であり、それはどこからどこまでが単語であり、どこからどこまでが一文を形成するのかも分からない、ただ漠然とした「オトの連なり」なのである。
そういう「オトの世界」に放り出されたアメリカの学者たちはおそらく「言語とは、そもそもオトであった」という事を痛烈に感じずにはいられなかった事だろう。
コトバは、まずは「オト」として、作られる。
「書き言葉」とは、既に「オト」として確立された言語を、どこかに定着させるために発明された、後発のものであったのだ。
たいていの場合、言語というものはまずコミュニケーションの場としての「話し言葉」を中心に作られて行くし、変化する場合も「話し言葉」を中心に変化していくものだ。
新たな言葉が出来る時は、コミュニケーション上でその新語が定着して来た後に、辞書や文献にその新語が現れてくる、という順序をとる。
だから「いま生きているコトバ」とは、日常人々が活発にやりとりしている会話としての「話し言葉」であり、それを研究しない事には言語の本質を考える事になはらないのではないか。
だから、「書き言葉」の分析ばかりを行う古典的言語学では、アメリカ言語学者らの研究の役には立たなかったのである。
言語学が研究対象としての言葉について「書き言葉」よりも「話し言葉」を重要視するのは、だいたいこのような理由があったわけである。
ソシュールが、自分の作り上げる「一般言語学」として、言葉の本質を研究する際に、まず真っ先に退けた「固定概念」が、「書き言葉」を重要視する古典的な「文法」研究であり「文献」研究であった理由も、そういった所にあったわけである。
(ちなみに現代は口から口へというコミュニケーションだけではなく、ネットや本で読んだ言葉が実際の会話に出るようになるといった、「書き言葉」が先に出来上がる新語というものも珍しくなくなってきたと思える。新技術時代の言語というものが、伝統的な言語とは条件が変わってきているという事なのかもしれない。しかし、「単語」レベルではそういう「書き言葉」先行の文化というものも登場してきてはいるものの、「言語=ラング」そのものが「書き言葉」主導で変化するという事は現代も起こっていない。「言語」というものは、あくまでその地域の人々が使っている「話し言葉」によって作られるものだからである)
◆◆◆
ソシュールの「一般言語学」では、言葉が固定された「紙の上のもの」だという考え方を否定し、それよりももっと曖昧で正体のなかなか分からないものであると教えている。
それは紙の上にも脳内にも各個として定着しているというものではなく、社会の中で人々の間でやりとりをされて初めてその実態が現れるもので、社会の各地で今なお刻々と変化を続けており、その認識は各個人によってバラバラである――という程のアヤフヤなものだというのが、言葉というものの本質である。
古典的言語学は、紙の上にある文字を追っていれば研究する事ができたからこそ、言語というものは確固とした不動の原理があって、それを研究すればいいのだという認識があったのである。
「書き言葉」で文法を論じる事ができるのも、それが「いま生きているコトバ」を対象にしているのではなく、過去どこかの紙の上に定着させられた「書き言葉」を対象としているからだし、紙の上に定着させられているからこそ、それが「固定的で不動の文法」であるという思い込みが生まれたのだろう。
ヨーロッパにかつて存在していた古典的言語学は、「紙の上の文字」を研究して、「書き言葉」メインで考えられていたからこそ、そういった固定概念が覆る事がなかったのである。
だが、そういった古典的言語学が教える「文法」というものは、ソシュールから言わせれば「規範学」であって、言語学が研究の対象とすべき「言語の本質」ではなかったのである。
ソシュールの考える言語とは、人間の認識システムそのものに大きく食い込んでいるものであり、それは「紙の上の言語」のみを研究していては出てこない発想であっただろう。
例えば、日本語で「青」とか「緑」とかっていう色彩の言葉を使う場合、我々は「どこからどこまでの範囲が"青"なのか?」という事を特別に意識しているわけではないと思う。
以前も言ったが「色」はグラデーションの中の「強度」であって、確固とした「青」という領域は決まっていないのである。論理的な区分けでも自然的な識別であるわけでもない。

では、われわれはどうして適度な「青さ」というものを理解しているのか?
「これはどちらかというと紫だ」や「ここまで行くと青というより水色だ」という「青」と「青以外の色」を区別して「青」という領域を判断しているのである。
ソシュールが「言葉は差異の体系だ」と言ったのはそういう意味でもある。そして、言語が人間の認識システムと関わっているという事の意味は、そういった部分にも現れているのである。
「青」単体で言葉の意味が成立している訳ではなく、その周囲にある関連した概念との差異の体系の中の各要素との関係性によって「青」という領域を判断しているのだ。
ここに例えば「藍色」という「青とは違う概念」がわれわれの生活の中で必要な考え方として入ってくると、この関係性は変化するのである。言葉は可変的なのだ。
この「青」というコトバと、実際われわれが「青い」と感じている色の領域との関係は「恣意的」なのである。根拠はない。時代や環境によって変化するのだ。
だから、厳密に言えば「blue」と「青」とは、完全なイコールではない。言語によって概念区分は変わる。コトバとは概念を区分するための思考ツールでもあるのだ。

例えば日本語で「川」を表す言葉はこれ以外にないが、フランス語では「海に注ぐ川」を「fleuve」と言い「川に注ぐ川」を「riviere」と言っているように、同じ「川」でも言語によって識別しているものは微妙に違っているのである。
ソシュールは「言語に先立つ概念はなく、言語が現れる以前は、何一つ明瞭に識別されない」と言っていたのだそうだ。
ある言語を理解するという事は、その言語を使っている人々の概念を含めて理解するという事でもあるのだ。

かくて、ソシュールの『一般言語学講義』によって、本来コトバというものの持っていた不定形な曖昧さというものがここでやっと認識され、以後現代言語学によって「言語の本質」という難解なテーマが追求されて行く事となるのである。
という事で、ソシュールの『一般言語学講義』ではそういった「言語の本質」にせまるソシュール思想を大いに学ばせてもらおうと思っている。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
