
シン・日曜美術館『ジブリの耳をすませば』~転~「自由画検定委員 中篇:雪渡り⑩」
前回はこちら
2019年 7月 フランス
アルザス地方 コルマール
RESTAURANT JAPONAIS NAGOYA
日本料理レストラン ナゴヤ

そして、鹿の子の歌に「西」と「北」があって「東」と「南」がない理由…
それは「東」が「イースト」であり…
「南」の中に「小さな羊」がいるから…

イースト? 小さな羊?
何のことだかサッパリわかりませんが、もしそれが理由だとしても、なぜ歌から除外されてしまうのでしょうか?

だよな。
しかも「鹿の子」とは何の関係もねえ。鹿と羊は全くの別物だ。

それでは解説しましょう。
賢治があの場所に「鹿の子」のシーンを入れ、「あの歌」を歌わせ、鹿の子をバカにした理由を。
もう一度、あの部分をよく読んでみてください…
何か気付きませんか?
そして三人は踊りながらだんだん林の中にはいって行きました。赤い封蝋細工のほおの木の芽が、風に吹かれてピッカリピッカリと光り、林の中の雪には藍色の木の影がいちめん網になって落ちて日光のあたる所には銀の百合が咲いたように見えました。
すると子狐紺三郎が云いました。
「鹿の子もよびましょうか。鹿の子はそりゃ笛がうまいんですよ。」
四郎とかん子とは手を叩いてよろこびました。そこで三人は一緒に叫びました。
「堅雪かんこ、凍み雪しんこ、鹿の子ぁ嫁ぃほしいほしい。」
すると向うで、
「北風ぴいぴい風三郎、西風どうどう又三郎」と細いいい声がしました。
狐の子の紺三郎がいかにもばかにしたように、口を尖らして云いました。
「あれは鹿の子です。あいつは臆病ですからとてもこっちへ来そうにありません。けれどもう一遍叫んでみましょうか。」

鹿の子の鳴き声「ぴいぴい」と「どうどう」も臭うな…

「ぴいぴい」といえば、長渕剛の『ろくなもんじゃねえ』でも連呼される。
何か意味が隠されていそうだ…

「ぴいぴい」と「どうどう」については、あまり深く考える必要はありません。
どちらも鹿の鳴き声の「擬音語」ですから。

確かに「ぴいぴい」と「どうどう」だ…
鹿って、こんな風に鳴くのか…

ふうむ。トリックのタネは鳴き声ではない…
どこに手掛かりがあるんだ?

こうすると、わかりやすいかもしれませんね。
そして三人は踊りながらだんだん林の中にはいって行きました。赤い封蝋細工のほおの木の芽が、風に吹かれてピッカリピッカリと光り、林の中の雪には藍色の木の影がいちめん網になって落ちて日光のあたる所には銀の百合が咲いたように見えました。
すると子狐紺三郎が云いました。
「鹿の子もよびましょうか。鹿の子はそりゃ笛がうまいんですよ。」
四郎とかん子とは手を叩いてよろこびました。そこで三人は一緒に叫びました。
「堅雪かんこ、凍み雪しんこ、鹿の子ぁ嫁ぃほしいほしい。」
すると向うで、
「北風ぴいぴい風三郎、西風どうどう又三郎」と細いいい声がしました。
狐の子の紺三郎がいかにもばかにしたように、口を尖らして云いました。
「あれは鹿の子です。あいつは臆病ですからとてもこっちへ来そうにありません。けれどもう一遍叫んでみましょうか。」

「踊りながら」「風に吹かれて」「鹿」「笛」「一遍」?
なんだこれは?

「風に吹かれて」といえば、ボブ・ディランだけど…
賢治の生きていた頃とは時代が違うしな…

「踊りながら」「風に吹かれて」「鹿」「笛」「一遍」…
これらが意味するものとは…
「南無阿弥陀仏」です。

なむあみだぶつ?

これですよ。


長渕剛のフィギュア?


この像は、京都の六波羅蜜寺(西光寺)にある有名な像…
運慶の弟子 康勝作の空也上人像です。

くうや? 何者なんだ?

空也は平安時代中期の僧で、日本における浄土教の祖とも呼ばれる人物。
難しい教義を理解したり戒律を守らなくても、ただ「南無阿弥陀仏」と唱えれていれば西方浄土に行けると説き、諸国を回って貧しい人々を救いました。
その際、みんなでダンスをしながら南無阿弥陀仏と歌う「踊念仏」をしていたとされています。

おどり念仏…
キーワードその1「踊りながら」か…

そして、空也の口から発せられた南無阿弥陀仏の神聖6文字は…
風に吹かれて6体の仏様になったといいます…


キーワードその2「風に吹かれて」…

空也は、笛の音のような鹿の鳴き声「ぴいぴい」を、こよなく愛していました…
そこからインスピレーションを受け、音楽に合わせてダンスする踊念仏を始めたとも言われています…
つまり、キーワードその4「笛」…

笛の音のような鹿の鳴き声が好きだった?
キーワードその3「鹿」も入ってるぞ!

ある日、空也が愛していた鹿が、漁師に殺されてしまいました…
空也は激しく悲しみ、その鹿の皮を衣にして生涯身につけ、その鹿の角を杖にして踊念仏の布教の旅へ出たのです…
キーワードその3「鹿」とは、まさに浄土教の祖 空也のこと。


そうだったのか…
では、最後のキーワード「一遍」とは?

「一遍」とは鎌倉時代中期の僧で、空也の踊念仏を300年ぶりにリバイバルさせた人物。
一遍による踊念仏ムーブメントはひとつの宗派を形成し「時宗」と呼ばれました。
「ときむね」ではなく「じしゅう」です。

「鹿の子」のパートに出て来るキーワードは、すべて「南無阿弥陀仏」に関することだ…
賢治は熱心な日蓮主義者で、日蓮同様に浄土教の「南無阿弥陀仏」を嫌っていた…
宮澤家の宗派を変えさせようと何度も父に折伏を試み、浄土真宗で行われた妹トシの葬儀にも出席しなかった…
だから「鹿の子」を馬鹿にするようなことを書いたのか…

『雨ニモマケズ』の最後お経部分にも「南無阿弥陀仏」は入っていませんからね。
ミンナニデクノボートヨバレ
ホメラレモセズ
クニモサレズ
サウイフモノニ
ワタシハナリタイ
南無無辺行菩薩
南無上行菩薩
南無多宝如来
南無妙法蓮華経
南無釈迦牟尼仏
南無浄行菩薩
南無安立行菩薩

もう間違いありませんね。
「鹿の子」が意味するのは、浄土教の「南無阿弥陀仏」で、間違いない。

しかし、なぜ「この場所」なんだ?
四郎とかん子がキツネの幻燈会に行くことが決まり、幻燈の題名が発表され、小狐紺三郎と別れて第一部終了でいいじゃないか。
なぜ読者が「幻燈会ってどんな風なんだろう?」とワクワクした後に「鹿の子」をディスって微妙な空気を作る必要がある?

そう言われてみれば、確かにそうだな…
なぜ賢治はここでこんなことをしようと思ったんだろう?

それを読み解く鍵が「鹿の子」という言葉と「西北があって東南がない」という謎かけなのです。
賢治にとって、どうしてもこの場面は必要だった。
しかもそれは「幻燈会の夜」になる前、日没前でなければならない。
しかし第二部は、日没して「幻燈会の夜」になったところから始まる。
だから、ここしかなかったのです。

どういうことだ?

♬その頃も賢治を支えてたのは、やはりこの曲だった♬

は? この曲って何の曲だ?

決まってるでしょう。
心のベストテン第一位、福音の曲「ルカ」ですよ。

ルカによる福音書?
しかしイエス・キリストの物語に「鹿の子」は出て来ないだろう?

ええ。『ルカによる福音書』に「鹿の子」は出て来ません。
だから『雪渡り』の「鹿の子」も、離れたところにいたままで、目の前には来てくれなかったのです。
聞こえてくるのは「東」と「南」が除けられた、鹿の子の「歌」だけ…
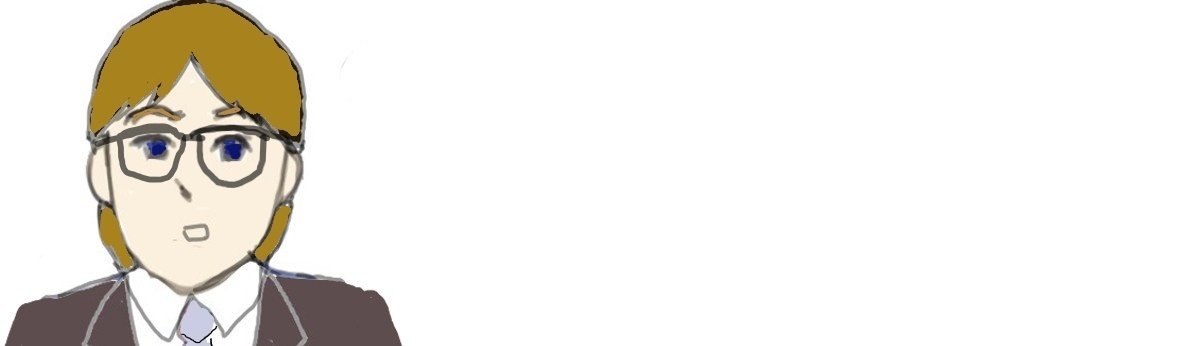
「東」は「イースト」…
「南」の中には「小さな羊」…
もしかして、鹿の子の歌に「東」と「南」が無かった理由とは…
除酵祭、過越しの祭り…

はァ? いったいなぜだよ?

除酵祭で除かれる酵母菌は、英語で yeast(イースト)…
つまり「東」を意味する east(イースト)との駄洒落だ…

イースト(yeast)とイースト(east)の駄洒落?

♬イースねー、なんてね♬

じゃあ「南」が無い理由は?

除酵祭(過越し)では、小羊が生贄として屠られ、食べられてしまう…
だから字の中に「小さな羊」がある「南」は無かった…

『Agnus Dei(神の仔羊)』
Francisco de Zurbarán(フランシスコ・デ・スルバラン)

ブラボー!

バウバウッ!バウバウッ!

その通りです、Jean-Paul O'Cahiermont(ジャン=ポール・オカエモン)。
賢治が読んでいたと思われる聖書『イイススハリストスの新約』の、ルカに因る福音書…
除酵節の本番の夜がくる前の場面を描いた第二二章冒頭ですね。
第二二章
一 除酵節 即 逾越と名づくる節は近づけり。
二 司祭諸長と學士等とは如何にイイススを殺さんと謀れり、蓋 民を畏れたり。
三 時にサタナは十二の一なるイウダ、稱してイスカリオトと云ふ者に入れり。
四 彼 往きて、司祭諸長及び庶司と共に、如何にイイススを彼等に付さんことを語れり。
五 彼等 喜びて、銀を彼に與へんことを約したれば、
六 彼 諾ひて、民の在らざる時にイイススを彼等に付さん爲に、好き機を窺へり。
七 徐酵日 即 逾越節の羔を宰るべき日 至れり。

イースト(東)は除かれ、小さな羊(南)は屠られる…
だから鹿の子の歌に「東」と「南」は無かった…

そして「ルカに因る福音書」第22章はこう続きます。
八 イイススはペトル及びイオアンを遣して曰へり、往きて、我等が食せん爲に逾越節筵を備へよ。
九 彼等 曰へり、何處に之を備へんことを欲するか。
一〇 彼は之に謂へり、視よ、爾等が城に入る時、水を盛れる瓶を攜ふる人 爾等に遇はん、之に随ひて、其 入る所の家に入りて、

口語訳では、こうですね。
8 イエスはペテロとヨハネとを使いに出して言われた、「行って、過越の食事ができるように準備をしなさい」。
9 彼らは言った、「どこに準備をしたらよいのですか」。
10 イエスは言われた、「市内に入ったら、水がめを持っている男に出会うであろう。その人が入る家までついて行って、

水瓶?
一年で最も寒い時期、1月下旬から2月中旬の「みずがめ座」だ!


そしてルカはこう続きます。
あの場面で賢治が、浄土教の象徴として「鹿の子」を登場させた理由は、この部分を再現するためだったのです。
一一 家の主に語げよ、師 爾に謂ふ、我が門徒と偕に逾越節筵を食すべき室は何處に在るかと。
一二 彼 爾等に敷き飾りたる大いなる楼を示さん、彼處に備へよ。
一三 彼等 往きて、其 言ひし若き事に遇ひて、逾越節筵を備へたり。

門徒?
門徒とは「南無阿弥陀仏」を唱える浄土教の信徒のことだったよな?
なぜ日本の聖書には門徒なんて言葉が出て来るんだ?

「門徒」とは、読んで字のごとく、本来の意味は「一門の徒」…
しかしいつの頃からか日本では、浄土教の信徒を指す言葉になりました…
おそらく賢治は、この日本正教会訳の聖書を読んで、信徒を指す訳語に「門徒」が使われていて、少し違和感を覚えたのかもしれません…

なるほど。そういうことだったのか…

そして賢治は、この部分から「鹿の子」を連想した…
まず「門徒」という言葉に注目し…
その後に出て来る「飾りたる大いなる楼(たかどの)」でイメージが膨らみ…
あの「鹿の子」が想起されたのです…

なぜ「飾りたる大いなる楼(たかどの)」から「鹿の子」が導き出されるのでしょう?

「飾りたる大いなる楼」とは「宴の席が設けられた二階の座敷・広間」という意味…
様々な歌曲に詳しい賢治は、そこから「鹿の子」を連想したのですね…
ちなみにこちらが口語訳です。
11 その家の主人に言いなさい、『弟子たちと一緒に過越の食事をする座敷はどこか、と先生が言っておられます』。
12 すると、その主人は席の整えられた二階の広間を見せてくれるから、そこに用意をしなさい」。
13 弟子たちは出て行ってみると、イエスが言われたとおりであったので、過越の食事の用意をした。

様々な歌曲? ルカに因る福音書の他にも、まだ音楽が関係するのか?

そうです。では解説しましょう…
à suivre
つ づ く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
