
225.「時」の歩みは三重である。
1.さて、どう生きていけばいいのか?
「やれやれ、オレはこれからどう生きればいいのだろうか。」
昭和47年の暑い夏、どん底っていうのはこんなことなのかもしれない。
手塚は苦しみながら考えていた。
「三島由紀夫は、死ぬ直前になにを思っていたのだろうか?川端さんは、あの死の部屋でなにを捨て、なにを得たのだろうか?」
ノーベル賞作家川端康成が、ガス管を口にくわえて自殺したのは1972年(昭和46年)丁度1年前の4月16日の夜。
手塚治虫、46歳。当時でいえば4億ぐらいの負債をかかえ、虫プロは手形の不渡りを起こし倒産した。
その日の夕刊には、「虫プロ商事倒産、手塚治虫行方不明」と大きく報じられ、さらに「鉄腕アトム遂にダウン、十万馬力は消えた」とも書かれていた。
「こうしてすべてを失い、ぼくのアニメに懸ける夢もついに去った」これからどうしたらいいのか、どう生きればいいのだろうか、残されたモノは多額の負債のみ。
この日を境に、マスコミや友人、取引先を含め、手塚治虫の順風満帆の頃にはまったく考えられない冷酷な現実が待ち受けていた。
人間愛、ヒューマニズムといわれてきた手塚治虫。
世間の眼や反応はきびしい。
手塚の大きな失敗は、アニメ映画にあるといわれていた。また資金繰りが大変になると、銀行以外の金融などでも手形を割引いたりしていた。
そして、数多くの債権者が手塚の前に立ちはだかってきたのである。
そこでふと、三島由紀夫や川端康成の死を思いだしていた。
現在の日本はアメリカなどとは異なり、倒産した人間に対する敗者復活制度というものはない。
それは、どの会社も借入に依存しなければ事業ができないという仕組みにも問題がある。
どんな会社にも必ず借入金があり、返済がある。
そして、その借入金に対しては、必ず個人保証が要求されてしまう仕組みがあり、これがアメリカにはない、日本の経済の特質ともいわれているもの。
つまり、会社が倒産すれば、個人保証している限り、個人の預金や資産(住居)はすべて差し出さねばならない。
そのために、今まで何十年もかかって築き上げてきたものすべてが一瞬に失われてしまう仕組みとなっている。
手塚治虫の大きな功績は、1963年1月1日に日本最初のテレビアニメ「鉄腕アトム」の放映にはじまり、最高視聴率は40.3%を記録したほどの大ヒットとなった。
しかし現実は、アニメ制作費を極端に安くしてテレビ局に売り込むことによって、当時から資金的に苦しみが生まれていた。現実の制作費は250万円かかるのに、手塚側は1本75万円で引き受けたからである。
それでは不足分をどうするかという部分が残るが、手塚は当時自信もあった。それはマンガで稼げばいいといった判断だった。
しかし当時もそれで解決はしていなかったが、その難問が思いもかけない現象によって救われるのである。
それは、アニメキャラクターの商品化(マーチャンダイジング)だ。これによって日本中にアトム・グッズが氾濫した。
有名な商品は、当時スポンサーだった明治製菓の「マーブルチョコレート」の空き箱でアトムシールがもらえるというもの。
虫プロの版権部は、手塚の全作品の著作物の版権を管理し、そのもとに大小50社の企業が「アトム会」を結成し、手塚キャラクターの商品化を行っていた。
1965年頃の版権収入だけで年間収入が3億円。アニメの不足分はかなりの部分をキャラクター商品などの著作権収入で支えていたことになる。
手塚の大きな功績は、マンガの著作権が確認されたこと、日本の版権ビジネスの歴史のなかでは、とても大きな意味のあることだった。
そして、さらに手塚は映画産業に次々と手を染めていくが…。
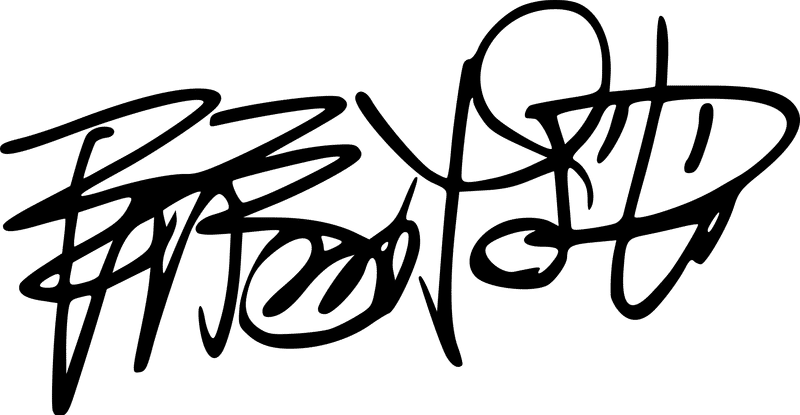
2.こどもたちに心から愛をもって接する
「さて、どう生きようか。どうしたらいい…。」
そんな時、育児器具で取引していた関西の業者、債権者のひとりでもあるが、手塚の前にある男が現れた。
「先生はマンガ家に戻りなはれ、あなたは事業家ではおまへん。こどもたちがみんな待っている。こどもたちのためによい作品を描く、それが先生の本業でしょう。金、金、銭、銭と思わずに、先生の場合には、無から生み出せる。先生には限りないアイデアがあるのと違いまっか。アトムをはじめ、無形の財産があれだけある。あれの活用次第で、何度でも、何度でも立ち直れるでしょう。先生はすっからかんだというが、あの財産とこの体験と経験は忘れずに大事にしなはれ」
手塚はこの男の言葉によって我にかえった。
確かに借金は4億ぐらい残っている。それに、わたしにはまだまだ描きたいアイデアがたくさんある、こどもたちが待っている。
この言葉が手塚の胸にズッシリと重く響く。
人は苦しくなると、金、金、金。
そして自己本意になり、他人の言葉に耳を貸すことができなくなり、自分が見えなくなってしまう。
「そうだ、もっともっとこどもたちのことを考えていかねばならなかった。自分の欲望ばかりに目を向け、結果、多くの人たちを傷つけてしまっていた…」

3.漫画家手塚治虫の人生哲学
さらに関西のその男は、
「・・・・なによりも人に誠意を尽くす。他人のために精一杯尽くせば、どんな不祥事でも必ず納得してもらえる。人のために尽くすことは、いつか自分に必ず返ってくることです。人はみんな、50%の利己心をもっておって、それが1〜2%でも大きい人は結局、人に嫌われます。世の中で一番よくないのは、なんでも自分のためにちゅうことばかりを考えとる人です。こんな人は死ぬとき、きっとさみしいやろ思いますなあ。あべこべに50%の中のわずかでも人のためという気持があれば、それだけ人に好かれるし、もっと大きければ、それだけ尊敬を受けます。するといつかほかの人から恩恵を受けるんです・・・・・。」
手塚はふと思った。
今までの44年間、マンガの市民権を得るための活動。
より多くのこどもたちに読んで欲しい、わかってもらいたい、知ってもらいたい。マンガは俗悪なモノではなく、素晴らしいもので芸術に匹敵するほどのもの。そんな願いから次々とヒット作を世に出してきた。
しかし、失ってきたものは一体何だったのだろう。
それは一番大切な自分の家族たちとの思い出…。
考えてみれば、今まで振り返る時もあまりなかった。いつのまにか3人のこどもたちも大きくなっている。
もう、その失った時間すら取りもどすことはできない。
残されたものは、家族の不安と心配。そして4億円という負債だけ。もう物理的にも不可能に近い、さて、どうしょう。
4.赤ちゃんを拝みなさい!
「先生、赤ん坊というのは口がきけません。なにか親が買い与えても、本人がそれについて何もいう術はありません。だからこそ、親でも、業者でも、口のきけん赤ん坊のかわりになって徹底的に吟味した最高のものを与えんといけません。育児商品でも、赤ん坊の体格や機能だけやなく、心理、情緒、すべての点から専門家が研究して最善を尽くさなあきません。たとえば色彩ひとつとってもそうです・・・」
「私は、赤ちゃんを拝むことをやりなさいと、みんなに薦めておるんです。神様に拝むことよりも、赤ちゃんは一番神様に近い生きものです。その赤ちゃんを一日に一回拝むことによって、深い愛情が生まれて家庭が幸福になります。赤ちゃんにとっても拝まれることはよいことやないですか・・・・・」
手塚はこの時、この男の言っている意味があまりわからなかったという。
しかし、もしかすると失った時間、失ったもののすべて、本当は何も失っていなかったのではないかと思うようになってきた。
もしかすると、もう一度、いや何度でも人生はやり直せるものかもしれないという、わずかながらの希望が湧いてくる気がした。
関西のこの紳士は、鉄腕アトム商品が全盛の頃、アトムの顔のついた育児器具で取引していた業者で、債権者のひとり葛西健蔵という人物だった。葛西氏は立志伝中の人でもあり、戦後、独立独歩、徒手空奉でこの業界に参入、その信念と努力によって、育児業界の国際的メーカー「アップリカ」の創業者となった人物であった。彼の人生哲学は、「こどもたちに対して心からの愛をもって接する」ということだった。
そして葛西氏は、自分自身が債権者にもかかわらず、先頭に立って手塚の整理の指示を始めるのである。
「先生、早くマンガ家に戻りなはれ、こどもたちが待っている。もう事業はやめて本業に徹し、よい作品をこどもたちに・・・・・」
こうして、手塚の第2の人生が始まった。失ったものはあまりにも大きかった。しかし、この葛西氏の助言によって、もう一度生き直してみよう、もう一度やり直してみよう、何度でも、何度でもチャレンジしてみようと考えた。

5.新しい自己
手塚の新しい自己がこうして生まれた。
のちに、手塚は虫プロ倒産の頃を回顧してこう語った。
「虫プロが倒産をして、私は物質的にすっからかんになってしまったけれど、精神的に得たものは極めて大きかった。それまで自己中心的な世界に安住して、その視野から世間をのぞけなかった私にとって、この試練はあらゆる立場の人々のナマの人間像と接する体験を与えてくれた。
私のまわりの人たちだけでも、そこに利害関係や信頼関係を含め、実にさまざまな人間性をもっていることを知った。依存していた人に見事に裏切られ、反対にほとんど無縁と思われていた人が献身的に協力してくれたり、励ましてくれたりした。それらは私の人生勉強の大きな糧となった。」
その後手塚は、この体験や経験を自らの財産として、次々と新作を発表。『MW(ムウ)』(ビックコミック)『ばるぼら』(ビックコミック)『ブラックジャック』(少年チャンピオン)『三つ目がとおる』(少年マガジン)そして、『火の鳥』『ブッタ』(希望の友)『シュマリ』(ビックコミック)『陽だまりの樹』『アドルフに告ぐ』(ビックコミック)等は、手塚の晩年の傑作といわれる。そして・・・・・
1973年:虫プロ商事倒産、手塚四十六歳。
1975年:『ブッタ』『動物つれづれ草』で文春漫画賞受賞。
1977年:『三つ目がとおる』『ブラックジャック』で講談社漫画賞受賞。
この年六月から講談社で壮挙ともいうべき手塚治虫漫画全集300巻の発行が決定。
1979年:児童マンガの開拓により巌谷小波賞受賞。
1980年:国際交流基金のマンガ大使として渡米。国連などで日本のマンガ文化について講演。
1983年:『鉄腕アトム』の創造で日本文化デザイン賞受賞。
『手塚治虫40年展』開催。
1984年:『陽だまりの樹』で小学館漫画賞受賞。実験アニメ『ジャンピング』でザグレブ国際アニメーション映画祭グランプリ受賞。ユネスコ賞受賞。1985年:実験アニメ『おんぼろフィルム』で第一回広島国際アニメーション映画祭グランプリ受賞。東京都民栄誉賞受賞
1986年:『アドルフに告ぐ』で講談社漫画賞受賞
1988年:戦後マンガやアニメの創造的業績に対して『朝日賞』受賞
1989年2月9日午前10時50分、胃ガンのため、東京都千代田区の半蔵門病院で、日本のストーリー漫画とテレビアニメの創始者、著作権のキャラクタービジネスのきっかけを作った漫画家、手塚治虫(てづか・おさむ、本名治)は死去した。
丁度、昭和天皇の死去のあとに続き手塚は亡くなった。

6.「時」の歩みは三重である。
手塚は、中学生から60歳で死ぬまで描いた枚数が15万枚という生産能力をもった知的職人ともいわれている。
虫プロ商事が倒産したのは手塚が46歳の頃、わずか2年後に復活をとげるのです。そして14年間という歳月を費やして、手塚の人生はこの時期に本当の意味で開花した。
手塚は亡くなる寸前まで、次のアイデアを黙々と考え、ペンがもてなくなっても、その手は休むことなく、空をキャンパスに最後の最後まで描き続けていた。
「神よ、あと少し、あともう少し時間を与えてくれ、そうすればもっと良い作品が生まれる・・・・・」
「もう少し、もう少し・・・・・」

coucouさんはこの日、強いショックを感じる中で、この時に昭和は終わったような気がしている。
生前2度だけ手塚治虫さんにお会いしたことがある。倒産後だったが、静かに、じっと、わたしの目を見つめながら語りかけてくれた、あたたかな優しいその目は今でも忘れられない。
丁度、本年の4月で鉄腕アトムが生まれてから71年目。アトムという著作物は、自らの意志(ストーリー)をもち、死後70年(現在手塚治虫さん死後33年目)という著作権の保護期間をもって生き続けています。
手塚さんの好きな言葉にこんな文がある。
「時」の歩みは三重である。
未来はためらいつつ近づき、
現在は矢のようにはやく飛びさり、
過去は永久に静かに立っている。 (シラー)

coucouさんです。みなさん、ごきげんよう!
coucouさんは手塚治虫さんの影響を物凄く受けて生きてきました。
子どもの頃の長い病院生活で、父から与えられた鉄腕アトムから始まり女の子の雑誌に連載されていたリボンの騎士からほとんどの本を読みあさりました。
coucouさんの世界は1800センチの長さと、900センチの小さなベッドの世界。そこからは、はみ出してはいけないし、歩いてはならない、絶対安静の数年間でした。
病院生活ですから父や母はいつもいません。
でも、一切寂しくはありませんでした。
それでも、そこには手塚治虫さんの世界があったからです。
やがて、数十年と過ぎた今でも、coucouさんの心のバイブルです。
coucouさんのあこがれの手塚治虫さんとは病院から退院し、中学生となり父に連れられて会うことができました。
その後は、虫プロ倒産後に会うことができました。
幼い頃と、やや大人になったcoucouさんの手を握り、分厚い眼鏡のため、目玉だけがとても大きい、宇宙人のような、それでいてとても優しい眼差しの前でcoucouさんの前身は硬直して固まってしまいました。
新聞やテレビで会社の倒産を知ったとき、手塚治虫さんが亡くなったときcoucouさんは生きる希望を失うくらいのショックでしばらく硬直したままでした。毎日が悲しくて、大げさに聞こえるかもしませんが生きる希望を失ったのです。
coucouさんはそんな中で手塚治虫さんの本を読み続けることにしました。
だって、これしか残されていないからです。
手塚治虫さんのすべてをもう一度読み終えるまで、数年の年月が過ぎ去りました…。
そして、次の言葉を手塚治虫さんは残しました。
言葉って、人の人生を変えたり、人を救う場合だってあるのですね。
ここからはcoucouさんの勝手なおまけ。
お時間のあるときにお読みください。
では、またあしたね!
ここまでのおつきあいに感謝しています。
7.手塚治虫さんの残した言葉
①人を信じよ、しかし、その百倍も自らを信じよ。
②人間は何万年も、あした生きるために今日を生きてきた。
③人生は一人じゃない。
二人三脚で走らねばならんこともある。
④物語はここから始まるのだ。
⑤好奇心というのは道草でもあるわけです。
確かに時間の無駄ですが、必ず自分の糧になる。
⑥最後まで努力をするってのが、本当の生き甲斐ではないでしょうか。
⑦数えきれないほど、悔しい思いをしてきたけれどその度にお袋の「我慢しなさい」って言葉を思い浮かべて、なんとか笑ってきたんです。
⑧医者は生活の安定を約束していた。
しかし、僕は画が描きたかったのだ。
⑨一攫千金は偽りの成功。
真の人生の勝負は、じっくり腰を落ち着かせてかかるべきだ。
⑩インプットがないのに、アウトプットは出来ません。
⑪人の後をついていたら安全というのは、この世界じゃ通りません。
⑫ぼくたちは、かけがえのない地球に「同乗」している、仲間です。
⑬終始一貫して僕が自分の漫画の中で描こうとしてきたのは、次の大きな主張です。「命を大事にしよう!」
⑭後世に残る作品をなどと気張らず、百歳まで描きたい。
⑮今ここで自分が描かなければ誰が描くんだろう。
⑯人の命なんて、心配してもしなくても、終わる時には無情に終わるもの。
⑰合理化はゆとりや遊びの空間を消して、むしろ人を遠ざけることになります。
⑱人間の「善」が、常に「悪」よりも先んじてほしいものです。
⑲仮病は、この世でいちばん重い病気だよ。
⑳君たち、漫画から漫画の勉強するのはやめなさい。
一流の映画をみろ、一流の音楽を聞け、一流の芝居を見ろ、一流の本を読め。そして、それから自分の世界を作れ。
㉑40年間負けん気でもってたみたいなもんです。
逆に言うと、劣等感や怯えがあったから、続いたともいえるんですね。
㉒日本の明日を担う子供達に、こんなものを読ませるのですか?
㉓「ダメな子」とか、「わるい子」なんて子どもは、ひとりだっていないのです。もし、そんなレッテルのついた子どもがいるとしたら、それはもう、その子たちをそんなふうに見ることしかできない大人たちの精神が貧しいのだ。
㉔子どもに殺しを教えることだけはごめんだ。
世界中の子どもが正義だといって殺しを教えられたら、いつか世界中の人間は全滅するだろうな。
㉕反戦だの平和だのの政治的なお題目では、子供はついてこない。率先して生命の尊厳から教えていく姿勢が大事。
㉖現代の教育は、どこか衰弱しているというか、勘違いでもしているようだ。
㉗時代は移り変わっても、子供たちの本質は変わらない。
㉘子供は、その時点時点で常に現代人であり、また、未来人でもある。
㉙自然への畏怖をなくし、傲慢になった人類には必ずしっぺ返しが来る。
㉚人間は、生きている間に、なぜもっと素晴らしい人生を送らないのかなぁ。
素晴らしい満足しきった人生を送れば、死ぬ時にそんなに苦しまなくたっていいんだろうなぁ。
㉛仕事に強い信念と情熱を長く持ち続けられる女性。
しかも世の中すべてに、やさしい愛を注げる心の広い女性…。
それをぼくは望みます。
㉜僕の体験から言えることは、好きなことで、絶対にあきないものをひとつ、続けて欲しいということです。
※coucouさんの電子書籍のご案内「~夢追い人~「贈り人2.」全2巻好評発売中!下記URLにて検索してください。
人生を楽しく明るく!幸せになるための文章。著書 https://www.amazon.co.jp/s?i=digital-text&rh=p_27%3ACou+cou&s=relevancerank&text=Cou+cou&ref=dp_byline_sr_ebooks_1

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
