
430.noteと言う世界㉕noteを心から楽しんでいる人と、苦労しながらnoteしている人。【後編】

1.note雑感「楽しみながらnoteする」
noteの面白さ、楽しさは、そのクリエイターさんが「面白がっているか?」「楽しんでいるか?」に分かれているように見受けられます。
やはり、楽しんでいる人はそのnoteに独自のリズムがあり、楽しんでいるということが読む側にも伝わる気がします。
リズム感のある人は、楽しそうです。
どうしても、毎日投稿しなければいけないとか?
ネタに苦しいとか?
noteがただのつぶやきで意味不明な人たちもいます。
ただのつぶやきならばXやフェイスブックで良いと思うのですが、noteの場合は似合わない気がします。
例えば、詩や俳句、短歌などの短文にはそれぞれの深い意味がありますが、ただの「つぶやき」はnoteの作品、表現とは思えない気がするのです。(つぶやきでも、わかりやすい、伝わりやすいのは良いですよね)
やはり、noteのクリエイターさんたちの目的は「読んでもらいたい」「見てもらいたい」「伝えたい」「表現したい」というのがクリエイターさんたちの本来の姿のように思えるからです。
ただし、そのつぶやきでも作品としての否定はしていません。
それぞれの考え方があってnoteをしているわけですから。
しかし、楽しんでnoteしているかと言うと本人は楽しくても、読む人にはつまらない、楽しくないと思う気がします。
やはり、noteはクリエイターさんたちの表現の場ですから、楽しい作品の方が素晴らしく思うのです。
また、楽しさ以外に「学べる」「知らないことを知る」こともできる素晴らしさもあります。
むずかしい専門的な文よりも、わかりやすい言葉は、わかりやすい。
わかりにくい難しい文はやはりわかりにくい気がしています。
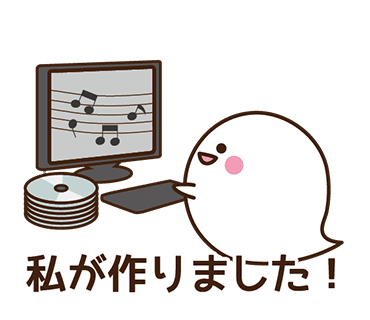
2.note雑感「苦しみながらnoteする」
様々なnoteを見ていると、勝手に私が思ってしまっているのかわかりませんが、苦しそうなnote作品も見かけます。
苦しいというのはそのnoteの作者が楽しんでいない、リズムを感じられない作品です。
おそらく時間をかけて1回、1回の作品に全力を傾けているのかもしれませんが、毎回、違うジャンルを取り上げています。
これもその方のリズムの場合は否定はありません。
ただ、毎回違うジャンルだと、せつかくの作者の意図が感じられなくなる場合があるからです。
別にnoteの中で「ネタがない...」とか、「ネタはこうして見つける...」なんて無理してネタ探しなど必要ない気がするからです。
これがビジネスであれば有料ですから読者の求めるネタ探しは必要だと思いますが、楽しみながらnoteする場合は、まず自分が楽しんで、その楽しみが読者の楽しみになったり、学べたらこんなに素敵なことはありません、
人はみんな違う考えを持って生きているわけなのですから、今の自分のそのままを表現するだけで他のnoteとは違いが必ず出る気がします。
noteは毎日続ければ良いことではありませんし、長ければよい訳でも、短い文だから駄目なものではありませんが、せめて作者のオリジナル、独自性に作品のリズム感が現れる気がします。

3.note雑感「無理しないnote」
無理しないnoteづくり、それが一番の楽しみ方かもしれません。
例えば、毎週1作品、月に1作品の人もいます。
私のように周3回と決めている人もいます。
私の場合は毎日noteに向かっている時間がないために仕事の合間をくぐって周3回と決めてnoteしています。そのため、コメントのご返事はいつも遅くなりそのことは少し胸が痛いため、すぐにコメントができない旨をお知らせしています。(申し訳ないと思います…)
しかし、おそらくほどんどの方が仕事しているか、何かしらをしている人たちが多いはずですから、その自分のペース、マイペースでできることが楽しみになるはずです。
もちろん、週2回でもおかしくはありません。
ただ、困るのはまるっきりの不定期の場合です。
数か月に1回ペースの方もおりますが、フォローしてあっても探すのに苦労してしまいます。
しかし、「無理してnote」している人たちの作品は、おそらくどなたが見てもわかる気がします。
noteにはこうあるべき、こうしなければならないなどというルールはありませんし、自由な表現の場なのですから義務などありませんし、責任感を感ずる必要もありません。
ただ、人気のある方はフアンが多いので、みなさんがその方の作品を待ち望んでいる場合は、クリエイターさん自身でも感じているはずです。
しかし、それでも無理せずに自分のペースで良いと思うのです。
なかには、毎回楽しそうな投稿をしている人もたくさんお見掛けします。
もう、note命というわけではありませんが、noteなしでは生きれない人たちのことです。
とても羨ましい限りです。
やりすぎ、依存し過ぎも身体を壊す場合もありますから、それは自分の身体とよく相談の上noteを続けてほしいと思います。そうしないと、続かないからです。

4.note雑感「楽しんでnoteをする人の特徴」
楽しみながらnoteをしている人たちを見かけると、noteするのが楽しそうに見えます。このnoteの世界を大切にしている人たちです。
その人たちには「感動」「満足感」「充実感」「達成感」なによりも「幸せ感」があるように思えます。
人生でこれだけ楽しめるものがあるというのは幸せなことです。
すると、読む側にも「感動」や「満足感」「幸せ感」をお裾分けしていただいているように思えることです。
これがビジネス、有利用の世界ですと、売れなければなりませんし、売るためのことばかりを考えるのが正義ですから、自由さを失う気がします。(有名作家さんは違うと思いますが)
そうです。
楽しんでnoteをしていますか?
もっと、楽しんでnoteをしてみませんか?
それをわけてください。
👇さて、何といってもnoteを語る上での「note哲学」の千世さんからは随分と学ばせていただいています。特に自分の考え、ブレない姿勢、noteに対する真摯な受け止めや考え方にはいつも共鳴してしまいます。無理しない、noteを楽しむ。マートは義務じゃあない、自由な世界なんだよ、と語り続けています。「向き合い方を変えみたら、自分のnoteが見えてくる」、まさにその通りです。自分だけの世界に浸ってしまうと自分を客観的に見ることがむずかしくなります。でも、自分にとってnoteって何だろう?そんな問いかけもあります。
👇ぜひ読んでいただきたい素敵なnoteのための作品です。
👇noteに関する「私のnote談義」がここにまとめられています。
👇これは千世さんのエッセイストとしての集大成、まさに過去から未来を見つめる「歴史探訪」の世界です。

ラインスタンプ新作登場~
第8章「noteという世界」シリーズを少しずつ始めましたのでどうかお読みください。
また、日々、拘束されている仕事のため、また出張も多く、せっかくいただいているコメントのご返事。お問い合わせメール、お手紙等のお返事がかなり遅れています。しかし、必ず読ませていただいて、翌週には必ずご返事させていただいていますのでどうかお許しください。
では、また(月)(水)(金)にお会いいたしましょう。
いつも読んでいただいて心から感謝申し上げます。
感動CM 日本人が失ないつつある心を思い出させてくれる海外のCMドラマ作品
[韓国のCM]感動!~誰しも忘れたくない瞬間がある~
※本内容は、シリーズ第8章「noteの世界」というテーマで著作権等を交えて解説、感想及びnoteの素晴らしさをお伝えしていく予定です。
私たちの著作権協会は市民を中心としたボランティア団体です。主な活動は出版と講演会活動を中心として全国の都道府県、市町村の「著作権・肖像権・SNS等を中心」にお伝えし続けています。皆様から頂いた問題点や質問事項そのものが全国で困っている問題でもあり、現場の声、現場の問題点をテーマに取り上げて活動しています。
それらのテーマの一部がこのnoteにしているものです。ぜひ、楽しみながらお読みください。
noteの世界は優れたアーティストの世界です。創作した人たちにはわからないかも知れませんが、それを読む人、見る人、聴く人たちがリアルに反応してくれる場所です。もし、本格的なプロの方々が参入してもこの凄さには勝てないかもしれません。プロもマネのできないnoteの世界。これからも楽しみにして皆様のnoteを読み続けています。
私たち著作権協会では専門的なことはその方々にお任せして、さらに大切な思いをお伝えします。
本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
特定非営利活動法人著作権協会
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
著作権noteバックナンバー👇見てくださいね~
↓著作権noteマガジン
Production / copyright©NPО japan copyright Association
Character design©NPО japan copyright association Hikaru
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
