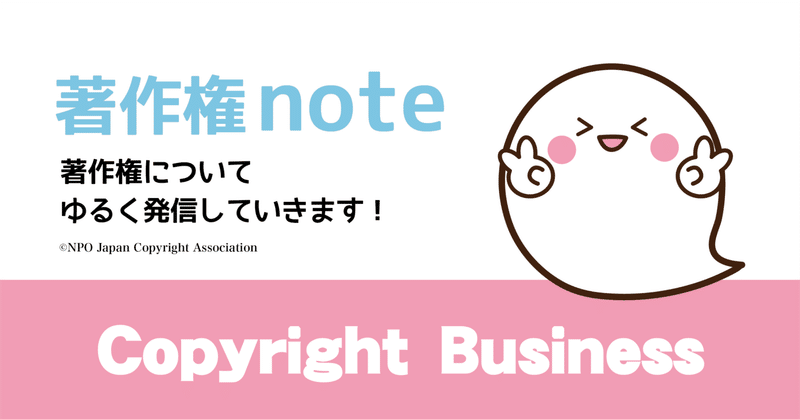
52.魅力のあるものはどんどん取り入れて、マネをしよう! 模倣と盗作は意味合いが違います。
著作権を無料・無断で使うための基礎知識
法律。どうして法律の専門用語ってむずかしいのだろう。今、問題の憲法九条だって、学者や政治家の間でも常に論争が起こっているように、この法律用語の解釈は抽象的でまったくわかりません。
このように人の著作物を「無料または無断で使うことは著作権侵害になる」ということは誰にでもわかることですが、「引用しただけだから侵害行為ではない」という人もいます。さらに、著作物でないものも引用する場合もあります。前頁の著作権法第三十二条の一、二に引用の条件が出ていますが、解釈はむずかしい。しかし、法律はルールです。このルールを理解してこそ様々な著作物を正しく自由に利用できるならば、最低限の知識は誰もが必要です。
また、著作権について考えるためには「使用」と「利用」の違いについても知らなければなりません。たとえば、
人の著作物を無断で利用する。
人の著作物を無断で使用する。
この言葉は著作権の世界では意味合いが違います。その二つの概念とは「使用」と「利用」。
まず「使用」とは、本を読むとかCDを聞く、映像を見るといった使用行為であり、いちいち著作権者に許可を得る必要はありません。これに対して「利用」となると、その本を売ったり、CDを利用して多数コピーしたり、インターネットで送信したりすることにあたり、必ず著作権者から許可を得なければなりません。このように無断で使用することと無断で利用することの違いが、著作権法の世界の解釈です。
また、「盗作」と「模倣」という言葉もあるが、この「盗作」という用語は著作権法上の言葉ではないが、一般的には他人の著作物の全部または一部をパクリ、つまり自分の著作物であるかのように発表することといわれています。
著作権侵害というのは他人の著作物を無断で利用することで、盗作は著作権侵害の中で最も代表的なもので許されない行為です。しかし、盗作と似た言葉に「模倣」という用語がある。「模倣」とはマネることであり、とくに短歌や俳句、絵や写真等のその他の創作物などすべて模倣から出発しています。むしろ模倣は上達の早道とも思われています。もちろん、ここでいうところの許されていることは作風をまねることで、他人の作ったものをパクリ、自分の名前で発表することではありません。
裁判所の判例でも次の趣旨を述べ、これを容認しています。模倣と盗作は異なっています。
「他人の書風、画風にならって書画を作成した場合に
それは著作権侵害とはならない」

どんな著作物でも個人的な使用であれば自由に利用できる
著作権法では、「個人または家庭内その他に準じる限られた範囲内で使用することを目的とする場合、使用者は著作権者の許諾を得なくても構わない」(著作権法第三十条一項)とされている。
この「個人的」の意味は、それを使用する者が自らの学習や趣味娯楽、調査や研究のためということを指しています。そのために本や雑誌の一部を複写したり、CDやFM放送から音楽を録音したり、テレビで放送された映画やドラマをビデオに録画したりすることは「個人的……」であれば自由に利用できます。
「家庭内」とは、あくまでも家族などで楽しむためという意味です。「これに準じる限られた範囲内」とは、友人間で楽しむためという意味で使用する範囲はプライベートな極少数の範囲に限られたもので、会社内の内部資料として配布するための複製や他に販売などをするために複製する場合などは、たとえその複製部数がわずかであっても私的複製の範囲には入りません。
このように「個人または家庭内その他これに準じる限られた範囲内……」であれば著作権者の許諾を得なくとも自由に複製することができます。
たとえば、パソコンでインターネット上の音楽を取り込むことも自由。パソコン内部に蓄積するだけでなくCD-ROMなどに保存することも自由。
ただし注意しなければならないことは、取り込んだ音楽を自分のホームページのコンテンツとしてインターネット経由で公衆に送信することは、著作権者の公衆送信権や演奏家・レコード制作者等の送信可能化権が適用されるため、著作権者の許諾を得なければなりません。つまり、ホームページ上のコンテンツとして使用する範囲を越えてしまうからです。


特非)著作権協会です。いつも読んでくださる皆様には心から感謝申し上げます。
「マネされると困る!」
しかし、「マネされるものでなければ魅力がない!」
だから「マネされるようなものが魅力のあるもの」
でも「マネはされたくない…」と思う。
でも、マネすることは別に悪いとではありません。
我が国日本は、ある意味模倣国家だともいわれていますが、ただの模倣でないことは誰にでもわかります。ただのマネであればそれは侵害行為となるからです。
つまり、日本人は他人の良い部分を吸収(インプット)し、改良に改良わ重ね、さらに工夫して、独自のものを創るという文化が優れているのかもしれません。
一つのアイデアや創作物をヒントとして何十、何百、何千、何万、何百万と無限に変化させることができるからです。
まさにマネをマネして、マネ続けて試行錯誤して独自の開発をするのですから、このようなマネは素晴らしいものと考えられるからです。
このようにマネなくして変化や成長がないことがわかります。
しかし、マネされるようなもの、マネされたくない、という正反対の考え方が働くこともわかります。そのため、心に残る独自性や魅力のある、味のある作品は常に輝きを増していることがわかります。
魅力のあるものはどんどん取り入れて、マネをしよう!
※特非)著作権協会おすすめ電子書籍「~無料・無断で使用できる著作権活用法②~〈無断OK!著作権〉」全4巻好評発売中↓で内容を検索してみください。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
