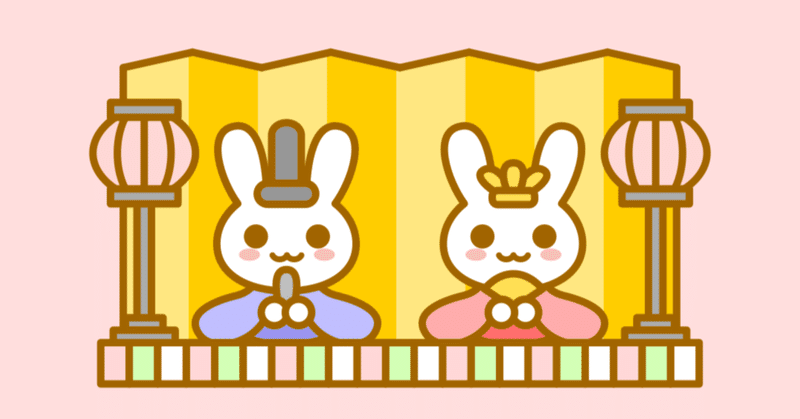
【うれしいひなまつり】
こんにゃちは🐈、猫月だんくるおすてうすです。
3月3日といえば―そう、桃の節句ですね。
日本ではひな祭り🎎の日でもあります。
保育園でも、2月の中頃からひな祭りへ向けての準備が進み、子どもたちがひな人形を制作する園も多いのではないでしょうか。
今回は、私がひな祭りやひな人形の制作で心懸けていることについてお話をさせていただきます。
○ひな人形とは?―
節句の一つである上巳の節句(桃の節句)では、川の流れで身を清め穢れを祓うという風習がありました。それが日本に伝わった際に、紙の形代に穢れを移し、川に流すという行事へと変化していきました。所謂「流し雛」ですね。
これが人形の造形技術の向上と共に、人形を飾ってお祝いをする行事へと変化していきます。
節句の由来である中国では、上巳の節句には桃のお酒や桃の葉を入れた風呂へ入浴して長寿を願う風習があったそうです。それが桃の節句とも呼ばれるゆえんであるとか。
桃は生命力が強く、長寿の象徴だったようです。また葉には殺菌効果があり、現在でもいろいろなメーカーが桃の葉ローションを販売しています。
私もあせもやカミソリ負けに、桃の葉ローションを愛用しております😊
ひな人形は貴族の風習でしたが、江戸時代に民間にも広まるようになり、桃の花を飾ることと相まって、現在のひな祭りやひな飾りへと発展していったようです。
そうそう、全くの雑学ですが、桃の種にはシアン化合物の毒💀があります。しかも青酸も含まれているので、かなり強い毒です。桃を食べる際には、種にお気をつけて。
○節句は実は5つある―
1年の節句は、実は5つあります。すべて知っていますか?
・1月7日:人日の節句(七草の節句)
・3月3日:上巳の節句(桃の節句)
・5月5日:端午の節句(菖蒲の節句)
・7月7日:七夕(星祭)
・9月9日:重陽の節句(菊の節句)
中国から伝来した「陰陽五行説」が由来とされていますが、その内の五つが日本の生活文化や風俗と混じり合ううちに残ったと言われています。
簡単に言うと、季節の変わり目の日とされ、邪気が入り込みやすい日とされたので、それを祓うために年中行事を行ってきたということです。
七草粥、ひな祭り、こどもの日、七夕は今でも残っていますね。
(昔は、重陽の節句こそが一年の締めくくりとして重んじられていたそうですが…😶)
あくまで、豆知識までー😉
○「女の子のお祭り?」―
ここからは、私の考えるひな祭りのお話です。
私がこどもの頃は、こどもの日🎏は男の子のお祭りで、ひな祭り🎎は女の子のお祭りという感じでした。
現在でもその意味合いは大きくは変わりませんが、ジェンダーフリーやLGBTQ+を考えていこうという昨今ですので、子どもたちにどう伝えようかとても悩ましい😵というのが実感です。
というのも、やはり保育をしていると、子どもの性自認と周囲の大人の考えているその子の性とに、ズレを感じることがあるからです。
正直に言って、まだまだ保育の世界でも「男の子らしさ」や「女の子らしさ」を口にする大人はいます。
「ジェンダーフリー」や「LGBTQ+」について話題にしても、ピンときていない…当事者ですら漠然としていることもあるから難しいのは分かるんですけどね。(そういう私だって、当人の想いや苦しさは分かりませんしね…😔)
そうはいっても、やはり保育士は人権の最前線に立つ存在ですから、できる限り子どもの性についても考えていく必要はあると思うのです。
さてさて、だからといって「ひな祭りをやめよう!」ということではなくてですね、大事なのは「いろんな感覚の子がいる中で、どうしたらひな祭りを楽しめるかな?」ということなんですよ。
桃の節句の意義は子どもたちに引き継ぎつつ、次代のひな祭りは彼・彼女らが作っていけば良いと思うので。
だから、私は節句の意義や由来を重点に置いて子どもたちに伝えるようにしています。「女の子の日」ではなく、「健康を願ってひな人形を飾るんだよ」とか「桃には病気を祓う力(殺菌力)があるんだよ」とかですね。
○どんなひな人形を作ろうか―
ひな祭りといえば、ひな人形の制作がついて回ります(憑物みたいに言うなよ…😁)。
ひな祭りは、紙の形代に穢れを移して健康を願うのですから、ひな人形を制作することは行事の意義にも沿っていますね。
これまでですと、男雛と女雛を作るのに、男雛は寒色、女雛は暖色の紙を使っていました。
ちょっと脱線しますと、「お内裏様」は男雛と女雛が揃って「内裏雛」なので、童謡「うれしいひなまつり」の『お内裏様とお雛様』という歌詞は誤りです。保育士、ここ要注意ですよ。毎年、間違いを子どもに吹き込んでますからね⚠
あと、内裏様とは天皇陛下と皇后様のことです。内裏は皇居のことを意味し、そこにお住まいのお二人を内裏様と呼ぶのです。
あと、男雛と女雛の飾る位置は畿内とそれ以外の地域(というか、京都と東京?)では異なるので、そこも気をつけましょう。大事な文化ですから。
話を戻します。
保育士になってしばらくはずっと、男雛と女雛の色を分けることに違和感がなかったんですよ。
”アンコンシャス・バイアス”(無意識の偏見)ってやつですね…。
男の色・女の色って思い込みがあったんです。
そこを考えるようになったのは、ここ数年の話ですね。LGBTQ+という単語はまだ存じていませんでしたが、“子どもの性自認”を考えると、「ひな人形の色を保育士が決めてしまうのはどうなんだろう?」という疑問は湧いていました。
そこでどうしたかと言うと、任せました(笑)
もう、その子の好きな色で作ったら良いじゃないかと。
お内裏様二人が同じ色の着物でいたって良いし、何なら男雛か女雛が二人だって良い。
Nintendo Switchの「あつまれどうぶつの森」はご存知ですか?
一応、男女の設定はあるものの、自分のアバターの姿は自由です。髪型も服装も顔のパーツも、男女問わずに選べます。ゲーム中でクローゼット(なぜか冷蔵庫もw)や鏡を使えばまた姿や服装を変えることもできます。
私はプレイした経験はありませんが、CD Projekt REDの「Cyberpunk 2077」だとルックスに関してはもっと自由ですね。性器も含めて身体も意のままに設定できるそうです。
“自由”であることが正しいことなのかどうかは分かりません。
我が家の雛人形は、吊るし雛です。飛騨高山のさるぼぼみたいな雛人形なので、男雛か女雛か見た目だけだとよく分りません。でも、それが良いなと思っています。5年生の娘は自分を“ぼく”と呼称します。髪型も服装も女の子のそれですが、色居合は黒基調のラベンダーかミントグリーンが好きです。彼女たちが成人する頃には、少なくとも先達による姓の押し付けは減っていて欲しいなと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
最後はちょっと話を大きく広げましたが、肝心なところは“子どもの個性を尊重する”という保育の基本です。私たちとは違う価値観の子がいる。そして、価値観の違う子たちが時代を担っていくから、人間は発展していく。
保育は未来の礎を築く仕事ですからね。
今回の記事を読んで面白かった、応援したいと思っていただけたら👇記事の購入をしていただけると嬉しいです。
ここから先は
¥ 220
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
