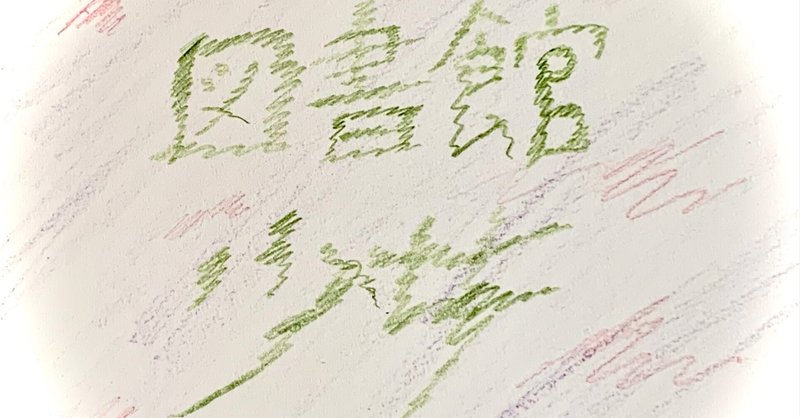
図書館少女 ~少女と~
地面に足が吸いついているような感じがする。糸で縫い合わされているかのように、つなぎ合わされているかのように。何か暗い、足の重さを感じる。私の足がまるで、私のものではないような、取りつけた機械が動作の悪い挙動不全を起こしているようにも思える。それはいくらでも言葉に表すことができる、けれど。端的に言うなら、暗い、足の重さを、感じている。
足はそれでも動いているし、はたから見ているとそんなふうには感じさせてはいないだろう。外から見る私の姿はどこからどう見ても、学校帰りに友人と仲睦まじく帰宅している途中の少女であって、私が何をどう感じ、考えているかなんてわかるとは思えない。実際にどう見えているのかも、私にはわからないのだけれど。それでも
隣を歩く、その笑顔と会話を見て、あぁ、きっと私も同じようにやれている、という気持ちになれる。私の暗い足取りとは裏腹に、笑みを努めている私の表情は、何も違和感なく、そこにあることができているのだろう。大丈夫、大丈夫……。そう言い聞かせながら、私は今日も一日を、無事に、終えられた。
また 明日
という、呪いのようなあいさつを交わすと、わかれ道に消えた。ようやく、足取りに軽さが現れる。重石がすべて取り払われて、羽でも与えられたかのようだ。月並みな表現しか出てこないのは、私に余裕がないからだろうか。どちらにしても、解放、という言葉がこれほどしっくりとくるときもない。解放、そう。解放だ。私は今、ようやく解き放たれ、私として歩き出せる。そんな軽やかな足取りが消えないうちに、図書館へと向かった。
巨人の玄関とでも呼ぶべき巨大な図書館の入り口は、何年前であったかは忘れたがたまたま私の横をすり抜けた子供たちの一人がそう口にしたのを耳にして以来、私の中では巨人の玄関として存在する、し、本当にそれを想定しているようにも思える。私はまだ、見たことがないけれど。
比率からしたら小人にしか値しない私は、この地図上ではどう映るのだろう。広大な敷地のすべてをこぢんまりとまとめた地図には、おおまかな情報と位置しか記されていない。各棟それぞれに設けられた地図を手にしない限り――したところではあるものの、詳細は知りえないのだ。
さて、今日はどこの棟に向かおうか。
昨日はたしか、歴史と民族について知りたくて二号棟に行ったけれど、民族についてだったら三号棟に行くべきだった。それなら、今日は三号棟にするか。しかし……
悩みに悩んだ末、とりあえず、中央エントランスでお茶をすることにした。特にこれといったものも浮かばず、地図を見てもいまいち決められず、動くことができなかったから。このごろの気分の晴れない自分の心を投影しているようにも思えて、幾分、気持ちを落とした。どことなく、あの、暗い、足の重さを感じる。図書館に来てまで、こんな暗い気持ちでいるのは嫌だった。……あぁ、とりあえず、中央エントランスに行こう。ひとまず、そこで気持ちを落ちつけよう。お茶を、飲もう
と、
顔を上げたタイミングに通り過ぎる影が目の端のほうへと抜けていき、自然に視線を傾けたときには気になるようなものは何もなく、まばらにいる人が統率もなく自由にしている姿だけが見える。一瞬、硬直した私の体は気がつけば自然に動き出していた。それは違和と呼ぶのも憚られるほど、小さな、小さな「かん」だった。私を突き動かしたものは、まさしく、それに違いない。まばらな人影とも、目の疲れとも思わずに、私は、私が捉えきれていない影の行く先を想像し、心に従って動いてみた。
それは逃げ水でも追うような感覚なのか。
具体的に何を追っているのかもつかめずに、心の赴くままに進行している足は、先ほどの重たさとは別の意味で私の意思を反映しておらず、かといって嫌な気持ちもしなかった。未知への好奇心とでも呼ぶべきものだろうか。私の「かん」が働く方向に、幻が形を成しているような、これまで見聞きしてきたものとは別次元の何かがあるように思えて仕方なかった。
そんな気配をたどりながら、今自分がどこを歩いているのかを見失っていた。周りに誰もいないどころか、空気も停滞しているように動きがない。正直、元の場所に戻れるのかどうかも不安だった。私の意思を反映していないこの軌跡は記憶に写せていないから。
この図書館が他に類を見ないほどの巨大な図書館であることは、この町の住人であれば(それどころか、この国の住人であれば)知らないほうが稀であるものの、こんな場所があることに少なからず動揺した。おそらく、地図にも記されていないに違いない。それに、普段であればこんなところに出る道はなかったようにも思える。不思議な感じだ。これまで何度も利用してきているのに。子供が一人で迷いこんだら永遠に帰ってこられないのではないか。
そうこう思いながら歩いていると、突然、
光が、ゆらめいた。
ゆらめきは陽炎のごとくきらめいては消え、イメージだけがその場に残る。気がつけば立ち止まっていた足は、そのイメージに向かって進んでいく。いまだ、足は私の意思を反映していないようにも思えた。
ぜんまい仕掛けの人形のような足は、ここがどこであるかもわからない不安も感じずに動力が続く限り動き続けるのであろう。不安は私の思考ばかりが担当し、まるで動く歩道にでも乗っているかのような心地にますますぐるぐると廻っている。実際に、ここはどこなのだろう。どこにつながっているのだろう……ふと、
何気なく目に留まったドアノブを認識すると、それは間違いなくドアノブとなり、まぎれもなく扉がそこにあることに気がついた。動力が切れたのか、はたまた足もそれに気がついたのか、扉を認識したとたん ぴたり 歩みを止めた。ふいに知らないところで目が覚めたような驚きと困惑のはざまで、何をすることもできずにただ、
その扉の前で立ち竦んだまま動くことができなかった。
扉には何も書かれておらず、意識から外れると壁に溶けて消えてしまいそうな危うさが感じられた。スタッフルーム、とは書かれていないが職員の私室なのだろうか。それとも、秘密の作業部屋なのか。わからない。
扉を前にして開けるのをためらいながらも迷っているのは、どこからくる気持ちだろう。私は結局、扉を開けてみることにした。きっと、罪とは、未知に対する無謀な欲と好奇心から引き起こされるものなのだ。そんな詩的なことを漠然と感じながらも、実際に思っていたのはただの興味ゆえだった。
扉はすんなりと開いた。鍵がかかっているわけでもなく、錆びついた音がするわけでもなく、私の動作をそのまま受け入れて拍子抜けするほどスムーズに、開いた。
扉の先には見覚えのある、しかしどこか違う風景が広がっていた。
図書の陳列、大きなテーブルが一つ、どこか仄暗く、人はほとんどいない――というより、ただ一人。少女が一人、本を読む姿だけが見えた。
扉を閉めて、中に入った。少女は私に気がついていない様子で、じっと本に目を落としたままピクリとも動かない。改めて見回してみても、どことなく仄暗い。それに、他の棟に比べて狭く、本の量も少なかった。縦長に配置された図書は梯子がなければ手に届きそうにない危なげな風情があり、そもそもの造りが違う気がする。各棟が作られる以前の試作的な部屋が今でもまだ残っていて、ここはその一つなのかもしれない。少なくとも、一般には知られていない場所なのだろう……と、思う。
「あら、めずらしい、迷子かしら。それとも、お客さん?」
あたりをきょろきょろしている間に――なのか、気がついたら目の前に立つその少女は、どことなく物色するような目つきで私を見つめていた。驚きのあまり声も出せず、たじろいでしまう。民俗学でも嗜んでいるかのような和装……袴に、紫の――あの柄は何て言うのだろう――着物を召した少女は、笑みとも無表情とも取れるような微細な口の動きで、
「どちらかと言えば、お客さんね」
静かな声音を発した。
見た目とは裏腹な大人びた声にすなおな反応もできず、むしろ警戒心が働いていた。明らかに職員には見えないし、一人だけ異なる衣装を纏った司書がいるとも思えなかった。少女の言葉も不可解なもので、疑問はさらに警戒心を強める。私がお客さん? 迷子だと思うけれど。と、口にしようとして、うまく声が出てこなかった。
改めて、ぐるりを見渡しながら、人の気配を感じない不気味な空間に、身動きも取れない。そうしたこわばりを見て取ったのか、そんなに警戒しなくても大丈夫よ、と少女は伝えると、先ほどまでいた席に戻る。
「よければ、好きなところにお坐りなさいな。少し、お話しをしましょう」
お茶も出せずに悪いけれどね、と、おどけたように言う少女の表情は温和なものにも思え、私の気持ちを汲んで、緊張をほぐしてくれるような心遣いが感じられた。それを受けて、幾分気持ちのゆるんだ私は、少しの間立ち竦んでいたものの、意を決して真向いの席に座った。私が席に落ちつくのを待ってから、
「うれしいわ、こうしてここに来てくれるのは」
読みかけであろう本を閉じながら、偽りなくうれしそうな表情をしていた。
その表情を見ながら、自然とそんなふうに感じられたのはなぜだろう。偽りのない表情。少女の目はまっすぐに私を射抜いて、それでいて不快を感じない。それにつられてまっすぐに視線を合わせていることに気がついて、目を逸らすこともできなかった。頭の中では様々なものが飛び交ってはぶつかり、こんがらがっては複雑に絡み合って、抜け出すことのできない思考が渦を巻いていた。何とかそれをつなぎ合わせてひとつの形にしようとしたけれど、うまくいかない。そうこうしている間にこぼれ出したものはそのとき考えていたものからは外れていたものの、口にしたとたんに意外と核心をついていることに気がついた。
「ここは、なんですか?」
少なくとも、私にとっては。
しかし、それを聞いた少女は不敵な笑みを浮かべながら両手の指を絡めて、顎を乗せる。
「ここは、図書館よ。それに変わりはないわ。図書館の、一部」
当たり前のように言う少女の言葉をすんなり受け入れたのは、それがあまりにも当たり前の答えだったからに他ならない。愚問だった、と感じる間もなく、
「さて、あなたは今日、何用でここまで来たのかしら?」
そんなことを聞いてきた。
一瞬、狼狽したものの、先ほどの自分の質問のように、何用で図書館に来たのか、それは本を読むため、と当たり前の答えを伝えようとして、うまく言葉に乗せられなかった。
何用で来たのか、そう問われたときに、正確に何しに来たのか、私にもわからなくなってしまった。
単純に言えば、もちろん本を読むためだった。本が好きだったし、図書館に来るのも毎日の習慣だった。けれど、改めてそう問われると、わからなくなる。本当は、何をしに、ここにきているのだろう。私は何のために、ここにきているのだろうか。
適当な受け答えもできず、かといって何が思い浮かぶわけでもなく、
「正確には……わからない」
そう、答えるしかなかった。
「それなら、それでいいのよ。人それぞれだから」
その言葉は少女のやさしさだったかもしれない。けれど、私の胸の中には入っていかず、ただ反響して意味をなさない音だけがかろうじて捉えられる。まるで迷宮を作り出してしまったかのように、いつまでたっても答えにはたどり着けない。少女の声が溶けていくように、複雑に入り組んで抜け出せない。それはむしろ、私自身が知りたいと願い産まれたかのようだった。
堂々巡りとは知りつつも、何度も反復しては口の中で反芻する。初対面の相手に対して何でこうも真剣に答えを模索しているのかもわからず、それに違和を感じていないことがまたそれに拍車をかけているようだ。少女は私の挙動を見て察しているのか、何も言わずに待っている。その姿勢がまた、思考に耽る余裕を私に与えてくれていた。
何用で……もしかしたら、用事なんて、なかったのかもしれない。あえて、そこに理由をつけるのなら、なんだろう。あえて、あえて。
「そんなに、固くならなくて大丈夫よ。無理に探さなくてもいい。自然に湧き上がった声があれば、それを聞いてみたいわ」
その声色は落ちついていて、深く、静やかに、浸透するようであった。前のめりになりすぎていた気持ちがなんだか抑えられ、立ち止まったとたんに ことり 落ちてきた声を拾い上げると、薄ぼやけていた形は線となり、境界を象って、言葉として表現することができた。
「ひとりに……なりたかった、から」
不思議と一度口にしてからは、それが求めていた真実であると、迷いなくそう思うことができた。何をこんなに悩んでいたのか、と思うくらいあまりにもあっさり納得した答えに身動きが取れず、思考もままならない。そう、私は、
ひとりに、なりたかった。ゆっくりと、過ごしたかった。誰にも気を遣わずに、気にすることもなく、不安も何も感じずに、自然と落ちつきたかった。ただ、それだけだった。
暗い、何か暗い、足の重たさを感じる毎日がこれから先も続くかと思うと、本当に耐えられるのかどうか、わからない。こうしてひとりになる時間だけが唯一それを感じさせないひとときで、私はきっと、そのためにこうして図書館に来ているのだろう。何か、理由をつけて。本を読みたい、という言い訳をして。違う。私はただ、ひとりになりたかった。だけなのだろう。
それはまるで懺悔のようだった。言葉が つらつら と流れては溢れ、次々と口から漏れてくる。少女の顔も見られず、うつむきながら。自然に湧き上がってくる言葉が止まらなかった。それは意識的よりも無意識さを感じるのは、こうして言葉を発している自分と思考している自分が乖離しており、幽体離脱でもしているように客観的に自分を眺めているからで、上空から見下ろしているイメージがそのまま私の瞳に映されていた。
浮遊したような視点から少女の顔をのぞき見ると、何も言わずに私の言葉を受け止めて、聞いてくれていた。私はそれに気がつかず、言葉を発し続けている。
うつむきながら少女の顔も見ずにただただ感情を発散するかの如く言葉をとめどなく吐く私と、うなずきながら私の顔を見つめてすべてを受け容れるように言葉を聞き入れる少女を、観察しながら少しずつ地上を離れ――突如、
私は私の中に戻り、戸惑いと共に言葉の波も穏やかに収まった。そうして改めて私の体から少女を見ると、静かな笑みを浮かべて私を見つめている。
ふいに訪れた静寂が、波の引きと共に心に するり 入りこみ、混乱する。昔話を語り終えた後に残るような独特の沈黙が戻ってきたばかりの私に襲いかかり、はっと気がついたときには、何でこんな見ず知らずの人に自分の想いをさらけ出してしまったのだろう、という慚愧と不安が押し寄せてきた。それを意識したとたん、不安は心配と恐怖を連れてきて、仲よく私の中で踊っているのがわかる。その踊りは楽しげに私を蹂躙し、やすやすと絶望の淵へと追いやった。少女の笑みさえ、その踊りを楽しそうに鑑賞しているようにしか、見えなかった。
体いっぱいに満たされた不安に耐えきれなくなって、すぐにこの場から出ていこうとした――けれど、体は動かなかった。震えて、思うように、動かせない。無理に立ち上がることも、体を支えることすらできなくてバランスを崩し、そのまま椅子から転げ落ちた。
呼吸が 苦しい 何も 見えない
「あら、よほど、不安の強い子なのね。仕方ないわね」
遠くで 少女の 声が 聞こえる
「どれ、起こしに行こうかしら」
すると 眩しい 光が 煌めいた
「あなたの――」
そして 意識を 失い 何もかも
「夢の中へ――」
すべて 消えて 闇へ 誘われた
※
気がつくと、そこに少女はいなかった。そもそも、図書館にいなかった。
ここから先は
¥ 200
いつも、ありがとうございます。 何か少しでも、感じるものがありましたら幸いです。
