
「量」の採用から「質」の採用へVol.8(1/7)
1.採用が変われば組織が変わる
先に私は、採用の目的を「企業競争力のアップにつながる人的資源の確保」というように記しました。企業のエグゼクティブたちは、企業価値を生むのは、「人」であると確信し、人材の採用のあり方について強い関心と問題意識をもっています。「人という資産」が自分たちの企業を存続・発展させ、競合他社との差別化につながるということを実感しているのです。
企業の採用意欲は高まっていますが、その一方で、若者の意識をはじめ働く人たちの考え方や価値観、キャリアの選択はますます多様化してきています。そうした変化に応じて、企業の採用戦略や採用の考え方の本質は変わったでしょうか。これには少し疑問を感じます。
というのも、現場で行われている採用活動や面接と、企業の経営者が掲げている問題意識を共有した活動とは、少し温度差があるように思えるからです。
「コンピテンシーをとり入れた採用方法」は、応募者一人ひとりの特性を事前に把握し、個人と組織のミスマッチを極少化するための優れた方法論だということは、これまで本コラムをお読みいただく中でご理解いただけたと思います。しかしながら、問題は「コンピテンシー採用」と「企業の競争カアップ」との因果関係が実証しにくいということです。
もちろん、会社が必要とする人材要件を満たし、企業風土や文化にも適応できる付加価値の高い人が数多く入社すれば、組織の活性化や生産性の向上が大いに期待できることは、みなさんも経験的には理解できるでしょう。私自身も、クライアントの「企業組織診断」を通じて、そのことを実感する機会は何度かありました。
たとえば、数年前から経営者の意向を受け、「コンピテンシー採用」をとり入れた採用システムを構築した企業に対して、私たちは継続的に組織診断を行っているのですが、その診断では、組織の活性度が少しずつ向上しているとともに、若手社員のほうが古くからいる社員に比べ、会社の経営方針や人事諸施策に対して「賛同」する人が増えている、という有意の結果が出ています。また、さらにうれしいことに、学生からのその企業に対する「賛同」は極めて高い数値が出ているのです。
とはいえ、この種の組織診断は、会社全体の組織活性度を調査するのが目的であり、新入社員の質的変化と組織との関係にフォーカスしたものではありません。前にも触れましたが、採用の影響が組織の活力に反映するまでには、時間がかかるからです。
加えて、組織の活性度や会社に対する賛同には、ビジネス環境などの外部要因も含め、いろいろなファクターがかかわっているため、一概に「コンピテンシー」を用いた科学的アプローチがいい結果を生みだしたとは言い切れないわけです。また私たち自身、この会社の人事制度改定にも深くかかわっているため、そのことも影響しているのかもしれません。
私の手許に非常に興味深い調査データがあります。パートナー企業であるDDI社が、アメリカのある製薬会社に対して、コンピテンシー採用導入後のMR(医師向け営業職)のパフォーマンスをリサーチした資料です。そのデータを見ると「コンピテンシー採用」がかなり高い信頼度で組織の生産性向上に寄与していることがわかります。この数値結果が示すように、採用が変われば組織もまた変わるのです。
次にこのデータの内容についてご紹介しましょう。

2.「コンピテンシー採用」が変えたMRの営業力
この調査は、製薬会社のMRにフォーカスし、「コンピテンシー採用によって選考・採用した社員と、それ以前の一般的方式で採用した社員とのあいだに、生産性において有意差があるか、という観点で行われました。
その調査結果のデータを見ると、MR一人あたりの「医師訪問件数」は、従来のMRの訪問件数とほとんど変わっていません。にもかかわらず一人あたりの「受注件数」は、「コンピテンシー採用」を通じて入社したMRのほうが、それ以前のグループに比べて断然高いのです。
つまり、「コンピテンシー採用」によって能力要件や適性をきちんと評価されて入社してきたMRは、そうでないMRと比較すると明らかに営業力が向上しているといえるでしょう。組織的に見れば、労働生産性の向上が着実に図られているわけです。
残念ながら日本にはまだこの種のデータ(外部的要因の影響を極力排除する環境下で実施された比較調査データ)がないという現状の中で、DDI社のこのデータはとても貴重なものだと思います。
私自身、多くの製薬企業においてMR採用のコンサルテーションを行っています。その際、データによる生産性の向上まではトレースしていませんが、採用をお手伝いしているいくつかの製薬企業からは、明らかにMR採用においてその精度は高まり、ビジネスの成功に大きく貢献しているという、うれしいフィードバックをいただいています。
その反面、ある企業のMR採用の現状を知り落胆しました。それはこんな話です。
「コンピテンシー採用」に関する私のセミナーを受講したある製薬会社の人事担当者から、後日、次のような質問を受けました。
「じつはMR候補のある女性を面接したんです。私はMRとしての能力要件に明らかに達していないから不採用と判断したんですが、面接に同席した担当役員の方が合格にしたんです。どう思われます?」
「担当役員の方が合格にした理由は何だったんですか?」
「そこなんですよ、問題は。その役員がいうには、「ドクター受け」がするからって。要するにかわいいんです、その女性。だからドクターに好かれて、たくさん注文をとってくるだろうっていうのがほとんど唯一の理由ですね」
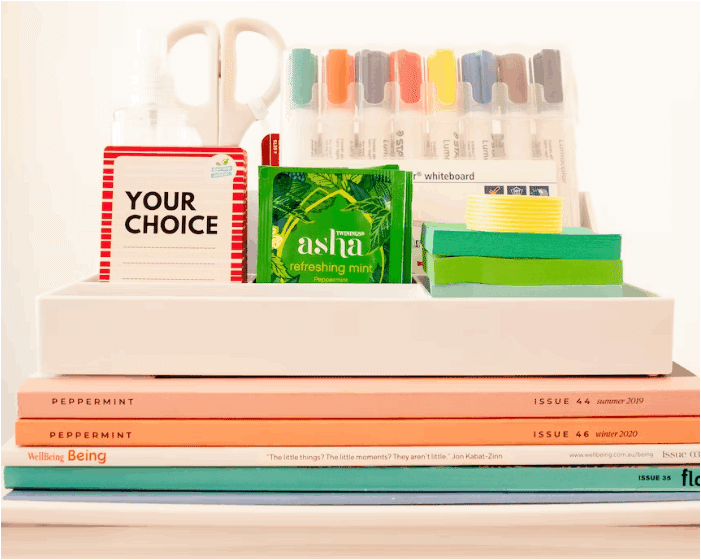
その担当者の評価内容から推量すると、その女性はたとえ“ドクター受け”したとしても、ドクターから拒絶された瞬間にダメになる可能性が高く、結局は気に入ったドクターのところにしか足を向けなくなる。そんな行動をとる人だと判断しました。そのように判断したところで、今さら合否判定はくつがえりません……。
「ドクター受け」という言葉を聞いて、私はその担当者と一緒に笑ってしまいましたが、そのあと残念な気持ちになりました。まだこんな合否判定がまかり通っているのか、と。そして、次のような感慨を深くしました。
――従来の採用を「コンピテンシー採用」に変えていくには、採用に対する問題意識を役員をも含め、トップの理解や意識改革、さらには積極的な参画が不可欠なのです。それとともに、人事部門もまた採用という重要なプロジェクトをもっと戦略的に構築し直し、それに基づいて新しい採用のあり方をトップに提言すべきでしょう。

【著者プロフィール】 伊東 朋子
株式会社マネジメントサービスセンター執行役員 DDI事業部事業部長。国内企業および国際企業の人材コンサルティングに従事。
お茶の水女子大学理学部卒業後、デュポンジャパン株式会社を経て、1988年より株式会社マネジメントサービスセンター(MSC)。
人材採用のためのシステム設計、コンピテンシーモデルの設計、アセスメントテクノロジーを用いたハイポテンシャル人材の特定およびリーダー人材の能力開発プログラムの設計を行い、リーダーシップパイプラインの強化に取り組む。
(※掲載されていたものは当時の情報です)
🔵おすすめソリューション
🔵会社概要
会社名:株式会社マネジメントサービスセンター
創業:1966(昭和41)年9月
資本金:1億円
事業内容:人材開発コンサルティング・人材アセスメント
🔵MSCソーシャルメディア
■note
https://note.com/msc_ms
■Twitter
https://twitter.com/MSC1966
■Facebook
https://www.facebook.com/ManagementServiceCenter.jp
■Linkedin
https://www.linkedin.com/company/management-service-center/
■anchor(ラジオ)
https://anchor.fm/management-service-center
■YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC5JYP6TtJ21WdNF7BgZIppQ
