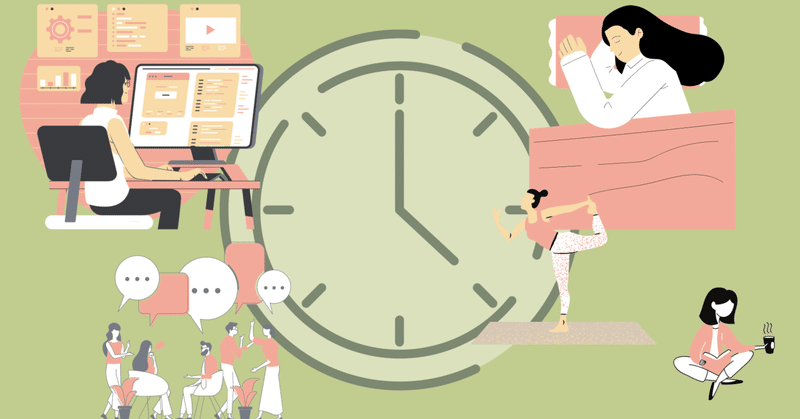
残業文化が変わらなければ少子化は止まらない
2022年の出生数が初めて80万人を割ったというニュースに関連し、「少子化対策」の議論が盛り上がっていますが、経済的支援や保育園等の充実はもちろん重要な一方、男性中心・長時間労働の仕事文化が変わらなければ20〜30代の女性が子どもを持とうと思うようにはならないと思うので、簡単に。まだ読み切れていませんが、次の本がデータも充実していてとても勉強になります。
山口一男『ワークライフバランス:実証と政策提言』日本経済新聞出版、2009年
少子化とワークライフバランスの問題は、私がそもそもジェンダー学に興味を持ったきっかけに大きく関係しています。日本の伝統的な職場で総合職として「男性並みに」働く傍ら、子どもを持って産休・育休を取り、その後も時短やフレックスで残業しない働き方を数年間はするとすると、私が面白いと思う仕事はさせてもらえないな…と気づいてしまったことです。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
避妊や中絶が普及している日本において、子どもを持つかどうかはかなりの部分、妊娠することになる女性の意思によります。そして、男女共に生物として妊娠しやすい若いうちは仕事で一番精進が求められる時期でもあるのです。今仕事を休んだり減らしたりするわけにはいかない、子どもを持てば出世ルートから外れることになる、パートナーがいても2人とも出世を手放しては経済的に困るから結局主に女性が子育てすることになる…こういった懸念が付き纏う限り、女性も家庭の外で働くのが当然かつ必要になった社会で出生率が上がるはずがありません。少子化は日本のジェンダー不平等の現実を如実に反映していると言えるのです。
そもそも、お家相続のために子どもを産むわけではなくなった時代、子どもを持つのは子育てをし、家族を作りたいからだと思います。それを無視して、お金と子供の預け先だけを提供しても出生率は劇的には上がらないでしょう。一番必要なのは心と時間の余裕です。子どもを持って、もっと家庭で時間を過ごしたいなと男女共に思え、社会的制裁なくそれが可能にならなければ、少子化傾向の根本的解決にはなりません。これは、前回書いた家事・育児の価値を見直すべきという話や、組織に根付く「男性的な/masculine」文化の問題と密接に関係しています。
イギリスでは最近、週休3日制(週4営業日制)を試験導入した企業の多くが生産性の向上と利潤の維持に加えて従業員の福祉・満足度等の向上を達成し、今後も週休3日を継続するというニュースもありました。日本ではいまだに、定時で帰ることすら組織への抵抗・反発のように捉えられています。プライベートを仕事に持ち込むべきでないという観念も根強く、母親が子どもの病気等で仕事を休むのがギリギリ容認されているーーただし、だから女性に重要な仕事は任せられないといった偏見付きでーーような状況です。人が人らしくあるためには一定の「ケア」が必要であり、そういう人間らしい私生活があった上での仕事でのパフォーマンスだという認識、仕事のために生きているわけではなくて、生きる中でその仕事を選んでいるのだという感覚が普及してほしいと思います。
「仕事一筋」が理想の「(男性)社会人」の生き方であり続ける限り、その歪みは少子化として顕れ、今の国籍法による「日本人」は減っていくでしょう。経済や社会福祉の観点だけであれば、機械化・自動化や移民受け入れで実務的な問題は解決し得ますが、均質・一元的な「日本人」「日本社会」という幻想を維持するには今の「日本人」の若者が子どもを持とうと思える社会に変えていかなければいけません。フェミニズムの観点からは、現在の日本の排他的な風潮も批判の対象なので、少子化問題への関心はジェンダー問題への対策のために戦略的に利用するということになるかと思います。私は個人的に子どもが欲しいというだけでなく、誰しも社会・共同体から支えられているのだから、家族に限らず誰かを「ケア」すべきではないかと思うので、男女共に私生活に時間を割くのが当たり前な社会に少しでも近づいてほしいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
