
センサー、錆び付いていませんか?
最近、「持続可能な資本主義」という本を読みました。
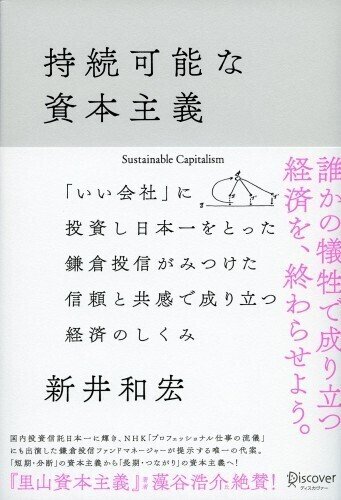
著者は鎌倉投信の新井和宏氏。
鎌倉投信は「投資はまごころであり、金融はまごころの循環である」を投資哲学として掲げ、金銭的リターンの最大化を目的とはせず、社員や取引先や地域を大切にしている会社への投資を重視しています。
当初は周囲の金融関係者から「そんなものは上手くいくはずがない」と言われたそうですが、多くの方々の共感を得て、今は運用実績を大きく伸ばしています。
以下、いくつかポイントをまとめてみました。
1.現代は投資目的が「お金」になってしまっている
現代の投資活動は「リターン=お金」だけになってしまっている。そのため、「投資したお金がどのように使われているか」ではなく、「自分が効率良く稼げるかどうか」が最大のモノサシになっている。
その結果、リーマン・ショックのようなことが起きた。リスクの高い債券を原形が分からないほど細かく切り刻み、別の債権と混ぜ込んで証券を作り上げたりしている。もはや誰に投資しているのかはどうでも良くなっており、どれだけ稼げるかが全てになっている。
お金の出し手と受け手が分断され、お互いの顔は見えず、どちらも「お金が手に入れば良い」と思っている。その人間の欲が、無限にバブルを膨張させていった。
2.目先の利益の最大化が求められている
現代の資本主義では、国も企業も一定期間内の利益である「フロー」の最大化が求められる(国ならGDP。企業ならROE経営)。
しかし短期的利益の最大化だけを求めると、社会基盤の破壊をもたらす。例えば、あえて寿命の短いものを作り、買い替え需要を生み出そうとしてしまう。林業で短期的利益を最大化しようとすれば、はげ山になっても良いから多数の木を切り倒せば良い。
私たちは資本主義に「時間軸」というモノサシを加えなければいけない。
3.心の豊かさは数値化できない
行き過ぎた資本主義の反動で、CSR(Corporate Social Responsibility)やCSV(Creating Shared Value)を重視する動きが進んでいる。
しかし、社会的に良い会社を数値で評価しようとするのは危うさがある。評価指標を設けると、単に指標を満たすことだけが目的になりがちである。つまり、本来の「社会を良くしたい」という思いからではなく、「自分たちが儲けたい」から指標を満たそう、という動機になってしまう。
良い会社には、経営者や社員の利他の思いがあり、取引先や社会との信頼関係がある。これらは客観的指標で測れるものではなく、主観的に感じるもの。だから鎌倉投信は実際に投資先に赴いて目利きをしている。
かつては日本の銀行も「見えざる資産」の評価を行っていた。しかし今は客観的指標だけで債権を評価するようになり、逆に銀行の目利き力は低下してしまっている。
4.資本主義の主権は消費者にある
資本主義の主権は消費者にある。どれだけ崇高な理念を持った企業が現れても、消費者に選択されなければ潰れてしまう。
アメリカでCSVが広まったのも、消費者がCSVを掲げる企業を支持するようになったから。つまり企業にとってはCSVを掲げる方が「得」になった。
私たちは単なる消費者ではない。ある時は地域住民であり、ある時は社員であったりする。そのようにして、いろいろな企業の様々なステークホルダーになっている。私たちステークホルダーの応援によって良い会社が育つ。
5.感想
CSRやCSVの分野において評価指標を設けると、「社会を良くしたい」という思いからではなく、「基準を満たしておけば格好がつくだろう」「非難はされないだろう」という思いでもって、指標を満たそうとしてしまう。
一見、同じような行動をしているようでも、その心の中は「利他」ではなく「エゴの思い」になってしまっている。
皆が「世界を良くしていこう」と思って動いているように見えて、心の中では「自分さえ良ければ」という世界が展開している可能性がある。
これはSDGsや温暖化対策の指標についても同じだと思いました。
しかし本当に世界を良くしていくためには、人間の心自体が変わらないといけない。心が変わらない限り、どれだけ規制や指標を設けたとしても世界は良くならない。
また、銀行が投資先を判断する際、客観的指標に頼りすぎて、会社の良さを主観的に感じる力が失われているという話がありました。
これは、私たちが買い物をする際にも言えることかもしれません。
モノやサービスに付いている「値段」。
その値段分のお金を支払うことで、モノやサービスを受け取る。
当たり前のことですが、そうすると、モノやサービスのありがたさを「自分で」感じるセンサーが鈍ってしまう。
本当は同じモノやサービスであっても、それに感じる「ありがたさ」は人それぞれだったりします。
私たち一人ひとりが本来持っている「ありがたさを感じるセンサー」。
いつの間にか錆び付いていたりはしないでしょうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
