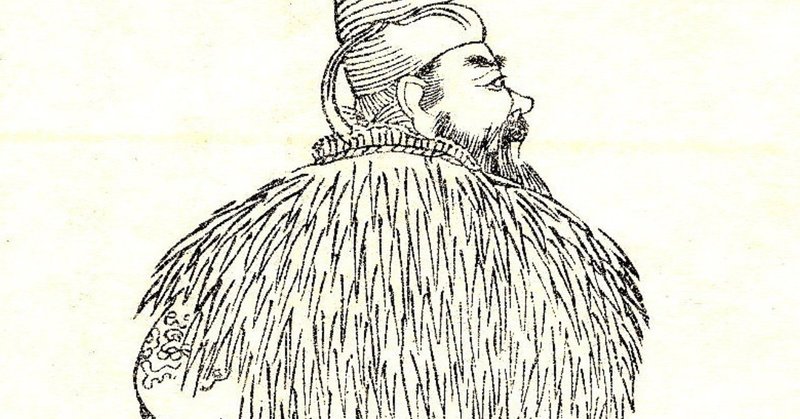
日本史のよくある質問 その2 「氏」「姓」「名字」のちがい①
このシリーズでは、日本史を教えてきて比較的多く寄せられた質問を、ちょっと掘り下げながら記事化しています。
主に大学受験~大人向けの内容ではありますが、冒頭のまとめ部分だけを使えば、中学生以下向けの説明にも使えるように書くことを心がけています。
さて、今回の日本史のよくある質問は…
生徒:質問です!
「氏」「姓」「名字」って何が違うんですか?
氏名とか姓名って言うし、名字と名前とも言うし。同じことですか?
私:確かに今は同じように使うね。
でも、昔は違うものを指していたんだよね…。
というわけで、今回は
「氏」「姓」「名字」の違い
がテーマです。
まずは「氏(うじ)」と「姓(かばね)」の違いです。
「氏」と「姓」は共に、古墳時代、ヤマト政権が「氏姓制度」というものを作ったことで制度化されました。
結論から書いてしまうと、
「氏(うじ)」は「血縁関係」
「姓(かばね)」は「朝廷内の立場」
を表しています。
古墳時代の「氏」として代表的なものは、
蘇我・平群・巨勢など =氏の名称は支配地に由来
物部・大伴・中臣など =氏の名称は職能名に由来
があります。
さらに後の時代になると、皇族から臣下になった(臣籍降下)した源や平、橘といった氏が加わります。
一方、「姓」として代表的なものは、
臣(おみ) =畿内の有力豪族
連(むらじ)=大王家直属の職能集団
があります。
畿内は摂津・山城・大和・河内・和泉(現在の大阪府の大部分、奈良県全域、京都府南部、、兵庫県南東部)を指しています。

ちなみに、蘇我氏・平群氏・巨勢氏などは「臣」です。
彼らは大和盆地(現在の奈良県)を中心に、畿内に大きな領地を持っている豪族です。
彼らは大王家に従属しているものの、立場としてはやや同盟者に近い豪族です。
江戸時代風に言えば「外様の大大名」と言えばいいのでしょうか(伊達や前田、島津家のような)。大王家としては、完全な部下ではないので微妙に気を遣わなければならない相手です。
氏の名前が支配地由来で、畿内の豪族は「臣」が多いです。
一方、物部氏・大伴氏・中臣氏などは「連」です。
彼らの多くは渡来系(主に朝鮮から渡ってきた人々)の有力豪族で、かなり早い段階からヤマト政権に服属し、特定の職能を果たしていました。
例えば、物部氏は軍事(総司令)、大伴氏も軍事(親衛隊長)、中臣氏は祭祀担当、といった具合です。
実は、大王家に従った順番としては連姓の豪族の方が早いのです。
江戸時代風に言えば「譜代大名」と言えばいいのでしょうか(井伊、本多家のような)。
大王からすれば、直属の部下なので遠慮なくこき使えます。
(物部氏は、はるばる九州まで反乱の制圧に行かされたり…)
氏の名前が職能由来の豪族は「連」が多いですね。
※「中臣氏」が「藤原氏」に改めたのも、この辺りに色々含みがあります。これもいずれ記事化します。
ということで、例えば蘇我馬子であれば、
「蘇我」一族で、朝廷内では「臣」という立場の馬子さん
といった感じになります。
ちなみに、蘇我氏は臣のリーダー役(大臣)になっていましたので、蘇我馬子は正確には「大臣」です。
「大」は「リーダー」という意味で使われました。
例えば「大伴」は、「大王のお伴のリーダー」=「親衛隊長」ということです。
…よく考えると、大化の改新の際に、蘇我氏は物部氏(軍総司令)に武力衝突で勝ったのですから凄いですよね。
姓は他にも、「直(あたい)」、「首(おびと)」、「史(ふひと)」、「村主(すぐり)」などがあります。
後の天武天皇の時代になると、真人(まひと)・朝臣(あそみ)・宿禰(すくね)・忌寸(いみき)など、朝廷での地位を序列化した「八色の姓」が作られ、上に出てきた姓はあまり使われなくなります。
ちなみに、古代の神話に出てくる人々の「ヒコ」、「ヒメ」、「ネ」、「ヌシ」なども、古代の姓です。それが制度化されたのが氏姓制度で、姓自体は昔からあったようです。
ただ、古代の姓は最後につくんですね…。
そういう意味でも、今の姓とは違う感じがします。
(例)カムヤマトイワレヒコ=神武天皇

さて、ちょっと長くなってきてしまいましたので、「名字」については次回の記事にしたいと思います。
いつもながら中途半端ですみません…💦
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
前回の「「の」がつく人、つかない人」の記事はこちらです。
もし、読者の方からのご質問があれば記事化していきます!
(時間はかかると思いますが、少しずつ記事にしますので気長にお待ちください<m(__)m>)
TwitterのDMなどで、お気軽にお問い合わせください。
もしよろしければ、フォローもお気軽に!(喜びます!)
サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。
