
地域の人とのつながりを大事に!みんなの居場所「りんごっこハウス」さま②~代表の邦永さんインタビュー編~
■最初に
こんにちは!サイボウズのもっちーです😊
前回、みんなの居場所「りんごっこハウスさま」のたくさんの取り組みを紹介しました。
私が子ども食堂を体験したことも書きました。
今回は代表の邦永さんが何をきっかけに活動をはじめたのか、そしてその想いをお話いただいたのでご紹介します。
このはじめたきっかけが面白い!スゴイ!
ぜひ読んでくださいね
前回の記事「取り組み紹介&子ども食堂体験編」はこちら
■インタビュー
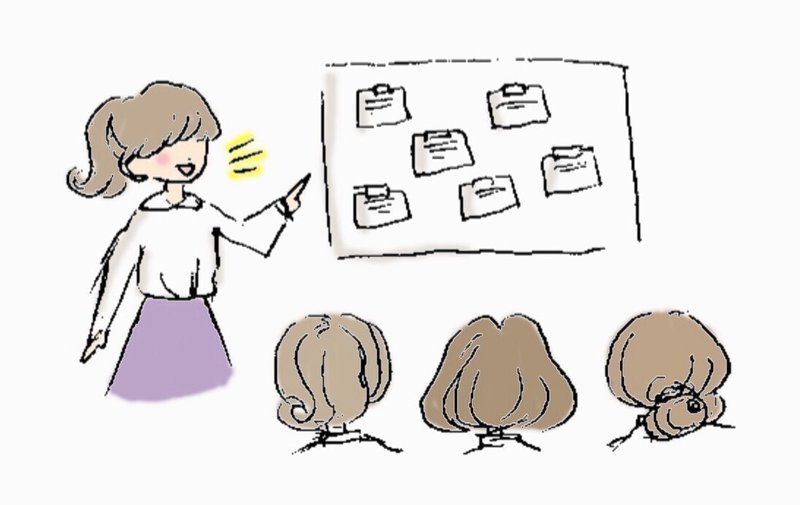
【私がやった方が早いと思った(活動のきっかけ)】
【保育付き講座に参加】
りんごっこハウスさんが、最初に始めたのはプレーパークです。
きっかけは公民館のワークショップの講座でした。
女性学級ということで、保育付きで学べるものを公民館でやっていたと言います。
その当時、1歳半の末っこさんがいて、講座に興味があったわけではなく、幼稚園の知り合いに声をかけられて、参加をしました。
この講座は当事者をつくろうと企画されたものでして、この講座を企画した方は今でもりんごっこハウスさんにかかわっています。
この方のお話も聞いているので、次回お伝えします!
~私がやった方が早い~
10回の講座の1回に、日本初の常設の冒険遊び場「羽根木プレーパーク」の初代プレーリーダーである天野秀昭さんの講座もありました。
その講座の中で、活きる力は学校では育たないという言葉が印象的だったそうです。
その当時の評価や点数で管理されている学校の生活で生きる力は育たないと邦永さんも感じていたといいます。
そこから、ではなぜ?と考えた時に
今の子に一番足りないのは遊びだなと行きつきました。
何かさせられることは山ほどあっても、自分がやってみたいを全力で出来るのが遊びだと納得し、
だからこそ、能動的にやってみたいという主体性を育てることが大事になってくると感じたそうです。

【今でも忘れられないこと】
周囲は子育ての大変さを言っていたが、ご自身は3人目ということもあり、子育てが楽になっている感覚があったり、今足りていないと思っていることがないという感覚があったそうです。
講座の中で、「子育て支援が進まない理由は何だと思いますか?」と質問がありました。
子どもが大きくなるにしたがって、足りなかったことが、どんどん過去になっていく、忘れていって、新しい課題がでてくるから、当事者が当事者のママでいられない。
小学校に行ったら、小学校の課題と、次々に新しい課題になっていくから、課題が置いておかれて進まなくなってしまう。
もし何か課題を抱えているのなら、そのことを忘れないで欲しい。
その言葉を受けて、
その時に「私にも忘れたくないことがあったな」と思い出した。といいます。
自分の中で、確かに足りていないことは過去にあったけれど、それは過去のものになっていた。ことに気づきました。

【180度変わった考え方】
邦永さんは講座や活動を通じて、考え方が180度変わったとお話くださいました。
前はスゴイ真面目で「べき論」が強かった。
子どもにも「ちゃんと」を求めていた。
いったん始めたものは最後まで続けないといけないという、強い母だった。と邦永さんはいいます。
他のお母さんやお子さんがどうであっても、子どもが習い事を辞めたいといっても絶対にやめさせなかった。
その考え方もプレーパークで変わりました。
今では、本当にやりたいことなんて小さいころにはっきりすることは少ないと感じ、
経験としてやることも大事だし、子どもの様子を見て、甘えがあってもよいという気持ちになりました。
大人だって会社を休みたいこともある。(有休もありますしね)
だけど、子どもには期待を押し付けがちになってしまう。
今は甘えで休むことがあってもよい、色んなことを経験してほしいと思うようになったそうです。
【どんどん増えていく活動】
今までやってきたことを全部やっている感じです。
活動の中で、やってきたことをやっているので、新しいことをやっている感覚ではないそうです。
名前がどんどんついていっただけといいます。
プレーパークが最初で、そこから派生して、認可外保育園として場所を借りる事ができたので、本当はもっと地域に開放したいと考えている。
基本的には毎日動いています。

【居場所としての活動】
プレーパークは0歳から18歳までと行政で決まっているだが、公園でやっているので、地域の人が来て、おしゃべりしたり、老若男女来てくれていています。
誰が来ても何しても自由、遊ばなくても座っていても工作していても良い。
居場所って何かをしないといけない場ではなく、ここにいて気持ちがいい場所で良いと思っている。
木曜日はカフェをやっています。
様々な年代の人、小さい子を連れたお母さんや、シニアの方も含め、お父さん世代の人などおしゃべりに来ている。
沢山の人に来てほしいという気持ちもあるので広報活動もしたい気持ちがあるといいます。
もっと広く声かけして地域の人たちと一緒に作っていきたい。

【小学生の駄菓子屋さん】
毎週水曜日は小学生の駄菓子屋さんの時間になっています。
駄菓子屋さんは小学生の「やりたい」の声から出すものを決めたといいます。
邦永さんが、やりたい子いる?やってみる?
と聞いて、集まった5人の子たちと、
どんなものを買いたいか、他の駄菓子屋さんに買い物にいって、自分の店だったら何が欲しいか3つ選んでくる体験をしたそうです。
5人いて、3つずつだして15個の中でなににするのか、を子どもたちがプレゼンをして決めました。
りんごあめが買えますよ!

【活動の特徴】
基本は野外というのが特徴です。
外がいい理由としては子どものやってみたいにつきあいやすいことがあります。
子どもの過ごしやすい、育つことにコミットする。
やってみたいことが出てきたときに、大人はどうしているのかというと、
まずは話を聞いて、やってみたいことを応援したり、やれるように提案したり、こんなことならできるよと一緒に考えることもあるそうです。
あとは離れてみることも大事。
子どもがやりたいことなので、見守りを中心にやっている。
私が訪問して感じたのは、子どもは色んなボランティアの人に声をかけてもらえることが嬉しそう!
野外活動でも、色んな人と関わりが持てることは特徴としてあると感じました。
■最後に
最後までありがとうございます!
邦永さんの180度変わった考え方もスゴイなと思いましたし、子ども関係のお仕事をしていたわけでもなく、たまたま講座にいったことがきっかけなことも面白い!と感じました。
たまたまだけど、大きく変わることがあるのですね。
次回は、たくさんの関わるひとのお話を聴いたので、そちらを公開します!
ボランティアの人、ワークショックの企画者、利用している人などそれぞれの立場からのお話を聞いています。
また見てくれると嬉しいです。
