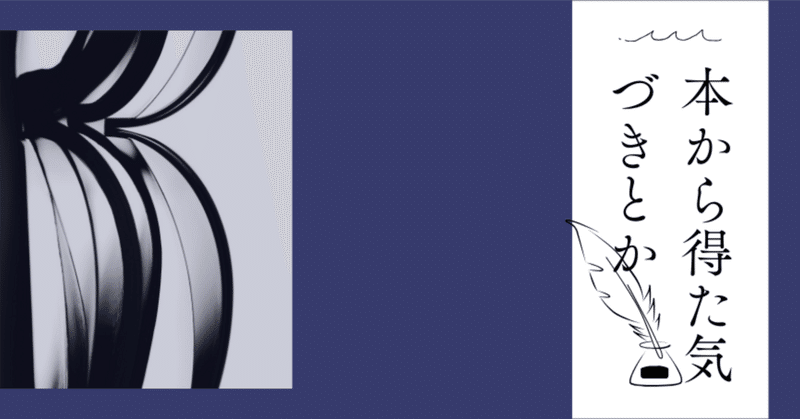
「今日誰のために生きる?」をINFJ-Aが超冷静にざっと読んだ感想。(ちょい辛口)
「今日誰のために生きる?」という書籍をご存知だろうか?
特にスピリチュアル・ナチュラル・引き寄せ・日本好きな方々の間では、号泣した、魂が揺さぶられたと、拡散に次ぐ拡散が重ねられ、大切な人にギフトとして贈る行為でますます流行してベストセラーとなっている本である。
著者は、ペンキ画家SHOGEN氏と、作家・幸せの翻訳家ひすいこうたろう氏。
ペンキアートに心を揺さぶられて、すぐ会社を辞めて単身アフリカのとある村に渡ったSHOGEN氏の村人との交流体験から、日本人が取り戻すべき生き方を列挙し、ひすい氏がその生き方を日常生活に落とし込むワークを伝授し、もって、日本人が忘れかけていた誇りを取り戻し、日本人の血に流れる縄文時代の感性の記憶を呼び覚ますことを目的とした本だ。
発売直後のブームが少々落ち着いたと思われる11月9日、Kindle版を購入し、ざっと一読したので、感想を冷静に綴ってみたいと思う。
ファンでもアンチでもない私が読んで感想を書く理由。
ブームの裏には意図がある。
薄々お気付きだろうが、私自身は、この本を純粋に読みたいという気持ちから購入したのではなく、考察のためと割り切って自腹購入して読んだ。二人の著者についても、名前こそ目にしたことはあるが、他の書籍も読んだことはないし、セミナー等にいったこともない。人となりは全くわからない。よって、ファンでもなければアンチでもない。
だが、私自身、この世のありさまには広く興味があり、スピリチュアルや占いも、好奇心や関心や問題意識をもって接している中で、つながりのある人々が複数名、短期間のうちにSNS等でこの本を推奨しはじめたことから、この本の存在と流行を認識した。
短期間で特定の界隈に集中的に引き起こされるブームというものは、何かしらの意図を持って引き起こされているものだと思っているので、モヤっとした。ただ、害がなければ、自分を外側に置いて眺めていれば良いので、放っておけば良いと思っていた。
だが、書籍と同時に拡散された動画等において、怖がらなくていいよと言いつつ、何らかのインパクトある出来事が日本人に起きるとされる年月日を、はっきり述べていたことが引っかかり続けた(年月日を知りたい人は動画を見るなり調べるなりしてください)。
災害に関する他の予言内容やらが、この動画等で述べられたインパクトのある出来事が起きるとされる年月と一致しているらしく、一斉にその年月日がクローズアップされ、見た人の意識にインプットされている様子がうかがえる。
このようなムーブは、組織的あるいはマーケティング上手なスピオカルト業界によくみられる、終末を仄めかして不安を醸成、自分たちの理想にとって都合の悪い現状を否定し変革を正当化する流れの端緒となるパターンに、ちょっと似ているようにも感じられ、私の中の警戒アラート(黄色信号)が点灯した。
存命中に、すでに阪神淡路、東日本、北海道、熊本の大地震を目の当たりにしているので、いつ来てもおかしくない災害への備えは、そこそこやっている。世界のありさまを自分なりに観察し、政治や経済や既存宗教の転換期を迎えているであろうことも知っていて、不十分かもしれないがそれなりの準備はしている。
だが、具体的年月日を提示して(時間がないというアピールとなる)、自分たちの主張する方向に「生き方」を変えることを説くやり方には、どうにもきな臭さを感じてしまうのが私だ。
そこで、まずは「大切な人へのプレゼント」にも使われブームを引き起こしているこの本が、どんな思想に基づいて書かれたものなのか、原著を確認の上把握しておく必要性を感じた。
圧倒的マイノリティの視点を投じる。
前置きが長くてすまない。私のまわりにいるこの本の読者層では、素直で疑うことを知らず、現実世界や競争世界では生きづらいと感じているけど、人の役に立ちたいと願っている、いわゆる繊細な良い人の声が大きい。私のように、冷静に一歩引いて違和感を持ってこのブームを眺め、批判的考察により多面的な検討をしていそう人は、残念ながらいない。ブームに乗らない私は圧倒的マイノリティだ。
他の人の考えや社会規範をそのまま受け入れるのではなく、自身の知識と直感を基に何が大事か判断して、それを見失わないよう努める人が提唱者です。
Amazonのレビューをみてみたが、思った通り、似たような賛辞で溢れかえっていて、辛口のレビューはごくごく僅かであった。まあ、これは、ファン化に成功している作家本のあるあるだ。
そこで、小さな小さな一石を投じる視点を提供するため、最も稀な性格とされるINFJ-A提唱者の性質を持つわたしの言葉が通じそうな場所として、ここで、率直につらつらと、「ここは共感できる」「ここは確証バイアスがかかりすぎている」「ここは納得できない」「ここはまったく共感できない」など、感じたことをとにかく書き残してみようと思い立った。
この記事を読まなくていい人。
両氏への誹謗中傷、人格攻撃などはする必要がないので一切含まないが、もし、あなたが、両名のファンであり、信者であり、本の一言一句に心酔なさっていて、彼らと同じ世界観の中だけで生きることを幸せだと定義している人ならば、この先は読まなくて良いと思う。
同じ周波数を有する人々の中だけで生きられれば幸せであり、異なる見解に触れることで、わざわざ心を揺らす必要はない、異なる見解は忠誠心を試すために天から使わされた悪魔のような存在である。このようにお考えなら、無理する必要はない。きっと私の言葉は通じない。私たちの間には、「あたたかい境界線」があるのだからそれで良しとしようじゃないか(本を読んだ人にはわかると思う)。あなたの価値観に揺らぎが生じたら、また戻ってきて読んでほしい。
この記事を読んでみて欲しい人。
もし、あなたが、この手のブームに一抹の違和感や危機感を持っていたり、コミュニティ内で人と密接に関わり続ける生き方を真似したいとはどうしても思えなくて肩身の狭い思いをしていたり、一つの世界観に引きこもり大いなる何かの翻訳者を名乗る教祖を崇め奉るより、さまざまな見解に触れることを生きる喜びとしている稀有な自由人なのであれば、何かしらの気づきを提供できるのではないかと思う。
誰が何と言おうと、世界が求めている、地球の意志だ、救世主だ、何だかんだと言われようと、奇跡と表現されているこの村の外に、縄文というキーワードが支配しないところに、あなたの居場所を求めたって良い。今日も自分の人生を精一杯生きる。生きる場所は自分で選ぶ。それで良い。そんなふうに感じてもらえたら嬉しい。
前置きを含めて、時間をかけて書いたので、文字だらけでちょっと長くなってしまったのだが、お時間があるときに、ゆっくり目を通してみてほしい。
目次を見れば大体わかりそう。
「今日誰のために生きる?」というタイトルや著者名を目にしても、まったく知らない、見当もつかない、というあなたのために、以下にAmazonに掲載されている目次を転載する。目次を見れば、どんな内容か、80%くらいわかると思う。
SHOGEN氏パート(アフリカのとある村での学び)と、ひすい氏パート(学びを日常に落とし込むワーク)の二部構成だ。
プロローグ――「効率よく生きたいのなら、生まれてすぐ死ねばいい」ひすいこたろう
Part1 ずっと幸せであり続ける奇跡の村 SHOGEN
ようこそ、ブンジュ村に!
1 その絵を見た翌日、僕は会社に退職届けを出した
2 200人の小さな村、ブンジュ村との出会い
3 ブンジュ村に伝わる「幸せの3か条」
4 世界一美しい仲直り
5 フラミンゴの羽の上で寝る
6 「言葉は抱きしめるようにして話すんだよ」
7 お腹いっぱいになったら、歌おう! 踊ろう!
8 ブンジュ村の挨拶「今日、誰のために生きる?」
9 仕事を愛する大人たち
10 残業しない理由
11 「私は、あなたのことを信じてる」
12 失敗した人は「人間らしいね、かわいいね」
13 失敗が満員御礼になる日
14 言葉より行動
15 一番大事なことは、まず自分を大切にすること
16 自分が、自分の一番のファン!
17 血の繋がらない家族
18 人を思う時間
19 あきらめる時間がくる幸せ
20 夢を叶える意外な方法
21 自分らしく生きる覚悟
22 思いを丁寧に伝える挑戦
23 思いを伝える「愛のリレー」
24 2日前のお昼ご飯、何を食べたか思い出せる?
25 おじいちゃんは、シャーマン
26 虫の音を聞ける日本語の秘密
27 世界語「ムシノシラセ」
28 日本人が虫の音が聞こえなくなった時、地球の破壊が始まる
29 まず、息を整える
30 ブンジュ村から帰ってからの僕
番外編 タンザニア日記1 夏の思い出、ファンタのパッションフルーツ味
番外編 タンザニア日記2 初めて見た、時間に追われるタンザニア人
part2 幸せがずっと続く6つの秘訣―シックス・センス ひすいこたろう
日はまた昇る
幸せがずっと続く秘密
・「私」と「あなた」は本心で繋がっている
・自分を満たすと周りも幸せになる
・奇跡なまでに平和だった縄文時代!
①小さな幸せが、一番大きな幸せだと気づくことから始める
WORK:「ハッピー習慣」を身に着けよう
②自分の本音を大切にする
・気持ちを分かち合うと「物」は「物語」になる
・気持ちを伝えることが平和の原点
・「和える」と「混ぜる」の違い
WORK:自分の本音に気づく
③無駄を大切にする(効率を求めない・今ここを楽しむ)
・日本はよりよい世界を創造する力をすでに備えている
WORK:今ここを楽しむ
④ダメな自分を「かわいい」とゆるす(完璧であろうとしない)
人間にできてAIにできないこと
WORK:唯一無二の主人公を生きる
⑤一番身近な大自然、体の感性を取り戻す(五感を磨く)
・「中今」を生きるとは?
・日常を丁寧に味わうと生活がアートになる
WORK:日本人の感性を取り戻す
⑥歓喜する!
・歓喜代表・岡本太郎と縄文人
・今ここ、日常こそ神々と繋がる扉
●WORK 最後に宣言しよう!
エピローグ――今日も、自分のために生きる SHOGEN
エピローグ――僕らのニュージャポニズム! ひすいこたろう
要するにこういう本だよね。
「かつての日本人らしさ」礼賛。
今の日本人の生き方は、アフリカの人口約200人の自給自足の村人の、ゆとりある生き方と比べて、人間の生き方として幸せとは言えない。でも本来、日本人こそ特別で、日本人こそ自然に愛され、日本人こそ世界を幸せに導けるはずで、その村人たちも、村のシャーマンの交信を通して、そのかつての日本人らしさを学んだから、ゆとりある豊かな生き方ができている。あなたも「かつての日本人らしさ」を取り戻して生きると決め、「日本人の血の記憶」「細胞の記憶」を呼び覚ませましょう!!と言っている本である。
(ちなみに、この人口200人の小さなブンジュ村、タンザニアにあるということで、どんな場所なんだろう?と調べてみた。BunjuというUrban Wardがあり、2022年時点で人口92,587人と書いてあるサイトに行き当たった。Google Mapの航空写真で見てみると、比較的大きめの町に見えた。まさかこんなにすぐわかる嘘を、出版社も巻き込んで堂々と展開するはずがないので、ここではない、Google Mapにも乗らない、検索しても出てこない、人口200人の自給自足の小さなブンジュ村がタンザニアのどこかにある、ということなのだろう。)
シャーマンを通して「かつての日本人」から教えを受けたという村人たちが守っていること
電気が使えるのは1日に3~4時間で、ライフラインはほとんど自然に頼っている、月2万もあれば十分な暮らしができるという村の幸せの3箇条はこんな感じ。
・食事に感謝できるかどうか。(感謝の心を持って丁寧に味わう)
・おかえりを言い合えているか。(コミュニケーションを大事にする)
・人の温もりをあたたかいと感じられるか。(肌の触れ合いを大切にする)
これらの大前提には、「ゆとり」「共有」というものがあって、心に余裕を持って、自分をまず満たし、あたたかい自分で他人を満たし、愛を持って日常生活を過ごせれば、お金(紙幣)に価値がなくなる時代になっても、生きていけるのだ、と説かれている。
要するに、大都会で暮らし、時間に追われ、自己犠牲的に働いていて、家族とのコミュニケーションが薄め、というステレオタイプな現代日本人像を、SHOGEN氏と人口200人の村人の交流を通して、人間らしくないと批判し、幸せになるためには、「かつての日本人」らしい生き方に転換するように促しているのであろう。
まあ、私自身も、満員電車に揺られて、働く時間と場所をきっかり決めて、お金のためにと、心身を労わらずに働くことは、もうできないと思っているし、晴耕雨読で季節の移り変わりを楽しみながら生活できたらいいよなあ、とは思う。
プロローグを含めた全体の印象は、、、
本編のSHOGEN氏パートには、共感できるところも数多くあったが、プロローグとエンディングをひすい氏が担当されていることもあり、私には、全体的に、「日本人が〜縄文が〜」の大合唱が、やや押し付けがましく感じられた。
争いがない平和なユートピアだった縄文時代に生きた日本人らしさを、ゆとりを、豊かさを取り戻そう、日本人がかつての感性を取り戻し、目覚めることが世界に求められている!という筋だ。
そういえばこの人は、予祝(「いま、喜ぶ。いま喜びに浸る。すると、未来においても喜びがやってくる。古代日本人がやっていた、夢の引き寄せの方法。」とされる。)を推している人である。
ひすい氏の信じる世界観のストーリーに、「なぜか不思議なことに、アフリカの小さな村に、シャーマンを通じて古代日本人の生き方が人知れず根付いていて、その日本人らしさを、村人との交流で取り戻した」とする現代日本人SHOGEN氏の体験談は、もってこいのピッタリの相性なのだろう。書籍内では、二人の出会いが、偶然の重なりで、あたかも何らかの大いなる流れ的なものに沿ったものと言う雰囲気たっぷりに、紹介されていた。
とにかくこの辺が気になった。
プロローグからエピローグまで、ひたすら持ち上げられる「日本人」が、「血の記憶」という言葉に滲み出ているように遺伝子レベルの話であるように思われ、人種で区別して、優位性を煽る側面もあるなと思いながら読み進めた。
そして、そもそも、この本の拠り所である、縄文時代が平和なユートピアだったという説には反対説もあることを、私は知っていた。
幻想かもしれない縄文ユートピア説に多くを依拠し、「日本人」の「血の記憶」という表現をしている本書の主張に、素直に身を委ねる気持ちにはなれないのは仕方がない。
まずは、縄文時代は平和なユートピア説に基づく縄文崇拝への疑問について、書くことにしよう。
盲目的縄文崇拝への疑問
本当に縄文時代はユートピアだったのか?
武器が出土していないので、縄文人は武器を持たなかった。争った形跡がなかった。縄文時代は奇跡的に平和な時代だった!!という言説は、昨今の縄文ブームに乗った某政治団体のパフォーマンス等を通じて目にしている人も多いのではなかろうか。
しかし、実は、縄文社会の平均寿命は10代前半とされており、「あまりに貧しくて人口が増えず、人々は戦争を起こす余力もありませんでした」ということではないか?とする説も存在するのである。(縄文時代は豊かで平和だったというのは本当か?「ユートピア」説に抱く疑問より)
実際、縄文時代の平均寿命は10代前半だったとされる。女性は子供を産める年齢になると、妊娠と出産を何回か繰り返し、子供をもうけるが、その多くは幼児のうちに亡くなり、10歳を超えるのは4割程度。出産自体も危険を伴った。
縄文時代に戦争がなかったという言説の最大の拠り所は、出土する人骨に戦死の形跡が乏しいことだとされる。けれども、平和だったはずという先入観を抜きにして、武器の変遷なども考慮して、より詳しく調査し直すべきだという意見がある。そうした見方を示す論文(「受傷人骨からみた縄文の争い」内野那奈・伊丹市教育委員会嘱託=執筆時点)もある。
また最近になって北海道の有珠モシリ遺跡で縄文時代後期における戦争の跡が見つかった(共同通信「頭に傷痕、複数の縄文人骨発見 集団間で争いか、北海道」)。多数の戦死者が出土したことに、個人の考古学愛好家も関心を示している。
縄文時代は平和説に対して、「平和だったはず、そうであってほしい」という先入観を抜きにして調査をすべき、という懐疑的な立場もある、と知っている人は、本の読者にどのくらいいるのだろう?と思った(まあ、ゆとりが大事で、信じることが大事だから調べないかな。。うまく教育されているなあ。)。
確証バイアスで集めた情報のみで、あたかも真実であるかのように断言され、それを信じ込むこの手の縄文崇拝は、私の目には、どこか宗教めいたものに映る。
この懐疑的慎重論の存在を知った上でも、会ったこともない誰それさんのことを信じきる、懐疑的慎重論はグローバリストによる日本を貶める陰謀だから絶対耳を傾けない、という、慎重さを欠き、狭い視野+周波数奴隷+上書きポジティブシンキング属性の人たちは、今後も縄文ユートピア説を盲目的に支持し、何なら外の世界と隔絶されたコミュニティーに引きこもるのであろうか。それは、本当に自由意志なのだろうか。
不安定な時代には、自分をつなぎ止める「わかりやすい」ものを外側に追い求める人たちの心に、宗教的なものがするりと入り込んでいくものだが、コロナ禍・戦争の拡大・経済不安という社会情勢下に置かれた人々にとっての縄文崇拝が、そうではないことを祈る。
私は、幻想かもしれない縄文ユートピア説に、多くを依拠している本書の主張に身を委ねる気持ちにはなれない。
火焔型縄文土器だけ使っていたわけじゃないよね?
もうひとつ、縄文土器について触れておきたい。プロローグ内で、ひすい氏は、無駄を楽しむ精神こそが幸せな生き方には重要であるとして、有名な火焔型縄文土器の写真を見せつつ、「火で焦げた部分や吹きこぼれのあとがあることから、食べ物の煮炊きに使う土器だとわかっていますが、ここまで世界観を盛り込んで作っちゃうと、煮炊きに使いにくい、使いにくい!」「でも、これぞ、無駄を楽しむ精神の結晶、ニッポンの心の原点だと言っていい」「かつての日本人が無駄を楽しんできた決定的な証拠」とまで述べておられる。
だが一方で、「何らかの儀式用にも使われていたのでは?」「火焔型土器は一般に祭りなどの儀礼に使用することがあったと思われていますが、いまのところその使用状況を示す証拠は得られていません。内面にオコゲが付着することがあるため、煮炊きに使われたことは確実です。」という記載もあり、「かつての日本人が無駄を楽しんできた決定的な証拠」と盛り上げて断言するには、少々心許ないのでは?過度の一般化では?とも感じる。
そもそも縄文土器には、火焔型だけではなく、日常使いの簡素なシンプルなものだって、たくさんあるのだ。縄文人は、岡本太郎の目を引くような、国宝たる火焔型縄文土器だけを、使っていたわけではないのだ。だいたい、約10,000年という長い長い時間を指して「縄文時代」と言うのだから、変遷があるのも当然であろう。
この本は学術書ではないので正確性を犠牲にして伝わりやすさを優先しています、ということかもしれないし、信者内では、小さいことは気にするな、失敗したって大丈夫の精神で丸くおさまることかもしれない。
決して粗探しがしたいのではなく、私レベルの素人でも、疑問に思い、ちょっと調べたらすぐ出てくる情報をみてみた範囲では、縄文ユートピア説も、少々強引な火焔型縄文土器へのラベリングも、「こうなんじゃないか?」「こうであってほしい」と言う遺跡関係者も含めた一部の人々が、声高に持ち上げすぎた結果なのかもしれないな、と感じたから、このまま書き残しておく。
日本人は幸せで上機嫌だったって本当?
これもひすい氏パートのプロローグで違和感を覚えた部分。
「江戸時代末期、海外から日本にやって来た外国人たちは、日本人を見て口々に、」「日本人は幸せで満足している」「町中に上機嫌な様子が行き渡っている」「顔がいきいきしている」「と記しています」と述べている。
学術書ではないので正確性を犠牲にして伝わりやすさを優先、なのかもしれないが、大きすぎる主語には警戒心がはたらく性質なので、ん?と引っかかった。(情報商材・セミナー・マーケティングライティングでは、購買行動に結びつけるためには、正確性よりも、断言するように推奨されることがあるのを知っているのでね。)
「黒船でやって来たアメリカのペリー提督」「イギリスのオズボーン艦長」などの外国人(要人)の記録を根拠にしているわけだが、彼らが会った日本人とは、どのような属性の人たちだったのだろう?温暖なエリアに住み、大都市江戸や、開かれた港や、あてがわれたエリアにいる、異人相手の商売をしていたり、自分たちに好意的な、オープンマインドな気質の日本人数名に抱いた印象のみで、日本人は〜と書いていたりしないのだろうか?
江戸末期といえば、言わずと知れた幕末の混乱期であり、生麦事件も起きている。薩摩の侍だって、日本人のはずだ。被害に遭ったイギリス人は、この日本人に対してどんな印象を持っただろう?
まあ、このような◎◎人論については、「そういう見方もあったかもしれないね、この人たちが出会った人はそうだったんだね」くらいの受け止め方で、ちょうど良いのかもしれないな?と私は思っている。
そもそも「日本人」って何を意味しているの?
国籍?居住地?遺伝子?
さて。「平和だと信じている」「無駄を楽しんでいたと信じている」縄文時代からの「日本人の血の記憶」を呼び覚ませば、世界や地球を救えるという主張についてであるが、この本に限らず、この手の主張では、「日本人」ってどういう意味で使っているのだろう?と不思議に思った人はいるのだろうか?
国籍?定住?なんとか遺伝子の有無?ここら辺は、客観的に該当するかどうかわかるけれど、日本人らしい心を持っているかどうか?などと言われては、解釈の安定性を欠き、結局、あなたはOK、あなたはだめ、とインフルエンサーの鶴の一声で決まる、みたいなことにならないといいな。と思っているが、どうだろう?
人種で優劣や役割を決めてないよね?
本書内では、「血の記憶」「細胞の記憶」と言っている以上、素直に読めば縄文人に特有とされる遺伝子を持つ人のことを指すのかな?と推察している。わざわざ「血」というのだから。たとえば、帰化した日本人であっても該当する、とおっしゃるのであれば、「血の記憶」云々の表現は、誤解を招かないように、さらに工夫が必要かもしれないと思うのだが、いかがだろうか?
この本では、日本人といえば、縄文人に特有とされる遺伝子を持つ日本人のことを指しているとすると、その日本人を「世界で一番自然から愛されていた人種」と表現し、日本人こそが世界の幸せに導ける、など、人種で優劣や役割をナチュラルに決めている、と受け取れそうな表現があることが終始気になった。
人間の特性、態度、能力、行動は、人種的な特質によって左右されるという考え方は、まさにヒトラーの施策を支えたものだ、と言えば、私の懸念が分かっていただけるであろうか?(ヒトラーを擁護する説もあるのは、何となく知っているがここでは横に置く。)
ナチスはまた、人種の質的階層を想定し、すべての人種は対等ではないとしました。 ヒトラーは、ドイツ民族は「アーリア人」と呼ばれる卓越した人種であると信じていました。 ドイツ人は他のすべての人種に勝る才能に満ちた「アーリア」人種であり、生物学的な優位性で東ヨーロッパ全土にまたがる巨大な帝国を支配する運命にある、とヒトラーは確信していました。
もし、遺伝子的に日本人であることに盲目的に心底酔いしれ、自己価値を高められたとし、世界・地球を救えるのは自分たちだけだ、と強く信じ込んでいる状態だとしたら、かのアーリア人至上主義とそれほど違わないようにも感じ、暴走したその行き先を想像すると、ちょっと怖いな、という思いを抱いた。
もちろん、私たち日本人はそんなことしない、ナチスとは違う、そんなつもりはない、と言うだろうけど、大衆を煽動して暴力によってでも他者を傷つけても変革を起こしたい人たちは、上手に意図を隠すので、変に利用されないようにと願う。
(なお、スピ業界では、宇宙由来の魂だとか、何とか星人だとか、前世が何だとか、とにかく、自分すごい!アピールのために、スケール化された分類のうち上位の魂だ、役割はこれだ、みたいなことを誇らしげに語る人々がいる。こう言う人たちに対しても、私は、かのアーリア人至上主義と似たような思考のかけらを見出し、あまり近づかないようにしている。悪人ではないんだけどね。)
押し付けられたら幸せじゃないのよ
ありがたいと思えるのは遺伝子のせいじゃないと思う。
私は、国籍も居住地も日本だ。知る限り先祖は父方母方ともに日本人であるが、何年か前に受けたDeNA社の遺伝子検査では、ハプログループが明示されず「アフリカ起源」という結果が返ってきた(母系ミトコンドリアはみんなそうなんじゃないかw)。自分は日本人です、ということに何のためらいもない。
海外を10カ国以上は訪れた経験に基づく実感を込めて、四季に彩られた日本の風土を愛していると心から言えるし、古き良き湯治場で癒されたり、注目されずひっそりと悠久の時を刻む遺跡を訪れてしみじみと感じ入ることもあるし、清潔感や節度のある振る舞いに触れて安心することもあるし、繊細な伝統芸の職人技に感嘆することもある。お米と、なめこ入りのお味噌汁と、納豆と、芋がらの煮付けと、温泉卵と、たまに魚とお肉が美味しくいただければ、十分満足できる。
他国・他民族との交流を経て、ダイナミックな混在と淘汰とを繰り返した結果、今、目の前にいる人や、残存する建物や、文化や、景色を慈しんでいる。大内宿も好きだし、赤煉瓦の洋館も好きだ。そばがきも好きだし、カステラも好きだ。
災害リスクを呑み込めば、日本に住み続けられていることを、心からありがたいと思っている。
私に日本人の遺伝子が流れているから、その人にもあるから、そういう人が作ったから、ではない。日本人の遺伝子を持っているかどうかなど、特段意識せずとも、幸せを感じることはできると思っている。
「日本人なのにできないの?」なんて言われたくないな。
SHOGEN氏のパートに、村の子どもたちから、「日本人なのにできないの?」と言われたというくだりがある。日本人は、虫に伝えたいことを託して、伝えたい人のところに飛ばした、と聞かされて信じている子どもが無邪気に言っていることではある。目くじらを立てる必要もないのだろうが、日本人イメージを押し付けられることには、違和感と抵抗感がある。
SHOGEN氏は、このような反応は、日本人へのリスペクトがあるから、期待があるからこそ出てくる、と表現するが、どうもモヤつく。
そもそも、この人口200人の自給自足のアフリカの村で、村長が子どもたちに語って聞かせた日本人イメージの出所は、村長の祖父であるシャーマンが日本人と遠隔交信したと言う内容に基づいている。
私は、シャーマンなどの存在が全員嘘つきと言うつもりはないし、人智が及ばぬ見えない世界もあるだろうと思っている。このシャーマンの言っていることも、あるかもしれないね、とは思う。
しかし、これって、神秘に名を借りた、現代に生きている日本人を遠く置いてけぼりにした日本人論ではないか。とも、感じるのだ。
こんな押し付け日本人論を、「正解」であると素直に丸ごと受け入れることが、私には難しいのだ。
「日本人なのにできないの?」なんて言われたくないのだ。
押し付け日本人論のもとで心のゆとりが失われる日本人がいるよね。
私はれっきとした日本人ではあるが、理性も合理性も、秩序やルールも大事にするし、自分の時間を確保するために効率を求めることもある。そもそも、かの村に入ることは許されない属性であろうが、あえてここでハッキリと言う。
人口200人のアフリカの村の人たちのように生きたい?それが幸せ?と問われたら、
「心にゆとりを持つことは大切だと思う。自給自足もある程度できたら素晴らしいと思う。田んぼの蛙の鳴き声や、秋の鈴虫の音もリラックスできて好きだ。でも、共有文化に組み込まれ、他者との境界が曖昧で、プライバシーがなく、積極的なコミュニケーションに晒され続けるスタイルを今押し付けられたら、むしろ心のゆとりが失われて、すごく不幸せだと感じます。」
と答えるであろう。
交わした約束やルールは大切にしたいし、パーソナルスペースも必要だし、とにかく決めつけられることが大嫌いな私にとっては、かえってゆとりを感じられない生活になる。だから、想像の範囲ではあるが、幸福になれるとは思えないのだ。
過度な共有文化とルール軽視社会はキツい。
まず共有文化。
血のつながりはなくてもみんな家族。包丁や調味料や洋服もシェア。外に干してある洗濯物だって着たい人が勝手に着ていい。むしろ「着てくれたんだ」と思う。そんな世界観。
これみなさんうらやましいの?私はたぶん気絶すると思う。所有の概念を敵視するスピの人って多いと思っているんだけど、私は、線引きをしっかりする環境で安心できる人。ちょっとした貸し借りは大丈夫ですが、勝手に洋服を持ち出されても普通、勝手に着用されることが普通、と言われたらゾワゾワして、安心できないので、心のゆとりがなくなる。
ルール軽視。
なかなか入手できない段ボールの取り置きを、商店の人と約束していて、遠路はるばる取りに行ったら、別の人の手に渡っていることが普通!
用途をいちいち丁寧に説明しないと、欲しい商品の取り置きの約束を一方的に反故にされることがあり、しかも、事後報告であるという状況を、甘受しなければならないなんて、絶対お断りである。
たとえ丁寧に説明することで、想いの循環が起きて、何らかのハッピーな結果になるかもしれないとしても、お断りである。
西洋的な思想だ!貧しい思想に洗脳されている!と言われても、私は、現代の商慣習・法令に基づく、安定的に秩序ある取引ができる場所を好むし、選びたい。
民族浄化思想につながらないことを祈る。
この本の多くの善意の読者たちは、彼らが心酔する日本人論に馴染まない人を排斥したり、日本人じゃないんじゃないか、などと主張することはない、と信じている。
ただ、自分たちの感覚に合うコミュニティをつくりたいだけで、自分たちが優れた人間であるとか、世界を救うとか、そんなことは思っていない。あたたかい、心の通ったコミュニケーションを大切に生きたいだけで、人との距離のとり方を押し付けるつもりはない。そんな人が多いのだろう。
万一、日本人種優越論のような主張が色濃くなり、自分たちと違う生き方を望む日本人を日本人ではないと声高に主張するようになったり、排斥するような動きが出てきたら、それはまさに、民族浄化につながり得るものであり、平和とは程遠い、強い思想に絡めとられている証左となろう。政治団体と組むようなことがあれば、超要注意だと思う。
今生きているのは私たちだ。
万一、この本のファンの人や、信者の人たちが、私のような人間を指して「日本人らしくない」と言葉にして放ったり、蔑むような言動があったり、「日本人らしくあるべき」と無理に染めようとするのなら、こうお伝えしたい。
今ここで生きている、お互いの生命をリスペクトしましょうよ。私たちの間には、あたたかいサーモンピンクの境界線があるのです。それ以上踏み込まないで。仲違いの原因はきっと解決しないけれど、とりあえず表立って喧嘩するのは終わりにしましょう。現代に生きている日本人を遠く置いてけぼりにした日本人論をきっかけに、日本人が分断されるなんて、残念すぎるでしょう?
SHOGEN氏の「世界一美しい仲直り」のパートを読んだ人になら伝わるかな?と思う。
共感できたこともあるから書いておく。
SHOGEN氏のパートで、素敵だな、共感できるな、と思った部分があるので、いくつか、簡単に触れておく。
ちなみに、ひすい氏のワーク部分については、さらっと読んだ。忙しいは心を亡くすと書く、とか、混ぜると和えるは違うとか、長所✖️短所=魅力とか、セミナーなどで、よく見かけるキーワードとか言い回しが多く見受けられたな、というのが率直な感想である。ワークをやることが大好きな人にとっては、きっと有用なのであろう。
以下SHOGEN氏のパートより。
仲直りの方法
仲違いした時は、その日のうちに終わらせる。人間は自然から生まれてきたから、大自然に包まれたらすべてを許せる。原因は解決できなくても、お互い生きられているんだから、と終わりにする。本の中では、ケンカした相手と一緒に夕暮れの海に入り、水面に映るオレンジの夕陽の光の束を指して、「あたたかい境界線だよ」と言う場面が出てきていた。
人と話すときの態度
人と話すときは、その人を抱きしめるようにして話す。あいさつも、相手の顔をみて、その人の状態を感じて、声をかける。抱きしめられた時の心の色はサーモンピンクの夕日の色。体温が乗った、あたたかいコミュニケーションの秘訣。
失敗したってかわいい
大人でも失敗するから、子どもも安心できる。
失敗は恥ずかしくない。隠さないでオープンにする。
失敗やヘマをしたら「人間らしいね。かわいいね」って言う。
不完全でもかわいいと肯定されるから安心する。
まず自分を満たしてから
愛が注がれたものからしか、愛を与えることはできない。自分に愛を注ぐからこそ、周りにも愛を注げる。まず自分を満たす。自分のいちばんのファンとして自分を愛する。自分の心を満たしてはじめて、本当の意味で誰かの力になれる。
自分らしく生きる場所は自分で選ぶよ。
私は自分を満たすために、無理に彼らの楽園に身を置かないことを選択する。
私の喜びは、知的好奇心を満たし続けることそのものにあるし、批判的考察をすることも喜びである。安心できる環境にあってこそ、喜びを感じられるので、過度な共有文化の元、ルールが軽視される傾向にある社会は、私にとっては歓喜できる楽園ではないのだ。
この本のように生きなければ幸せになれない。
そう思った瞬間に、幸せではないのだ。
私が自分らしく生きる場所は自分で選ぶ。その一言に尽きる。
もし、この本を読んで、自分が否定されたように感じてしまった人がいたら、私のような考えの者もいるよ、安心して、とまずはお伝えしたい。
彼らの楽園に行きたいと、行かなければではなく、行きたいと、そこで生きたいと心から願うのであれば、あたたかい境界線の向こう側で生きてみたら良い。
繰り返すが、この本のように生きなければ幸せになれない、そう思った瞬間に、幸せではない。あなたの喜びは、あなたがいちばんわかっているはずなのだ。他の誰かに決めさせてはならないよ。
もし、あなたが、この本のファンでありながら、この長い記事をここまで読み進めてくださったのなら、感謝とともに、再度お願いする。
日本人種優越論のような主張が色濃くなり、自分たちと違う生き方を望む日本人を日本人ではないと声高に主張するようになったり、排斥するような動きが出てきたら、それはまさに、民族浄化につながり得るものであり、平和とは程遠い、強い思想に絡めとられているのだと、警戒心を持っていただきたい。
終わりに
特にこの2年くらい、縄文・古代日本担ぎ、共有文化やコミュニティづくり推奨ブームにモヤモヤしていた違和感を、なんとか言語化できたように思う。
この本を読んだおかげで、モヤモヤの輪郭がはっきりした面があるので、この本の著者である両氏にお礼を申し上げる。
また、作家でも何でもない、素人の感想文をここまで読んでくださったあなたにも、お礼を申し上げる。ありがとう。
もし何かしら、あなたの気づきにつながったのなら、いいねを押してもらえると、とても励みになるので、お願いしたい。
自分のために生きると決めている私の喜びは、さまざまな知識に触れ、噛み砕き、自分の中の情報図書館にインストールすることで得られる。
考古学や、人類学や、歴史学等を学ばれている人の視座や視点で、こういったライトな本への客観的な批評が書かれたものがあればいいなあと思う。もしあれば、今後、積極的に読んでいきたい。
もしよろしければサポートを検討なさってください。いただいたサポートは、良質な記事を書くための書籍等購入や環境整備のために、大切に使わせていただきます。
