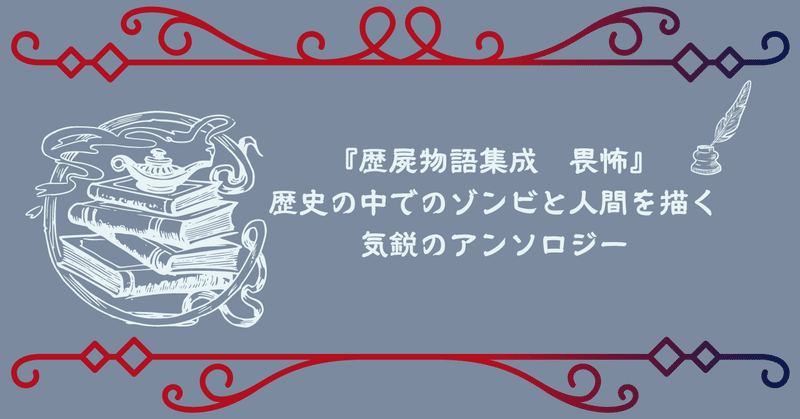
『歴屍物語集成 畏怖』 歴史の中でのゾンビと人間を描く気鋭のアンソロジー
はじめに
様々な作家と作品に巡り会えるアンソロジーという形式は胸がときめくものですが、それが現在の、そしてこれからの歴史小説を背負う面々の作品集とくれば見逃せません。それもテーマがゾンビ、つまり生ける屍者の物語とくればなおさら!
そんな本書に参加しているのは、矢野隆・天野純希・西條奈加・蝉谷めぐ美・澤田瞳子――いずれもデビュー十数年、蝉谷めぐ実に至ってはわずか四年という気鋭のメンバー。それぞれ独自の作風を持つ作者たちが、歴史上に現れた生ける屍たちを如何に描くのか――時代ホラーからは縁遠い印象の作家もいるだけに、大いに気になるところです。
ゾンビ時代劇というのは、他のメディアも含めれば実は決して少ないわけではないのですが、しかしこれだけの顔ぶれで描かれるというのはおそらく初めて。ここはやはり、一作品ずつ紹介するほかありません。
なお、本書の序章と終章では、東北に調査にやって来たある学者(幼い頃に何度か神隠しに遭い、官僚としての勤めの傍らに奇談を蒐集しているという……)が、不死と称する女から昔語りを聞く姿が描かれます。本書の全五篇は、そこで語られる物語という趣向です。
有我 一二八一年、壱岐(矢野隆)
気がつけば骸の山の中にいた男・海野三郎。記憶は薄れて言葉もまともに喋れず、自分の四肢も上手く動かせない彼を突き動かすのは強烈な渇き――自分がいたのは異国から来襲した敵の船だと知った三郎は、少しずつ自分の記憶を思い出しながらも、本能のままに船の中に死を撒き散らしていきます。
三郎に傷を付けられた者は彼と同様の存在と成り果て、死者が死者を生む地獄の中、三郎の向かう先は……
巻頭において本書の何たるかを強烈に示す本作は、元寇を背景に描かれる物語。デビュー以来、様々な「戦い」を描き続けてきた作者ですが、しかしこれだけ奇妙で奇怪な作品は、さすがになかったと断言できます。
何しろ本作の主人公は、ほぼゾンビになりかけの日本人武士。ある望みを抱いて異国の軍勢との戦いに赴いた彼が、何故かゾンビと化して目覚め、ほとんどゾンビ視点から物語が描かれていくのは、凄まじいとしか形容しようがありません。
さて、思わず無造作に「ゾンビ」という言葉を使ってきましたが、ここでいうそれは、生ける屍(アンデッド)という広義の意味であります。もちろん広義のゾンビにも様々なタイプがいますが、本作はいわゆるロメロゾンビ――緩慢な動きながら強烈な力を持ち、そして食人欲求に動かされ、傷を受けた者も同じ存在になり果てるという、一種吸血鬼めいた、しかし優雅さの欠片もない存在です。
これまでロメロゾンビが時代劇に登場することは皆無ではありませんでしたが、しかしそれを武士の成れの果てとして描き、半ば死者、半ば武士として戦わせたのは本作くらいではないでしょうか。
「何故」という点も気にならなくなるほど、凄まじい勢いで駆け抜ける一編です。
死霊の山 一五七一年、近江比叡山(天野純希)
比叡山の僧兵ながら、ごろつき同然に日々高利貸の取り立てに明け暮れる信濃坊。ある晩、恋人の百合のもとを訪れた彼は、近頃坂本で狐憑きが続発していることを聞かされます。
突然人が変わったように人に襲いかかり、体がボロボロになっても暴れ続けるという狐憑きを一緒に臥した信濃坊ですが――しかしその晩、百合の隣人たちが狐憑きに変貌、それだけでなく坂本中で狐憑きが出現し、無数の犠牲者が出ることになります。
百合を連れて逃げこんだ比叡山で、あまりに意外な狐憑きの正体を知った信濃坊。この地獄から何とか逃れようとする信濃坊と百合ですが……
戦国時代を中心に骨太の、そしてその中に時に奇想を交えた作品を発表してきた作者が描くのは、戦国時代の比叡山を舞台とした物語です。主人公の信濃坊は悪法師としかいいようのない男ですが、それだけにリアリストの彼が、突然現実を侵食する生ける屍たちに襲われ、恋人と逃れようとする姿が、一人称で生々しく語られていくことになります。
なるほど、ゾンビに追われての逃避行と立て籠もりは一種の定番ですが、それをこの舞台でこう描くのか! と驚かされますが、時代と場所から、終盤の展開はある程度予想できるかもしれません。
しかし、そこから最初のロメロゾンビ映画を思わせる悲劇を描きつつ、さらに一歩踏み込んで、残酷な運命の暴力に一矢報いようとする「人間」の姿を描いてみせたのには脱帽であります。
まさしく、作者ならではのゾンビ歴史小説というべきでしょう。
土筆の指 江戸時代初期、中部地方(西條奈加)
半月ほど前に亡くなった稗八の墓から、土筆のようなものが四本突き出しているのを見つけた小坊主の真円。しかしひとりでに蠢くそれが人の指だと気付いた真円は、兄弟子の実慧に慌ててそれを知らせます。
実慧が寺男の悟助に手伝わせて墓を掘り起こしてみれば、そこにいたのは半ば腐っているのに確かに動いている稗八。好奇心から彼を検分する実慧ですが、後に遺した恋女房の名を耳にした途端、稗八が暴れ出して……
前二作では激しいゾンビとの戦いが描かれただけに、まさかまさか西條奈加も――とドキドキしましたが、蓋を開けてみれば本作は、どこか民話めいた中に生々しさを散りばめた、作者らしさを感じさせる物語です。
他の作品と違い、本作がどこか呑気な空気を感じさせるのは、真面目で臆病な真円、探究心旺盛な実慧、異様に冷静な悟助の三人が、それぞれにゾンビにリアクションする姿に、妙な現実感があるからでしょう。その一方で、科学者的な視点で稗八を観察する実慧の姿にちょっと恐ろしさを感じたりもするのですが……
しかしそんな騒々しい状況の中で、やがて明らかになっていくゾンビ側の事情は、あくまでも深刻で切実なものであります。ここまでくると、むしろゾンビの側に人の情を感じてしまう自分に驚かされるのですが――そんな人間とゾンビが奇妙に絡み合う物語の末に描かれる、他の作品と一線を画すゾンビ誕生を巡る結末の一捻りにも理由にもまた脱帽なのです。
肉当て京伝 一七九三年、江戸銀座(蝉谷めぐ美)
何をしたってうまくゆく人生を送ってきた山東京伝が、妻に迎えた元遊女のお菊。彼女には遊女の頃から深く馴染んでいた京伝ですが、しかし彼女は突然、自分は実は陸に上がった人魚だと言い出します。
驚きながらもそれを受け容れ、仲睦まじく暮らす二人ですが、やがてお菊は病に侵され、日に日に弱っていくのでした。
しかし一度死んでも甦ると語った通り、亡くなった後に、京伝のもとに戻ってきたお菊。ところが生前の姿から変貌していく彼女を恐れるようになった京伝に対して、お菊は食事時にある行為を強いて……
本書の中で最も異色作というべき本作は、生ける死者の物語としては大きな変化球であると同時に、極めて切なく、そして恐ろしい愛の物語であります。
京伝の妻・お菊(実在の人物です)が実は人魚だった――というのも驚かされる内容ですが、そこまでは人間と化け者が同じ世界にごく普通に存在する、ある意味作者らしい世界ならではといえるかもしれません。しかし本作の凄まじさは、そこから先にあります。
強く愛し合った二人が幽明界を異にした時、その界を越えようと誓ったことから生まれる恐怖と哀しみの物語は、古今東西に(それこそこの国の始まりの時から!)存在します。しかしそれをこのような形で「料理」してみせるとは――タイトルに繋がる、作者の着想の卓抜さに驚かされます。
しかし本作は鬼面人を驚かすだけの物語ではありません。終盤にお菊が呟くある言葉――彼女の「熱くて粘り気のある」愛に応える覚悟を決めた京伝の想いと、ありのままの自分を受け止めてほしい彼女の想いの間に、どうしようもない断絶があることを突きつけるその言葉は、深くこちらの胸に突き刺さるのです。
極めて特殊な生ける死者の物語だからこそ描ける、しかし男と女の普遍的な愛のすれ違いの姿がここにはあります。
ねむり猫 一八二六年、江戸城大奥(澤田瞳子)
ある朝、大奥の長局の庭で息を引き取っているところが見つかった一匹の猫。その猫――徳川家慶の側室・お波奈の方の愛猫・漆丸の焼却処分を求める局女中に、漆丸を可愛がってきた部屋子のお須美は強く反発するのでした。
大奥に古くから現れる奇病「腐れ身」。人に限らず、犬や猫、鼠などに感染し、感染したものに咬まれたり、傷をつけられたりした者は、意識を失った後に同様の存在となって、周囲の人や獣の肉を食もうとする――漆丸は他所の局に現れた腐れ犬と組み合い、この病に罹患していたのです。
自分たちを守って罹患した漆丸、天涯孤独の自分を癒やしてくれた漆丸を焼くわけにはいかないと決意を固めたお須美。彼女は元部屋子だったというお半下の助けで、漆丸を連れて大奥を抜け出します。しかしそんなお須美と漆丸たちを、ある目的を秘めて追う侍たちの姿が……
本書の掉尾を飾る五番目の作品の作者は澤田瞳子――本書のメンバーの中で、おそらく最も「そうしたもの」から遠い作品を発表してきた作家でしょう。
はたしてその作者が如何なる形でゾンビを描くのかと思えば、最初の二作品に登場した感染するゾンビを描くだけでなく、大奥では実は古くから腐れ身=ゾンビ病が蔓延っていたという、伝奇性の強い設定に驚かされます。
しかしその設定にアプローチする切り口は、あくまでも作者独自のものです。
可愛がってきた猫がゾンビ化する運命を背負った幼い少女が、猫を慈しむ一心(この辺りの猫への想いが強く伝わってくるのは、作者が愛猫家なればこそでしょう)で繰り広げる逃避行。その中で彼女は、腐れ身を巡る残酷な事実と、それすら利用しようとする大奥の大人たちの思惑を知ることになる――大奥を題材とすることで、ゾンビを題材にこのようなドラマを描けるのか、と胸を打たれます。
そして特に印象に残るのは、作中の大奥に語り伝えられている側室・お紺の方の存在であります。
いつの時代のことか、腐れ身に感染した己の愛娘を完全に化け物となっても慈しみ続け、ついには時の将軍の命で、姫君ともども焼き殺されたというお紺の方――物語の終盤で明かされるその「真実」が示すものは、ほかならぬ大奥でゾンビが留まることなく生まれ続けている理由を(象徴的な意味で)暗示しているように感じられます。
もちろん、お須美を愚かと笑うことは容易いでしょう。彼女の行動は問題からの逃避であり、幼い愚かしさの現れなのかもしれません。しかし彼女が抱えた煩悶と苦しみは、間違いなく彼女が、利己心からあるいは人から命じられて動く「ゾンビ」だからではなく、「人間」だからこそ抱くものなのです。
どこか『ペット・セマタリー』を思わせる設定、あるいはゾンビ・パンデミックものの序章のようにも取れる設定から描かれるのは、あくまでも命の意味と重みを描く物語――お須美の覚悟に、どんなに小さくとも幸あれと祈るばかりです。
おわりに
以上全五篇――歴史上に現れた生ける屍者を真正面から扱いつつも、それぞれの作者らしい佳品であることは、これまで述べてきたとおりです。
そしてその物語の中で描かれるのは、かつては我々と同じ存在であり、そしてあるいは我々もいつかこうなるかもしれない(!)怪物
の姿でした。それは人外の魔族でも、宇宙からの怪物でもない、我々と地続きの存在にほかなりません。だからこそどの作品からも、そんな「身近な」存在だからこそ感じられる畏怖と悲哀が感じ取れるのです。
ゾンビという刺激的なテーマを扱いながらも、それぞれの作家性を発揮し、そしてゾンビを通じて歴史のifとその中での人間の姿を浮かび上がらせる――(私とは逆に)題材から敬遠する方もいらっしゃるかもしれませんが、食わず嫌いならさずに、ぜひお手にとっていただきたい一冊です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
