
それは、パクリではありません!【第1話】【全4話】
【あらすじ】
中井紀子は、本の制作に携わる仕事(小説家や、出版社など)に憧れていた。ところが就活、公募コンテストも上手くいかず、夢破れて編集プロダクションで派遣社員として働く日々。
ある日、紀子はインターネットで「漫画広告」を目にする。漫画は、紀子が小説サイトで綴っていた小説と、タイトルや内容が酷似したものだった。
作品をパクられたと感じた紀子は、漫画家をSNSで告発をするが、今度は名誉棄損などの罪で法的措置を取られる羽目に……。頭を抱えていた矢先、ファンと名乗る男性からDMが届く。男は弁護士で、紀子をサポートしたいと伝える。
著作権問題と戦う、派遣社員の奮闘ストーリー。
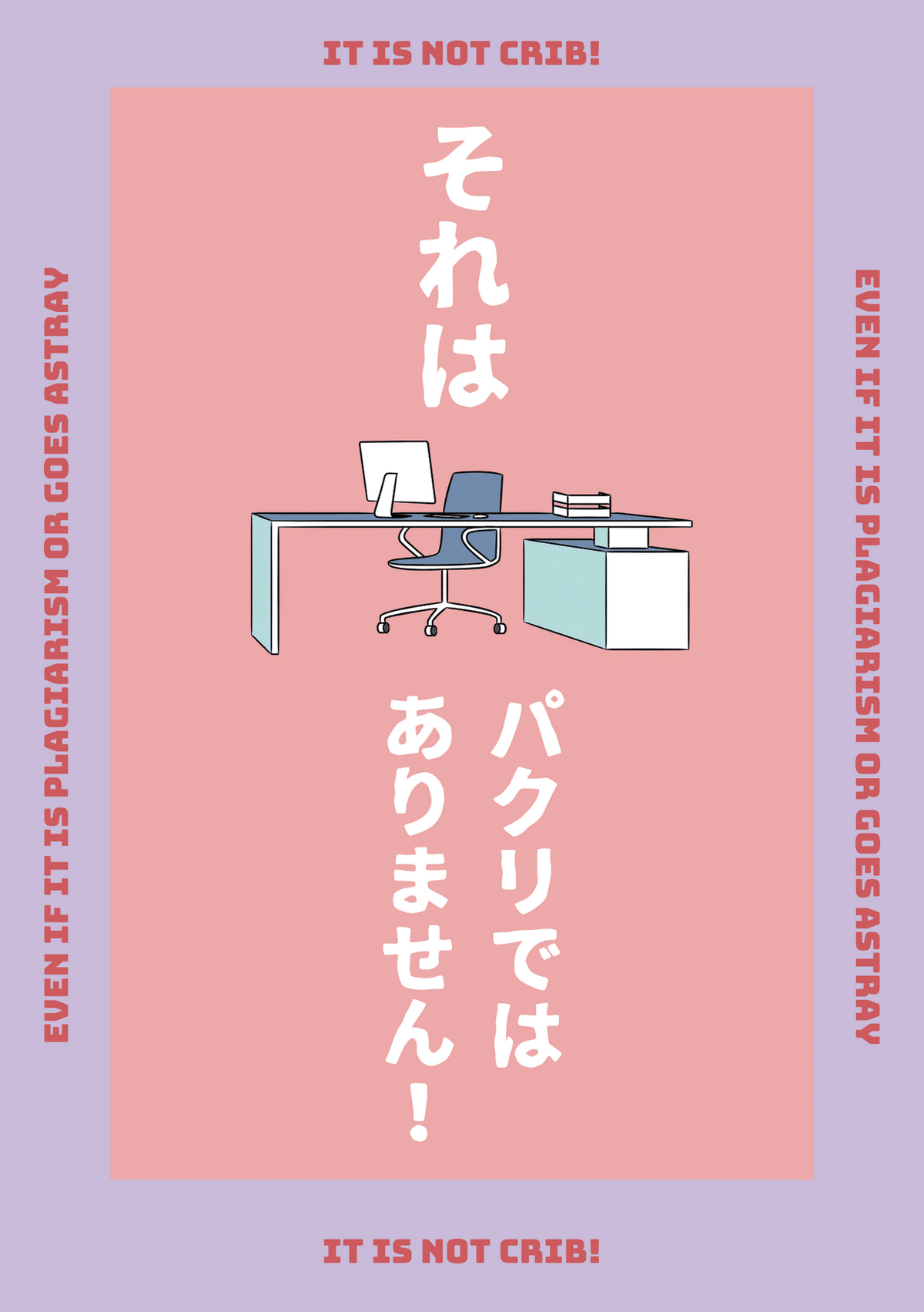
第1話
パクリなのか、それとも
チカチカした画面を、何度も食い入るように覗き込む。ブルーライトの光が瞬き、瞳の奥が痛い。瞼を、ぐいっと指で擦る。残像が霞み、スクリーンの輪郭が朧げになる。このまま、何もかも幻覚になり、いっそ消えてなくなればいいのに。
缶チューハイを持つ手が、カタカタと音を立てる。腕にしゅわっと泡が流れ、パチパチと音を立てた。
どうか、今見たものはすべて、嘘であって欲しい。 中井紀子は、漫画のネット広告を見るなり、呆然とする。
祈るような気持ちで眺めたその画面には、どこかで見覚えのある題名、キャラクター、ストーリーの漫画広告が嘘偽りなく映っている。紀子は頬をぎゅっと 抓る。じんわりとした痛みが頬を伝う。違う。これは、夢じゃない。
ネット広告の漫画は、「30歳、キャリアを捨てて地元に帰ります!」というタイトルのものだ。紀子が漫画広告をクリックすると、あらすじ紹介のページが登場する。
あらすじの文を、震える指でなぞる。文を読み進めるのが怖い。でも、この目で確認しなきゃ。
あらすじの内容によると、ストーリーは主人公の恵子が出版社で働く仕事を夢見て、東京へ上京する。恵子は憧れの出版社で勤務したものの、激務でストレスを抱える日々が続く。
やがて恵子は、仕事に限界を感じて退社する。その後、恵子が地元に戻り、再起を図るというストーリーらしい。
実にありふれたストーリーだけど、登場人物、構成からそっくりな物語を、紀子は知っている。漫画広告を見るなり、紀子はふらふらとした指で「 星平リエ 小説」と打ち込み、インターネットをググった。
星平リエとは、紀子がネット小説投稿用に使用していたペンネームだ。名前は、高校時代に憧れだった吉田君の苗字と、憧れている作家の 堀理恵の名前を組み立てて命名した。
過去に作った小説投稿用アカウントを見るなり、紀子の手が止まる。やっぱり、この作品は盗作だ。間違いない。紀子の手が、たちまち震えた。
震える手で、缶チューハイをごくりと飲む。レモンの酸味が、しゅわっと音を立てて喉に流れ込む。爽やかで大好きな味のはずなのに、今はとても苦くて、しょっぱい。
紀子は過去に、小説投稿サイトのコンテストに応募するため、星平リエ名義で「30歳、キャリアを捨てるけど何か問題ある?」というタイトルで、小説を投稿していた。
ストーリーは、出版社の仕事に憧れた女性「恵子」が、東京へ上京する。真面目に仕事へ取り組んだものの、30歳目前に会社からリストラを宣告される。恵子は泣く泣く地元に戻り、再起をはかる。
物語は、主人公が都会での経験をベースに、小さな出版社を立ち上げるところで完結する。紀子はそのストーリーを作ることで、地方でも諦めずに夢を追いかけて欲しいという願いを、作品に託すつもりで執筆した。
紀子にとっても、まさに渾身の作品だった。なのに。あの漫画は、キャラクター名はおろか、あらすじから構成まで、生き写しのように酷似している。
——やっぱり。私の作品、パクられている……。
紀子はその漫画広告をみるなり、わなわなと震える。怒りが収まらず、缶チューハイをぎゅっと 捻り潰した。
【10年前】
中井紀子は幼い頃から、本を読むのが好きだった。父は一人親方の大工で、母は看護婦。共働き夫婦の家庭で育った紀子は、一人っ子として中井家に誕生する。
兄弟が欲しくなかったといえば、嘘ではない。それでも、紀子が母に「兄弟が欲しい」と懇願することはなかった。
理由は、母が紀子を出産して5年後、子宮がんの検査に引っ掛かったからだ。検査の結果は、ステージ0。母の担当医からは「手術で、子宮を取り除く必要はありません」という話もあったそうだ。ところが、母は大胆にも子宮を取り除くことを決意してしまった。
「母さん、ちょっと手術してくるから」
あの日の母は、いつもと変わらずけらけらと笑っていた。まるで、スーパーへ大根を買いに行くみたいだねと、父は笑った。でも、父の目は憂いを帯びていた。
あの時、まだ5歳になったばかりだけれど。幼いながらも、母の表情を今でも鮮明に覚えている。あの日の母は、相変わらずの朗らかな笑顔だった。けれども、唇は屍のように青ざめていたように思う。きっと、彼女なりに手術が上手くいくのか心配だったのだろう。
母が看取る患者の中には、子宮がんで亡くなった方も少なくない。母によると、癌になる可能性のあるものはすべて取り除きたいと思い、手術を決意したそうだ。
子宮、取る必要なんてなかったのに。もったいないよ。かけたい言葉はたくさんあったが、グッと飲み込む。手術が終わった頃には、母の唇もほんのりと血色を帯びるようになった。
顔の血色は徐々に戻りつつあったが、時々お腹をぐっと抑えて、唇を顰めるような表情を取ることもあった。苦しさの度合いもわからず、なんて声をかけていいのかわからない。
「お母さん、無理しないでね」
母がしんどそうな表情をする度に、紀子はこう答えた。すでに母が子宮を取り除いてしまった以上、こんなありふれた言葉しかかけられない。母は「ありがとうね」と、その度に優しく微笑みかけてくれた。
どんな時も、家族の前では気丈に振る舞っていた母。それでも、毎日一緒にいると、彼女の表情に綻びがあることに気づく。なにか不安なことや、心配なことがあれば、相談してほしい。母に、そう伝えようと思ったことは何度もある。
でも、母には何を言っても無駄なことも、紀子は理解していた。きっとあの人には何を言っても、右から左。家族に心配をさせまいと無理をして、平常心を装うはずだ。
母が、時折不安げな顔を浮かべていた理由。きっと、父の仕事が安定しないから、自分が働かなければと思っていたのだろう。
父は、一人親方として企業に雇用されずに働く大工だ。一人親方とは、個人事業主として、施主、請負会社、施工会社などからの依頼により仕事を請け負う大工のこと。経理は苦手なので、税理士にもちろん丸投げだ。
確定申告の時期になると、父はいつもそわそわしながら、税理士へ相談し始める。来年もこの売上で大丈夫か。家族を養っていけるのか。眉間に皺を寄せ、難しそうな話をする父の姿を一体何度見たことだろうか。
父が難しい話をしていた時、紀子は決まって耳を 攲てる。父は小声で話すので、内容はいつも聞き取れない。すっかり折れ曲がった父の背中はか細く、頼りなさそうだ。
企業に雇われていない父の仕事は、常に不安定だった。家族が安定して暮らせるようにと、母は夜勤もきちんと勤め上げ、必死で働く。
紀子にとって、留守番の寂しさを紛らわせたのが、小説だ。小説は未知の世界へと、紀子を 誘う。1人きりでも、小説さえあれば退屈しななくて済む。紀子は、小説が大好きな文学少女だった。
——いつか、自分も小説を書いて、誰かの孤独を埋めたい。あなたは1人じゃないからと、未知の世界へと今度は私が連れて行ってあげたい。
紀子は高校になると、作家の道を志す。公募で文学賞を探しては、コツコツと応募をし始めた。残念ながら、公募はいずれも落選。
小説の公募には、何百、何千もの応募が届く。その中で選ばれるのは、所詮一握りでしかない。やっぱり私には、小説の才能はないのかしら……。落選の通知が届くたびに、紀子はがっくりと肩を落とした。
紀子が高校2年生になった頃、父の仕事に異変が起こる。
「大工の仕事、なくなるかもしれない」
悲しそうな表情で、父はぽつりと呟く。父の話によると、どうやら 昨今の住宅業界では、大手住宅会社が建てる高気密・高断熱の家が主流らしい。
いつもイキイキとした様子で、仕事に向かう父の姿が、紀子はたまらなく大好きだった。父は家も、家具も。丹念に心を込めて、丁寧に手作業で製作する。
お客様から依頼があれば、家のインテリアに合う家具の制作も受注することもあった。紀子が住む家も、机も、家具も。もちろん、すべて父が作った作品だ。
「今まで頑張ってくれたから、いいのよ。お父さん。私が頑張るから」
母は、父の肩をぽんと叩く。母の目は、すっかり充血している。すでに働き盛りは過ぎているのに、夜勤続きで、ほぼ寝ていないのだ。
父は、ごめんと申し訳なさそうに頭を下げた。
家が、なんだか大変そうだ。
そう思った紀子は、東京への進学を諦め、地元の大学へと進学した。
本当は、東京の大学へ行きたかったな。東京なら、書籍の仕事に携われる出版社で働く縁にも、恵まれるかもしれない。でも今は、自分の夢より家族が大切だ。
紀子は猛勉強を経て、地元の国立大学文学部を受験。試験は無事、合格した。
「紀子、やったな。おめでとう」
大学に受かった瞬間、両親は泣いて喜んでくれた。父は、合格のお祝いだからと、ケーキと赤飯、お寿司を用意した。和洋折衷てんこ盛りなテーブルを見て、おかしくて紀子はぷぷっと笑う。
赤飯を口に放り込むと、小豆とお米のふんわりとした甘さに、心が満たされる。もぐもぐと赤飯を口にしながら、合格の喜びをひしひしと嚙み締めた。
母はあいかわらず夜勤で、家にいない。それでもテーブルには「紀子ちゃん。大学合格おめでとう」と書かれた、母の置手紙が置いてあった。
この頃になると、父はいつも家にいた。母は「少し定年が、人より早く訪れただけ」と言って、けらけらと笑いながら仕事へ向かう。
父は寂しそうに、いつもテレビを能面のような顔で見ていた。父は体をくねらせ、うずうずしているようにも感じる。何もすることがなくて、焦ったいのだろうか。
「お父さん、椅子が古くなったから作って」
いたたまれず、紀子は父にお願いした。父は「あいよ」と言って、嬉しそうに作業へと向かう。ニコニコとした様子で、椅子の設計から始める父。やっぱり、仕事をしているお父さんが好きだ。
紀子は大学で、文学部を専攻する。文学部を選んだ理由は、文章に関わる道が僅かでも残っている気がしたからだ。
大学生活は、それなりに楽しい。友達とご飯を食べ、買い物へ行き、時には合コンにも顔を出す。友達に誘われてなんとなく入ったアウトドアサークルも、嫌いではない。
ただ、何をしてもどこか退屈だった。毎日、砂を噛むような思いがする。満たされない。両親からはお金も出してもらっているし、文句は言えないけれど。
友達と過ごす時間は楽しいし、サークルの仲間とも上手くやっている。なのに、どうしてだろう。自分は一体何をやりたくて、なぜ大学へ進学したのか。文学部へ進学したのに、本当に勉強したいことって、これで合っているのかもわからないし。
紀子がぼんやりとした大学生活を送っていた、ある日のこと。いつものように、紀子はインターネットを暇つぶしでググり続ける。
紀子がインターネットをふらふらと徘徊していると、小説投稿サイト「小説LOVE」にて、文学賞コンテストが開催されているのを発見する。
文学賞
小説LOVEは、登録者数が100万人を誇る人気小説サイトだ。小説サイトに登録すると、サイト上で募集している文学賞へ応募できる。
小説LOVEで開催される文学賞への参加方法は、まずはアカウントを登録し、作品を投稿する際に「#〇〇文学賞」とハッシュタグをつけるだけでOK。簡単だ。これなら、私でもできそう。紀子の胸が高鳴る。
小説LOVEで開催される文学賞は、人気小説サイトが運営していることから、各メディアからの注目度も高い。入賞者にはスポンサーがつき、書籍化デビューが約束されている。
紀子は文学賞コンテストのお知らせを見るなり、自分が小説家を目指し、公募を繰り返していた日々をふと思い出す。
——もしかしたら、これは神様が最後に与えてくれた最後のチャンスかもしれない。小説投稿サイトなら、誰でも気軽に応募しやすいし、自分にも書籍化のチャンスが訪れるかも……。目標ができれば、少しでも充実した日々を送れるだろうか。
そう感じた紀子は、すぐさま小説投稿サイト「小説LOVE」にアカウントを開設した。小説家になる夢を、紀子はまだ捨てきれていなかったのだ。
小説の投稿サイトでは、PV(※ページプレビューといってページの閲覧数のこと)などもチェックできた。
小説を投稿するなり、紀子の小説「30歳、キャリアを捨てるけど何か問題ある?」は、あっという間に1万PVを達成する。読者からのコメントも多く届き、紀子はすっかり有頂天になった。
読者の中には、紀子が一話小説を投稿する度に、「最高です。続きが気になります」とコメントをする熱心なファンもいた。作品のPVも良いし、熱心な読者ファンもいる。もしかしたら、小説は文学賞を受賞するかもしれない。
紀子は投稿した小説について、既に自信満々だった。コンテストでは大賞を受賞するだろうと、高を 括る。ところが、紀子の小説は、「小説LOVE」の文学賞コンテストに選ばれるどころか、中間選考すら残らなかった。
「なぜ……。どうして……。PVも多いし、読者ファンもこんなについているのに。渾身の作品だったのに!」
中間選考すら残らなかった紀子は、悔しさのあまり、その場で泣き崩れた。その1年後、紀子は再び小説を読み直す。小説は1年経ってもなお、読者からのコメントで溢れかえっていた。読者の中には、続編を希望する方も少なくない。
こんなに、人気がある作品だというのに。つくづく、審査員は作品を見る目がないと思った。しかし、スクリーンに映る文字を改めてチェックすると、誤字脱字、冗長表現の多さ、ストーリーの稚拙さに改めて気づく。
審査員は、間違っていなかった。やっぱり私には、小説の才能なんてなかったのだ。誤字脱字まみれの作品を前に、紀子はすっかり項垂れた。それからの紀子は、あれから一度も公募コンテストに応募していない。
紀子が大学4年生になると、母から突然「東京、行きたいんでしょう?」と声をかけられた。
「いや、別に。地元で就職しようと思っているけど」
「お父さんから聞いた。いつも紀子は、東京の本ばかり読んでいるって」
母からそう言われるなり、ふと本棚に目をやる。リリーフランキーと 江國香織の東京タワー、 吉田修一の 東京湾景。
本棚の表に並んでいる小説に、たまたま「東京」が入っていただけなのだけど。でも、もしかしたら無意識のうちに、自然と選んでいたのかもしれない。
「家のことは、心配しなくていいから」
そう言って、母は紀子に通帳を渡す。おそるおそる通帳を開き、数字を見て目を丸くする。通帳には、200万円の残高が記載されていた。母はいままで、コツコツと紀子の将来に向けて、お金を貯めてくれていたらしい。
「お母さん、ありがとう」
東京への就職を決意したあの日から、10年が経過する。
【30歳】
枯れ葉がさらさらと、アスファルトを這う。街には、そわそわと浮き足立つカップルたち。秋も終わり、もうすぐクリスマスの時期か。紅葉色の空を見ながら、紀子はふぅと溜息をつく。
30歳になった紀子は、編集プロダクションの派遣社員として働いている。大学を卒業したのち、書籍に携わる仕事へ憧れた紀子は、東京にある複数の出版社へ履歴書を送り続けた。
残念ながら、書類審査で毎回落とされる日々が続く。自分は文章が上手いはずだし、出版社でも力になれるはずなのに。
紀子はふとパソコンを開き、応募した出版社が公式サイトで公開している昨年度の「新入社員紹介のお知らせ」のページを覗く。
一体、どんな人が出版社へ就職しているのだろう。どきどきしながら紀子がサイトページを眺めると、そこには有名大学を卒業した美男美女たちの顔写真で犇めき合っている。
——みんな綺麗で、高学歴の人ばかり……。私なんかじゃ、絶対に無理だ。
地元の大学を卒業し、上京して出版社に勤務するのは、やはり難しいのだろうか。そう思った紀子は、がっかりした顔でパソコンを閉じた。
出版社の書類審査で落ち続けた後、紀子は都内にある編集プロダクションの会社にも就活をし始めた。編集プロダクションの仕事なら、もしかしたら書籍に携わる仕事に関われるかもしれない。
しかし、何社応募しても、面接どころか書類の時点で落とされてしまう。正社員の道を諦め、派遣で探すと1社のみ内定した。
あれから10年、紀子は複数の派遣会社を転々とする。今は都内の小さな編集プロダクションで、編集の仕事を続けている。
地元の国立大卒であれば、本来なら仕事を選ばなければ正社員で働く道はいくらでもある。それでも紀子は、本に携わる仕事に拘り続けた。小説家になれないなら、せめて誰かの本づくりのサポートがいつかできれば……。
紀子が派遣の仕事で受け取る手取り金額は、現在20万円。夜勤補助、福利厚生はゼロに等しい。紀子が暮らすアパートは、都内にある1DKのお部屋だ。
ハリボテのように薄い壁に、ミシミシと音を立てる床。夜になると、隣の部屋からカップルの喘ぎ声が漏れて眠れない。
朝、廊下で隣人とすれ違って気まずいのは、自分だけ。隣のカップルは、いつもスッキリした表情をしている。いいよね、あなたたちは。こっちは喘ぎ声のせいで、眠れないんだけど。
6畳一間の狭い部屋とはいえ、家賃は13万円。地方なら高いけど、都内では安い方らしい。
上京前に、母から貰った200万円はとうの昔に使い果たした。本当はもっと大切に、あのお金を使いたかったのに。母は、娘の夢を叶えるために、身を粉にして働き、必死になってお金を貯めてくれたはず。
有意義に使いたかったけど、そうも言っていられない。東京の1人暮らしは、お金がかかり過ぎた。
通帳の残高は、12,350円。中途半端な残高を眺め、紀子は重い息を吐く。今更地元に戻っても、30歳になった紀子に働ける仕事は少ないだろう。
紀子は結局、高校生の頃に書いた小説「30歳、キャリアを捨てるけど何か問題ある?」の主人公と同様に、生活と仕事の限界を感じていた。
今の状況を振り返ると、あの頃書いた小説は、自分への呪いだったのではないだろうか。紀子は、がっくりと肩を落とす。
仕事
紀子が働く編集プロダクションでは、企業から依頼されたオウンドメディア(※企業が自社で保有するメディアのこと)にのせるコラム、ブログ記事の執筆から、PR向けのメディアにのせるPR記事、書籍のライティング・編集を行っている。
紀子は書籍のライティング・編集を希望したが、願いは通らず、WEBメディアに配属された。会社によれば、書籍は修正がきかない分、現時点では正社員しか配属する予定はないそうだ。
書籍に携われると思って、派遣で会社に入ったというのに。正社員と派遣の壁は、紀子が思う以上に分厚い。
紀子の担当は、WEBメディアに乗せる記事の編集だ。編集といえども、最終チェックは隣の席の近藤敬子が担う。派遣社員の紀子が、すべての業務を完全に任されることはない。
近藤さんは、黒縁メガネとボリューミーなお団子ヘアがトレードマークの編集者だ。近藤さんは正社員で、記事の最終確認、PVチェックなどを行う。
メディアを運営する場合、PVが取れないとアドセンスや広告収益などに結びつかない。メディアが利益を得るには、まずPVを増やす必要がある。
オウンドメディアについては、記事のPVのみならず、商品やサービスの売り上げがどう変化したかなどについても分析しなければならない。
もちろん、どんなにPVが増えても、記事が炎上したらメディアの評価が落ちてしまう。どうすれば安全に、PVを増やせるのか。近藤さんは額にこびりつく汗を抑えながら、いつも頭を抱えていた。
記事の執筆は、業務委託のライターに依頼する。これは、紀子の仕事だ。
ライターの募集は、クラウドソーシングを通じて行う。クラウドソーシングとは、インターネット上で文章・デザイン・動画・プログラミングなどの仕事を発注・受注できるサービスのことだ。
クラウドソーシングを利用すれば、支払い手続き、契約などの面倒な手続きもスムーズに行えるため、編集プロダクションでは、外注で仕事を依頼する時に使うことが多い。
紀子の仕事は編集の他にも、ライティングのお仕事をクラウドソーシングで募集し、ライターの選定業務も含まれている。
紀子はクラウドソーシングで、連日のように「【初心者歓迎】文字単価2円!恋愛コラムが書けるライター募集」、「【主婦OK】誰でもできる簡単なお仕事です。データ入力のお仕事」など、お仕事の募集をし続けた。
紀子が募集する仕事は、いずれも文字単価1.5~2円など、決して条件が良い訳ではない。それでも募集をかければ、連日1件につき、20~30件の応募があった。
ライターから記事が納品されると、校正に取り掛かる。誤字脱字、冗長表現がないか。隅から隅まで、原稿をくまなくチェックする。目を酷使するので、目薬は手放せない。
校正はすらすらと進む時もあれば、お直しに何時間もかかることもあった。
難解なパズルを延々とはめ続けているような日もあるが、文章がぱちっと整った瞬間は、実に清々しい。
紀子の仕事には、他の文章をコピーペーストしている人がいないか、チェックする業務もある。コピーペーストとは、他の文章をコピーして、そのまま使用することを指す。業界では、コピペと略して呼ぶことが多い。
ライターがコピペしていないか確認するために、紀子はコピペ率をチェックする「コピペツール」を使用する。
紀子がライターから納品した文章を確認すると、なかにはコピペツールに引っ掛かるものも少なくない。ツールに引っ掛かった文章を納品したライターに、紀子はメールで注意喚起をする。
「あなたの文章をコピペツールでチェックしたところ、コピペ率80%となりました。もしかして、他記事を写していませんか?
申し訳ありませんが、コピペされて納品されたものを、成果物として認めることはできません」
紀子は震える手で、メールを送信する。ライターに逆ギレされたら、どうしよう。その不安は、見事に的中する。
中井様
お世話になります。ご指摘ありがとうございます。私は、コピペなんてしていません。私は、インターネットの検索上位に上がった1〜10位までのサイトから情報を抽出した上で、この記事を執筆をしています。
1記事書く所要時間も、3時間かかりました。何かの見間違いだと思うので、もう一度チェックしていただけないでしょうか?
もしどうしても気に入らないのであれば、報酬は要りません
コピペツールで引っかかったんだから、これ以上チェックできないんだけど……。紀子は、頭を抱えた。
やれやれと頭を抱えながら、紀子はカップに注がれた珈琲を口に含む。ほんのり苦くて、甘い珈琲は、疲れた心と体にちょうどいい。
紀子は、ライターに対し「すでに仮契約が完了しているので、そのような訳にはいきません。もう一度推敲して、修正をお願い致します」と、すぐに返答する。紀子はため息をつきつつ、再び他の文章をチェックし始めた。
「中井さん、ちょっと」
近藤さんが、声を震わせる。
「どうしたんですか」
「このまえ公開した記事が、炎上しているみたい」
紀子は、目を丸くした。炎上した記事は、一体どれだろう。ここ数日だけで、100本は記事をチェックしているし、心当たりのある記事すら思い出せない。
「ほら。前にライターさんが納品した子育て記事で、お受験のコラムあったじゃない。ライターの実体験が盛り込まれていて、参考になる記事ではあるんだけど。どうもライターの主観が強すぎて、SNSでコメントが荒れているみたいなの」
「でもお受験なんて、人それぞれだし。体験が盛り込まれていたら、それは仕方ないんじゃ……」
紀子がそう言うと、近藤さんは顔を顰めた。なにか不味いことを言っただろうか。
「でもね、中井さん。読者への配慮を怠らないことが、私たちの仕事なの。炎上したら、メディアの評価が落ちてしまう。一生懸命記事をアップしても、PVが取れても。信用を落としたら、そのメディアはもう終わり」
「そんな……。全方位へ配慮なんて無理です。色々な考えをもつ人はいるし、批判する人も少なからずいるだろうし」
「中井さんは、考えが甘いのよ。こっちはね、メディアの価値を保ちつつ、成長させることに命を懸けているの」
仕事に、命を懸けるって。いくらなんでも大袈裟だ。メディアが消えても、近藤さんが別に消える訳でもないのに。何を言っているのだろう。
「前から思っていたけど。中井さん、ちょっとフワフワしてるのよ。なんで私がこんな仕事してるんだろうって顔してる」
「そんなつもりないですけど」
「顔見たらわかるのよ。こっちは。あのね、私は何年正社員で働いてると思ってるの?」
「知らないです。私、派遣でここに入ってまだ数年なんで」
「ちょっと。最後まで話を聞きなさいよ!そういうところが、中井さんの悪いところだと思う。色々な派遣社員と仕事してきたけど、中井さんが1番仕事に身が入っていない気がするわ」
ああ、またか。近藤さんの正社員マウント。どうせ派遣だから、あなたはいい加減な仕事しかしないんでしょうと。近藤さんは時折、圧をかけてくる。
こっちだって、必死に文章のチェックもしているし、奮闘しているつもりだ。そんなこと言われる筋合いはない。
紀子は机の引き出しから耳栓を出し、きゅっと耳に入れ込んだ。これで、近藤さんの声が聞こえにくくなる。快適だ。
「あなた。ふざけているの?本当に社会適応力ないわね。そういう時は、すみませんって謝るのよ。これだから派遣は……」
ぶつぶつと、近藤さんは何かをいっているようだ。微かに声が聞こえるので、何を言っているのかは理解できる。
でも、近藤さんの小言を聞いていては身が持たない。小言は遮断して、業務に集中しなければ。まだまだ、チェックしなければならない記事は山ほどあるのだから。
午前0時。休憩時間のランチタイムだ。やっと休憩だ。紀子は、両手を掲げて体を伸ばす。凝った背がほぐれて、気持ちいい。
「近藤さん、ご飯食べに行きます?」
「はぁ?なんであなたと……」
ぶつぶつ言いながらも、近藤さんは「仕方ないわね」という顔で、紀子の後ろをついて来る。小言はいうが、紀子のことは決して嫌いな訳ではないのだ。
紀子が働く編集プロダクションの近くには、昔ながらの定食屋がある。他の店と比べて、価格もお手頃だ。
お店で、一番の人気メニューは日替わり定食だ。からあげ、ハンバーグ、コロッケ、鮭の塩焼き。
その日のメインメニューが何であるかは、その日のメニュー表を見ないとわからない。ドキドキしながら定食屋へ向かうのが、紀子の密かな楽しみでもある。その日の日替わり定食は、からあげ弁当だ。
「近藤さん、何にします?」
「私の勝手でしょう」
そう言いつつも、近藤さんは「日替わり定食」と書かれたメニューを凝視する。つくづく、わかりやすい性格の人だと、紀子は思った。
2人は、からあげ定食を注文する。テーブルに、あつあつのからあげがのった定食が届く。
「わぁ、美味しそうですね」
2人の顔が、ぱぁぁと明るくなる。紀子がからあげを口に入れた瞬間、ふわっと肉の旨味が広がる。美味しい。紀子の頬が緩んだ。
日々、くまなく文章をチェックしていると、腕や目に疲れを感じることもしばしば。それでも、美味しいご飯を食べている間は、その疲れも不思議と吹き飛んでしまう。
「あなた、もうちょっと仕事頑張りなさいよ。真面目なのはわかるけど、ツメの甘さが気になっていて」
近藤さんは、心配そうな顔で紀子を覗き込む。
「ご忠告ありがとうございます」
「本当は、書籍の仕事やりたくてウチに来たんでしょう」
「はい。でも、派遣だから仕方ないと諦めてます」
そう言うと、近藤さんの表情が曇った。また、何か不味いことを言っただろうか。
「派遣だからって言って、さっきは悪かったわ。でもね。派遣とか、正社員とか。それは業務形態の話だから、私はどうでもいいと思ってるの」
どうでもいいと思ってるなら、最初から言わなければいいのに。近藤さんの小言は、さらに続く。
「私はそれ以上に、目の前の仕事をきっちり責任持ってこなすことが大切だと思うの。中井さん、いつもふわふわしてるから気になっていて」
「ふわふわって。前からよく近藤さん言うけど、何ですか?」
「心ここに在らずという意味よ。本当は、なんでこんな仕事してるんだろうって思ってない?」
近藤さんからそう言われて、紀子はぎくりとした。
「目の前の仕事を責任もってこなさないと、やりたい仕事には辿り着けないから。あなた、頑張りなさいよ」
近藤から忠告を受け、こくりと深く頷く。自分では奮闘していたつもりでも、人から見れば甘かったのかもしれない。明日から、もっと真剣に仕事へ取り組もう。紀子は決意した。
17:30。仕事が終わる。紀子は寄り道もせず、一目散に家へ帰る。
街を歩けば煌びやかなネオンと、きらきらしたお店達の群れ。綺麗にお化粧した女性と、スーツをパリッと着こなし、足早に去っていく人々。
ふらふらと歩けば、都会の輝きに吸い込まれてしまいそうだ。東京は、つくづく誘惑が多い。
家につくなり、紀子は缶チューハイをぷしゅっと開ける。プルタブをひゅっと引くと、口からしゅわしゅわと泡立つ。紀子は、泡を啜るようにぐいっと飲み干し「ぷはぁ。上手い」と、声を上げた。
きゅっと音を立てて飲むと、爽やかなレモンの酸味が、喉にすうっと溶け込む。やっぱり疲れた時は、すっきりした喉越しのレモンチューハイに限る。缶チューハイなら、外で飲むよりお金もかからないし、気軽に気分転換できる。紀子にとって、自宅の缶チューハイは最高の贅沢だ。
缶チューハイを口に含みながら、紀子は携帯の画面をすらすらとスクロールする。ふと、ある漫画広告を目にして、紀子は、目を丸くする。広告に表示された漫画は、10年前に作成した自分の小説と、題名やストーリーが酷似したものだったからだ。
その漫画家の名前は、 明智ユリア。売れっ子の漫画家だ。明智は、これまで数多くのヒット作を世に送り出している美人漫画家として有名だ。
大きな瞳と端正な顔立ち、奇抜なファッションセンスが人気となり、現在ではテレビのコメンテーターとしても活動を続けている。
——まさか私の作品、パクられているのでは。
紀子は、広告を見るなり、たちまち明智に苛立ちを覚える。酷似している箇所を確認するために、明智の作品を隅から隅まで読み、自分の作品と比較し続けた。
漫画をチェックすると、いくつかのフレーズや、アイデアが酷似しているようにも感じた。やっぱり、これは私の作品をパクっているに違いないだろうと、紀子は 憤慨した。
そもそもあの作品は、紀子が三日三晩寝ないで書いた、渾身の一作だというのに。自分の作品を守るためにも、何とかしなければ……。苛立った紀子は、すぐさま出版社にメールを送った。
第2話へ続く
⭐️第2話〜第4話リンクはこちら
第2話
第3話
第4話
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
