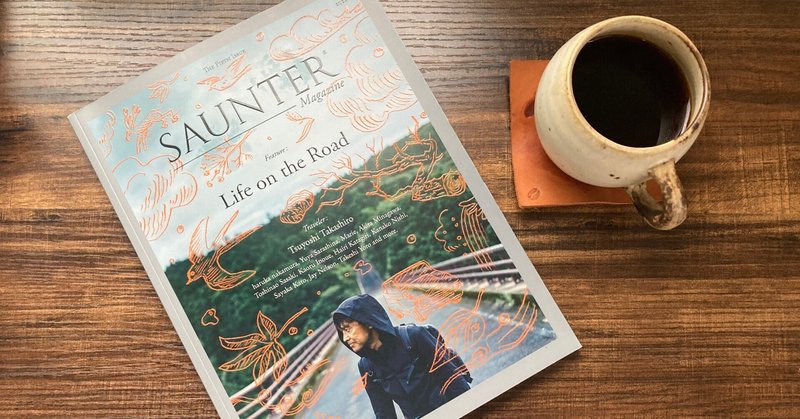
非合理性、非効率性の追求〜旅に出るということについて〜
何をやってもうまくいかなくなった時期がある。
その時点では、この先どうなるんだろう?という不安ばかりが取り巻いていたように記憶しているけれど、今となっては、30代前半に"それ"を経験できたことは、とても幸運だったと思っている。
この前回のnoteに書いた内容で、ご心配のお声を多く頂戴しました。心配をおかけするつもりで書いたわけではなかったので、とても申し訳なく思っています。そのnoteに書いたように、どんなにこちらが誠実に、真面目に生きていたとしても、自分と合わない人間が近づいてきて言われなのない批判、非難を受けることもある。批判、非難をするくらいなら、そっちも不愉快だろうから近づいてこなければいいのに、と思うけれど、「歪んだ正義感」を振りかざすことが生きがいの人間も世の中には多数存在する。
人生におけるトラブル(というほどのものでもないけれど)の原因の9割は「人間関係」だ。もしこれを読んでいる方の中に、「悩み」を抱えている方がおられるとすれば、その悩みを突き詰めて考えていくとその原因もほぼほぼ「人間関係」に行き着くのではないか?と推察する。
少なくとも、30代前半の僕は人間関係に悩まされた。
2週間後についに40代になる今の僕から見ると、それらはすべて「若気の至り」という言葉で片付いてしまいそうな些細な出来事なのだけれど、それでも、あれだけ悩んだ日々であるにもかかわらず、"それを経験していなかったら・・・"と思うとちょっとゾッとする。なぜなら、それがなかったら、間違いなく今の僕は存在し得ないからだ。
僕は、悩みの坩堝(るつぼ)の中にいるとき、唐突に「旅に出る」ということを決意することになる。このnoteにも何度か書いているアメリカのシアトルとオレゴン州ポートランドへの一人旅だ。初めての海外旅行で、アメリカを選び、しかも一人旅。さらに、僕はほとんど英語は話せない。そんな感じで、よくあの旅を決意したものだと想う。でも「あの旅」がすべてを変えてくれた。

シアトルのSEA-TACと呼ばれる国際空港に降り立った時に、僕を取り巻いた強烈な恐怖感・不安感を今でも鮮明に覚えている。周りに日本人はおらず、まったく聞き取れない英語での会話が飛び交い、案内板からも日本語は消え英語ばかりになった。当たり前のことなのだけれど、その当たり前がイメージできていなかった。初めての海外での空港なので、入国のための手続きもどういう流れになるのかよくわからない。入国審査のゲートに行くと屈強な警察官が「さっさとこっちへ来い」とでも言わんばかりの雑な手招きで僕を呼び寄せる。
「何をしにUSヘ来たんだ?」「何人で来た?」「一人?友達がシアトルにいるのか?」「いない?じゃ、何をしに来たんだ?」「日本での仕事は何だ?バケーション中か?仕事はどうした?」
不愉快になるほどの疑いの視線を浴びせかけられながら、あれやこれやの質疑を受ける中で、「何でこんな国に来ちゃったんだろう?」という自問自答が始まったことを今でも覚えている。アメリカにいたのは1週間程度の短い滞在だったのだけれど、その1週間の間「心地いい」と思ったことはただの一度もなかったと思う。言葉もわからない異国で、つねに付き纏う緊張感と共に、居心地の悪さを感じている時間の方が長かった。



街を一人で散策していると、向こうからあどけなさの残る顔立ちでありながら、ガタイのいい少年の二人が歩いてきた。二人の手には、スタンガンが握られていて、それをバチバチ言わせながら歩いている。シアトルは治安のいい街だと聞いていたけれど、そんなものを最初に見てしまうと一気に緊張感が増してしまうのは無理からぬ話だった。

もちろん、シアトルもポートランドもとても良い街だった。でも、この旅を思い返す時に、最初によぎる感情はやはり「恐怖感」であり「不安感」であり「緊張感」ある。



けれど、とはいえ「初めての海外一人旅」が終わった後、海外旅行なんてコリゴリとなったか?というと、そんなことはなくむしろハマってしまったのだ。その後、僕は「半年に1回は海外に行く」という目標を立てた。実際に、台湾・マレーシア・台湾(2回目)・ベトナム・タイ・(世界的疫病を挟んで)再度ベトナムという感じで、海外に出かけるようになる。







アメリカの後は、東南アジアの各国を回っているから、アメリカよりも「気が楽だったのか?」と思われるかもしれないけれど、そんなことはない。その他の国でも「恐怖感・不安感・緊張感」というのはどうしても付き纏う。それはどこの国に行っても変わらない。



かつての先人の想いをイメージしてみる。



スむしろ、僕はその「恐怖感・不安感・緊張感」を求めに、海外へ出かけるよいうになったのだ。僕はアメリカから帰国したあと、何か「くぐり抜けた」という感覚があった。その要因は、あの「恐怖感・不安感・緊張感」を感じまくったことが大きな要因だったと思う。






何を、どう、くぐりぬくけて、何が変わったのか?ということを、うまく説明できない。それは、とても感覚的な事柄で、とても個人的なことだと思う。




そんな中で、僕が確信をしていることは、何かを解決したいと思ったら、「合理性」や「効率」ばかりを追い求めてはいけないということだ。かつての僕は「無駄」なことは一切排除しようとしていた。イッパシのビジネスパーソンを気取って、合理性、効率性追求してそんな「気分」に浸っていた。今の僕が、あの頃の僕への最大のダメ出しは「無駄かどうかをどう判断しているの?」ということだ。「これは必要で、これは無駄」という主観的な判断そのものが稚拙で幼稚だ。まさに若気の至りである。
「旅」を経験することがなくても、人生は成立する。
時間をかけて遠くまで行き、決して少なくはないお金を使うことになる。
人によっては「無駄」そのものであるかもしれない。
でも、僕は、この「無駄」な行為によって、本当の意味で「人生が始まった」ような気持ちでいる。旅をすることで、僕自身が創られているし、人生というものを創っているという実感が持てるようになったからだ。
一切の無駄を省き、合理性、効率性を追求すれば、人生は成功するわけではないと僕は確信している。むしろ、その稚拙で幼稚な判断は、きっと間違いなく「後悔」という名の失敗を呼び寄せてしまうのではないかと思っている。人生の最期のときに。
僕は、これからも、旅という「非合理性」「非効率性」をこれからも追求したい。自分の人生は自分の手で創り上げたいからだ。
「非合理性」「非効率性」つまりは「無駄」の中にこそ、僕自身のオリジナリティが生まれるのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
