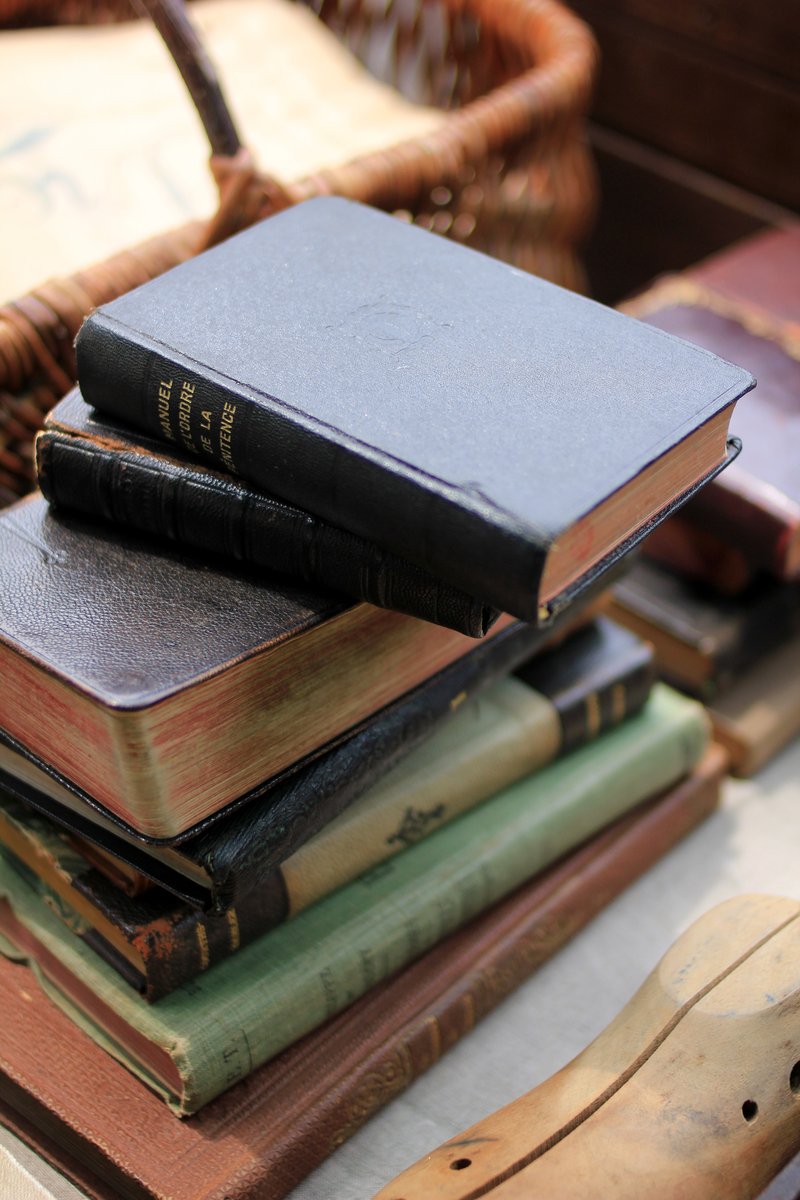#俳句鑑賞
【俳句鑑賞】停年の後のことなどふらここに 義明
ふらここ。これ、実は「ぶらんこ」のこと。春の季語なんです。ぶらんこはふらここ以外にも、鞦韆(しゅうせん)、秋干、ふらんと、半仙戯(はんせんぎ)とも言われます。俳句をしていると言葉を覚えますね(笑)。
なお、なぜ半仙戯という漢字が当てられているかというと、
〔唐の玄宗が寒食(かんしよく)の日に,宮女に半仙戯(鞦韆(しゆうせ))の遊戯をさせたことから。「半仙戯」は半ば仙人になったような気分にさ
【俳句鑑賞】春尽きて山みな甲斐に走りけり 普羅
時期、まさに晩春。あと1週間ばかりで暦の上での「夏」が始まる。晩春のこの時期、夏にむけたワクワク感で心も体も満たされている幸せを感じる。
前田普羅(まえだふら)。1884年(明治17年)4月18日 - 1954年(昭和29年)8月8日)は、俳人。高浜虚子に師事。「辛夷」主宰。本名は忠吉(ちゅうきち)。別号に清浄観子。(以上Wikipediaより)
俳句には山岳俳句というものがあり、これは登山し
【俳句鑑賞】春深し女は小箱こまごまと 青邨
山口青邨(1892-1988)俳人。岩手県出身で高浜虚子に師事。工学博士として東大に勤めながら作句に励んだ。科学者としての目も生かした写生・観察に加え、省略や象徴、季語の活用によって複雑なものを単純化することを目指した。(以上Wikipediaより)
ところで、揚句の季語は「春深し」。2月4日から5月5日までが俳句でいう「春」となるので、春が深い季節は桜が散った後のちょうど今頃というところか。4
【句作】なすがまま 子を見送りて 氷消ゆ masajyo
久しぶりに句作もしたいと思います。これまで、鑑賞文末に作っていたものを一部添削してこちらに掲載させていただきます。どうぞ、十七音の世界を味わいくださいませ。
今回から、よりイメージが湧き立てばいいな、と一句ずつアップさせていただきました!
【俳句鑑賞】しののめの薄氷は踏み砕くもの 雅人
しののめ=東雲。夜明け、明け方のこと。薄氷は俳句の季語では「うすらい」と呼ぶ。これをスムーズに読める人は俳人の疑い大いにあり。言葉の通り、早春の季語である。
夜明けの光を受け、自分の歩く道の先に小さな水たまりが。見れば、その一部は凍っている。暦の上では春だが、ここそこにまだ冬の名残が感じられる。ことに早朝はまだ「冬」と言ってもいいほどだ。そんな中、行き先にある水たまりの氷を踏んで砕いた。
踏む
【俳句鑑賞】夕月や納屋も厩も梅の影 鳴雪
内藤鳴雪(ないとう めいせつ) 1847年~1926年。明治・大正期の俳人。松山藩出身。本業は官吏だったとのこと。年下の正岡子規を師匠とし、ホトトギスにも参加したみたいですね。
梅の咲く季節は、心がウキウキしている。それは桜の咲くころのウキウキとはまた違ったもの。まだ寒さが残る毎日に梅の花が咲いているだけなのにほんのりとした希望を感じたものだ。
初春のまだ少し尖っている夕月が影をつくる。納屋も
【俳句鑑賞】猫の目のまだ昼過ぬ春日かな 鬼貫
上島鬼貫(うえしまおにつら)。こんな人、国語の教科書に載っていたかな?印象は薄いのに、おにつら、という名前の人がいるっっぽいことだけ知っていた。
江戸時代中期の俳人らしい。本業武士。兵庫県伊丹市の人。芭蕉さんとも親交があったんですって。
昨今の猫ブームのすごいこと。猫俳句もいいかもしれません。
春の日はゆったりと時間が過ぎていく。愛猫なんかとグダグダ過ごすのもいい。なんにもしない。ごはんなん
【俳句鑑賞&料理】行く春や鳥啼き魚の目は泪 芭蕉
30数年生きてきて、生まれて初めて自分の作る料理がおいしいと思う。いや、その以前に、生まれて初めて自分の食べるごはんを自分の手でDIYしている。そのきっかけは写真の「金目鯛の煮つけ」
なんせ、料理する時間があるくらいなら、ビジネス書を読んだり企画書を作成している方が楽しかったオンナである。この変わりように一番驚いているのは何を隠そう、この私。
1月吉日、ふと、スーパーで金目鯛と目があった。コワ
【俳句鑑賞】春の航小浦小浦に人降ろし 桃子
春の航小浦小浦に人降ろし 辻桃子
2月4日は立春。といえども、まだまだ北風に体を苛められている頃合い。この日を過ぎると、体感的には冬のままであっても、小さな春らしいものを見ると心が浮き足だっていることに気が付く。
私は普段、とても水辺を好む。息づまると水があるところに行きたくなる。東京でいたときもそうで、浅草の隅田川の川辺や勝鬨橋や築地市場を眺めることができる川辺沿いに行っていた。
しかし、
大人は、もっと自分を大切にしていいんだ。
ここにいることで感じていること。それが実は大切なのかもしれないと思い始めた経験が私にはある。
1分2分の時間を縮めることに躍起になり、やれ効率的だ、と食べること、寝ることをおろそかにし、お酒で紛らわせる。心の中にある自分の気に入らないことを、お酒のチカラで自分のカラダから発する。そう、今、人は自分の中に入ってくる嫌なことを放出することで手一杯なんだ。美しい自然、心にしみる詩、ドキドキする小説