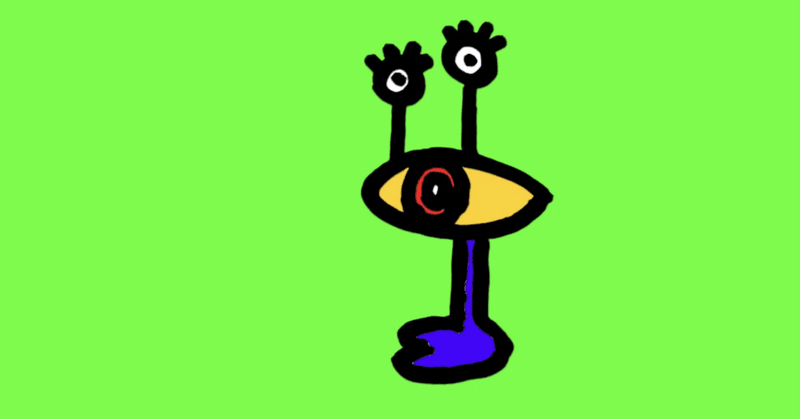
「発達障害」の子を、「普通」の子にするということ〜「発達障害」と診断された人のための「発達障害」の説明書3〜
一緒に作るマガジン
この度、【「発達障害」と診断された人のための発達障害の説明書】と題して、マガジンの作成を始めた。
このマガジンは、『一緒に作るマガジン』という設定にしている。
「受け身ではない、主体的な学びの機会を作りたい」
という思いからの『一緒に作るマガジン』。
マガジンの作成に読者が参加してもらうことで、きっと、受け身ではない、主体的な学びの機会が作れる。
このマガジンで扱う内容は、「今まで誰も言ったことのないことを言う」とか、「段違いにわかりやすい」とか、そんなことはおそらくないのだけれど、参加型で、一緒に作っていくという点だけは、チャレンジングで価値ある試みであるように感じている。
たとえば、もし何か質問が出たら、次回はその質問について取りあげた記事を書きたいし、もし発達障害について書いた記事を紹介していただけたら、次回はそれについて一緒に考えたい。
そんな風に、発達障害のことについて一緒に考え、理解を深めていきたい。
そんな風にして行う皆さんとのやりとりこそ、リアルな「発達障害」の説明書になり得ると考えている。
「発達障害」の説明書、よかったら、一緒に作りましょう。
おことわりと前回の続き
【おことわり】
今回の記事は、内容が盛りだくさんで、文字数が4500字を超えています。
最後まで読んでいただくとすると、個人差はありますが、約5〜10分程度お付き合いいただくことになるかもしれません。
お時間に余裕があるときに、読んでいただけると嬉しいです。
それでは、前回の続きから入っていきたいと思う。
DSM-5の診断基準は、たとえば自閉スペクトラム症(ASD)であれば以下のようになっている。
以下のA、B、C、Dを満たすこと
A:社会的コミュニケーション及び相互関係における持続的障害
B:限定された反復する様式の行動、興味、活動
C:症状は発達早期の段階で必ず出現するが、後になって明らかになる物もある
D:症状は社会や職業その他の重要な機能に重大な障害を引き起こしている
これらA、B、C、Dをすべてを満たせば、自閉スペクトラム症と診断することができる、ということである。
ここでの、AとBは、発達特性に関する記載。
Aは、ASDの空気の読めなさやコミュニケーションの苦手さに関する部分。
Bは、ASDのこだわりに関する部分。
Cは、それらの特性は生まれつきのもので、医学的には神経発達症群に含まれますという部分。
そしてD。
D:症状は社会や職業その他の重要な機能に重大な障害を引き起こしている
前回、発達障害の人への支援としては、このDの状態を改善することが大切ということを書いた。
ただ、きっとはじめて我が子が発達障害と診断されたとき、保護者が発達障害の治療として最初に求めるのは、AとBを改善しようとすること、つまり、発達特性をなくして、「普通」の子にしようとすることではないかと思う。
発達障害の子を、「普通」の子にしようとすること
かく言う支援者の世界でも、まだ、発達障害の子を「普通」の子にしようとする、そんな考えは根強かったりする。
支援者の中には、「発達障害の子どもを支援するには、まず最初に定型発達(いわゆる「普通」の子の発達)を知らなければならない!」と声高に叫ぶ人がいるのである。
もちろん、知識として、定型発達の知識を持っておくことを別に否定しているわけではない。
でも、それが優先順位のトップかと言われると、どうだろうと思う。
「定型発達を知らなければならない!」と声高に言う人は、どこかで「発達障害の子の治療とは、彼らを『普通』の子に少しでも近づけることだ」と考えているのだと思う。
発達障害の子を「普通」の子にするためには、その基準(目標)となる「普通」の子の発達を知っておかなければならないから。
でも、私はそれは違うと思っている。
そのことについて、自閉スペクトラム症(ASD)の発達特性を持つマナブくんを例に挙げて考えてみたいと思う。
発達特性に合わせた支援って、きっとこういうこと
ASDの発達特性を持つ子は、その子オリジナルの学び方や捉え方をすることがある。
そして発達の順序に関しても、その子特有のオリジナリティが強く出ることが多い。
そんなオリジナリティの強いASDの子、マナブくんを支援したいとする。
もし、定型発達については知っているけれど、ASDの子の発達について知らない人がマナブくんを支援するとしたらどうなるだろう。
きっと、定型発達と異なる点ばかりに目が向いたり、自分の知っている順序で発達しないことに戸惑ったりする。
仮に、定型発達の子が、Ⅰ ⇒ Ⅱ ⇒ Ⅲ ⇒ Ⅳ という発達の順序を辿るとするなら、ASDの子は Ⅰ ⇒ Ⅲ ⇒ Ⅳ ⇒ Ⅱ という発達の順序をたどる、なんてことがよくある。
Ⅰ の発達段階にいるマナブくんの発達を促そうとするとき、支援者がもしASDの子の発達について知らなければ、マナブくんに対してⅡ に近づくための支援を一生懸命しようとするだろう。
定型発達の子にそうするように。
しかし、ASDの子は Ⅰ の次は Ⅲ という順序で発達する。
ASDの子にとって、Ⅱ は、 Ⅲ と Ⅳ を経てたどり着く姿である。
よって、Ⅰ の発達段階にいるマナブくんに、Ⅱ に近づくための支援をいくらしても、彼らにとってはあまり効果的でないということになる。
ASDの人の共感の仕方
もう少し具体的な例を挙げてみる。
ASDの子は他者の感情を読む力が弱いと言われる。
しかし、ASDの子が一生他者の感情を読むことができないかというとそうではない。
ASDの子は、概ね思春期頃になって他者の感情を読み取ることができるようになると言われているが、その感情の読み取り方が、定型発達の子とは異なると言われている。
定型発達の子どもは、脳の中のミラーニューロンという回路を働かせて他者の感情を読み取る。
それは、共感の能力と言われることもあるが、すごく単純に言うと、相手が感じているように自分も感じることができる能力のことである。
それが、定型発達の子は大体3~4歳頃から獲得され始める。
だから、就学前、あるいは小学校低学年の子どもに対して指導をするときには、「あなたがされたらどう?」とか、「(あなたがいじわるをした)○○さんはどう思ったと思う?」という方法が伝統的に取られることが多いということである。
それは、定型発達の子のミラーニューロンの発達を前提とした指導が行われているということである。
しかし、ASDの子はこのミラーニューロンの発達に弱さがあると言われる。
したがって、「あなたがされたらどう?」とか、「(あなたがいじわるをした)○○さんはどう思ったと思う?」と言われても、イメージすることが難しい。
では、ASDの人たちはどのように感情を読み取るのか。
ASDの人たちは、人の表情を理論的に読むのに長けている、と言われている。
つまり、「眉尻がこのように下がったから、この人は悲しんでいる」とか、「眉間にしわが寄ったから、この人は怒っている」とか、そのように表情を詳細に読んで感情を理解すると言われているのである。
それができるようになるのが大体思春期頃。
と、もしこのような知識を持っていたとしたら、就学前あるいは小学校低学年のASD児にたいして、「あなたがされたらどう?」とか、「(あなたがいじわるをした)○○さんはどう思ったと思う?」というような指導は積極的には行わないだろう。
そうではなく、もっと表情の細部の変化に注目できるような声かけを行うだろう。
ASDの子たちが、細部の変化に注目できるような年齢になってから。
環境が発達障害児を作る
決して定型発達の子と同じような指導をしてはいけないという訳ではないが、大人は往々にして、自分の指導が伝わらないときや、自分が知っている通りに子どもが発達しないときには、イライラしたり戸惑ったりして子どもに八つ当たりをしたりしてしまう。
その八つ当たりがASDの子たちにとってはよくない。
なぜ怒られているのかわからず、ただ漠然と自分が悪いと感じ、自己肯定感が低下してしまう。
そして、そのような失敗体験を繰り返すと、上記の診断項目Dを満たすような、発達障害の状態になってしまう。
定型発達だけを知り、ASDの子たちの発達が思うような順序で進まないことに焦り、それでも「普通」の子に近づけようとして、結果子どもを不適応の状態にしてしまうことは、少し強い言い方になるが、「環境が子どもを発達障害の状態にしている」とも言える。
支援者に必要なことは、子どもの発達特性(上記の診断基準AとBに当たる部分)をよく理解し、発達特性をふまえたかかわりをするということである。
それは、発達障害の子を「普通」の子にしようとするかかわりとは違う。
たとえばASDの子への支援であれば、彼らのこだわりを十分発揮できるような環境を与えたり、彼らが学びやすい方法でコミュニケーションについて教えるということ。
それらを通して、子どもが自分の発達特性を存分に活かしながら、そして時にはカバーしてもらいながら、生き生きと生活できるようになることが支援の目的である。
そのような支援が実現すれば、きっと、子どもは不適応の状態にはならず、診断項目Dに該当するような状態にはならない。
生き生きと生活しているその子は、ただの発達特性を持った元気な子であり、発達障害の子ではなくなるということである。
そのような支援を提供するために、支援者は、定型発達の知識よりもまず、発達特性を持つ子の発達を知ることが大切だということである。
今日のところまとめ
発達特性を持つ子を、「普通」の子にしようとするかかわりは、私は好ましくないと思っている。
発達特性もある種の才能なのだから、そちらを伸ばせるものなら伸ばしてあげたい。それが、発達特性を持つ子が自分らしく生きるということではないかと思うからである。
ただ、やっぱり社会は「普通」の人が生きやすいように作られていて、発達特性のある子たちが、自分の発達特性を活かしながら生きていこうとすると、きっとつらいことや苦しいことが出てくるだろうと思う。
そういうことを思えば、親御さんたちの、できれば「普通」の子に少しでも近づけたいと思う気持ちもわからないではない。
でも、私はその「普通」の人だけが生きやすいような社会の方が変わっていけばよいと思うし、変わっていく兆しは見えてきていると思う。
発達特性のある子だけが「普通」に合わせようと頑張るのはおかしい。
発達特性のある子たちが「普通」に合わせようと努力しているのと少なくとも同じ程度には、社会も発達特性のある子を包めるように変化する努力をすべきと思うのである。
そう考えると、やっぱり、発達特性を持つ子を「普通」の子にしようと努力するのではなく、自分で自分のことを理解したり、コミュニケーションをとりながら自分たちのことを主張したりできる力を身につけさせたい。
そうして彼らには新たな時代をつくっていけるような、そして社会の在り方を調節していけるような人間になってもらいたい。
彼らこそ、社会をより成熟したものに変えていける、そんな可能性を持っているはずだから。
次回予告(仮)
次回まで、発達障害についての私のスタンスを書きたいと思う。
その後、自閉スペクトラム症、ADHD、LD、知的障害、DCDをひとつずつ、それぞれピックアップして取り上げていきたいと思う。
よろしければ、お付き合いいただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
