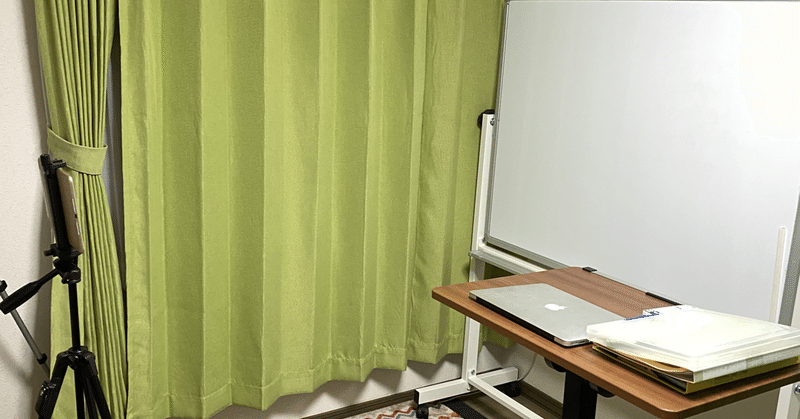
- 運営しているクリエイター
2021年4月の記事一覧
地震への備えは学びから知る
地震予測を知ることが日頃、よく出てくる社会ニュースで私たちの防災を見直すという時期である。東日本大震災だけではなく、宮城県や福島県の大地震が最近起こっている。まだ先日、新しい地震予測が発表され、発生確率が高くなっていることの調査結果が出ている。
地震が起こりやすい大国といわれる日本は、なぜそうなってしまったのか。理科と社会科を関連付けて学ぶ必要性が高まっているのが新しい科目「地理総合」「地理探
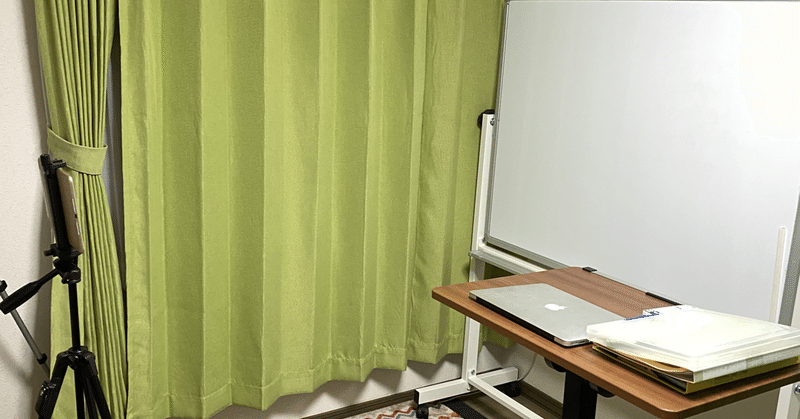
地震予測を知ることが日頃、よく出てくる社会ニュースで私たちの防災を見直すという時期である。東日本大震災だけではなく、宮城県や福島県の大地震が最近起こっている。まだ先日、新しい地震予測が発表され、発生確率が高くなっていることの調査結果が出ている。
地震が起こりやすい大国といわれる日本は、なぜそうなってしまったのか。理科と社会科を関連付けて学ぶ必要性が高まっているのが新しい科目「地理総合」「地理探