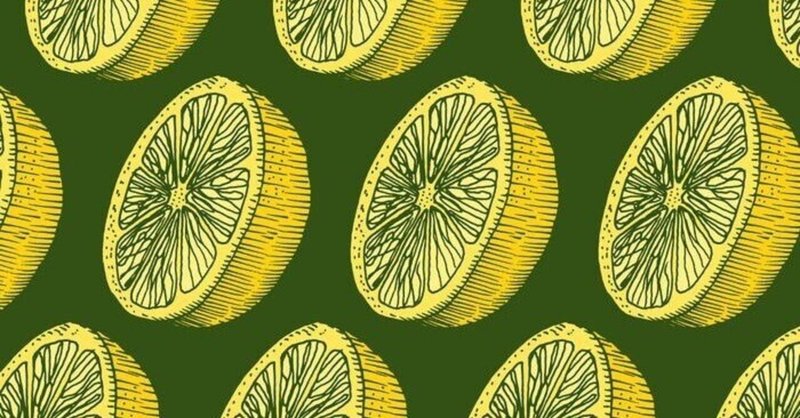
檸檬読書日記 写真はモノクロで、写真家はパリで、死は白い満月のもとで。 11月27日-12月3日
11月27日(月)
寒くなったと思ったら暑くなったり、世界はどうなっているのやら。
クレマン・シェルー『アンリ・カルティエ=ブレッソン:20世紀最大の写真家』を読む。
写真の巨匠であるフランスの写真家、アンリ・カルティエの生涯について書かれたもの。
最近、モノクロ写真に惹かれていて、正直最初はこの方について全く知識はなかったが、表紙の写真に惹かれて読んでみた。
この人の人生、結構面白い。
まず写真家になる前、2年ばかりではあるが、絵画を習っていたというのが、興味深い。
最近読んだ村山槐多も黒澤明も、自分が惹かれる人は大概、絵の道を通っている。
「絵」という芸術に関わったからこそ生まれる何かを、アンリカルティエも持っているように感じた。
例えば、光と影。モノクロではあるが、色彩感覚。
それらがやはりずば抜けている気がした。
詩、映画、写真、皆違う道ではあるが、絵があったからこその魅力がある気がした。
そしてアンリカルティエは、多方面の芸術家たちからの影響も受けている。
交友関係が広く、美術、詩人、映画、作家等々、あらゆる才能あるもの達との交流がある。だからこそ生まれたセンスなのではないかなとも感じた。
その上アンリカルティエは、美術、写真だけでなく、途中で映画にも手を出している。映画に興味を持ち、作成してまっているのだから凄い。
ただこの人は、センスや才能だけでなく、運も持ち合わせている。
アンリカルティエは、ガンディーの最後の姿をカメラにおさめた写真家であり、スターリンの死後にロシアに足を踏み入れ撮影をした最初の写真家でもあった。
他にも驚くことをたくさんしていて面白いが、ただ単純に、写真も素晴らしい。
アンリカルティエの写真は、独特だ。
けれど「何が」と明解に言うのは難しい。でも、見ていると落ち着かなくなる。不快という訳ではないが、違和感を感じるのだ。何か欠けているような、反対に多いような、不思議な感覚。それがまた、良い。
瞬間的なのに凝っていて、でも不思議で、面白い。
解説も然ることながら、写真もたくさん載っていて、短いながらも充分に楽しめる本だった。
最後に、本の中で気に入ったアンリカルティエの言葉。
「時は過ぎ去り、流れていく。われわれの死だけが、時間に追いつくことができる。
写真は永遠のなかで、目もくらむような一瞬をとらえるギロチンの刃だ」
昔見た、建物から飛び降りた瞬間のモノクロ写真が今でも印象に残っていて、それがアンリカルティエの写真だと思い、それもあって読んでみたのだけれど、結局それは違っていた。
それならあれは誰の写真だったのだろう。
その写真を撮るために、命綱もつけずに飛び降りて、全身を骨折した人は、一体誰だったのだろうか。
11月28日(火)

菊の花を貰ったのだが、少し変わっていて面白い。
ラッパみたい。

感化されてモノクロにもしてみた。
のだけれど…んー、やはりモノクロって難しいな。
パリッと感が出ない。
川上弘美『大好きな本 川上弘美書評集』を読む。
内田百閒の有名な言葉「イヤダカラ、イヤダ」の話。
「イヤダカラ、イヤダ」という言葉、いかにも百閒的である。百閒の作品を愛読している者ならば、すぐさま「百閒先生がおっしゃりそうな」と相好を崩すことだろう。
常識的な世界からのごく自然な逸脱。現実から遠く離れてはいないのだが、必ず背後に漂っている幻想性。直截な表現。それらの作風から推し量った百閒という人物が口にして、非常にぴったりな言葉ではある。そして、聞いた読者たちも手放しで安心してよろこべる言葉でもある。
百閒は百閒以外の誰でもない。誰にもなれない。誰にもなりたくなかったろう。自分が百閒であることに、ずいぶんと満足していたことだろう。同時に、自分が百閒であることが嫌でしかたないけれど、決して百閒以外の者になれないことをよく知っていただろう。そこに寂寞があり、おかしみがあり、生と死をみはるかす目がうまれるのである。
確かに。
最近気づいたけれど、自分が好きな作家は、皆内田百閒を押している気がする。
川上弘美然り、森見登美彦、小川洋子。作家ではないけれど黒澤明。やはり通ずるものがあるから、惹かれるのだろうか。
糸井重里『ふたつめのボールのようなことば。』を読む。
風呂につかって考えた。
世界なんて、ころころ変わる、おれの機嫌しだいでね。
何があってもあまり気にしないようにしよう。とりあえず笑顔でいたら、いつの日かいい方に転ぶかも。自分の機嫌は自分で取らなくては。
ということで、本でも買いますか?
11月29日(水)
今、カフカが生誕140周年を迎えているらしい。ほお。
その記念に『城』と『審判』の新装版とか出ないかなあ。
『パリ・ドアノー ロベール・ドアノー写真集』を見る。
写真家ロベール・ドアノーがパリを舞台に撮った、少し洒落の効いた写真集。
面白い。
これまたモノクロ写真なのだが、この写真集は、どの写真にもユーモアがある。
きっと撮った瞬間にほくそ笑んでいたのだろうなと想像出来るような、どれにもちょっとした仕掛けのようなものがあり、面白い。
けれどロベール・ドアノーの素晴らしいところは、それだけではない。面白い仕掛けはあるが、全くわざとっぽくはないのだ。自然で、だからこそ決定的瞬間な面白さがある。(いや、そもそも自然で撮ったのかもしれない)
人生は決して楽しいばかりじゃない。それでも私たちにはユーモアの心がある。
それは、私たちの感情が閉じ込められている隠れ家のようなものだ。
そして、面白い以上に、どの写真もいかにもパリらしさがあって、パリをめいいっぱい堪能出来るのも、この本の魅力だ。
本当は、写真集の前にこの方のエッセイ『不完全なレンズで-回想と肖像』を少し読んだ。
けれど、載っている写真は惹かれるものの、難しくて挫折してしまった。
とはいえ、言葉は素晴らしいのだ。単語単語は綺麗で、バラバラと煌めくものが散りばめられている。だけど、頭の弱い自分では、それを頭の中で1つにまとめることが出来なかった。
おそらく凄い好みなのに、吸収されずに落ちてしまう。悔しい。
でも、もう少し成長したら、また挑戦してみようかな。
11月30日(木)
アンネの悲鳴はいつ届くのだろうか。
届く日は来るのだろうか。
物質主義はいつになったらなくなるのだろう。
欲はいつ衰えるのだろう。
あらゆることが衰え消えてしまう中、年をとっても唯一衰えないで成長し続けるのは負の感情らしいけれど、唯一消えないのは欲な気がする。
こんなこと書いてるから駄目なんだろうなあ。
ヘロヘロだから脳が上手く働かない。
今日は10km歩いているらしい。そりゃヘロヘロになるわ。流石に眠いなあ。明日は早起き。ひえぇ。早く寝よ。
12月1日(金)
遂に12月になってしまった。今年も残り1ヶ月か、早いなあ。
12月はクリスマスの季節だから、妙にワクワクする。好きなんだよなあ。クリスマスツリーに赤色と緑色の装飾。シュトレンに、気分が上がるクリスマスソング。全部が最高。
クリスマスソングは好きすぎて、クリスマス関係ない時期でも歌ってしまうくらい。夏とかも。(え)
クリスマスの絵本も小説も好きで、本屋に行くとたくさん並んでいるから嬉しくて堪らなくなる。
いやぁ、最高の時期になった。
『暮しの手帖』25号を読み終わる。
(初代編集長・花森安治から)いつもこう問われている気がするのです。「君たちは、なぜもっと本気で怒らないのか」と。
花森は、たとえ日本が経済的に豊かになっても、自分の雑誌が成功して認められても、そんなこととは無関係に、ずっと怒りの炎を燃やし続けられた稀有な人だと思います。それは、戦争(略)をはじめ、私たち普通の人の暮らしを踏みにじる「大きな力」への怒りにほかなりません。
思えば昨今は「機嫌よくいること」が大事で、「怒り」はネガティブなものとして捉えられがちではないでしょうか。もちろん、私もできればご機嫌で暮らしたいと思うほうですが、そのためには、本気で怒ることも必要なんじゃないかと思うようになりました。
私たちが働いて納めた税金で、人を殺める武器は買わないでほしい。人を育てることにこそ、お金を使ってほしい。神宮外苑の再開発は、なぜあんなに急ぐのだろう。これでいいのだろうかと逡巡し、時間をかけて議論することって、そんなに格好悪いことなのか……と、こんな感じです。
(略)
もっと言葉にして、表に出していきたいものです。「何も変わらない」と諦めていては、やすやすと暮らしを「変えられて」しまうのですから。
今号は(略)戦火をくぐり抜けて生きてきた90代の方々が、戦争に傾くいまの日本の状況に怒りながら、本気のメッセージを託してくださっています。当事者の方から体験を伺える機会は、残りわずかなのかもしれません。当事者でなくても、たとえ想像が追いつかなくても、メッセージを受け取った私たちが「語り継ぐ」ことで何かを変えられるのなら。いまだからこそ、お考えいただけたらうれしく思います。
最初から最後の言葉まで、余すことなく素晴らしい雑誌だった。
これからも読み続けて買い続けて、支えたいと思った。
もっとこの雑誌が、たくさんの人に届くといいのになあ。
言葉が制限されていないうちに。
12月2日(土)
「熊は恐ろしい生き物らしい」
突然父親が語り出した。熊の恐ろしさと並外れた嗅覚について。
(※大したことはないとは思うけれど、少しでも怖いのが苦手な方は飛ばして下さい)
熊は犬の何倍もの嗅覚を持ち、何十キロ先の匂いも嗅ぎ分けるのだとか。
だから人が逃げたとて、決して逃げ切ることは出来ない。
北海道で、ある事件が起きた。
森に来ていた数人の集団が、熊に襲われたのだ。当然ながら人は逃げる。だが全員がバラバラに、遠くまで逃げたにもかかわらず、1人、また1人と捕まり、そして食われてしまったらしい。
それだけではない。これも北海道の事件。
数人の狩猟者が、ある熊の親子と遭遇し、発砲した。弾は小熊の方に当たり死に、親熊はその場から立ち去った。
その夜、猟師たちは小熊を持ち帰り、100人くらいの人達が集まって、取った小熊を鍋にして宴会を開き、騒ぎ明かした。
宴会終了後、ほとんどの者が酔いつぶれたため、大人数で川の字になって、その場で眠りについたらしい。
深夜、明かりのない真っ暗な中、物音がした。
数人が目を覚ますと、そこには熊がいた。
熊はのそのそと歩くと、真ん中に寝ていた1人の男を咥え、立ち去った。
明るくなり、皆で男を探すと、原型を留めない状態で転がっている男を発見した。
襲った熊はおそらく小熊を殺された親熊であり、殺されたのは、小熊を撃った男だった。
撃った瞬間も数人いて、男がいた場所も森から相当に離れ、家の中には大勢の人がいたというのに、熊は追いかけ嗅ぎ分け、復讐を果たした。
それほどまでに、熊の嗅覚は恐ろしく凄いらしい。そして、逃げ切ることは困難。怖すぎる。
尚且つ、今は作物被害だけで済んでいるが、もし仮に人を襲い、人の味を知ってしまったら、もっと危険になるかもしれない。
人間は何よりも栄養価が高く、動物よりも遅く襲いやすいから。
「きっと人間は熊にとっては美味いと思うだよな。そこら辺の木の実を食ってる動物なんかより、熊にとっては断然人間の方が美味いに違いない」
と、何故か父は熊側になって語っていた。でも確かに、熊にとっては人間はご馳走になりえる。
1度覚えたら忘れない知能の高さと、食べものに対して異常な執着を熊は持っている。だから、知ってしまったら…。
まあでも、そもそも人が悪いのだけれど。木を切ってゴミを出して汚して、気候を狂わせてしまったから。
でも怖いよなあ。
北海道のドキュメンタリーを見て、相当話したかったのか熱弁する父親の熊話で、少し気持ちが下向。
だけどそれを聞いた母親が言った。
「確かに熊は速いらしいよね。時速500kmあるらしいよ」
自分は単純にバカだから、へーそうなんだと思った。でも父親はすかさず「それを言うなら、500mだろ」と突っ込んだ。
「500kmじゃ、新幹線より早いじゃねぇか」
と。瞬間、熊が猛スピードで頭の中を駆け抜けた。新幹線を追い越していった。
もう笑うしかない。
「そりゃ、人間は勝てないわ」
皆でケラケラ笑った。
12月3日(日)
高原英理編『川端康成異相短篇集』を読む。
「白い満月」を読み終わる。
病気は完治しているが療養中の「私」は、自分を蔑ろにする濁った瞳の娘を雇う。
娘は父親から受け継いだ瞳で死を見、「私」と「私」の兄妹である2人の妹は、父親から受け継いだもので嫉妬の炎を燃やす。
生と死、目に見えない不条理によって苦悩することで、今まで見てきたものとは違う裏側が、次第に明らかになっていく。
正直、全てを掴みきることは出来なかった。不思議で、夢を見ていたようだった。
水に写った月を見ているような、本物と同じくらい綺麗だけれど、釣られてフラフラと近づくと、足を滑られせて深い水の中に落ちてしまうような。
何より文章の綺麗さにくらくらする。
この時、瞼が病的な線を画いているお夏の眼が不思議に清らかに光っていた。山深い夏の白い満月が黒い瞳の上につつましく姿を重ねていた。
私たちは竹林の月影を歩いていた。白い満月が黄色く染まると谷川が生き生きと動き出した。清らかな白蛇が死から蘇ったように、早瀬が谷間から浮かび上った。黙って歩いている八重子の影が銀色に光る流れの上に長々と伸びているように私は感じた。
川端康成の文章は、何処か神経質なまでに綺麗な感じがする。
芥川龍之介が、あえて墨を垂らして現実味を持たせているなら、川端康成は、一滴の墨さえ許さず、完璧な白さでもって遠ざけようとしている気がする。現実という生々しさを完全に排除しているような。だからか、読んでいても遠くに感じる。でも、それがまた良いのだけれど。
不思議で、幻想的で、凄く惹かれる。
嵐山光三郎『追悼の達人』を読む。
「泉鏡花」編を読み終わる。
言わずと知れた。
泉鏡花は、追悼文を滅多に書かなかったらしく、書くのは弔詞ばかりだったとか。
ただその弔詞はどれも1級品で美しく、多くの人に模倣されるなどお手本になっていたらしい。流石である。
故に、泉鏡花に対する追悼文は困りものだった。
とはいえないかといえばそうではなく、志賀直哉、谷崎潤一郎、佐藤春夫などが、力作な追悼文を出している。
神経質なまでに美を追求した泉鏡花への敬慕が節々に伺え、そしてどれもが追悼文というよりも1種の文学作品のようであったという。
(略)ひたすら故人を美化したり、悲しい淋しいといっためそめそした追悼はない。そうであるのに、鏡花への思いは深く、鏡花の神秘性はいっそう濃くなる。これは稀有な例である。追悼文で、故人の知られざる一面が語られ、それはすべていい話ばかりで、すがすがしい。鏡花がいかに慕われていたかがわかる。
知られざる一面(エピソード)についても書かれていて、それがまた良かった。
志賀直哉が里見弴といた際、泉鏡花と出くわした。泉鏡花は、里見弴の姿を捉えると、急にしゃがんで両手に雪を掴むと、里見弴にぶつける仕草をしたのだとか。そんな無邪気な一面があったとは…。可愛いな。
里見弴のエピソードは他にもあり、泉鏡花は人づきあいは悪いと言われていたが、心を許した者にはめっぼまう甘く面倒見が良かったらしい。
里見弴へ対しては、「弴さん、弴さん」と呼んで弟のように可愛がり、小説を批評した。酒が入ったころに、鏡花は「今月の小説を拝見しました。じつに結構で、私などがとやかく申しあげる隙はないが……」と切り出した。それから、痛み入るような鄭重(ていちょう)さで、「あすこがこうであったなら、なお一層よかろう」(略)と、気づいた点を指摘した。弴が「ありがとうございました」と頭を下げると、「いえ、とんでもない」と、鏡花は弴と同じ低さまで頭を下げた。座布団と座布団がぴったりついていると、髪と髪かさわるのはしょうちゅうで、頭をぶつけてしまったことがある(略)
イメージが一気に変わった。
潔癖症で、師匠である尾崎紅葉以外の者に対しての興味が薄いのかと思っていたが、少し違っていたらしい。
今回読んで、一気に好きになってしまった。
この興味深いエピソードの元、おそらく文藝春秋から出ている『泉鏡花追悼文』のようで、読んでみたいと思ったのだけれど、探してみたら結構入手困難そうでがっくり。
まあ、いつか出会えるかなあ。
そしてそろそろ泉鏡花の作品読もうかなあ。
最近何かと忙しない。
だからnoteもあまり見れないけれど、投稿がされているのを見るだけで、皆元気に読書しているのだなあと思って癒されていたり。少しよく分からない境地に来ている。
もう何を言っているかも分からない。
こんなよく分からないところまで読んで頂き、ありがとうございました。
皆様がいつまでも元気で、素敵な読書生活をおくれますよう、願っております。
ではでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
