
#49 心のガラクタを大切にしよう~スティーブン・ジョンソン『世界をつくった6つの革命の物語 新・人類進化史』より~|学校づくりのスパイス
今回はスティーブン・ジョンソン氏による『世界をつくった6つの革命の物語――新・人類進化史』(朝日新聞出版、2016年)を手がかりに、創造性と教育について考えてみたいと思います。「創造」というと、才能に恵まれた人のヒラメキによって生まれるもので、現在の学校のような制度的教育とは相性の悪いものとイメージされがちです。
けれども、毎日の服装のチョイスから夕食の献立に至るまで、小さな発想の工夫は私たちの生活の至るところにあります。こうした「草の根の創造性」こそが、一人ひとりの生活をより楽しく、豊かなものにしていくためにも、そしてこれからの日本社会のためにも、必要とされているのではないでしょうか。
「創造」とは、新たな組み合わせ
この本はガラス、冷たさ、音、清潔、時間、光という、六つのテーマに軸にしながら、テーマに絡めて世界がどのように変化してきたかを描いた作品です。
たとえばガラスの進化から展開してきたストーリー(第1章)は次のように描かれています。
人類によるガラスの利用、エジプトの王族等の「装飾」にはじまり、膏薬(こうやく)を用いたガラス容器が紀元1~2世紀までに出現します。ガラスを透明にする技術が12~13世紀頃に発達すると眼鏡の原型となる「目のための円盤」がつくられて修道院の学者に重宝されます。
やがて15世紀に印刷技術が発明されると、眼鏡の需要は一気に高まり、やがて望遠鏡や顕微鏡へと応用されていきます。
一方で15世紀の初め頃に鏡がつくられ、自画像が描かれるようになると、実生活のみならず意識にも影響を与えます。ヨーロッパ人の意識に「自分を中心にすえる」という根本的な転換が起こり、これがルネッサンスの一因になったのではないかことも示唆されています。
さらに物理実験装置のためにガラスを細く伸ばそうと考えて石弓の一端に溶解ガラスをくっつけて矢を放つという方法を試みたところ、このガラスの強度が高かったことからグラスファイバーが発明され、これが後に光ファイバーへと進化しています。
ガラスの進化史からうかがわれるのは、たまたま発見されたモノの性質が、新たな社会環境のなかで光を当てられることになって開発が進み、中世の鏡から今日のネット回線に至るまで、人々の生活や意識にまで影響を与えてきたという、いわば「偶然の恩恵」です。
この構図は他のテーマについても当てはまることで、「冷却革命」のシナリオについて次のようにまとめられています。「冷却革命を先導した夢想家にピンときた瞬間はなく、彼らの優れたアイデアがたちどころに世界を変えることもほとんどなかった。彼らにはその予感はあったが、その予感を何年、あるいは何十年も辛抱強く温めておいて、最終的に必要なピースが集まったのだ」(113~114頁)。
創造とは人間の計画に先導されるというよりは、環境変化から生じた新しい「組み合わせ」に先導されます。そしてそこからモノや社会や人々の意識にも変化を生じさせるという、人知を越えた変化の連鎖が連なっていきます。
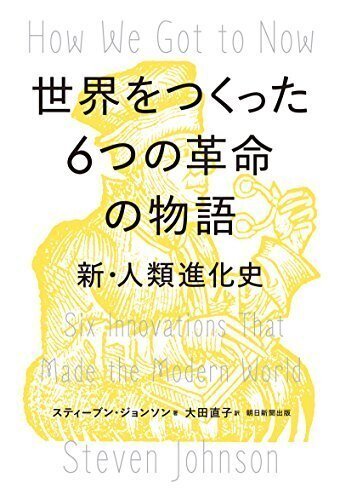
心のガラクタが輝くとき
私事になりますが筆者は最近、空調装置で特許取得に成功しました。こう言うと大袈裟に聞こえますが実は大したことではありません。
発想のルーツを思い出してみると、もう20年以上も前にインド農村でフィールドワークをしていたときの経験です。当時、村に水道や冷蔵庫がある家は稀で、どの家庭も井戸から組んできた水を金属か素焼きの壺に保管して使っていました。あるとき、素焼きの壺に保管してある水は金属の壺よりも冷たくなるのだ、と村人から教えられ、実際飲んでみるとそのとおりでした。
最初は「そんなものなのかなぁ」程度に思っていたのですが、後にそれは、素焼きのような多孔質セラミックは少しずつ水を吸収し空気中に放出する性質を持っていて、このため水が微細な隙間から吸収されては少しずつ蒸発して気化熱を奪っており、それによって冷却効果が生じるためだと知りました。打ち水と同じ原理です。
そこでこの仕組みをうまく使えば、冷房のように使えるのでは……と思いついて休日にホームセンターで材料を買いあさり、何通りか装置を試作してみました。本やYouTube等でちょっと勉強してみると特許取得もそれほど高いハードルではなさそうです。
そしてやってみたら実際そのとおりでした。
さて、創造の原理として考えてみると、筆者の趣味の特許も世紀の大発明も基本的な構造に違いはありません。何かのきっかけで自分の思考回路とは違ったモノや目的の組み合わせを見つけることで、当初とは異なった機能や価値を獲得することになるのです。
となると逆に、「それが何のためになるの?」と有用性ばかりが強調されガラクタづくりが許されないと、私たちの生活からは創造性が失われていく可能性があります。このことは授業その他の教育活動でも同じことで、創造のためには心のガラクタが必要です。
幸いにして私たちの頭は決められた目的ばかりを追うようにはつくられていません。会議に出ていても、授業をしていても、家事をしていても、そして誰かに叱られていても、目的や意図とは関係なくいろいろなことが頭をよぎります(違っていたらゴメンナサイ)。
こうした心のガラクタは、そのときには何の役にも立たないように思えても、いつか思わぬところから顔を出し、私たちの人生の転機を生み出す救世主になるかもしれません。
この本は次のような言葉で結ばれています。「自分自身のアイデンティティ意識や自分自身のルーツに誠実であることには、同等のリスクもある。そういう直感を疑い、文字どおりにも比喩的にも、地図に載っていない領域をさぐったほうがいい。同じルーティーンに収まったままでいるより、新しいつながりをつくる方がいい。(中略)もし『隠れているものに対する直感的な知覚』を持ちたいなら、その場合、少し道に迷う必要がある」(319頁)。
こんなふうに、自分にはいまだ見えていない世界についての期待を持ちながら人生に向き合えることができたら、毎日の生活や仕事も、もっと好奇心に満ちたものになるのではないでしょうか?
【Tips】
▼スティーブン・ジョンソン氏はアイデアの誕生をTEDでも語っています。
【Tips2】
▼筆者の冷却装置の発明小話は……
(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)
【著者経歴】
武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
