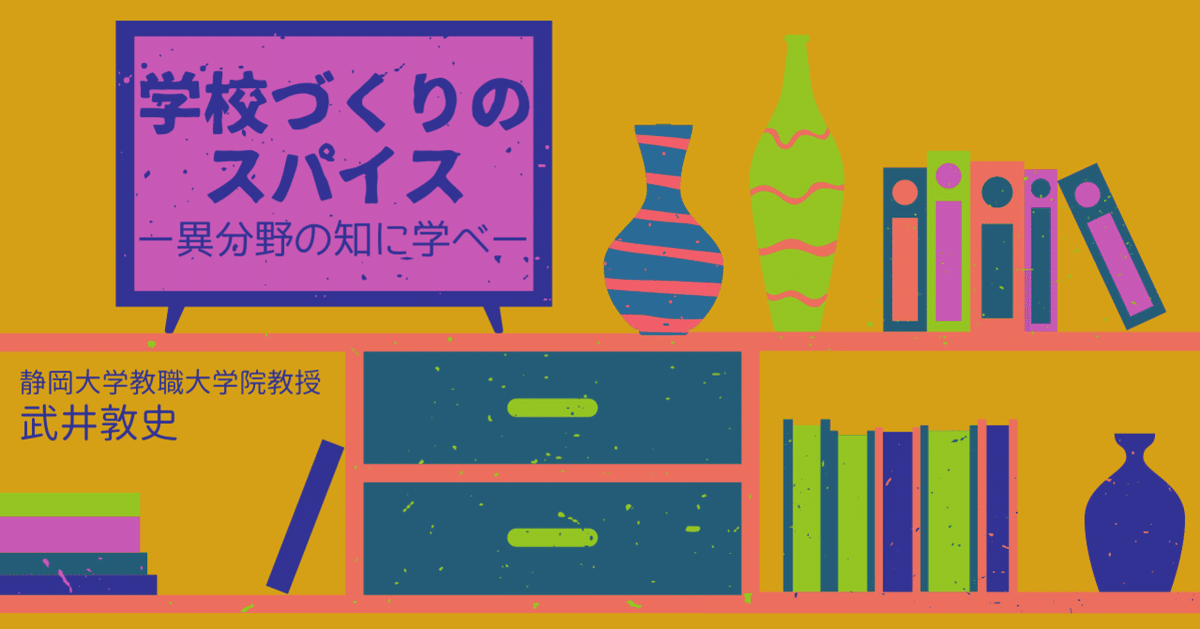
#7 公教育の「埋蔵金」~ リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット『LIFE SHIFT』より~|学校づくりのスパイス
「人生100年時代」という言葉を頻繁に耳にするようになりました。2017年には内閣官房に「人生100年時代構想会議」が設置され、2017年の流行語大賞にもノミネートされました。ただ、急速に広まったためか言葉だけが一人歩きしてしまい、長寿命社会の展望を生産的に議論する向きは少ないように思います。これはもったいないことではないでしょうか。長寿命社会についての話題の火付け役となった、ベストセラー『LIFE SHIFT――100年時代の人生戦略』(東洋経済新報社、2016年)には、これからの時代における人の生き方や仕事について、非常に幅の広い議論が展開されています。今回はこの著作を手がかりに、教員の人生をより長期的なスパンで考えることの意味と可能性について、探ってみたいと思います。
長寿命化のインパクト
人の人生の長さを想定することは、人生のデザインを規定することであり、公教育のあり方を考えるうえでも、教員自身の人生を考えるうえでも欠かせないトピックであるはずです。しかしこの問題が学校関係者の間できちんと議論されることは稀(まれ)です。多くの教員にとって「人生100年時代」から想起される課題というと、「長い老後をいったい何をやって生活していこうか?」「年金は大丈夫だろうか?」といったところではないでしょうか。
しかしこの本を少し丁寧に読んでいくと、そこで展開されているのは、こうした漠とした不安よりもはるかに緻密で生産的な議論だということがわかります。筆者が長寿命化対応の論点として注目するのは次の点です。
まず人の人生が100年続くと考えると「教育」「仕事」「引退」という三つのステージより構成される「3ステージ型人生」が、経済的にも、人生の質の点からも成り立たなくなります。100年分の生活費を40年で稼ぐことに無理があることは明らかで、また、そうしなければならない必然性もありません。
「変身資産」という視点
そして、こうした長い人生を生産的に生き、活動を持続させていくためにはお金や不動産などの「有形資産」だけでなく生活を長期的に持続させていく「無形資産」がより重要になるはずです。「無形資産」にはスキルや知識などの「生産性資産」、肉体的・精神的健康としての「活力資産」、そして「変身資産」に分類されます。
「変身資産」とは自分自身を知り、人的ネットワークを築き、新しい経験に対して開かれていることなどが含まれるとされます。この「変身資産」はこれまでとくに見過ごされてきましたが、自らの考え方や立場を変えながら生き抜いていく力を、「資産」としてとらえている点は、この本のとくにユニークな点といえるでしょう。
そこから出てくる発想はたとえば、仕事以外の時間を「余暇」としてとらえるのではなく、“re-creation” つまり「再―創造」のための時間としてとらえ、現在の活動時間の一部を将来投資に充てることで、自分の人生を自ら定義してマネジメントしていく発想です。

リンダ・グラットン 、アンドリュー・スコット著『LIFE SHIFT』東洋経済新報社
公教育の「埋蔵金」
この視点から見ると、現在の学校教員のキャリアは根本からとらえ直す必要があるように思います。
退職後の生活を成り立たせるという点で、経済的にも少なからぬ課題はあるでしょうが、たとえその問題がなんとかなったとしても、それ以上に深刻な課題となるのはおそらく「生き甲斐」についての課題です。
教員の仕事の目的ややりがいについては、「学び続ける教員」の理念のもと教員育成指標が整備されてきてはいますが、多くの自治体で依然課題になっているのが、ベテランの成長目標と動機づけについてです。そしてたとえ指標や研修が十全に機能したとしても面倒を見てくれるのは(60+α)の退職時までの約40年間で、その後に残された約40年間については政府が面倒をみてくれる見込みはほとんどありません。
しかし逆転の発想も不可能ではありません。たとえば、現在の義務教育段階の学校教員人件費約6兆5,000億の1%(650億円)をシニア教員(敬意を込めて定年以降の教員をこう呼ぶことにします)の雇用に充てるとします。これを全国の学級数(2017年度の小学校学級数26万8,787+中学校学級数11万1,914=合計38万701)で割ると一学級あたりの年間予算はだいたい17万円です。ということは現在の再任用教員の平均時給単価を1,500円として計算すると約110時間、休業期間を除く週当たりに換算すると2.5時間が、シニア教員の勤務時間に充てられるということになります。
そしてこの2.5時間の勤務時間に対してシニア教員は授業準備等の時間を除いた2コマ分の授業を受け持つことにしたらどうでしょうか(現在の教員に比べてだいぶゆとりがあります)。たいへん粗い計算ではありますが、「人件費の1%で週2コマ分の授業減」という効果です!
「埋蔵金」の活かし方
さて、このような提案に対する学校現場の反応は大体想像できます。近年再雇用教員は増えていますが、その評判が必ずしもはかばかしくないからです。「退職教員の再雇用が増えるとお目付け役のようになって現役世代がやりにくくなる」「学校現場の内情を知っていればこそ、退職後も意欲的に働こうというような奇特な人はそれほどいない」……だいたいこんなところではないでしょうか。けれどもこのようにしか考えられないのは想像力に乏しいからです。経験も知識も豊富な退職後の人材に対して、教員の補完的な位置づけしか与えられなければ、有能な人であるほどに目標を持てず、意欲も湧かないのは当然です。
しかしたとえば、「キャリア教育」「市民性教育」「道徳」や「地域との連携活動」といったテーマについて、一定程度独立したかたちでカリキュラム化し、地域のシニア教員で組織をつくって一括して担当してもらったらどうでしょうか。既存カリキュラムのなかへの組み込みが単純にいかなければ、教育課程特例校制度を活用することを考えてもよいでしょう。時間的にゆとりがあるシニア教員なら、時間をかけて工夫してカリキュラムを創ることができる一方で、現在の教員は学校教育のもっとも手のかかる部分から解放されます。
教員の多忙化軽減効果に加えてシニア教員の生きがいにもなり、生活も潤い、地域とのパイプも強まり、教育の中身もきっと充実します。一石二鳥ならぬ一石五鳥です。ところが現在の「教員の働き方改革」の議論からは、こうした雇用改革の話はほとんど聞こえてきません。その背景には、教育委員会と財務当局との微妙な駆け引きが垣間見えます。
本物の「金」は土に埋まっていれば残り続けますが、こちらの「埋蔵金」は使おうとしなければ本当に使えなくなってしまいます。知恵の出しどこではないでしょうか。
【Tips】
▼その後も「人生100年時代構想会議」については、「一億総活躍社会」や「働き方改革」とも絡んで、もつれ合いながら議論が進んでいます。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/jinsei100nen/
(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)
【著者経歴】
武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)ほか多数。近刊に『地場教育』(静岡新聞社、2021年7月刊行予定)。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
