
#30 今こそ尖った教育論を!~ 森本あんり『異端の時代 正統のかたちを求めて』より~|学校づくりのスパイス
コロナの感染拡大が国内では少し落ち着きましたが、その波紋は今後とも続くでしょう。学齢期の子どもが学校に毎日登校して学ぶことは自明ではなくなり、オンラインを活用した学習の可能性も拓かれました。そして同様の事態が再び起こりうるとなると、その課題は危機対応だけには収まりません。従来の「学年主義」「履修主義」の前提を一度括弧に入れて、公教育全体を再デザインする必要が出てくるはずです。
こうした時代の転換期にあって、柔軟で足腰の強い議論を展開するために必要なのはどんなことでしょうか。その手がかりとして、神学者の森本あんり氏の『異端の時代――正統のかたちを求めて』(岩波書店、2018年)にヒントを得て考えてみたいと思います。
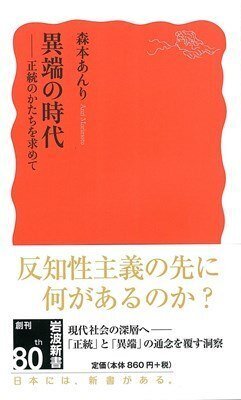
ぼんやりした「正統」とくっきりした「異端」
森本氏がこの本でテーマにしているのはキリスト教の歴史を通じた「正統」なるものの成立です。それが思想でも政治でも宗教でも、私たちは通常、「正統」と呼ばれるものは一定の根拠に基づいて成立していて、一方「異端」というと多数派にケチをつけて針小棒大に物事を論じる「はねっかえり」をイメージしがちです。
森本氏はそうしたイメージを否定します。氏によれば「初代教会の歴史を振り返ってみると、正統は正典や教義によって作られたのではなく、逆に正典も教義も正統によって作られたことがわかる」(116頁)そうです。詳しくは本書に当たってほしいのですが、新約聖書が成立したのは紀元1世紀半ばからほぼ百年の間、ユダヤ教の旧約聖書もそれが「正典」となったのは紀元後のことで、あえて正典をつくって教義を体系化したのは、異説を区別し排斥するためだったようです。
では正統はどこから生じるのかというと「正統は『どこでも、いつでも、誰にでも信じられている』かのように存在していなければならない」(234頁)と述べられています。つまり人々の間で常識化されていた信念や考え方が正当性の根拠で、それが体系化されたのが正典であり教義です。
一方で異端と呼ばれた人々はけっして「はねっかえり」ではなく、「古今東西の歴史に見る真正の異端は、みな志の高い人々である」(239頁)といいます。人々が自明視する常識を突き詰めて、問い正そうとする真摯さなしには異端は成立しないと氏は述べます。
こうした「正統は特定しがたく名状しがたく把握しがたい全体性を特徴とし、異端は明示的な要素と輪郭を持った彩度の高い主張を特徴とする」(236頁)という対照関係は、クモの巣をイメージすると分かりやすいように思います。中心の正統は宙ぶらりんですが、異端という論理的整合性を持ったいくつかの支点を持つことで構造的に安定するのです。
だから書名の『異端の時代』とは、きっと「骨のある異端が今こそ必要なのだ」という現代社会に向けた希望の表明です。この正統と異端の対比を頭に置いて考えると教育施策も分かりやすくなります。
例として新学習指導要領を取り上げてみましょう。「主体的(・対話的)で深い学び」の「主体的」とは何のことで、「深い」か浅いかはどのような基準で判断されるのか? 「教科横断的な視点で学校の教育目標達成に必要な教育課程を組織的に配列する」といったカリキュラム・マネジメントの大作業を個々の学校にできるのか等々……突き詰めていくと筆者には分からないところだらけです。
これに対して、新学習指導要領の考え方に背後で影響を与えてきたと思われる諸々の教育論……たとえば「協調学習」や「拡張による学習」の理論、「イエナプラン教育」の考え方などは、もう少しはっきりとした輪郭を持ち、一定の議論の系譜があります。
教育のポピュリズム化を防ぐには
このように、学習指導要領という「公教育の正典」も確かにぼんやりしてはいるのですが、考えてみるとそれも無理からぬことです。というのも、指導要領は聖書と同様にぼんやりしたものにしかなり得ないような仕組みのもとで創られているからです。
学習指導要領は文部科学大臣の諮問を受け、中教審の教育課程部会で原案が作成されて答申がまとめられます。審議会には多様な委員の参画を得ることが前提で、答申はそこでの合議を基盤に作成されていきます。
だから仮に各委員の方々が一定の理論的バックボーンを持っていたとしても、特定の個人の意見が強く反映されたものになってしまえば審議会の趣旨は失われてしまうので、答申はそれらを「混ぜ合わせたもの」にする必要があります。となれば、学習指導要領がいくらかあいまいなものになるのは論理的に当然の帰結です。
問題はむしろ、正統を脅かすような異端が存在しにくくなっているところにあります。異端と正統の弁証法を前提とすれば、異端がなくなるときには正統も腐敗します。そして、その結果として、全体的な将来構想を待たないにもかかわらず、「雇用」「移民」「テロ」などの特定の社会的課題に限定して支持を得ようとするポピュリズムの蔓延(225頁)を食い止めることができなくなると、森本氏は警鐘を鳴らします。
2020年度にもコロナ禍への対応として9月入学が急浮上してドタバタ劇が演じられましたが、このような浮き足立った議論に社会全体が引きずられたのは日本の教育関係者の知的体力が弱っている証左ではないでしょうか。
考えてみると、現在の日本はさまざまな社会不安が増大する一方で、政治や経済の仕組みが見えにくくなっており、ポピュリズムが蔓延しやすい環境がそろっています。そしてまさに森本氏が指摘するように、扇動政治が世界中で奏功しているように見えます。
しかし、現代の教育にとって本当に必要なのは足腰の強い議論を重ねて、より多くの人が納得できるような公教育の「代案」を模索することではないでしょうか? そして、そのためにこそ必要となるのが、現代の教育のあり方に異論を唱えうるような尖った教育論だと思うのですがいかがでしょうか?
【Tips】
▼月刊『教職研修』の2022年2月号でも紹介されていますが、森本氏は「寛容」についても大変鋭い指摘をしています。
(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)
【著者経歴】
武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
