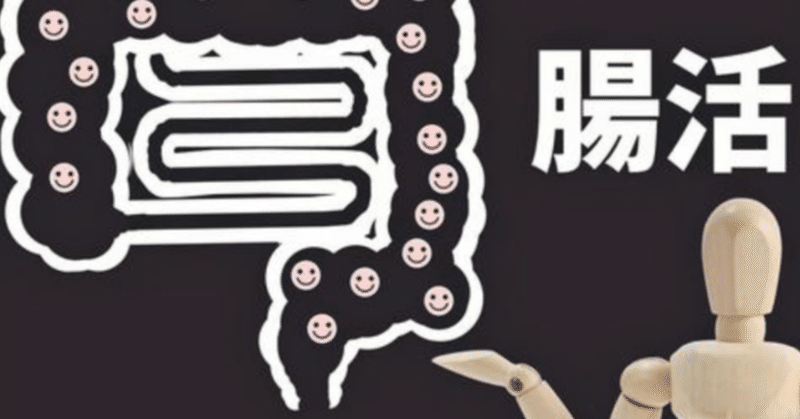
【腸内細菌学 用語辞典ver.1.0※あ行まで】
こんにちは(o・ω・o)カエルです。
□まずはじめに
当noteは、「腸活とか腸内細菌とか腸内フローラとか腸内細菌叢とか、色々ありすぎて分からん」というごくごく一般的な見解を基に、腸活・腸内細菌学において頻出する用語をなるだけ軽めに解説することを目的としています。
wikipediaや論文などから解説を引用することが多々ありますので、詳細を希望する方はリンクからご確認ください(o・ω・o)
腸内細菌学においては、体内の情報、排泄物などに関する情報は避けて通れないので、苦手な方はご自身の判断でブラウザバックをお願いいたします。
また、膨大な情報量となる可能性が高いため、noteを分けたり、随時更新となります。予めご了承ください。
記載ミス、誤情報などには細心の注意を払っていますが、万が一、表記ミス、論文の刷新などがありましたらソースを記載の上ご指摘お願いいたします。
□あ行
■アッカーマンシア属(ムシニフィラ)
ヒトの腸内にも存在するムチン分解菌。多数の動物種の消化器官内で繁殖することができる。
肥満、糖尿病、炎症との関連について広範な研究が行われている。
過敏性腸症候群、炎症性腸疾患(IBD)などの炎症状態との間に逆相関を示している。
※消化器官系疾患の患者はアッカーマンシア・ムシニフィラが少ない
■イヌリン
イヌリン(inulin)は、自然界において様々な植物によって作られる多糖類の一群。炭水化物の一種、果糖の重合体(フルクタン)の一種。
ヒトの消化器では分解不能で、大腸の腸内細菌叢によって代謝されるため、栄養成分表示では糖質ではなく食物繊維として扱われる。
※腸内細菌(特に大腸後半に分布するビフィズス菌等の善玉菌)にとって有益な食事。イヌリンの腸内細菌発酵率は100%
・毎日イヌリンを飲むと痩せるという論文
・腸内細菌のご飯不足は食欲増進を招くという論文
・イヌリン(&イヌリンの強化版)は食欲を抑えるという論文
■ウンチ(糞)
糞便の内容物は、水分、新陳代謝によってはがれた腸内細胞、大腸菌などの腸内細菌、胆汁などの体内分泌液、摂取した食物のうち消化しきれなかったもの(食物繊維など)、または体内に蓄積していた毒素などである。
人間の場合、便を構成する成分のうち食物の残滓は重量比にしてわずか約5%に過ぎない。
水分が約60%を占め、次に多いのが腸壁細胞の死骸で15%〜20%。細菌類の死骸も食物の残滓より多く10%~15%である。
【腸内細菌の歴史】
・オランダのアントニ・ファン・レーウェンフックが17世紀、顕微鏡で糞便を観察して多数の「小さな生き物」を見出したことが、腸内細菌の観察・研究の始まりとなった。
彼は「微生物学の父」と呼ばれており、微生物そのものの発見と同時期に、1674年から自作の顕微鏡を使って環境中の様々なものを観察し、ヒトや動物の糞便に含まれる、後に腸内細菌と呼ばれるようになった微生物をスケッチしている。
・1876年 ロベルト・コッホが炭疽菌の純粋培養に成功したのをきっかけに様々な細菌が単離されるようになった。
健常者にも存在する常在菌として、大腸菌(1885年)など、いくつかの腸内細菌科の細菌が分離同定された。
・1899年 パスツール研究所の研究員であったティシエは、母乳栄養児の糞便から偏性嫌気性菌であるビフィズス菌を分離した。
この当時、母乳と人工乳のどちらが与えられるかによって新生児の発育や死亡率などに違いがあり、母乳栄養児の方が健康状態がよいということが知られていた。ティシエはこの違いを明らかにするために糞便中に分離される腸内細菌に着目し、当時はまだ技術的に未熟であった嫌気培養法によってビフィズス菌の分離に成功して、母乳栄養児にこの菌が多く見られることを明らかにした。この発見によって、腸内細菌が宿主の健康に関与していることが注目されるようになり、また20世紀初頭にかけて、多くの偏性嫌気性菌の分離が行われるようになった。
・1965年 リリーらによってプロバイオティクスとして提唱され、以降、乳酸菌を用いた醗酵食品を腸内に到達させる研究が進んでいった。
・1995年 有用な腸内細菌を増殖させる物質としてプレバイオティクスという概念が提唱される。プレバイオティクスの代表的なものには食物繊維やオリゴ糖がある。プロバイオティクスとプレバイオティクスの両方の機能を併せ持った食品はシンバイオティクスと呼ばれる。
■炎症
炎症(英: Inflammation)とは、生体の恒常性を構成する解剖生理学的反応の一つであり、恒常性を正常に維持する非特異的防御機構の一員。
生体内に炎症を引き起こす組織異常には擦過傷などの外傷、打撲、病原体侵入、化学物質刺激、新陳代謝異常による組織細胞の異常変化、極端な温度環境、外耳道、肺などへの水の浸入などがある。
※腸内細菌の多様性・増減による体内炎症は「病原体侵入、化学物質刺激、新陳代謝異常による組織細胞の異常変化」に該当する
■オオバコ
オオバコ(学名:Plantago asiatica)とはオオバコ科オオバコ属の多年草。葉は薬草として利用され、漢方薬でも使われている。
外皮からとれる食物繊維は、カロリーが低く満腹感を感じさせるもので、ダイエット食品の材料としても使われている。また、吸水すると粘性のゲルを生成する性質を利用し、小麦アレルギー、セリアック病患者の為にグルテンの代用品として、サイリウム等の名でも利用されている。
オオバコには「便秘解消」「糖尿病改善」「コレステロール値改善」「高血圧改善」などの効果かある。
ここから先は

【1分で読めるnoteシリーズ】
1分で読めるnoteのまとめ それぞれは全部無料で読めます 読んでみて「これは価値がある」と思えたら、100円投げ銭してくださいませ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
