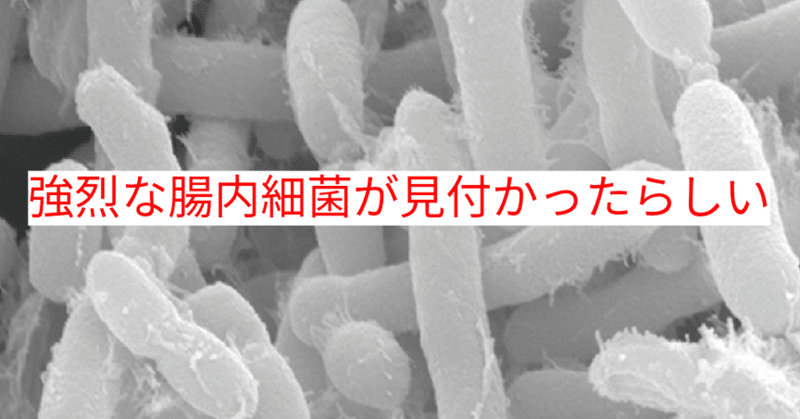
【noteで学ぶ腸内細菌38:『オドリバクター』という長寿菌】
こんにちは(o・ω・o)カエルです。
今日は【1分で読めるシリーズ】ではなくしっかり、かける限り書くやつです。
先ずは今noteを書くきっかけになったコチラのNEWSを紹介。
NEWSの内容をざっくりと紹介しますと、
慶応大と理化学研究所などの研究チームが、
100歳以上の長寿者の腸内には抗菌作用のある物質『イソアロリトコール酸』を生み出す『オドリバクター』という腸内細菌が多く存在していることを発見。
日本の長寿者、100歳以上の約160人(平均107歳)の便を調べたところ、若年層〜中高年層の数十倍『イソアロリトコール酸』が多かった。
『イソアロリトコール酸』は『オドリバクター』が生成する物質で、下痢や腹痛を起こす悪玉の腸内細菌(大腸菌とか)の増殖を抑える働きがある。
研究者である慶大教授の本田賢也(腸内細菌学)は「イソアロリトコール酸は抗菌薬が効かない一部の細菌にも効くため、治療や予防に役立つ可能性がある」
という論文が英科学誌ネイチャーに掲載された。
という話(o・ω・o)すっごぉーい!
(蛙・ω・)<こんなん、調べん訳にはいかねぇ!
てことで、今回は『イソアロリトコール酸』と『オドリバクター菌』について掘り下げて調べて学んでいこう。って話でございます。
面白そー(o・ω・o)
■イソアロリトコール酸
isoalloLCA(イソアロリトコール酸)
今回発見された新しい胆汁酸
□胆汁酸
胆汁酸は肝臓でコレステロールより生合成されるステロイド化合物。
一部の胆汁酸は大腸の腸内細菌の作用によって変換される。
・肝臓で生合成された胆汁酸を、一次胆汁酸
・腸内細菌による代謝物は、二次胆汁酸
と呼ばれている。今回発見されたイソアロリトコール酸は後者の二次胆汁酸に分類される。
□胆汁酸の役割
①乳化作用
消化管内の水分中で脂溶性の高い物質を乳化する。胆汁酸が消化管で食物の消化を促進し、特に食物中の脂肪の吸収を助ける
②殺菌作用
胆汁酸が界面活性剤として作用、細菌の細胞膜を溶解する。小腸内や胆管での細菌の繁殖を胆汁酸が妨げている。
胆汁酸の乳化作用により細菌の細胞膜は打撃を受けるため小腸では繁殖できる細菌が限定され、腸内細菌の多くは大腸が主な活動場所になる
③代謝調整
腸管内で胆汁酸が検知されると、甲状腺ホルモンのサイロキシンがより生理活性作用の強いトリヨードサイロニンに変換され、ヒトのエネルギー消費量を調節する
④コレステロールの排泄
胆汁酸の一部は大便中へと排泄される。
胆汁酸はコレステロールの肝臓での代謝産物(一次胆汁酸)なので、胆汁酸の排泄=コレステロールの排泄となる
ヒトの身体は複雑で重要なものでしか構成されてないんだなーって思わされますね(o・ω・o)
要約すると、
✅胆汁酸は殺菌作用・コレステロール管理・脂肪の吸収をコントロールする
という話で、
✅『イソアロリトコール酸』はその中でも殺菌作用が強力
ということです。
『イソアロリトコール酸』限定の特殊効果は有りそうですが、それは今後の研究に要注目ですね。
■オドリバクター菌

・現在3種類発見されているオドリバクター属の細菌※ヒトからは2種が発見されている
□Odoribacter laneus
『オドリバクター ラネウス』※上画像
□Odoribacter denticanis
『オドリバクター デンティカニス』
□Odoribacter splanchnicus
『オドリバクター スプランチュニカス』
・以前はバクテロイデス属として日和見菌に分類されていた
・名前は"臭う"という意味のラテン語"odor "から名付けられており、便のニオイの元はこのオドリバクター菌が生成するインドール(スカトール)という成分。
必須アミノ酸のトリプトファン(ブロッコリーに多く含まれる健康効果の高い栄養素)からインドールを生成する
・インドールは微量だと良い匂いになり、シャネルの5番など有名な香水にも使用されている
・isoalloLCA(イソアロリトコール酸)を生成する←NEW!
などが現在判明しているオドリバクター菌の情報です。
オドリバクター属自体が2008年まではバクテロイデス属に分類されており、研究がまだ浅い細菌ですので、今後の研究に期待が高まります。
■オドリバクター以外にイソアロリトコール酸を生成する細菌
□Parabacteroides merdae
□Odoribacteraceae
オドリバクター同様にイソアロリトコール酸を生成している
ヒトの腸内に存在する約1000種(大体965種)のうちイソアロリトコール酸を生成するのが判明したのは計3種。
■イソアロリトコール酸による病原性細菌の増殖抑制作用
□悪性細菌『クロストリディオイデス・ディフィシル』

・Clostridioides difficile『クロストリディオイデス・ディフィシル』(上記画像)という悪性の細菌は抗菌薬に対する耐性を持つ細菌。
薬での治療が難しい下痢症や偽膜性大腸炎を引き起こす。
重篤化すると手術が必要になる。さらにヒトからヒトへ感染する可能性もあり、院内感染リスクがあることから厚生労働省から医療機関への注意喚起がされている
この悪性細菌に対し、今回の慶応大と理化学研究所論文ではイソアロリトコール酸を用いた実験を行っています。
その結果、
✅極めて低濃度のイソアロリトコール酸でクロストリディオイデス・ディフィシルの増殖を抑制することを確認した
また、クロストリディオイデス・ディフィシルを感染させたマウスにイソアロリトコール酸を産生するOdoribacteraceaeを経口投与した結果、腸管内に定着したOdoribacteraceaeによるイソアロリトコール酸が増加。クロストリディオイデス・ディフィシルが排除された
悪性細菌に対する強力な増殖抑制作用がイソアロリトコール酸の強烈な特徴として、今回国際学術雑誌『Nature』オンライン版に掲載されたのです。
■今回のまとめ
✅オドリバクター菌(+2種)がイソアロリトコール酸という胆汁酸を生成する
✅イソアロリトコール酸は腸内の悪性細菌に対して強い増殖抑制作用を持つ
✅日本の長寿者(100歳以上)にはオドリバクター菌が多く、若者の数十倍のイソアロリトコール酸を有していた
✅イソアロリトコール酸は発見されたばかりの新しい胆汁酸。研究はこれから深まっていく
以上でございます(o・ω・o)調べられる範囲で調べまくりました。
オドリバクター菌(+2種)を増やすための手段などは調べた範囲では見つかりませんでしたが、
・オドリバクター属は、元バクテロイデス属に分類されていた
・オドリバクターはトリプトファンからインドールを生成する
・胆汁酸はオドリバクター菌が代謝により生成する成分
このことから推察するに、
✅ブロッコリーで『トリプトファン』を摂る
✅バクテロイデスが好む水溶性食物繊維『イヌリン』を摂る
この方法は効果があるのではないかと考えられます(o・ω・o)この辺りはこれまでのnoteで散々解説してきたことですね。
てことで、冷凍ブロッコリーとイヌリンのリンク貼っておきます。
どちらもオドリバクター菌と関連しない部分でも超身体に良いものですので、健康の為に活用できます。
ぜひお試しあれ。
どちらにしろ後悔はしないので。
いやー、今回の調べ物は疲れました。
noteの作成時間は約180分です。お疲れ様です。
最後に良かったら♡スキをお願いします。
それではまた〜(o・ω・o)ノシ
【参考記事】
腸内細菌の中にオドリバクター属というやつがいますが、こいつらスカトールという、うんこの匂いの元凶のような物質を発射します。実はこのスカトール、微量だといい匂いになり、シャネルの5番等の有名な香水に入っているのです。いい匂いも大量だとうんこの匂いになります、何事もほどほどが大事。
— 日本うんこ学会 (@unkogakkai) August 24, 2017
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
