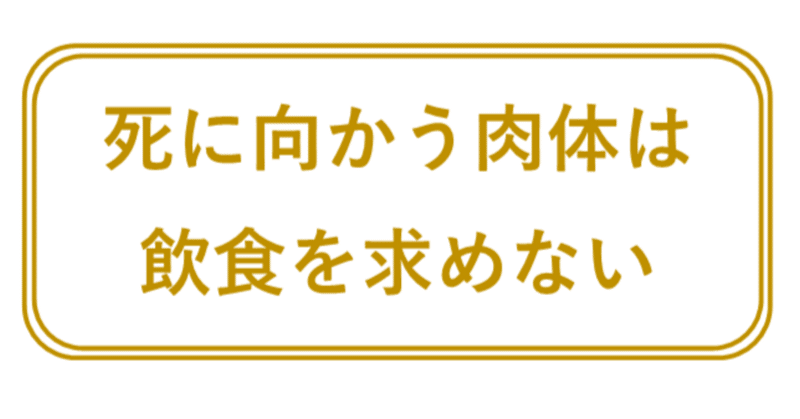
死に際の方への思いやりが、仇になることもある。話しかける・見守るだけでも十分な看取り
本記事は、介護施設における看取りの経験から、死の間際の高齢者の肉体のあり方と、その状態に対して飲食による思いやりがリスクを起点にした内容を伝えたいと思う。
このような内容にしようとしたきっかけは、フォローしているmikeneko さんの以下2つの記事である。ご興味があれば一読いただければ嬉しい。
――― というわけで以下、本文。
■ 肉体は朽ちるもの
生物は必ず朽ちる。動物でも植物でも枯れていく。
どんなに水分や栄養を補給しようにも、その器は受け入れられなくなる。
それは当然、人間も同様である。
急な病気や事故などを除いて、年齢を重ねていくと筋肉も内臓も衰えていき、皮膚もシワシワになってく。
そして最終的に骨と皮だけになる、それが生物としての死である。
悲しいことではない、文字通り自然なことである。
■ 死に向かうと飲食が困難になる
何だかポエムのような出だしとなったが、事実を書いているだけである。
特に水分や栄養を補給しようにも、筋肉や内臓が衰えると受け付けなくなることは忘れないほうが良い。
飲み込みをするにも首まわりの筋肉は必要だし、水分や栄養を吸収するには内臓が機能していることが前提となる。
肉体が衰えて死に向かうにしたがって、水分や栄養を摂取するための「飲む」「食べる」という当たり前にやっている行為が困難になる。
もちろん、胃ろうや点滴と言った医療的な措置をとることはできるが、本来の生物という観点から見れば、食べられなくなることは死に向かうということと同義である。
歳をとるということ、高齢になるということは、もしかしたらそういうことかもしれない。
■ 徐々に栄養を求めなくなる
「飲む」「食べる」ということが困難と言うと、何だか悲しい気持ちを抱かれると思う。
しかし、高齢になると栄養の必要量は落ちていく。高齢になると活動量が落ちていくので、基礎代謝を維持できる程度の栄養と水分で十分になる。
もちろん、アクティブに活動したり食欲旺盛な高齢者もたくさんいる。
しかし、そのような人たちがずっと元気でいるわけではないし、死なないわけではない。
いわゆる「ピンピン・コロリ」が理想的な死と思われているかもしれないが、今は元気な人でも徐々に活動量は落ちていき、そして肉体を維持できるだけの飲み食いで十分となる。
そして維持してきた肉体が衰えるにしたがって、必要とする栄養や水分も少なくなり、さらに徐々に肉体が栄養や水分そのものを求めなくなる。
■ 無理な飲食は肉体に負担かける
徐々に肉体が栄養を求めなくなることは、肉体が死に向かう準備をしている状態であると考えてもいい。
この状態までくると飲み込む力も衰えているので、ゼリー状の食べ物やとろみ剤をつけた食事や水分を口に含むことはできても、飲み込めずに口内に溜め込んだり、仮に飲み込めたとしてもむせ込む可能性がある。
また、内臓機能の低下により体内で吸収しきれない水分が、全身あるいは肉体の一部に浮腫(むくみ)として表れることもある。
あるいは、肉体が「もう栄養や水分を受け付けることができない」として、食物や水分を異物扱いすることもある。それが痰として表れる。
せっかく栄養や水分を摂れたとしても、喉や口内付近で痰がらみが始まり、それによって誤嚥や喉詰まりを引き起こしたり、誤嚥性肺炎も招く。
何が言いたいのかと言うと、肉体が死に向かう準備をしているところに無理な飲食をすることは、肉体に大きな負担をかけるということだ。
これを知らずに「死ぬ前に好きなものを食べさせたい」「口が乾いてかわいそうだから水を飲ませよう」とすると、死を早めるリスクがあるのだ。
■ 何かしてあげたい気持ちはわかる
このように書くと、「死ぬ間際の人に素人が余計なことをするな」と言っているようだがそうではない。
もうすぐ死を迎える人を前にすると、誰もが「何かしてあげたい」という気持ちになるのも自然なことだ。
その1つとして分かりやすいカタチが「好きなものを食べさせたい」となるのだと思う。
実際、介護施設の運営として看取りの高齢者と関わってきた経験を踏まえ、ある程度のやり取りができる時期にケーキやお寿司、お酒などを持参するご家族は少なくない。
中にはお煎餅などの硬いお菓子を持ってきた方もいたので、誤嚥リスクや噛み砕く力がないことを伝えるも「好きだったから、食べさせてあげたい」とおっしゃたので、好きにさせることにした。このときは結局、飲み込む・噛む以前にご本人が拒まれた。
「死」とは当人の話であるが、ご本人に愛情を注いできた人でも、それまで関りを避けてきた人でも、ある意味での当人との決別および精算の機会なのだと思ってしまう。
それは直接の家族ではない、仕事として介護を行ってきた介護従事者も同様の振る舞いをすることがある。利用者がお亡くなりになる前にそれまで関わってきた自分を振り返るのか、まるで禊(みそぎ)を落とそうとうするかのように水分摂取や食事介助を躍起になって行う。
ときには無理にでも全部食べるよう介助する。看取りの利用者に対してやり切った感を得ようとしているかのようだ。
しかし、それが仇になるのは上記でもお伝えしたようなことだ。
■ 話しかける・見守るだけで十分
高齢かつ死に際とは言え、飲食ができない状態になったとき、ご家族などは「何もできることがない」「何かしてあげたい」と思っても、思いやりの表現法がなくなってしまう。
もはや本人に声を掛けても返ってくる言葉は微弱で、一方的に話しかけるだけになる。最終的には見守ることしかできない。
しかし、大切な人の最期において、何もできないことに絶望する必要はない。話しかける・見守るだけで十分なのだ。
前述のように死の間際にいる人は、もはや肉体的に飲食を求めていない。
肉体的な苦痛はあるかもしれないが、それを大切な家族に取り除いてほしいなんておそらく思っていない。
介護施設で今まで看取ってきた人たちは色々いたが、恨みの言葉を吐きながら世を去った人はほぼいない。それどころかオムツ交換が終わったり、天気が良い日に窓を開けたり、話しかけたときに「今までありがとう」「元気でね」と感謝の言葉を述べられた方もいらっしゃった。
このような体験からも、排泄介助や食事提供といった介助だけが介護の役割でないと気づかされる。
そして、死を間際に感謝の言葉を述べられるという高次な精神に胸を打たれるとともに、自分も死を迎える間際にはこのようにありたいと思う。
そのためには、1日1日を「やりきった!」「他人のために動けた!」と言えるように行きたいとも思う。
ここまで読んでいただき、感謝。
途中で読むのをやめた方へも、感謝。
mikeneko さんへも、感謝。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
