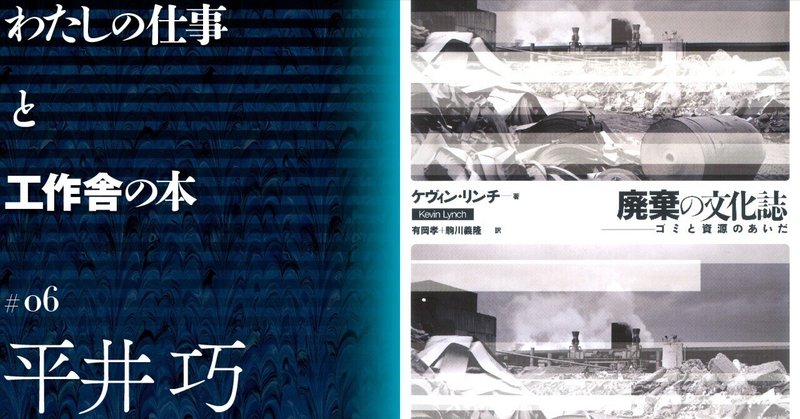
フードデザイナー平井 巧さんが読む『廃棄の文化誌』──わたしの仕事と工作舎の本#6
「わたしの仕事と工作舎の本」第6回は、フードデザイナー平井 巧さんに寄稿していただきました。
平井さんの「フードデザイン」という仕事は、食品やメニューを考案したりすることとはちょっと違っています。料理のイベントや食の生産現場ツアーなど実践的で楽しい学びを通して、人間と食のありかたを見つめ直し、新たな提案をしていくことに取り組んでおられます。
そんな平井さんが出会った工作舎の本、都市デザインで知られるケヴィン・リンチの『廃棄の文化誌』。ご自身の仕事の原点ともいうべき、食品ロス問題の視点からこの本を読んでくださいました。

ケヴィン・リンチ=著 有岡孝+駒川義隆=訳
A5判上製 320頁 定価 本体3,200円+税
ケヴィン・リンチ
『廃棄の文化誌──ゴミと資源の間』
平井 巧
食品ロスは本当に悪いことなのか
新卒で当時原宿にあった広告代理店に入社し、メーカー、流通、小売業界の企業をクライアントに、主にセールスプロモーションやPR企画を担当。学生の頃から「食」の分野に興味のあった私は、自然と食領域のプロジェクトに関わることが増えてくる。そうすると、いままで気づくことのなかった食の裏側も知ることになる。
食べものがこんなに捨てられている。
私の目にはただ明るく映っていた食の世界も、食品ロスを通して資本主義の歪みを見た気がした。
30歳になる直前に、意を決して勤めていた会社を辞めて独立。企業・行政の「食品ロス問題」にまつわる課題解決を手がける「一般社団法人フードサルベージ」を設立した。2019年には、人と食の関係を描き、「このさき、どう食べていこう?」を創造するフードデザインチーム「株式会社honshoku」を設立。新しい食文化や価値観を創りだすことこそhonshokuの役割として、サステイナブル領域における食の在り方の提案、コンテンツのプロデュース、学校現場や企業向けの教育・研修企画の提案、クリエイティブ制作などを行ってきた。
気候変動、世界規模での人口増加、国内の食料自給率低下による食料安全保障の不安など、いまの食環境にはたくさんの課題がある。一方でフードテックをはじめ、新感覚の飲食サービスや、個性あふれる食のプレイヤーの活躍など、食の可能性はこれからもどんどん生まれていく。そんないま、新たな食文化や価値観をデザインする必要性も高まっている。これまでの食の在り方を探るのはもちろん、人や地球の要望を汲み取り、持続可能な解決策を探求していくことが大切だ。
個人的にも長く探究している食品ロス問題。まだ食べられるのに廃棄される食品を「食品ロス」と呼ぶ。日本国内ではおよそ523万トンの食品ロスが発生※1している。この数字を見ても量が多いのか少ないのかいまいちピンとこないと思う。正直わたしにもわからない。SDGsの目標12「つくる責任、つかう責任」の中のターゲット12.3で、「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食品廃棄物を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品の損失を減少させる」と掲げられるくらい、食品ロスは持続可能な世界に向けて解決すべき問題のひとつとされている。SDGsは2015年に国連で採択されたが、その考え方が日本に入ってきたのは2017年ごろと言われている。この頃から、「食品ロス=悪」というネガティブなイメージを纏わされたのではないか、と考えている。本当に食品ロスは悪なのか。
※1 農林水産省及び環境省「令和3年度推計」
生ゴミを燃やす時に発生するガスが気候変動の要因になる。生産したものを食べないで捨てるということは、それをつくるために使った土地やエネルギーを無駄遣いしたことになる。飢えに苦しむ人が約10億人もいる中で、我々は食べ物を余計につくって食べずに捨てている。環境負荷だけでなく、飢餓など社会問題にもつながっていることを考えると、やはり食品ロスの量は少ない方がいい。その理屈はわかる。
日本では政府がSDGsを落とし込んで「2030年までに食品ロス半減」を掲げ、多くの自治体もそれに倣っている。なぜ1/3でもなく1/4でもなく半減なのか。半減にする方法は? いろいろな「?」が浮かぶけど、あくまでSDGsはよりよい世界へのコンパスのようなもので、解決に向けたアイデアを示すものではない。でも世間はそうした事情がよくわからず、ニュースやSNSでも「食品ロスは良くないことだ」の一辺倒で思考停止している。
食べ物を捨てる現場を目の当たりにし、企業も生活者も意外と捨て方には無頓着で、でも捨てることに「もったいない」と感じていて、その感情のやり場に困っている。「もったいない」つまり感情論だけの捉え方になっていないか。そもそもロスは悪いことなのか? 食品ロス問題に対して、僕らは一体何をどうすべきなのか? この問いの答えをおよそ10年間探し続けている。
廃棄や衰退も新たな価値を生む
食品ロスを語る上で、何かが足りない。人間の欲だったり、願望だったり、営みや文化それについても考えて行かなければ、本当の意味で食品ロス問題の解決にはならないのではないか。こうした環境問題は人間が引き起こしたものなのだから、人間自身が自分達のことを理解せずして問題は解決するはずがない。そんなことを考えているときに、池袋にある大型書店で『廃棄の文化誌』に偶然出会った。本を手にとってパラパラとページをめくってみると、最初の方にある「編者による序のページ」に書かれていたつぎの一文に心を動かされた。
本書は、「警告」ではなく、廃棄物と廃棄の過程の多くが、人、モノ、場所のいのちにとって貴重であり必要不可欠な要素であることの認知を求める、ひとつの「申し立て」である。
これまで都市や地域の計画、デザインに関する著作が多かった建築家ケヴィン・リンチの残した最後の本である『廃棄の文化誌』は、「廃棄や衰退を生活の中にどう取り組むか」をテーマに書かれている。廃棄は生命や成長に欠かせないことであり、我々人類はその価値を尊び、上手に廃棄する術を学ばなければならない。この本に書いてあることは、食品ロス問題にいま必要な、廃棄に向けられた哲学的で社会的な問いだ。
何かを探求する際に、別の領域から視点を持ってくることで、知と知がくっついて新しいことに気づいたり、整理ができることがある。この本では、食とは別のモノ・コトを対象に書かれている部分が大半だ。だからこそ食と距離をとって「食品ロス」について考えることができた。
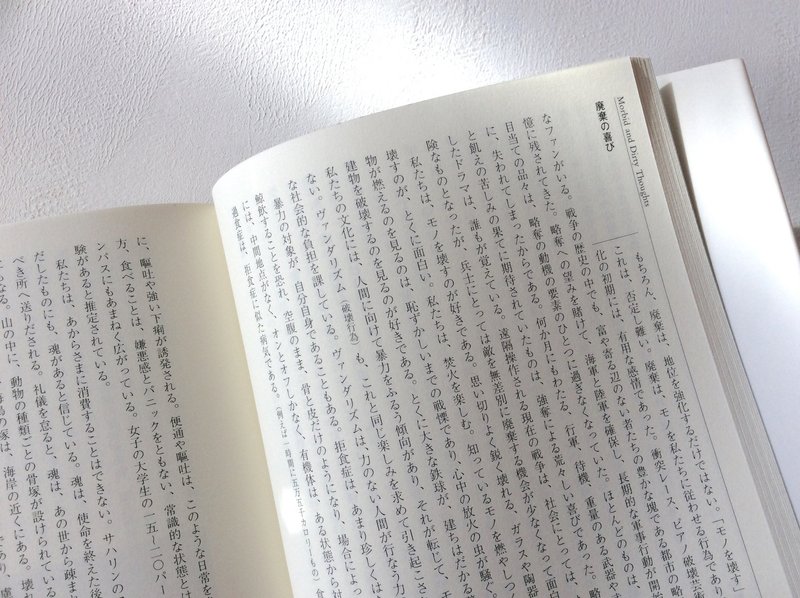
そもそも廃棄とは何か?
本の中でケヴィン・リンチは、「廃棄物」を次のように置いて考察を始めている。
人間にとっては価値がなく、使われないまま、外見上は有用な結果をもたらすこともなくものが減少すること。それは損失、放棄、減退、離脱であり、また死である。
これだけ食べることが経済に組み込まれた現代。たくさんの商品が開発され、原料となる食材が地球上で生産され、人口増加で食べものの量はさらに必要になっていく。効率よく食べ物を生産し、それを手元に届けるために規格が生まれる。規格があるから、当然のように規格外も発生する。規格外の商品は経済的には価値を生み出さないものとして廃棄される。手元に届いた食品も、食べきれなくて腐敗して捨てることもある。人間はどうしたってロスが生まれる世界で生きているのだ。それはいまに始まったことではなく、私たちの祖先の時代にも廃棄することはあった。先人たちはそれを循環のプロセスの中に組み込んでうまいことやっていた。しかしモノが溢れる今の時代では、廃棄がうまくプロセスに組み込まれないこともある。つまりケヴィン・リンチからすれば、循環プロセスの中に組み込まれる捨て方は問題のない廃棄であり、今の私たちのような捨て方は良くない廃棄だと言える。
ロスを減らす上では生産量を減らすことも大事だけど、経済活動の中で、企業が生産量を減らす方向に調整するのはむずかしい。チャレンジしている企業もあるが、多くの企業は売上の減少につながるかもしれないことはやりたがらない。企業はロス対策として生産量を減らすより、食材を無駄なく使うことで新しい商品を開発しようとする。食材を無駄なく使うことは、食品ロス削減のため、地球環境のためという大義名分も掲げられる。
たしかにこれまで捨てていた端材を原材料として使うことで、コスト削減にはなるし新商品開発できるしで、企業としては良いことだらけだ。捨てる食材を別の食加工品に生まれ変わらせることは一見ナイスアイデアだ。だがこのことがモノとしての食品の大量生産につながり、結果的に企業の自己満足にしかなっていないことが多い。
国連WFPによると、世界には全人口を賄うだけの十分な食料があるにもかかわらず、9人に1人は飢えに苦しんでいる。一方で世界の食料生産量の3分の1は捨てられていている。これを「食の不均衡」と呼ぶ。食品ロス問題に対してできることを考えるとき、この「食の不均衡」の事実は外せない。そもそも人間の胃袋はひとつだから、人間が1日に消費できる量はある程度決まっている。目の前の「食品ロス」を少なくするために商品を生み出しても、満たされた胃袋だけでなく飢えた胃袋にまで届くフードシステムが構築されていかなければ、食の不均衡は解決しない。
食品ロスに関しては、もったいないから捨ててはいけない、という目先の感情論だけで捉えがちだ。それよりも、人間活動の中でロスは発生することを前提に、ロスになる食べ物をどう循環プロセスの中に組み込み、人間が食べる以外の新しい価値を創り出せるかを考える方が、よっぽど前向きであり有益なのではないか。
捨てるしかなかった食べ物に新しい価値をつくる事例が、いま生まれ始めている。コーヒーかすと竹の粉を使用した植物由来素材のお弁当箱「BENTO box COFFEE」や、休耕田のお米や廃棄されてしまうりんごなど未利用資源を発酵・蒸留して出る発酵粕を、化粧品の「原料」や鶏・牛の餌に活用し、さらにその鶏糞や牛糞を畑や田んぼの肥料にするなど、ごみを出さない循環をつくる「株式会社ファーメンステーション」の事業活動などがある。
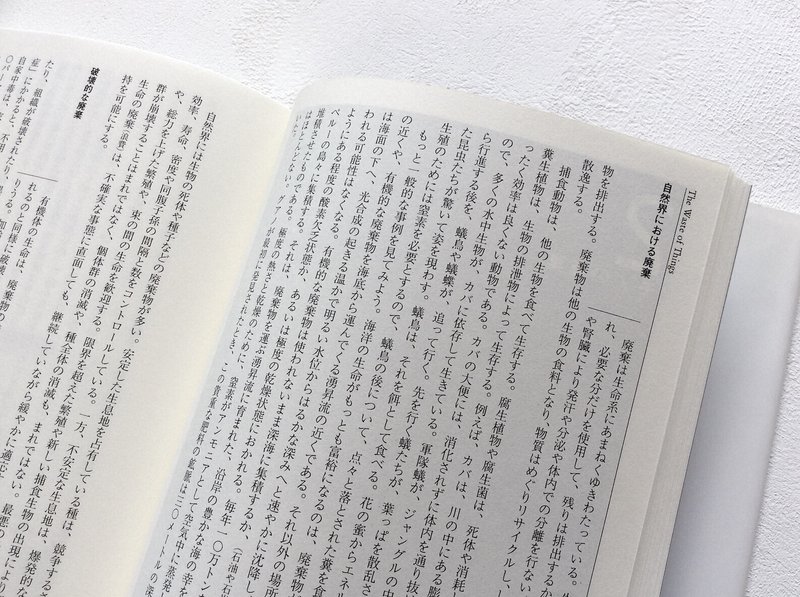
生命の成長という絶対的な価値に欠かせない廃棄
ケヴィン・リンチが論点にしている「有用性の喪失」の話は、食品ロス問題にも重なる。
人間が食べるとお腹を壊しそうな腐った豚肉や魚のように、使うときに有用性が必要以上に失われている資源は、「廃棄されている」と考えられる。例えば、「雨漏りのする屋根」や、「多作で消耗してしまった田畑」は廃棄されている状態だ。だけど適切な維持のために生じた通常の消耗による場合には、それは廃棄とは言えない。出来事の予測と管理が向上するにしたがい、逆に人の怠惰や過失(ヒューマンエラー)による「腐った豚肉や魚」や「雨漏りする屋根」のような廃棄物を生産する機会は増加する。前述の効率のために規格を設けることで規格外が生まれロスが増える、という話と同様だ。
ケヴィン・リンチは言う。有用性の喪失(=廃棄)は、技術や需要や供給の変化がもたらす「時代遅れ」という状態で現れるのかもしれない。それは、物質的な変化ではなく、認識の変化であるとし、wasteful(無駄)は、認識の変化が利益をもたらすのか否か、費用が効果よりも少ないのか否かによって判断される。
食べものだけの話ではなく、現代ではさまざまな資源から途方もない量の廃棄物が生まれている。廃棄したものを(人間以外の者も含む)次の利用者へと譲り渡すことが、この地球上における本来の循環である。そうした連鎖によって生命体は維持され、成長してきた。このさき食品ロスは、うまく生命の維持や成長に寄与させることで「不可欠な廃棄」になり得るのかもしれない。
平井 巧(ひらい・さとし)
フードデザイナー
1979年生まれ。広告代理店での企画営業を経て独立。foodloss&waste の課題解決を手がける一般社団法人フードサルベージを2016年に設立。未来のための食を創りだすフードデザインチーム株式会社honshokuを2019年に設立。「サルベージ・パーティ」「ごはんフェス」「フードスコーレ」「Shokuyokuマガジン」など手がけたコンテンツ多数。
『廃棄の文化誌』について──工作舎より
『廃棄の文化誌』(原題:Wasting Away)は、アメリカの都市計画家ケヴィン・リンチが晩年に残した原稿をマイケル・サウスワースが編集して1990年に出版されました。工作舎は1994年にその全訳を刊行しました(2008年に新装版刊行)。翻訳者は有岡孝さん、駒川義隆さんです。
若い頃にフランク・ロイド・ライトに師事し、都市の再生計画に取り組んできたケヴィン・リンチ。代表的な著書である『都市のイメージ』(丹下健三・富田玲子訳/岩波書店)は日本の都市研究者によく読まれています。
本書『廃棄の文化誌』も建築関係者に人気の高い本で、書店では建築書の棚に並んでいることが多いようです。この本を、食のデザインを生業とする平井さんが目にとめ、手に取ってくださったことが意外でもあり、とても嬉しく思い、この原稿を依頼しました。
「食品ロスは本当に悪いことなのか」。
のっけからこんな言葉で始まった平井さんの原稿に虚をつかれました。そして読み進めていくうちに、平井さんの葛藤を通して、そもそも「ロスってなんだろう?」「人間にとって、廃棄するとはどういうことなのだろう?」という本質的な問いが迫ってきます。それこそが、本書『廃棄の文化誌』の問いかけでもあります。
平井さんがご自身のnoteに書かれていたこちら↓もぜひお読みください。
都市という巨大な有機体を相手にしていたケヴィン・リンチは、都市が排泄する大量の廃棄物に途方にくれながら、一方ではその可能性や両義性に魅了され、この本を書き進めていたのでしょう。平井さんの原稿をいただいて、あらためてこの本の射程の広さ、深さ、現代性を認識しました。
本書には、高レベル放射性廃棄物の懸念についても書かれています。リンチが亡くなったのは1984年。その2年後にチェルノブイリ原発事故が起きています。
福島第一原発事故を経て、日本にはいま行き場を失って核のごみがたまり続けています。地下深くに処分するべしとする最終処分法に対して、2023年10月に地質学の専門家グループは「日本に適地はない」と声明を出しました。廃棄できるどこかなど、どこにもないのです。
編集者の私がこの文章を書いている今は2023年12月末。工作舎も大そうじの日が迫っています。私の机の周りも、かつては有用だったけれど今は不要物となったモノ(主に紙)がいっぱいです。ペーパーレス、いったいどこの星の話?という感じの仕事場です。
工作舎は、紙ゴミをたくさん排泄しながら紙の本を生み出しています。
紙の本も、売れなければいずれは廃棄するしかありません。
たとえ売れて読まれても、いつかは廃棄されることになるでしょう。
せめて、後者の道をたどってほしいです。
ということでケヴィン・リンチ『廃棄の文化誌』まだまだ在庫ございます。(文責・李)

『廃棄の文化誌』について工作舎のホームページの情報はこちら
全国の書店やネット書店でもご注文いただけます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
