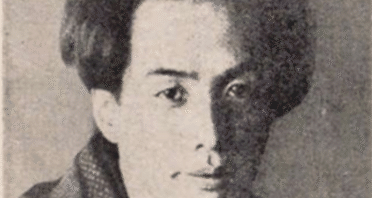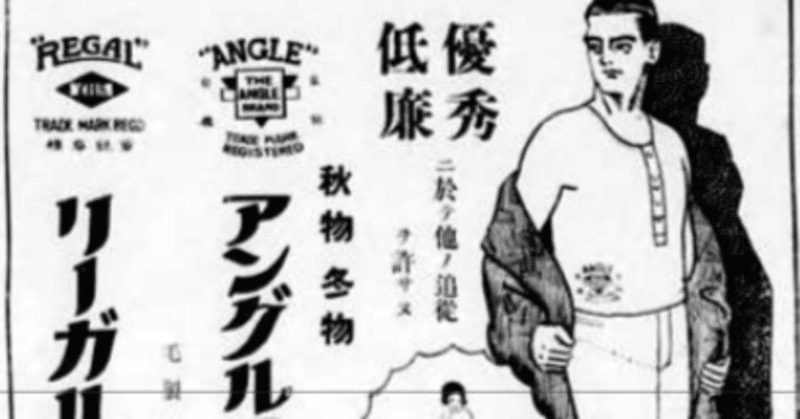2023年12月の記事一覧
芥川龍之介は夏目漱石をどのくらい知っていたのか② 読んだ作品は限られている
近代文学1.0の終焉は、結局夏目漱石作品が解らないということに気が付かないところで訪れたものではなかろうか。文学が多少なりとも影響力を持っていた時代、という柄谷行人的区切りを置いてみた時、夏目漱石作品が解らないので「漱石をやり過ごす」「漱石に不意打ちを食らわせる」として表層批判に留まることを宣言した蓮實重彦の漱石論は、漱石のコードを無視するというやり方で夏目漱石作品が解らないという問題を回避した
もっとみる芥川龍之介は夏目漱石をどのくらい知っていたのか① 生い立ちを知らないかも
近代文学2.0の主題は「芥川龍之介は如何に漱石文学を継承したか、或いはしなかったのか」というあたりにある。夏目漱石作品が中学生からお爺さんまでに大人気であり続けていて、なおかつ学者や作家に長年読み誤られていて、岩波書店の『定本漱石全集』の註釈は間違いだらけという頓珍漢な状況に加えて、かりに芥川龍之介までが漱石文学を継承しなかったとすると、そもそも漱石文学とは何だったのかということになりかねないか
もっとみる吉田精一は余計なことをしないでほしい① 妙な具合に話を広げるな
芥川龍之介の『支那游記』に、
とある。
こちらは新橋の芸者なので湘南にはいまいし、年が合わない。
そしてややこしいのは、註解者が、
と余計なことを書いているのだが、
かなしかる初代ぽん太も古妻の舞ふ行く春のよるのともしび
かなしかる初代ぽんたも古妻の夜半は舞はめと春ふかみかも
どういうこと?
散りのこる岸の山吹春ふかみこの一枝をあはれといはなむ 実朝
これはそ
芥川龍之介の『歯車』をどう読むか59 症状はあったか
昭和二年五月五日の日記である。
私は『歯車』論をアポフェニアの概念から書き始め、ここは見落としていた。
この日の日記が真っ赤な嘘でなければ、(その可能性がなくはないと思うが)この虎も、「症状」とみなすべきかもしれない。
この前にはこうあるからだ。
言ってみればここにはかなり手慣れた文芸的修辞がある。あまりにも文芸的なのだ。つまり読み流しかねないようにわざとさらりと書いている。前掲の作
夏目漱石の『イズムの効過』と芥川龍之介の『イズムと云ふ語の意味次第』をどう読むか①
夏目漱石がこう書いたのは明治四十三年。これを芥川が読んだかどうかは、はなはだ怪しいと私は考えている。芥川は漱石の弟子と云えるほどの分量、つまり小宮豊隆のように夏目漱石作品の全てを丹念に読んでいたわけではなさそうだ。大正十三年に出た『漱石全集』を買った、読んだ、感動したという記録が見つからない。
従ってこういうニアミスのようなことが起きうる。小宮豊隆が同じ題で書けば、夏目先生が述べられていたよ
たかられて小銭渡すや超河童 芥川龍之介の俳句をどう読むか193
世界戦争後の改造文学の超国家性
まずこれが俳句かどうか意見は分かれるところであろう。私はこれは俳句ではないと思う。
改造文学は、芥川の死後さらに盛り上がり、そして世界戦争後には、ほぼ消えた。大正十四年、芥川のところに失業した労働者が三人やってきて金をせびっている。当時は資本主義も社会主義も雑な時代で、少しでも金のあるもので社会主義に理解のある人間は労働者から金をせびられるのが珍しく
ためつものそらだき行くや八仙人 芥川龍之介の俳句をどう読むか192
飯中の八仙行くや風薫る
この句もまた無言の鑑賞にさらされている。多分、ほとんどの人が意味の解らないまま、ただ芥川の句だという理由だけでありがたく眺めているのであろう。
この「八仙」には註が付いて、『飲中八仙歌』の俳諧化だとされている。
問題はそこである。
これは解る。
問題は「飲中八仙」ではなく「飯中八仙」なのだ。註釈者はそこに踏み込んで説明できていない。解っていないのにほっ
紫の鰻踊るや九月雨 芥川龍之介の俳句をどう読むか191 解らないものは解らない
掻けば何時も片目鰻や五月雨
解らないところを何とか突き止めた句もあるが、相変わらず解らない句というのもある。例えばこの句、五月雨は解る。ごぐわつあめと読ませている。解らないのはこれが大正八年九月二十四日に詠まれていることだ。九月に降る雨は九月雨であり五月雨ではない。
次に片目鰻が解らない。
調べると、小説が一つ伝説が二つ見つかる。
しかしそこにちなむような引っかかりが見つからない。
芥川龍之介の俳句をどう読むか190 ここまでのまとめのようなもの②
青蛙おのれもペンキぬりたてか
そもそもこの句が北原白秋、飯田蛇笏、佐藤惣之助という錚々たる詩人たちのなかで「雨蛙汝もペンキ塗りたてか」「青蛙汝もペンキ塗りたてか」「青蛙おまへもペンキ塗りたてか」と様々に記憶されてい混乱から俳句の読みを確認する作業が始まった。
今のところこの句がルナール『博物誌』が元ネタであるというのは眉唾であると考えており、
①ペンキ塗りたてのようにしっとりしている
②ペ
芥川龍之介の『O君の新秋』をどう読むか① うら寂しくさえない秋
別に芥川龍之介の死の覚悟、自殺の決意の時期を確かめる為ではなかったが、俳句の鑑賞のために書簡集を一通り読み直してみてやはり、結果として
①自殺の覚悟は『温泉だより』が書かれた時期
という考えは改めるべきではないかと考えるようになった。二年前から死に方を研究していた、漱石の命日に死のうとしていた、でいいじゃないかと思えなくもないが、本来どうでもいい自殺の覚悟の時期の問題が、芥川の晩年の作品に
芥川龍之介の俳句をどう読むか189 ここまでのまとめのようなもの①
これまで芥川の句を百以上読んできて思うのは、
・目の前のものをそのまま詠もうという考えはさらさらない
・漢詩、和歌の要素をふんだんに取り入れている
・「知的なひねり」を加えている句が少なくない
……といったことが言える。
菊の酒酌むや白衣は王摩詰
これなどは詠んだ季節はあっているものの、目の前に王摩詰がいるわけもないので、詠み方としてはいかにも和歌的なものだ。
ただこの句の解釈を
甲比丹乃ききすぐすかや沓手鳥 芥川龍之介の俳句をどう読むか188
甲比丹(カピタン)乃つんぼ咎めそほととぎす
[大正十四年六月二十三日 吉田東周宛]
甲比丹もつくばはせけり君が春 ばせを
という芭蕉の句がひねられたものか。甲比丹とは、
「つんぼ」とは耳が聞こえない人のこと。差別用語であるとして、現在では使用することが禁止されている。
もちろん当時の芥川にはことさら障害を揶揄う意図はなく、ごく当たり前に使われていた言葉を使
芥川龍之介の『教訓談』及び『追憶』をどう読むか② ついでに『侏儒の言葉』と『猿蟹合戦』を読むけど解らない
どう云うわけか芥川は「かちかち山」に深いこだわりを持っているようだ。「舌きり雀」や「桃太郎」が混ぜ込まれたこの詩のようなお話の題はあくまでも「かちかち山」であり、やはり何の教訓も見いだせない。
しかしまるで何かの成功を勝ち誇るかのように言葉は紡がれる。
あるいはこの日輪と桜は日本の象徴ではないかと思ってみる。「獣性の獣性を亡ぼす争ひに、歓喜する人間」という表現に見える棘は、兎や狸ではなく