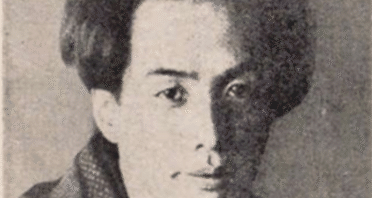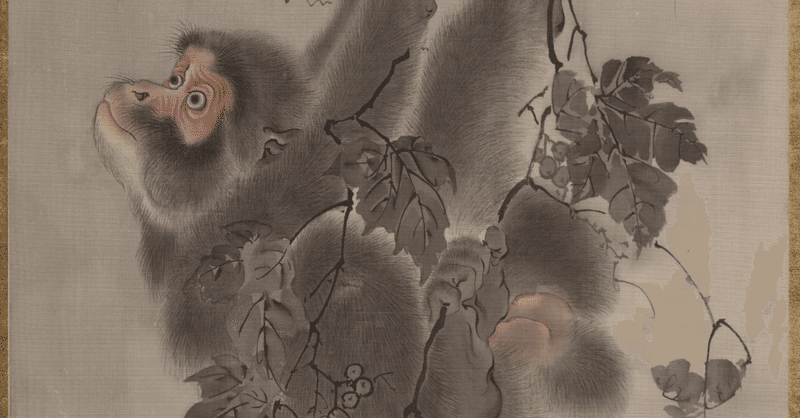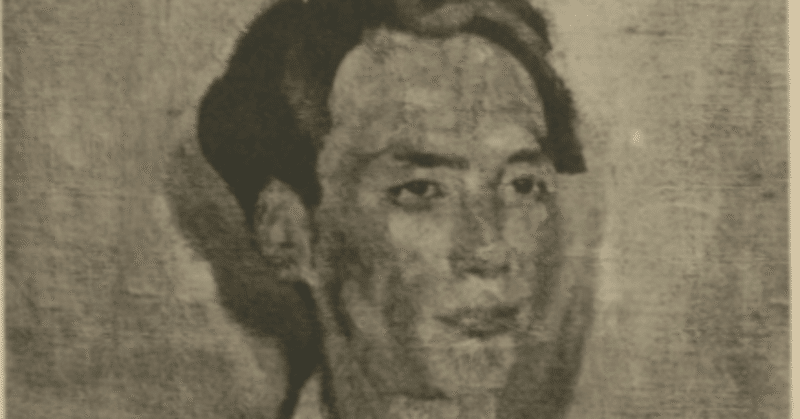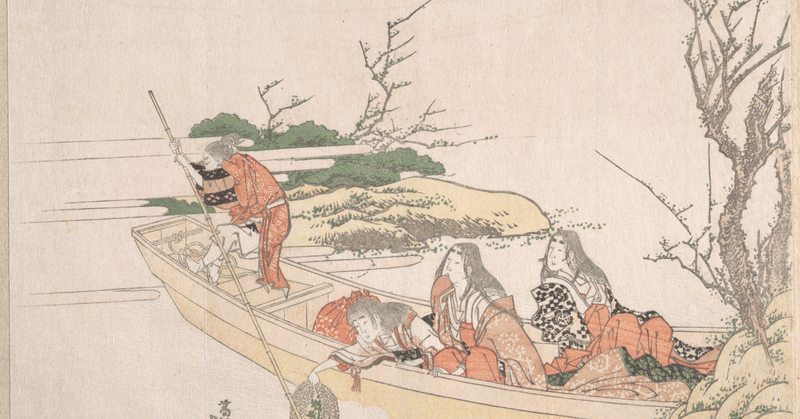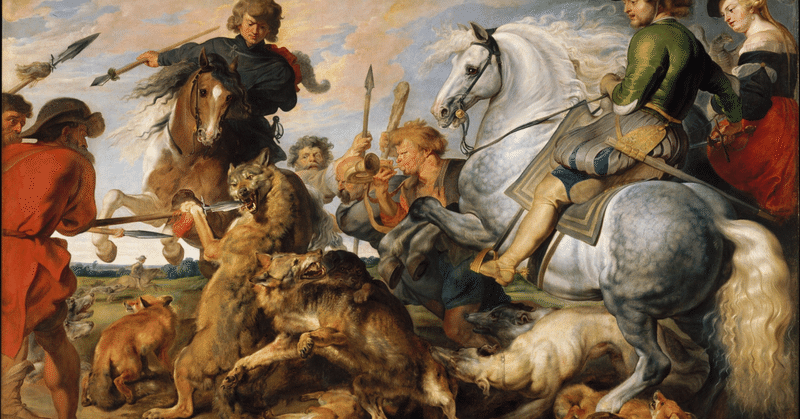2023年10月の記事一覧
谷あひの杉むらとよむ谺かな 芥川龍之介の俳句をどう読むか46
山がひの杉冴え返る谺かな
伊太利人だって言葉の意味を求めているのに、日本人は「ふーん」で済ませている。
冴返る身に沁々とほつき貝
に関しては既に書いた。
漱石の「冴え返る」についても既に書いた。
この句には「高野山」の文字が添えられている。
さて「山がひ」とはどこだろうか? 「谺」というからには、芥川は「やっほー」とでも叫んでみたのだろうか?
高野山で叫べば杉が冴え返る
元日や啓吉の名もおめでたき 芥川龍之介の俳句をどう読むか45
元日や啓吉も世に古箪笥
先に、
元日や手を洗ひをる夕ごころ
の由来については書いた。
この句はやはり、
と添えられていることから、まずは
「元日にしみじみ思うよ、菊池寛も偉くなったものだなあ」
という程度に読んでおけばいいであろう。
なお、
元日の居ごころや世にふる畳 太祇
という句が元ではないかという説を見かけたが、
子規は、
元日の居心や世に古疊
山茶花の石女となる師走かな 芥川龍之介の俳句をどう読むか44
山茶花の莟こぼるる寒さかな
一見この句にはさしたる工夫が見られない。……ように思える人はどうかしている。明治期の山茶花の句と比べてみよう。
こうして明治の句を連ねてみると、「山茶花」の莟を詠んだものに、
山茶花は蕾がちなり初時雨 河葵暮
があり、「初時雨」が晩秋から初冬にかけての時期の最初の時雨であることからこの時期に莟であることが解る。
そして、
山茶花は散てしまふ
こはざれに麦からかけよラズベリー 芥川龍之介の俳句をどう読むか43
園芸を問へる人に
あさあさと麦藁かけよ草いちご
なんでそうなる?
この「あさあさ」にも色んな意味がある。
あさあさと色うつくしき重の茎
この「重」が「空櫃」についているなら、
茎は青菜であり、野沢菜のような漬物か。すると「あさあさ」は、
浅漬けにかかる。
ただしこの「あさあさ」は白菜ではない。白菜は
と、かなり遅く日本に這入って来たもので、まさに野沢菜のようなものが漬
すががさに霜降る夜やひそかごと 芥川龍之介の俳句をどう読むか42
そうか。やはり伊香保に来たのか。
霜のふる夜を菅笠のゆくへかな
伊香保と言えば、
こんな話があり、明確に怪しい。
まあ「別情自ら悄然たり」という背景はあったのだろう。
この句は室生犀星から菅笠が「皮かむりの古さ」「餘りに古きに從ひ過ぎ做ひ過ぎる」と指摘されている。漢口ではヘルメットだったが、
霜のふる夜をメットのゆくへかな
ではさすがに浮ついている。
ところでこの句、
蒲の穂の蓮華にまどふあしたかな 芥川龍之介の俳句をどう読むか41
蒲の穂はなびきそめつつ蓮の花
北原白秋にはたくさん蓮が出てくる。
芥川は三四郎池でピンクの蓮の花を見ていた筈だが、『蜘蛛の糸』では白い蓮を描く。白秋の影響はなかろうか。ないな。芥川は赤や白や金色の、さまざまな蓮を書いている。
この句は、
……が元だろうか。
おお、漱石。
蒲の穂はなびきそめつつ蓮の花
この句は「蒲の穂」と「蓮の花」の取り合わせ、そして「なびきそめつつ」と
こけにされ命映えたか日のにほひ 芥川龍之介の俳句をどう読むか40
夏の日や薄苔つける木木の枝
さてこの句も「夏の日」が「夏の一日」「夏のある日」なのか「夏の太陽」「夏の日差し」なのか曖昧にされている。
この記事で「日のにほひ」は「日光」だと書いた。「巴旦杏」「いとど」に続いてこの句でも曖昧なところに意味を持たせようとしている。
夏の日や千度千引の岩根松三年ふるしけりやあつき苔の下
実際どちらともどちらでないとも判じきれないものだ。
これで言えば
おもはずや瓦に枝垂る暑さかな 芥川龍之介の俳句をどう読むか39
木の枝の瓦にさはる暑さかな
さあ、これは解らないぞ。さっぱり解らない。どういう状況だ。何の木だ。
まず「さはる」は、
こちらの意味ではなかろう。
いまはのきはのさはりかなしき、ということもなかろう。瓦は病気にはならない。芝居のさわり、つまり出だし部分……これもないだろう。「さはり」とは言うが「さはる」とは言わないからだ。「巴旦杏」「いとど」「ほどろ」「日のにほひ」同様まず「さはる」
詩集 澄江堂遺珠 芥川龍之介遺著 佐藤春夫纂輯
はしがき
岩波版「芥川龍之介全集」の中に收錄された詩篇は堀辰雄君の編纂にかかるものにして、故人の遺志を體して完成を重んずる精神を飽くまでも尊重せる細心の用意をもつてなされたもの、出來得る限り多數の採錄を努められたるも、その嚴密なる用意の結果は却つて多少の遺漏を生じてそこに逸せられたものも尠くない。
これを惜んで先年、遺友の間に故人の三周忌記念として散佚せる詩篇を集成して更に一卷の詩集を得ば
寝崩れて上ぬるむかはたつのすけ 芥川龍之介の俳句をどう読むか38
更くる夜を上ぬるみけり泥鰌汁
薄田泣菫の詩に「うはぬるみ」という言葉が現れるが、「上ぬるみ」という言葉そのものは他に見ない。そして「日の光蟬の小河にうはぬるみ」の「うはぬるみ」は小河が少し温められている様子で、「上ぬるみ」は熱々の泥鰌汁がやや冷めた状態で方向性が真逆であろう。
ネットでは、
夏の夜や崩れて明けし冷やし物
という芭蕉の句が基になっているという話があるけれど、これも方向性
そんな俳人もいそうだけど 芥川龍之介の俳句をどう読むか37
唐寺の玉巻芭蕉肥りけり
この句は全集では「からでらのたままきばしょうふとりけり」と詠まれているが、どういうわけかネットでは「たままく」に直されて紹介されている記事が多い。「玉巻」の季語が「たままく」と広く訓じられている所為なのだろうか。
この句には「再び長崎に遊ぶ」という言葉が添えられていて、注によればそれは大正十一年四月のことらしい。
そういえば『長崎日録』にあった句だ。少し印象が
何の言い訳にもなっていない 芥川龍之介の俳句をどう読むか36
しぐるるや堀江の茶屋に客ひとり
これも冬の時雨を詠んだ句であろう。
皮かぶりの古さは良かった。全集では「堀江」に注がつき、「待合茶屋多し」と上品に誤魔化されているが、堀江の茶屋は元禄からの遊里である。
さて、この句の味わいは、子規の、
星月夜星を見にゆく岡の茶屋
……のように「しぐるるや」がまるで何の言い訳になっていないところである。而比再得時雨宿宿潤澤と『後漢書』にあるから、し
季語殺し炸裂夏のにほひかな 芥川龍之介の俳句をどう読むか35
唐黍やほどろと枯るる日のにほひ
この句もかなり誤解されているようだ。
まずは「ほどろ」。
この意味に解釈している人があるようだが、「まだらに枯れる」? つぶつぶがまだらに白茶けるという意味? 剝けばそうだろうが、そもそもそういうやり方で詠み手自らが状況を迎えに行くことは、俳句ではあまりお上品とされていないのではなかろうか。
ここはあくまでも穂が長けて、立ち枯れているよ、という程度の
屋根裏に鳴くや環境依存文字 芥川龍之介の俳句をどう読むか34
あかつきや蛼なきやむ屋根のうら
蛼を「こおろぎ」と訓じている人もあるがルビは「いとど」とふられている。そして巴旦杏をスモモ、蛼を「こおろぎ」と説明してしまっている人もいるが、他人に説明する前にはよく調べた方がいい。
※「蛼」 ……「あしまつい」、こおろぎ。
要するに「蛼」とは「李」とあえて書かずに「巴旦杏」と書くような細工である。
現代の主要な国語辞典では「いとど」に「蛼」の漢字を