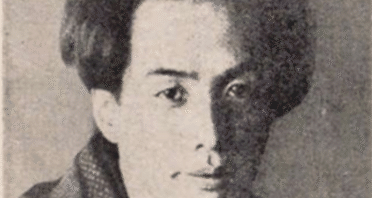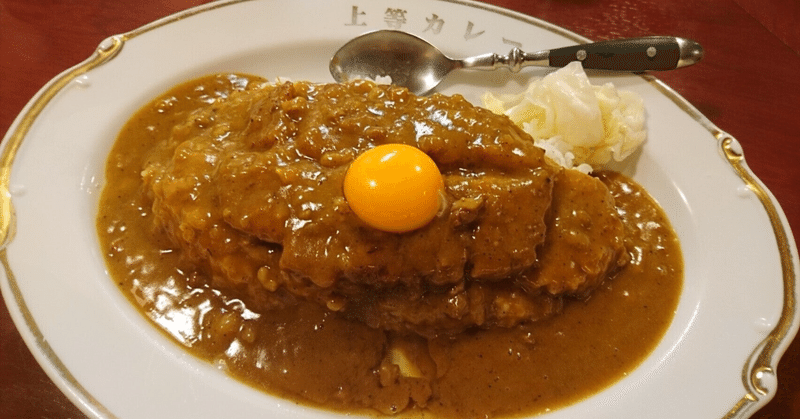2023年6月の記事一覧
芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか⑫ 考えながら読もう
「職業に貴賎なし」といつぐらいから言われていたかと調べていたら、少なくとも明治時代の小学校の教科書の指導要領に出てくることが解った。当然それ以前は貴賤があったわけで、今でも現実的にはあると思う。スパムメールを送る仕事とか。
禍の根を断ちたいのじゃがとはどういう意味か?
ここで若殿様は原因を取り除きたいと言っている。つまり平太夫はただ縛られるだけではないのだ。蝋燭を垂らし……はしないだろうが、
芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか⑪ もっとどんどん読もう
おや、珍しい
芥川のこの「から」の言いさしは珍しいのではなかろうか。会話文までは全部記憶していないが、地の文では「けど」の言いさしはなかったように思うし、そもそも言いさしそのものがそんなに好きではない筈。何故なら話すように書くのではなく、書くように話したいというところで、いわゆる言文一致をほぼ「現代文の書き言葉」と言うところまで持って行った一人が芥川だと思うから。芥川は擬古文を練るように現代文
芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか⑩ 切支丹ものか敵討ちものか
そういえば、九章から十二章までの間、若殿様は登場しない。何か用事があったのか?
やはり切支丹ものなのか
やはり『邪宗門』は切支丹ものであったかと、「頭を濡らすと云う、灌頂めいた式」で臭わされる。女菩薩、天竺、震旦と目くらましをしながらやはり十字の護符とこの洗礼の儀式は基督教を仄めかすものであろう。
そう気が付いてみて、キリスト教の沈黙を貫く神のイメージが大きく突き崩されていることに改め
芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか⑨ あっちと繋がっていたとは
買わない客もいる
どんなに優秀なデモンストレーションが行われようと絶対買わない冷やかしの客と云うものはいる。そもそもこの名もなき語り手は、『地獄変』の時からずっと近代的自我さえ持たないただの傍観者だった。ただ観察して語ることに徹して、その場にいながら自らは当事者であることを避けるかのように言葉を発しない。
自分の考えは述べるものの、自分の姿かたちは語らない。何を食うているのか、そもそも財布
芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか⑦ 漢字とひらがなを読もう
何故かも何もないものだ
いやいや、これまでのいきさつをちゃんと読んでいたら「なぜか堀川の御屋形のものを仇のように憎みまして」はないものだ。堀川の大殿様が中御門の少納言を毒殺したのであれば、『邪宗門』が敵討ちものとして『或敵討の話』、『伝吉の敵打ち』、『猿蟹合戦』のグループに分類されてもおかしくないのだ。
しかしタイトルが『邪宗門』なので切支丹ものみたいでややこしい。なんなら『地獄変』の続編
芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか⑥ 坐って読もう
じゃ、そこからでよかったんじゃないの?
この「天が下は広しと云え」→「皆、恋がさせた業じゃ」というつながりは解らないところ。「天が下は広しと云え」「わし一人じゃ」で収まるところをあえてちらかしたものか。それとも単に捻じれたものか。「恋がさせた業ではないものがあろうか」とつらなるべきというのは現代的感覚で、この作品の舞台となる時代ではこの連なりが正しいのか?
今三島由紀夫の対談を読んでいて思
芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか⑤ 早起きして読もう
そうか、サロンにするのか
なるほど、「もの静な御威光」で「繊細で、またどこまでも優雅な趣」「眉の迫った、眼の涼しい、心もち口もとに癖のある、女のような御顔立ち」とくれば、まさにホストには適任というわけか。
飲んで、飲んで、飲んで、飲んで、飲んで、飲んで、飲んで、飲んで、ハイ、ハイ、ハイ、ハイ……。という喧しいホストではないから客がやってくる。自分から探しに行かなくとも自然と事件の方がやって
芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか④ もう少しチャッチャと読もう
また先に書いちゃって
いやいや。また先に書いちゃって。「大殿様の御隠れになる時まで」「睨み合いがずっと続いて居りました」ということは大殿様と若殿様の間では表面上はいさかいが起きなかったということになる。これはこの時点で話の展開が決まっていなければ物語に制約を加えることになり、あまりよろしくないことだ。
作家には三島由紀夫のように最後の一行まで決めてから書くタイプと村上春樹さんのように適当に
「ふーん」の近代文学③ 悪いことばかりじゃない
あれもこれもなくなった
おそらく芥川龍之介は夏目漱石の「則天去私」を継承しなかった。というよりも遺作『明暗』からして、何が「則天去私」なのか判然としない。小手先で誤魔化したようなこじつけはいくつか見たことはあるが、『明暗』のどこが「則天去私」なのか理路整然と説明した文章を私はこれまで一度も目にしていない。
しかしそう気が付いてみると「写生文」にしても「非人情小説」にしてもいつの間にかどこか
芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか③ 篳篥は吹いていたのか?
細かいところを突いてきたな
これは第三章の冒頭である。第一章で主人公を殺し、第二章で人物紹介を始めたと思ったら、第三章では「笙」に意味があることを改めて持ち出す。序破急も起承転結も関係ない。
私は文学の肝は「サリンジャーの焼きそば」なのではないかと考えている。
あるいは「黒板の前に立っているときの格好」でもいい。こうした微妙なところの微妙さを捨てて、豪快なストーリーだけを追った物語には
芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか② 縦に読もう
え、死んじゃうの?
え? まだ一章なのに「無残な御最期」って死んだ? 殺すの早すぎない? これで話が持つの?
そう思うのは読者ばかりではなかろう。どうも私には芥川が『偸盗』に続いて何か大きなものにぶつかろうとして、それが単に長さ、原稿の量などではなく、「型破り」の方法に向かっているように思えて仕方ない。
この『邪宗門』は古典的な「はじまり、真ん中、終わり」という軸を持った物語ではない。
「ふーん」の近代文学②兼芥川龍之介の『偸盗』をどう読むか⑤ 刃傷沙汰はもう古い
新感覚派という、横光利一らを指すキャッチフレーズが滑稽なのは、優れた作家と云うものは概ね卓越した独自の感覚、ひょっとすると冗談だとしか捉えられない奇妙な感覚を抜かりなく見定める能力を持っているからだ。例えば三島由紀夫の『盗賊』には、「服の下は裸」という感覚が描かれる。当たり前のことながら、これを掲示板に書き込むと「天才」と呼ばれる。「服の下は裸」、この感覚を冗談でも何でもなく捉えられることこそが
もっとみる