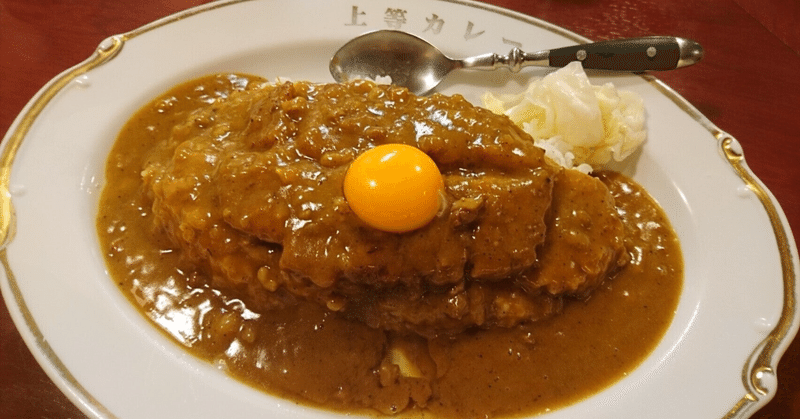
芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか⑥ 坐って読もう
じゃ、そこからでよかったんじゃないの?
その御話のそもそもは、確か大殿様が御隠れになってから、五六年たった頃でございますが、丁度その時分若殿様は、前に申しあげました中御門の少納言様の御一人娘で、評判の美しい御姫様へ、茂々御文を書いていらっしゃいました。ただ今でもあの頃の御熱心だった御噂が、私どもの口から洩れますと、若殿様はいつも晴々と御笑いになって、
「爺よ。天が下は広しと云え、あの頃の予が夢中になって、拙い歌や詩を作ったのは皆、恋がさせた業じゃ。思えば狐の塚を踏んで、物に狂うたのも同然じゃな。」と、まるで御自分を嘲るように、洒落としてこう仰有います。が、全く当時の若殿様は、それほど御平生に似もやらず、恋慕三昧に耽って御出でになりました。
この「天が下は広しと云え」→「皆、恋がさせた業じゃ」というつながりは解らないところ。「天が下は広しと云え」「わし一人じゃ」で収まるところをあえてちらかしたものか。それとも単に捻じれたものか。「恋がさせた業ではないものがあろうか」とつらなるべきというのは現代的感覚で、この作品の舞台となる時代ではこの連なりが正しいのか?
今三島由紀夫の対談を読んでいて思うのは、三島がそれぞれの作家の文体と云うものをかなり細かく分析しているということ。それにしても鴎外に関しては何でも書ける唯一の文体の使い手と褒めながら、案外芥川に対する言及がない。
坪内逍遥が谷崎潤一郎の『文章読本』を読んで「レトリックが書いていないじゃないか」といったという話があって、はっと気がついたのは、三島と谷崎には幼いころからの観劇という共通の素養があって、その点では泉鏡花に連なるようなところがあるのだけれど、そういえば谷崎の漢籍への造形の深さのようなものは、漢文をそのまま振り回すようなところは三島には見えないなと。むしろ「古典がしっかり身に着いた最後の世代」という三島の自負における「古典」とは「大鏡」とか「古今集」であって、その点でも谷崎、漱石とは違い、むしろ芥川に近いのではないかと。
三島も芥川もレトリックに関して言うと、結び目を緩く解くようなことをやる。三島自身は四六駢儷に拘り対をつくると言いながら、割とかっちり結び目を保つ漱石や谷崎と違い、芥川や三島は結び目を緩く解く。
とりあえず芥川で言うならば、
するとそこに洋食屋が一軒、片側を照らした月明りに白い暖簾を垂らしていた。
客は外套の毛皮の襟に肥った頬を埋めながら、見ると云うよりは、睨むように、狭い店の中へ眼をやった。
その姿は見れば見るほど、敵役の寸法に嵌っていた。
保吉は月明りを履みながら、いつかそんな事を考えていた。
こんな言語感覚だ。「保吉は月明りに照らされながら」ではなく「保吉は月明りを履みながら」だから心地よい。
神西清は三島由紀夫の『花ざかりの森』を読んで芥川龍之介の再来だと書いた。
有為子は留守だった。
三島由紀夫の『金閣寺』はこの一言の為にあると言っても良かろう。この言語感覚が芥川と三島由紀夫を結ぶラインだと私は思っているのだが、味方は神西清くらいしか見つからない。
さて本題に戻る。「天下広しと雖も~なし」「~くらいなもの」の懸かりを解いた用例は……あるな。
天下廣しといへども子を思ふ親の心は皆一つである
明治天皇御聖行
天恩奉謝団本部 纂天恩奉謝団本部 1935
あるにはあるがどうも緩い感じがする。
そもそもこの恋は本物か。「物に狂うたのも同然じゃな」と客観的に言えるくらいだから、物に狂うてはいない。そもそも艶書合せといった遊びは、懸想である。それは恋を戯れ事として捉えていればこそできる遊びだ。つまり本気ではない。
ではさて若殿様はどれくらい本気なのか?
というより、そもそも話の組み立てとしてはこの章からスタートでも良かったのではないかという気がしなくもない。まだその意匠は解らない。
それ、うるさいんじゃないの?
しかし、これは、あながち、若殿様御一人に限った事ではございません。あの頃の年若な殿上人で、中御門の御姫様に想いを懸けないものと云ったら、恐らく御一方もございますまい。あの方が阿父様の代から、ずっと御住みになっていらっしゃる、二条西洞院の御屋形のまわりには、そう云う色好みの方々が、あるいは車を御寄せになったり、あるいは御自身御拾いで御出でになったり、絶えず御通い遊ばしたものでございます。中には一夜の中に二人まで、あの御屋形の梨の花の下で、月に笛を吹いている立烏帽子があったと云う噂も、聞き及んだ事がございました。
いや、現に一時は秀才の名が高かった菅原雅平とか仰有る方も、この御姫様に恋をなすって、しかもその恋がかなわなかった御恨みから、俄に世を御捨てになって、ただ今では筑紫の果に流浪して御出でになるとやら、あるいはまた東海の波を踏んで唐土に御渡りになったとやら、皆目御行方が知れないと申すことでございます。この方などは若殿様とも、詩文の御交りの深かった御一人で、御消息などをなさる時は、若殿様を楽天に、御自分を東坡に比していらしったそうでございますが、そう云う風流第一の才子が、如何に中御門の御姫様は御美しいのに致しましても、一旦の御歎きから御生涯を辺土に御送りなさいますのは、御不覚と申し上げるよりほかはございますまい。
この「菅原雅平」は架空の人物のようだ。『邪宗門』の種本『古今著聞集』には「公事」「文学」「和歌」などの章があり「好色」という章もあったので、何か似たような話でも出てくるものかと調べてみたが、とくにこれというものは見つからない。どうやらここは「中御門の御姫様」のもてエピソードというだけの話のようだ。
それにしても三島由紀夫の『盗賊』でもあるまいに「その恋がかなわなかった御恨みから」「皆目御行方が知れない」とはなんと蒼くて脆くて弱いことか。
三島由紀夫は本人としては近代文学を全否定して王朝物語に連なる意識と言うものを隠さないが、それはこのような蒼くて脆くて弱いピュアな精神に連なるということでもあるのだろうか。
恋心を伝えるために月に笛を吹くとはいと優にありけるにや。
でた、人の悪い芥川龍之介
が、また飜って考えますと、これも御無理がないと思われるくらい、中御門の御姫様と仰有る方は、御美しかったのでございます。私が一両度御見かけ申しました限でも、柳桜をまぜて召して、錦に玉を貫いた燦やかな裳の腰を、大殿油の明い光に、御輝かせになりながら、御瞼も重そうにうち傾いていらしった、あのあでやかな御姿は一生忘れようもございますまい。しかもこの御姫様は御気象も並々ならず御闊達でいらっしゃいましたから、なまじいな殿上人などは、思召しにかなう所か、すぐに本性を御見透しになって、とんと御寵愛の猫も同様、さんざん御弄りになった上、二度と再び御膝元へもよせつけないようになすってしまいました。
ああ、よかった。
このままだと褒めてばっかりでつまらないところにいきなり性格の悪さを持ってきた。
芥川が女を善く書く訳はないのだ。
性格の悪い美人に惚れたと。
それじゃあ上手く行くはずがない。で、それからどうした?
そこから持ってくるか
それがほど経てから、御門の扉が、やっと開いたと思いますと、平太夫と申します私くらいの老侍が、これも同じような藤の枝に御文を結んだのを渡したなり、無言でまた、その扉をぴたりと閉めてしまいました。
そこで泣く泣く御立ち帰りになって、その御文を開けて御覧になると、一首の古歌がちらし書きにしてあるだけで、一言もほかには御便りがございません。
思へども思はずとのみ云ふなればいなや思はじ思ふかひなし
これは云うまでもなく御姫様が、悪戯好きの若殿原から、細々と御消息で、鴉の左大弁様の心なしを御承知になっていたのでございます。
※「若殿原」……若い武士たち。
この「思へども思はずとのみ云ふなればいなや思はじ思ふかひなし」は『古今和歌集』の詠み人知らずの歌だ。こうしてふられた奴もいると。
それからどうした?
そっちの姫にしておけば良かったのに
こう御話し致しますと、中には世の常の姫君たちに引き比べて、この御姫様の御行状を、嘘のように思召す方もいらっしゃいましょうが、現在私が御奉公致している若殿様の事を申し上げながら、何もそのような空事をさし加えよう道理はございません。その頃洛中で評判だったのは、この御姫様ともう御一方、これは虫が大御好きで、長虫までも御飼いになったと云う、不思議な御姫様がございました。この後の御姫様の事は、全くの余談でございますから、ここには何も申し上げますまい。が、中御門の御姫様は、何しろ御両親とも御隠れになって、御屋形にはただ、先刻御耳に入れました平太夫を頭にして、御召使の男女が居りますばかり、それに御先代から御有福で、何御不自由もございませんでしたから、自然御美しいのと、御闊達なのとに御任せなすって、随分世を世とも思わない、御放胆な真似もなすったのでございます。
そこで噂を立て易い世間には、この御姫様御自身が、実は少納言様の北の方と大殿様との間に御生まれなすったので、父君の御隠れなすったのも、恋の遺恨で大殿様が毒害遊ばしたのだなどと申す輩も出て来るのでございましょう。しかし少納言様の急に御歿りになった御話は、前に一応申上げました通り、さらにそのような次第ではございませんから、その噂は申すまでもなく、皆跡方のない嘘でございます。さもなければ若殿様も、決してあれほどまでは御姫様へ、心を御寄せにはなりますまい。
なるほど、堀川の若殿様と中御門の御姫様は腹違いの兄妹との噂があると。これまたスパイシーな話だが、噂の根拠というのが「御闊達な」性格だけとは、よほど堀川の大殿様の悪名は世間に轟いていたということになろうか。
みんな芥川の『地獄変』でも読んでいたのだろうか。

この「その頃洛中で評判だったのは、この御姫様ともう御一方、これは虫が大御好きで、長虫までも御飼いになったと云う、不思議な御姫様がございました。」の姫君は『堤中納言物語』の「蟲愛ずる姫君」あたりを意識してのことだろうか。
こっちの方がにょろにょろ君向きではないか。
[余談]
『全小説』からも省かれた、大江健三郎の幻の小説『夜よゆるやかに歩め』ですが、国立国会図書館デジタルコレクションで読めるんですね。
— 緑雨 (@ryoku28) June 22, 2023
検索結果 - 国立国会図書館デジタルコレクション https://t.co/dxWLbtNBjv
へー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
