
芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか⑪ もっとどんどん読もう
おや、珍しい
が、若殿様は相不変らず落ち着き払って、御胸の先の白刃も見えないように、
「してその方たちは、皆少納言殿の御内のものか。」と、抛り出すように御尋ねなさいました。すると盗人たちは皆どうしたのか、一しきり答にためらったようでございましたが、その気色を見てとった平太夫は、透かさず声を励まして、
「そうじゃ。それがまた何と致した。」
「いや、何とも致さぬが、もしこの中に少納言殿の御内でないものがいたと思え。そのものこそは天が下の阿呆ものじゃ。」
若殿様はこう仰有って、美しい歯を御見せになりながら、肩を揺って御笑いになりました。これには命知らずの盗人たちも、しばらくは胆を奪われたのでございましょう。御胸に迫っていた太刀先さえ、この時はもう自然と、車の外の月明りへ引かれていたと申しますから。
芥川のこの「から」の言いさしは珍しいのではなかろうか。会話文までは全部記憶していないが、地の文では「けど」の言いさしはなかったように思うし、そもそも言いさしそのものがそんなに好きではない筈。何故なら話すように書くのではなく、書くように話したいというところで、いわゆる言文一致をほぼ「現代文の書き言葉」と言うところまで持って行った一人が芥川だと思うから。芥川は擬古文を練るように現代文も練っていた。読むのは物凄く速いのに書くのが遅いのは、自然と出てくる文語文を口語文に翻訳していたからなんじゃないかと思う。
そして理屈も練ってきた。
やはり中御門の少納言殿の家来の頭としての平太夫と「頭立ったの」のアンバランスな関係性を突いてきた。お前ら上手く使われているぞと言わんばかりに、仲間割れを誘う考えのようだ。少納言殿の御内でないものにはそもそも敵討ちの大義はない。あらかじめ許可を取っていない場合は敵討ちとは言いながら単なる人殺しになりかねない。
振り回してくるなあ
「なぜと申せ。」と、若殿様は言葉を御継ぎになって、「予を殺害(せつがい)した暁には、その方どもはことごとく検非違使の目にかかり次第、極刑(ごっけい)に行わるべき奴ばらじゃ。元よりそれも少納言殿の御内のものなら、己が忠義に捨つる命じゃによって、定めて本望に相違はあるまい。が、さもないものがこの中にあって、わずかばかりの金銀が欲しさに、予が身を白刃に向けるとすれば、そやつは二つとない大事な命を、その褒美と換えようず阿呆ものじゃ。何とそう云う道理ではあるまいか。」
ばら【輩・原・儕】 〔接尾〕 人を示す名詞に添えて、複数、またはその人の階層・境涯の範囲を表す。敬意に欠けた表現に使うことが多い。「殿―」「法師―」「奴―」
ようず
〔助動〕
(例えば助動詞ウズのサ変に付いた形、セウズがショウズ、さらにシヨウズのように変化してできた語形。一段型活用・サ変型活用の語の未然形に付く)
①意志を表す。…したい。…しよう。大淵代抄「一挙に打ち殺してもくれやふず者を」
②推量を表す。…するだろう。天草本平家物語「其儀ならば、北面のともがら箭をも一つ射ようずる」
ここは「殺害(せつがい)」「極刑(ごっけい)」「奴ばら」「ようず」「阿呆もの」と古めかしい言い回しを現代語に挟んでぶん回しているところ。これが擬古文になると引っかかるが、ベースが現代文なのでスラスラ読めてしまう。しかし例えば「阿呆もの」で青空文庫を検索すると芥川だけが出てきて、「阿呆者」でも牧野信一ほか二例しか見当たらない。
しかし近松が「痴気もの、阿呆もの」で、

たとえば『栄花物語』とか『宇治拾遺物語』『大鏡』『うつほ物語』『源氏物語』なんかにも「馬鹿」も「阿呆」もなくて、本当に古い言い方そのものとしては「痴れ者」ではあるんだけど、

たまたま「馬鹿者」も「痴れ者」も現代まで残ってしまったことから、言い回しとしては「痴れ者」よりも「阿呆もの」の方がやや古さびて感じられるという言語感覚で「阿呆もの」という言葉がチョイスされているのだろう。


「殺害(せつがい)」の読みはまだ辛うじて辞書に残されているが、「極刑(ごっけい)」の読みは主要な辞書類からは消えている。つまり消えた言葉をわざわざ持ち出してきて使おうという莫大な知識量を駆使した遊びのようなことが行われている。
勿論当時は古典文学語句検索データベースなんてものは存在しないので、己の感覚だけでこういうことをやっていると考えると凄いことだ。
そして中身の話に戻ると『猿蟹合戦』ほどイロニカルに走ることなく、仇の当人でもないものを殺して無事でいられると思うなよと、至極真っ当なロジックが展開されている。
まさにそう。敵討ちだか何だか知らないが、やはり「今更」なのである。
これは血だな
これを聞いた盗人たちは、今更のように顔を見合せたけはいでございましたが、平太夫だけは独り、気違いのように吼り立って、
「ええ、何が阿呆ものじゃ。その阿呆ものの太刀にかかって、最期を遂げる殿の方が、百層倍も阿呆ものじゃとは覚されぬか。」
「何、その方どもが阿呆ものだとな。ではこの中うちに少納言殿の御内でないものもいるのであろう。これは一段と面白うなって参った。さらばその御内でないものどもに、ちと申し聞かす事がある。その方どもが予を殺害しようとするのは、全く金銀が欲しさにする仕事であろうな。さて金銀が欲しいとあれば、予はその方どもに何なりと望み次第の褒美を取らすであろう。が、その代り予の方にもまた頼みがある。何と、同じ金銀のためにする事なら、褒美の多い予の方に味方して、利得を計ったがよいではないか。」
若殿様は鷹揚に御微笑なさりながら、指貫きの膝を扇で御叩きになって、こう車の外の盗人どもと御談じになりました。
さすがは鬼神の倅、太刀の切先を向けられて堂々と談判とは並大抵の肝ではない。まず相手の組織のちぐはぐなところに眼をつけ、この敵討ちの遅さを指摘、盗人どもと平太夫の力関係を見抜き、ビジネスライクに交渉している。とても風月の人ではない。
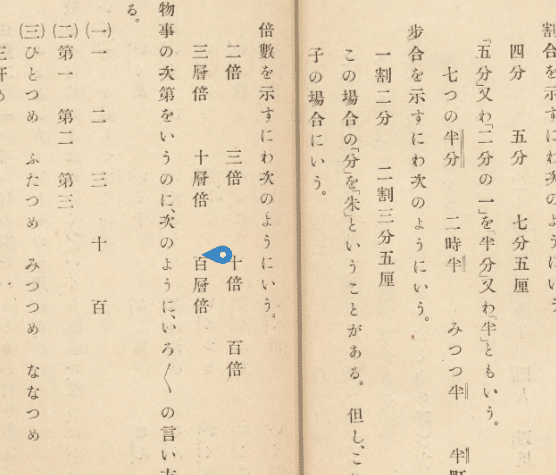
これはどうやら若殿様の血脈が間違いなく堀川の大殿様に繋がっていることを意識させるところ。つまり中御門の御姫様がやはりこれくらい肝が据わっていたとしたら、二人が兄妹という可能性もなくはないと……いかんいかん。そう早まってはいけない。
この続きはまだ誰も知らない。何故ならまだ私がこの続きを読んでいないからだ。
[余談]
ジャパンサーチ
11件か。
優秀。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
