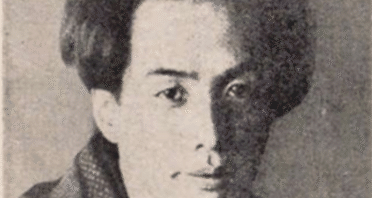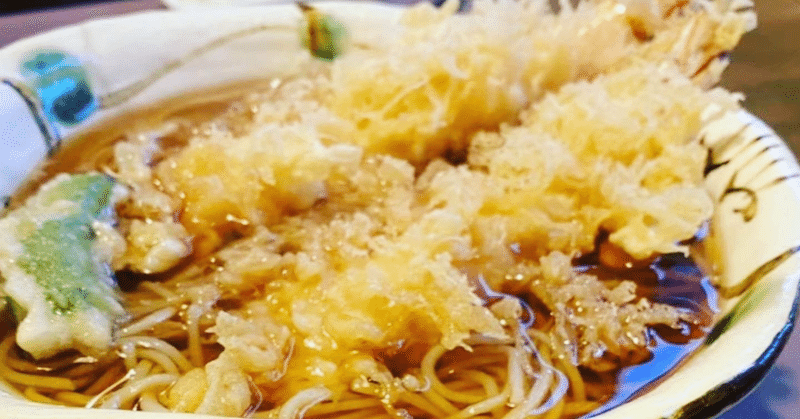2022年11月の記事一覧
芥川龍之介の『一夕話』をどう読むか② この日だけの話で終わる筈もない
大正十一年、まだ関東大震災が起こる前、そしてまだ自殺の意思がなかった当時、既に芥川が「我々は皆同じように、実生活の木馬に乗せられている」と書き、その実生活をメリイ・ゴオ・ラウンドに例えたことが私には興味深い。メリイ・ゴオ・ラウンドはデッドヒートもしないし、アキレスと亀にもならない。何の進歩もない生活だからこそメリイ・ゴオ・ラウンドなのだろう。
この時奥さんのお腹は大きかったはずだ。十一月に長
芥川龍之介の『温泉だより』が解らない① 国粋的省略法とは何か?
これのことか?
はたまたこれのことなのか?
あるいはこの(畧)という結びの事なのか?
私には『温泉だより』に出て來る「国粋的省略法」が解らない。
はて、国木田独歩に「の字さん」というような名前の省略があり、それが国粋的省略法と呼ばれていたかどうか、……そう考えてみて、やはり私には全く記憶がなかった。
名前を略すだけならこのように某を使えば事足りるも、これは誰しもが用いる方法で
芥川龍之介の『一夕話』をどう読むか③ 崩れかける寸前
レボーター「敗因はどこにあるんでしょう?」
解説者「何と言っても失点したことですね」
そんな小泉進次郎botのような話に聞こえるかもしれないが、『一夕話』はまず、
医者と弁護士が メリイ・ゴオ・ラウンドに乗る話
……だと捉えて良いだろう。
レポーター「誤読の原因はどこにあるんでしょう?」
解説者「何と言っても読み誤ることですね」
そんなことを繰り返し指摘してきたが、実際にそのまま
津田さん あるいは葱を買わなくてもがっかりすること
これは『葱』をどう読むか、の番外編のような話。
お君さんは葱によって田中君を退ける。これを田中君を失望させたとか、呆れさせたとか、がっかりさせたというような様々な捉え方が出来ると思う。まあ、「冷めた」「引いた」というところだろうか。
これは単に「家庭的なところを見せたから引かれた」ということではないと思う。
※ここに実話挿入。
キャンプの時のことだった。飯盒炊爨の為に米を研いでい
芥川龍之介の『一夕話』をどう読むか① ただ一つの現実があるのみだ
大正八年十二月に書かれた『葱』と大正十一年六月に書かれた『一夕話』を比べて読むとどうだろう。例えば「通俗小説的な恋愛と生活の衝突」というものが前者のモチーフであれば、後者は「当世の通人に対する反動で俗に堕ちる女」であろうか。
当然そこには芥川らしい逆説が持ち込まれる。
ここで現れる通人若槻は『葱』で言えば自称芸術家の田中君であろうか。お君さんはデートの最中にネギを買うことで実生活に留まるが
芥川龍之介の『葱』をどう読むか⑤ 無いことが小説になる
作品の解釈としては、芥川が話者の身体性を作中に持ち込み、書かれえない作品という仕掛けを拵えたこと、現に書かれているものの書き手であることの不可能性を演出したこと、そして物語の背後に事実があるかないかということがどうでもいいことを証明するために、物語の外側でお君さんをいそいそと外出させるという、小説を離れた事実を仄めかしたこと、辺りで話は尽きている。
通俗小説というあだ名の主人公が作者の手を離れ
芥川龍之介の『永久に不愉快な二重生活』をどう読むか
こう言っては何だがレタスは人の生存のために必ず必要な野菜ではない。いわば趣味の食べ物だ。レタスがないからと言って、人はたいして困らない。しかしレタス農家の人はレタスの価格が下がると「農家を馬鹿にしている」と感じる。
私はそのことを批判している訳ではない。
この本は250円で、一冊売れると175円が私の収入となる。これがなかなか売れない。この本を読まなくても誰も困らないからだ。しかし私はその
芥川龍之介の『葱』をどう読むか④ 葱二束は多い
リンク先にある阿部公彦氏が「読解力がないとはどういうことか」について考察した資料を読んだ。内容としてはまさにそのとおりではあろうが、少し引っかかる。例えば他人はそもそも自分と異なる読み方をするもので、自分と異なる読み方をしていることに苛立つ、という状況があるのだと考えた場合、そもそも他人の読み方を許容できない側が読解力がないことにされてしまいかねないのだが、このロジックでは多数決になってしまわな
もっとみる芥川龍之介の『葱』をどう読むか③ 大きく話をふっている
作中の架空の人物の現実逃避のための通俗芸術。俗に通じるとは大衆として時代から沸き上がったものたちとのコミットメントであったのだろう。それにしてもこのすこぶる理智的な「おれ」は、いつもにもまして作中に顔を出し、直截なコメントを吐き過ぎではなかろうか。そしてそのようなやり方で、さして理智的とも思えない「おれ」という戯画のようなものが次第に出来上がっていく。芥川作品だけを読んでいると、ちょっと何が書か
もっとみる芥川龍之介の『葱』をどう読むか② 虚構と現実の区別はできない
嬌嗔とは美人のなまめかしい怒りである。お君さんの親切はスマートだ。しかしこういう縄張り争いのようなものは男女を問わず、どこの世界にでもあることなのだろう。しかしこうしたいかにもさりげない親切というプロットを拾い出し、展開を作り出すところ、その親切のさりげなさが尋常ではない。落ちたものを拾うとか、そういうことでは駄目なのだ。ただ「足を止めた」というところが見事だ。
出た。
省略法。
お松さ
芥川龍之介の『葱』をどう読むか① 「何しろ」「とにかく」「とか何とか」
作家が小説を書くこと、アマチュアが処女作を書くのではなく、プロの作家が依頼原稿を現に書くこと、その枠組みを明らかにして書くこと、書いたうえで、それがいかにもサイズ的には小品であることを承知しながら、話に落ちをつけ、そしてさしたる満足感もなく筆を置いたことまで書き、なんなら批評家のことまで意識していることを明示するのは……太宰治に伝承されたかと思えるほどの太宰節の原型であり、何某かの意匠と思える。
もっとみる芥川龍之介の『闇中問答』をどう読むか①
その年齢を考えるとあまりにも青くてもろい『闇中問答』をどう読むか、どう受け止めればいいのか、私はずっと迷っていた。今回遺作の『歯車』を整理し、
保吉ものを整理したことにより、
なんとかこの『闇中問答』ともちゃんと向き合えるんじゃないかと読み直してみた。うん、青くてもろい。
本が一番売れるのは、作家が死んだ時だ。誰も生きている作家に儲けさせようとはしない。兎に角何とか一圓でも金が渡らな