
伝統は革新を経て最強となる
伝統と革新というセオリー
伝統と革新。
使い古された言葉である。
耳にタコが出来る話かと思う。
しかしこのパンデミックで改めて伝統は危機に瀕したのでは無いだろうか。
伝統は、経済が正常に回っている時は目を向けられるものだが、不要不急が叫ばれる昨今は苦しい状況だと推察する。
ただ、伝統を掲げる企業やブランドの中には、日頃から革新に向かって準備してきたので、このパンデミックの状況下であっても絶好調であるという企業も少なくない。
中川政七商店など奈良発祥の老舗工芸品屋さんはブランディングを取り入れた革新でもう絶好調であると思う。私は九州の波佐見焼(はさみやき)のHASAMI PORCELAINを妻が使っていることで知った。
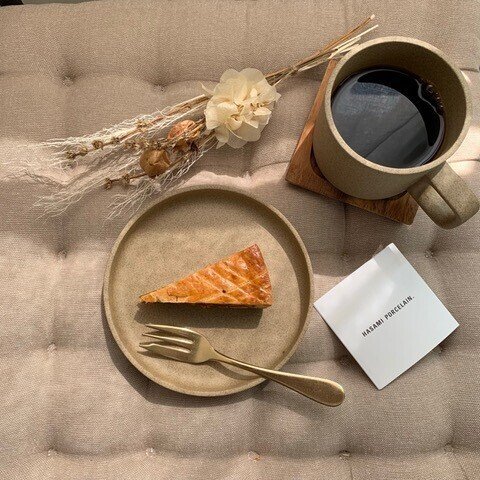

「このコーヒーカップでコーヒーを飲むと美味しいね」の一言に妻が「それ、波佐見焼だよ。」と。
波佐見焼?波佐見焼は九州に住む人間からしたら少し田舎の陶磁器で有名なのは有田や伊万里だったし、大変失礼ながらこんなに洗練されたデザインのイメージはなかったのだ。
驚愕するほど洗練されていて美しいデザインだった。
これがデザインの力。
まさに革新の力だと。

伝統芸能も最強だ
それは伝統工芸であるからの話。
私の関わる世界、伝統芸能はどうであろうか。
歌舞伎、狂言そして落語、講談。
このジャンルはパンデミックで圧倒的に苦しんだ。
いや、苦しんでいる。
私は宝塚のOGのショーをホテルと組んで行う予定を2020年の4月にしていたがパンデミックで中止となり人が集うことは”悪”とされまさに不要不急とされた。
ところがこの伝統芸能や宝塚などの興行は歴史がある。
それはもう文化なのだ。
その文化の力で乗り越えていくのではないかと信じている。

ラスベガスのシルクドソレイユが解散したようにエンタテインメントは立ちいかなくなったケースを数多く聞いた。
廃業もたくさんあった。
世界でダンスで活躍するダンサーから聞いた。
「こういう時にエンタテインメント(=娯楽)は弱いが文化は強いね...」と。
その言葉を聞いて感じたことがある。
伝統芸能、郷土芸能で芸妓という仕事がある。
所謂、お座敷遊びだ。
京都の舞妓さん、芸妓さんのあれだ。
実は京都だけでなく地方にもそれは存在する。
自治体やそれを応援する人のクラウドファンディングなどで復活している団体もあると聞く。
支援が手厚いのだ。残していかなければならない、保存していかねばならないそれが文化なのだ。

地方の伝統芸能も魅力がたくさん
私は演出の仕事をしている。
その縁で伝統芸能に携わる人との縁も多い。
博多の伝統芸能である博多独楽という素晴らしい芸がある。

博多独楽 (二十代当主宗家 三代目筑紫珠楽 氏)
その博多独楽という伝統芸能もこのコロナで深刻なダメージを受けたそうだ。
やはり博多を中心とする日本から世界までその芸を一目見ようと様々な公演を行っていた彼らも、その技を披露する場を奪われてしまったそうだ。
この危機をきっかけに世の中に広く知ってもらおうとテレビ等マスメディアへの露出という展開へ舵を切ってみたらしいがやはりそこはその奥深い歴史、そして技がある。
たくさんのメディアから声がかかっているそうだ。
私はこの技の現在の伝承者と博多をテーマに映像を作った。
博多の音をテーマとし彼の博多独楽と別の伝統の技、博多金獅子太鼓という和太鼓とジャズピアノのコラボを映像にした。
こちらもご覧いただきたい。
このように私が拠点とする博多にも歴史、そして文化があるのだ。
そして文化はやはり”強い”と感じる。
そして博多にも博多のお座敷遊び、博多芸妓がいる。
博多の華・博多芸妓
芸者といえば東京の浅草、京都の祇園などを思い浮かべる人も多いだろう。
しかし実は、福岡にも「博多芸妓(げいぎ)」と呼ばれる芸者たちの歴史があり、お座敷文化を継承している。
長崎が外国との交流の地であったためそこに大阪や京都から芸妓が出張したことが博多芸妓のルーツであるようだが、一時は2,000名を超える芸妓で賑わったのが博多の花街であったようだ。
しかし時代の波はここにもやってきて今は十数名という人数となっているそうだ。
そんな博多芸妓も私はエンタテインメントの一部としてお付き合いもある。
コンベンションのアフターパーティーで博多の文化としてステージを披露したり、企業の祝いの席で芸を披露してもらうことも多い。
そんなご縁もあり、今回初心に帰り、博多芸妓の紹介どころ、博多券番へ足を運び、その芸を見てきた。
改めて感じたのは郷土・福岡のことを唄にしてあり言葉を覚えたり、その歴史や背景を学べること。
そしてお座敷遊びとは何たるかを知っておくことも一つの大人の嗜みとなることを感じた。
こんなコロナ禍の苦しい時期であるからこそ、博多という場所にこのような伝統や文化があること。
それに触れることが出来るのはシンプルに嬉しい気持ちとなった。要は文化というのは尊いのだ。


伝統はそのままでも根強い。そして伝統は革新を経て最強となる
改めてこのコロナ禍で地域というものを見直す契機となった。
海外や遠方への移動が避けられ、人が集うエンタテインメントは不要不急が騒がれる中、失うものは多い。
だが、私たちが住む地域に様々な宝があるということを改めて感じいることができた。
伝統と革新という言葉は叫ばれて久しい。
しかし、私は伝統はそのままでも強く、とても魅力的であると考える。
ただし、その地盤にあぐらをかいていてはならない。
発信やPRは何より大切であろう。
だから伝統は発信を通してそのままの姿でも強いのだ。
しかし、伝統は革新を経ると、それはもう最強となるだろう。
以前に私が書いたこちらの記事も併せてご覧ください ↓
いいなと思ったら応援しよう!

