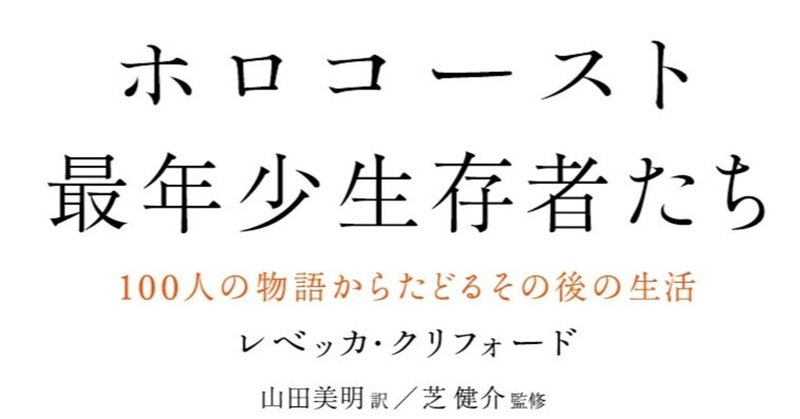
困難な旅路、無視されてきた重要なテーマ|ホロコースト最年少生存者たち|芝健介【日本語版解説公開】
「生き残れて幸運だったね」
「どうせ何も覚えてないだろう?」
「家族と再会できてよかったじゃないか」
それって、ほんとう?
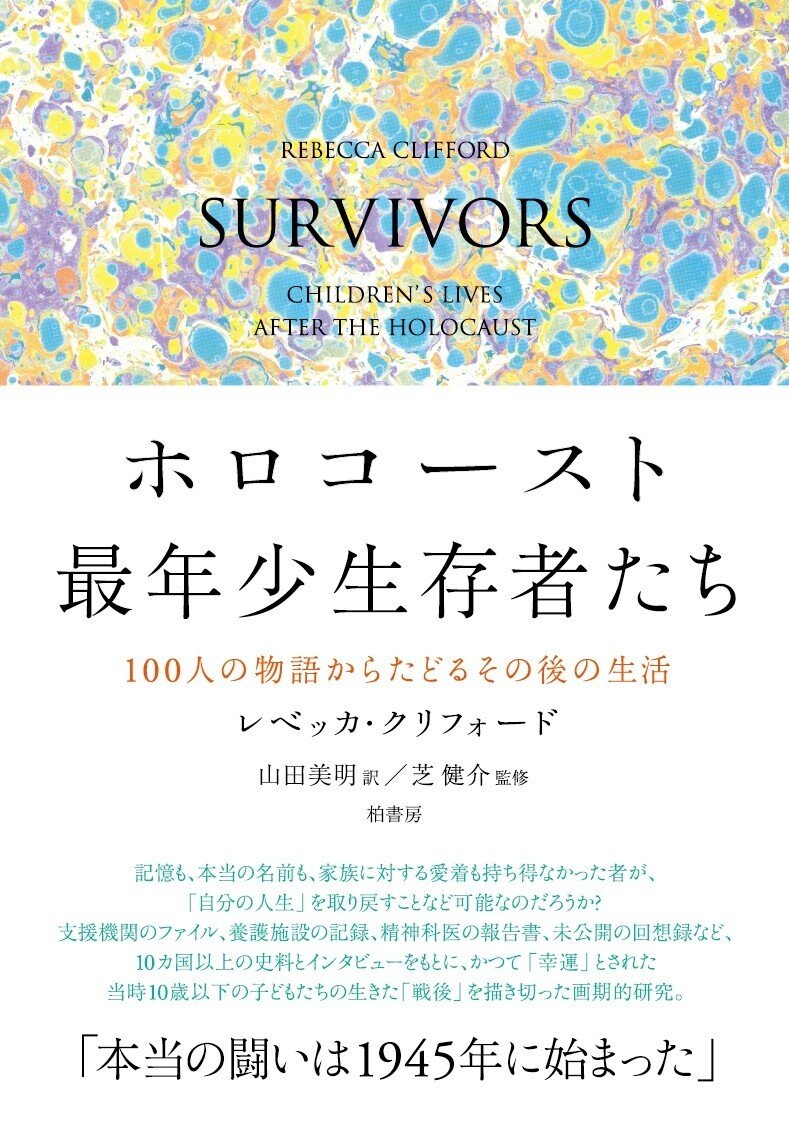
2021年8月27日に、柏書房からレベッカ・クリフォード著『ホロコースト最年少生存者たち――100人の物語からたどるその後の生活』が刊行されました。
記憶も、本当の名前も、家族に対する愛着も持ち得なかった者が、「自分の人生」を取り戻すことなど可能なのか? そんな問いを軸に、支援機関のファイル、養護施設の記録、精神科医の報告書、未公開の回想録など、10カ国以上の史料とインタビューから、かつて「幸運」とされた当時10歳以下の子どもたちが経験した「戦後」を描き切った一冊です。
監修に『ホロコースト』(中公新書)著者・芝健介さん(東京女子大学名誉教授)を、翻訳に山田美明さんを据え、2021年ウルフソン歴史賞候補作品を早くも全訳しました。本稿では特別に、芝健介さんが執筆した「日本語版解説」を無料公開します。ひとりでも多くの方に、彼ら・彼女らの物語が届くことを願います。
▼序章はこちらで公開中▼
日本語版解説
第二次世界大戦がようやく終わりを告げ、ヨーロッパ・ユダヤ人が大戦中にこうむった破局的災厄は、ナチ・ドイツがおかした「人道に対する罪」の追及を通じてその犯罪概念をはじめて国際社会に知らしめたニュルンベルク裁判等で少しずつ明らかになっていった。虐殺された約六百万人のうち、子どもの犠牲者は四分の一を占めていたとも指摘される。一方で「幸運にも」生き延びた子どもの数は、英米を中心に連合国のさまざまな人道支援組織の保護を受けられた子どもの数を基本にして、約一五万人と見積もられているが、子どもの生存者の割合は、生きてホロコーストを潜り抜けられなかった子どものだいたい一〇分の一(いま少し正確には一一%)のスケールとされている(『星をつけた子供たち――ナチ支配下の子供たち』デボラ・ドワーク著、芝健介監修・甲斐明子訳、創元社、一九九九年)。一方この推計値に含まれない生存者もまだかなりいるはずであるが、東西冷戦体制解体後もほとんど把握されていないのが偽らざる現状である。
本書は、ホロコーストを生き延びた子どもたちの「戦後」の生活、心情や経験を基本的なテーマにしている。この解説小稿では、彼らがナチ・ヨーロッパ支配下、とくに戦時中どのように生きていたのか、何を犠牲にして生き残れたのかという歴史的前提条件について、ユダヤ人の子どもたちの生活をとり巻いていた環境や生活状況をまず確認しておきたい。子どもたちが多くの困難に直面しながらホロコーストを潜り抜けた経験のなかでも、戦時体験に重要な影響を及ぼした局面として、①中立国や連合国への逃亡、②ゲットーや通過収容所での生活、③強制収容所での生活があったが、それとともに④この上なく好ましいものから嫌になるほどひどいものまでかなりばらつきのあった潜伏生活があげられる。身体的・精神的・性的虐待も受けやすく弱々しい子どもたちが、以上のような戦時生活の諸局面で最も深刻に感じていたのは、恐怖と孤独であった。
解放された強制収容所で(場合によってはそこからの強制撤退としての「死の行進」の途次)、あるいはキリスト教家族の一員として偽装され、あるいはまた修道院の奥深くに預けられ、中には村から村へ転戦するパルチザンに混じって森をさまよい歩く姿で、さらにはまた民間の、なかんずく農家にかくまわれた形でしばしば発見された子どもたちの多くが、孤児になっていた。またこれは生き残る手だてにもなった方便だったが、実際より老けた齢を騙り、身体は子どもの姿をしているものの既に立派な大人であると自称するケースも頻繁に見られた。
幼い生存者たちも、圧倒的にホロコーストの犠牲となった子どもたちに劣らず虐待され、屈辱を受け、強制的に働かされ、飢えに悩まされ、甘えることも許されず酷寒下放置され、また医学的生体実験の恰好の対象にさえされた。最も近しい家族を失い、幼年期享受しうる当然の権利を奪われ、幼稚園や初等学校にも通えず、身元を偽り赤の他人の恩顧にたよって生活していたのである。
八歳でキリスト教徒の家庭の子として偽装された少女ヤナ・レヴィの場合、「戦慄を覚えるほどのたまらない恐怖」だったとのちに述懐したものには、「自分の本名が何だったのか、もう憶えていませんでした。〔中略〕忘れることがどうしても必要だったので、本当に忘れ切ってしまったのです。〔両親が〕今の私の名前を知らなかったら、私を見つけだせないことはわかっていました。〔中略〕その人〔ほかの人間〕になり切ってしまった。だから〔中略〕その下に潜んでいたはずの私のこともだれひとりわからない」という重大な不安も含まれていた(ドワーク、前掲書)。
戦時中オランダの農村に身を隠したとき、やはり八歳だったモウリッツ・コーヘンの場合は、別の場所に潜伏した一〇歳と一二歳の兄がいたが、どちらも生き残れず彼だけが生きて戦後を迎えた。四〇年後、子どものホロコースト史を最も精力的に跡づけた歴史家デボラ・ドワークに以下のように語っている。「戦時中ぼくは子供だったし、毎日生きることに精一杯だった。戦争がもたらしたものに衝撃を受けたのは戦争が終わってからです。ぼくの戦争は、〔ナチ・ドイツとオランダとの戦いが始まった〕一九四〇年でなく、一九四五年に始まりました。父と母が、兄たちが、もう戻らないと知った時、その時ぼくの戦争が始まったのです。みんないないという考えに慣れるのには何年もかかりました。自分の境遇、そう、自分が天涯孤独だということを受け入れ、自分を立て直すには長い時間が必要でした。〔中略〕それだけ、生き残った者にかかる重圧は大きかった。ぼくは子供ながら、そのすべてをひとりで負っていかなくてはならなかったのです」(同上)
みずからのアイデンティティを消し去ってまで環境に順応・適応してようやく生きることを許されるような過酷な状況があったこと、感情を殺し悲しみさえ殺して生き延びた子どもたちの感情的麻痺あるいはトラウマないしサバイバー・シンドロームが、戦後も往々にして悪夢となって存続していた事実を、私たちは重く受け止めねばならない。
本書で紹介された百人の子どもたちは、基本的に一九三五年から一九四四までに生まれた終戦(解放)時に一〇歳以下だった子どもたちである。これまで歴史研究の対象にされることは、ほとんどなかった。この年代の子どもたちはホロコーストのあいだ、高齢層を除外すれば、他のどの年齢層にもまして生き残れる可能性が少なかったというのが実情であるが、生き残っても戦前の記憶がぼんやりとしているか、そもそも存在せず(戦前そのものをまったく経験してない)、また幼いころの記憶の鍵となる詳細を満たし教えてくれる大人が生きていない場合が多かったから、自らの原点となる過去の物語を組み立てようと何十年も苦闘することになった。
人道支援組織のスタッフ、また場合によっては再会できた両親や縁戚者、預けられたホストファミリーや育ての親、精神衛生の専門家等、自分をケア・観察・養育し、自らの人生を特徴づけてきた人たちとの諸関係においても、最愛の世界から強制的に引き剝がされるつらい体験をそれぞれ刻印されながら、他方では無害な偽物の過去という形での噓をつかれ、ないがしろにされていると感じつつ、解釈しようもない記憶とともに取り残されていることが多かったのであった。この子どもたちは心身成熟期から文化的成年に達していく思春期を、最年長者の場合一九四〇年代後半に迎え、最年少者の場合一九六〇年代前半に終えたことになるが、自分の幼年時代の真実を知り理解できる年齢になったという自覚も芽生え「本当の自分とは?」という最も根本的な問題の解を求める小「歴史探索者」にならざるをえなかった。「過去の扉」をこじ開けることに関心を集中し、惨酷な事実から彼らを守ろうと保護者たちが築いてきた障壁にも挑んでいったが、戦時中のヨーロッパのユダヤ人に関する歴史的情報が容易に手に入るような時代でもなかった。
一九五〇年代の西独・連邦補償法はナチスの迫害により家族や生計手段を失い健康を損なわれた人びとが最低限の補償を受けられるためのものだったが、申請者は迫害を受けたこと、あるいは戦時中の生活環境が非人間的だったことを証明しなければならず、戦時中に子どもだった被害者にはたいてい不可能だった。実際のところ、当局は彼らの体験を補償に値するとはみなさず、請求を却下することになった法的プロセスは、被害者の記憶の空白を埋める情報や貴重な資料を提供する機会にもなりうる意想外のケースがあった一面、ほとんどの場合の請求棄却という帰結自体、被害者にとっては、酷薄で屈辱的な体験を再度味わわされるつらい局面にほかならなかった(第六章「変容」)。戦後史(第二次世界大戦終了後の世界史的過程)の決定的な局面としてようやく問題の全貌をあらわしつつあるといっても過言ではない戦後補償過程の歴史そのものが、現在本格的な見直しへと向かって進行中であるが、ここにもかつての子どもたちの視線からのアプローチが欠けてはならないことを著者クリフォードは静かに訴えかけている。本書ならではの視点が示されているといえよう。この西独の賠償事業問題を契機に、精神科医や精神分析医のあいだで以下のような議論が生まれた重要性も著者は見逃していない。ホロコーストを生き延びた子どもたちは、一九五〇年代初頭にアンナ・フロイトたちが主張していたような回復力を備えていたのか、むしろ心にいつまでも残る傷を負ったのではないか、という議論である(第七章「トラウマ」)。
一九六〇年代から七〇年代にかけて、トラウマ概念に対するアプローチも、ホロコーストの歴史に対するアプローチも劇的に変わったという。トラウマとなる経験の影響がいつまでも残る問題は、補償の法的プロセスにまつわる議論を通じて表面化したが、本当の意味でこの問題に関する精神医学的研究が盛んになったのは、ベトナム戦争以降であると著者は指摘する。PTSD等を念頭におけば、やはりそうなのだと解説者なども納得させられてしまうのであるが、ホロコーストを幼年時代に経験した人たちにもその経験を証言する能力があると認識されるようになっていった過程を跡づけることこそ、むしろ無視されてきた重要なテーマなのであり、本書の眼目たることをここであらためて強調しておかねばならない。
アメリカのテレビ・ミニシリーズ『ホロコースト』が欧米や日本で放映された一九七〇年代末以降、ランズマン監督『ショア』の公開も相俟って、ホロコーストを直接経験していない広範な一般人のあいだにも「集合的記憶」が発展していく「メモリー・ターン」(記憶をめぐる認識の転回)によって、一九八〇年代には証人として、あるいは記憶の主体として、子どもの価値がしだいに重視されるようになっていく(第八章「幸運と言われた生存者」)。
一九八三年には画期的なユダヤ人ホロコースト生存者アメリカ大会がはじめて開催されるが、会場では年上の生存者の経験を優先する記憶の序列化の傾向が依然みられ、幼年時生存者自身の経験が二の次にされがちだった問題を本書は見過ごしていない。大会での年上の生存者の対応に怒りを覚えないではいられなかった幼年時生存者アンリ・Oの、以下の血の出るような肉声を掬い取っている。
「あの大会が開催されることがわかると、収容所にいたことがないのに参加してもいいのかどうか悩んだ。収容所にいたことを示す証拠が何もなかったから。〔中略〕せめて腕に数字の入れ墨〔囚人番号〕があれば自分の苦しみを人に伝えられるのに、とさえ思った。〔中略〕年上の生存者たちは『当時は子どもだったんだろ。だったら何がわかる? 覚えてないじゃないか』と言う。実際、大会の会場でよくそう言われた。『覚えてないんじゃないの』って」(以下、引用はいずれも本書から)
一九三八年にパリで生まれ、一九四三年に仏OSE(児童援助協会)の手を借りて「中立国」スイスに密入国し、スイスのホストファミリーのもとで戦時期を過ごしたジャクリーヌ・Rは一九八五年、ほかの仲間と協力し、ニューヨークに幼年時生存者の団体を設立。一九九一年には潜伏児童の第一回国際大会にも参加し深い感銘を受けているが、上記のアンリとは逆に「あの大会がすべてをもたらしてくれたみたい。過去に取り組むようになったのも、一九八三年からだから。いまでは、過去が私をどのように形づくり、私の行動や信念、価値観にどんな影響を与えたのかがわかる気がする。両親のことも、以前よりよくわかった。二人が経験したこととか、失ったものとか、私との関係とか」と一九九二年のインタビューで述べており、一九八三年の全米大会が、過去をもっと詳しく理解しようとする旅路の幕開けになったと高く評価している。本書の著者自身も、一九八三年の大会が、ホロコーストの生存者とは誰なのか、生き残りとはどの範囲を指すのか、といったより大きな物語が変化していくなかで、幼年時生存者がその大きな物語の中に自分自身の物語を組み込んでいく場面や機会を提供したとし、彼らがそうしたのは、「生存者」や「生き残り」と呼ばれることを求めていたからだけではなく、生き延びてきたことの意味を、これまでとはまったく異なる形で探求したかったからだとし、この重要なプロセスを通じて、社会の側の意識も変わったと意義づけている。
この大会後、アメリカやカナダ、ヨーロッパ諸国、オーストラリアなどに、同様の生存者団体が何百となく設立された。一九九七年には、これらの統括組織「ユダヤ人幼年時ホロコースト生存者世界連盟」が発足、代表者のステファニー・セルツァーが、毎日のように寄せられる加入希望者からの電話について「半世紀以上沈黙を貫いていたという話をする人が多かった」と記しているように、幼年時生存者を代表する組織の存在により、彼らに共通する物語を公の場で伝えることがやっと可能になったといえよう。その結果、生存者自身も自分の体験を、より大きな物語に欠かせない価値ある物語とみなせるようになった。かつての「孤児」は、同世代の生存者との一体感を強調し、年上世代の生存者とも「第二世代」とも異なる形の物語を提示するなかで、まさにかけがえのない自分自身の経験を自分たちの物語の中心に据えることができたのだと、第九章「ホロコースト生存者になる」を結んでいる。本書により、歴史的出来事を経験した人々へのインタビューを通じて過去を研究するオーラルヒストリー、口述史の意義に覚醒・開眼させられたという読者も少なくないのではなかろうか。
本書の核心的テーマのひとつとして第一〇章の標題にもなっている、孤児たちの「それぞれの物語」については、ホロコーストを経験した国々を中心に世界の精神科医や精神分析医、そして口述史家のあいだでどう受け止められてきたのかも、続く第一一章「沈黙」で鋭く問題の俎上にのせられている。「教師は子どもたちを再び戦場に送るな」を戒めとして、二〇一五年、日本教育学会が「戦争と子ども・教育」を主題に「戦後七〇年を教育学としていかに受けとめるか」(第七四回大会シンポジウムⅠ副題)という大きな問題意識のもと、メインテーマ「戦争と子ども・教育」を取り扱い、「戦争の直接の被害者になるばかりでなく、親や家を失って成長発達するための環境を奪われたり、対立の担い手、当事者に育てられる教育を受けたりするという意味で、子どもは戦争の最大の被害者となりがち」と子どもの立場が整理されたのが注目されるが(司会・米田俊彦〈お茶の水女子大学教授〉)、「敗戦直後の日本における浮浪児・戦争孤児の歴史」という切り口から長年貴重な研究にとりくんでこられた逸見勝亮(北海道大学名誉教授)が報告の中で、「過度の単純化」に抗う孤児たちの「語り」に耳を澄ます大切さにしみじみ言及されて印象的であった。本書は、どちらかというと従来、戦争孤児よりもむしろ、かつての(闘う)年少皇国民のほうに関心が傾きがちだった「戦争と子ども」研究者にはもちろんのこと、日本のドイツ史家はじめ現代史研究者にとっても大きな刺激となるであろう。
トランプ政権終焉の始まりが展望されつつあった二〇二〇年秋のアメリカのある世論調査報告(The Guardian, 16. September 2020)によれば(対象世代一八~三九歳)、ナチ体制によるホロコースト(ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅政策)は「神話」、歴史的虚妄にすぎない、あるいは不確かないし度過ぎた誇張と考えている人が二三%、ナチ収容所あるいはゲットーの名を一つもあげられなかった人が四八%、アウシュヴィッツ=ビルケナウが何であるか、の正解者は四四%、同様にベルゲン・ベルゼン(アウシュヴィッツからの「死の行進」でアンネ・フランクが最後に辿り着き命を落としたことでも知られる通過収容所の名)の正解者はわずか三%であった。一九七二年にカーター大統領が設立を呼びかけ、首都ワシントンに開館した国立のホロコースト記念博物館施設を有する合衆国の政治文化に鑑みても、この結果である。アメリカの現在の歴史教育事情の意外な一断面が露わになったといえなくもない。ひるがえって日本の場合、上記より世代幅は狭いが、ほぼ重なる広義の若年層(一八~三四歳)に絞って世界現代史のクイズを仮に試みれば、調査結果はどうだろう。多少の差はあっても大なり小なり惨憺たるものではなかろうか(中高年層にあっても結果は変わらず怪しいかもしれないが)。
いずれにしても痛感させられるのは、どれほど私たちが、ホロコースト及びその影響をいまだ十分に理解しないまま、世界史的知の現境にいたっているか、という問題である。特に本書が描出したような、幼年時生存者一人ひとりの、自らの過去への何十年にもわたる長い旅路の困難さに向き合わされると、あらためて粛然たる気持ちになる。なお本研究は、二〇二一年ウルフソン歴史賞候補作品になっている。
目次
※以下、括弧内は書籍版のノンブル(ページ番号)です。各章の、特に巻末資料のボリューム感をイメージしやすくするために掲載しておきます。なお、原注や索引は奥付側から開く仕様になっています。また、本文とは別に巻頭に口絵(写真27点、全12頁)が入ります。
略号(6)
謝辞(7)
ホロコースト生存者の名前について(12)
序章(14)
第1章 もう一つの闘いの始まり(31)
第2章 大人の視点(60)
第3章 引き取られる子どもたち(84)
第4章 家族との再会(123)
第5章 ヴォセル館の子どもたち(150)
第6章 変容(175)
第7章 トラウマ(204)
第8章 幸運と言われた生存者(234)
第9章 ホロコースト生存者になる(259)
第10章 それぞれの物語(281)
第11章 沈黙(310)
終章 最後の証人(336)
日本語版解説(349)
原注(397)
参考文献(419)
図版クレジット(421)
索引(429)
著者紹介
レベッカ・クリフォード
ウェールズのスウォンジー在住。2008年にオックスフォード大学にて博士号を取得(近代史)、オックスフォード大学ウースター・カレッジでのジュニア・リサーチフェローシップを経て、2009年、現在所属するスウォンジー大学(近代ヨーロッパ史/准教授)に移籍。王立歴史学会と高等教育アカデミーのフェローも務めている。著作は、2013年にオックスフォード大学出版会から刊行されたCommemorating the Holocaust: The Dilemmas of Remembrance in France and Italyがあり、彼女の所属チームが共著したEurope's 1968: Voices of Revoltにも協力している。本書Survivors: Children's Lives After the Holocaustはイギリス学士院のリーバーヒューム・トラストの研究助成を受けて制作されたものである。
訳者紹介
山田美明〈やまだ・よしあき〉
英語・フランス語翻訳家。東京外国語大学英米語学科中退。訳書にエマニュエル・サエズ+ガブリエル・ズックマン『つくられた格差――不公平税制が生んだ所得の不平等』、エディス・シェファー『アスペルガー医師とナチス――発達障害の一つの起源』、デビッド・リット『24歳の僕が、オバマ大統領のスピーチライターに?!』、プク・ダムスゴー『ISの人質――13カ月の拘束、そして生還』(以上、光文社)、ジョセフ・E・スティグリッツ『スティグリッツ PROGRESSIVE CAPITALISM』(東洋経済新報社)、トム・バージェス『喰い尽くされるアフリカ――欧米の資源略奪システムを中国が乗っ取る日』(集英社)、他多数。
監修者紹介
芝 健介〈しば・けんすけ〉
1947年、愛媛県生まれ。東京女子大学名誉教授。専門はドイツ現代史。著書に『武装SS――ナチスもう一つの暴力装置』(講談社選書メチエ)、『ホロコースト――ナチスによるユダヤ人大量殺戮の全貌』(中公新書)、『ニュルンベルク裁判』(岩波書店)など、訳書に『総統国家――ナチスの支配 1933-1945年』(岩波書店)、『ファシズム時代のシオニズム』(叢書・ウニベルシタス)、『二つのドイツ――1945-1990』(岩波書店)、共訳書に『ホロコースト大事典』(柏書房)、監修に『星をつけた子供たち――ナチ支配下のユダヤの子供たち』(創元社)など、ナチ関連書多数。
