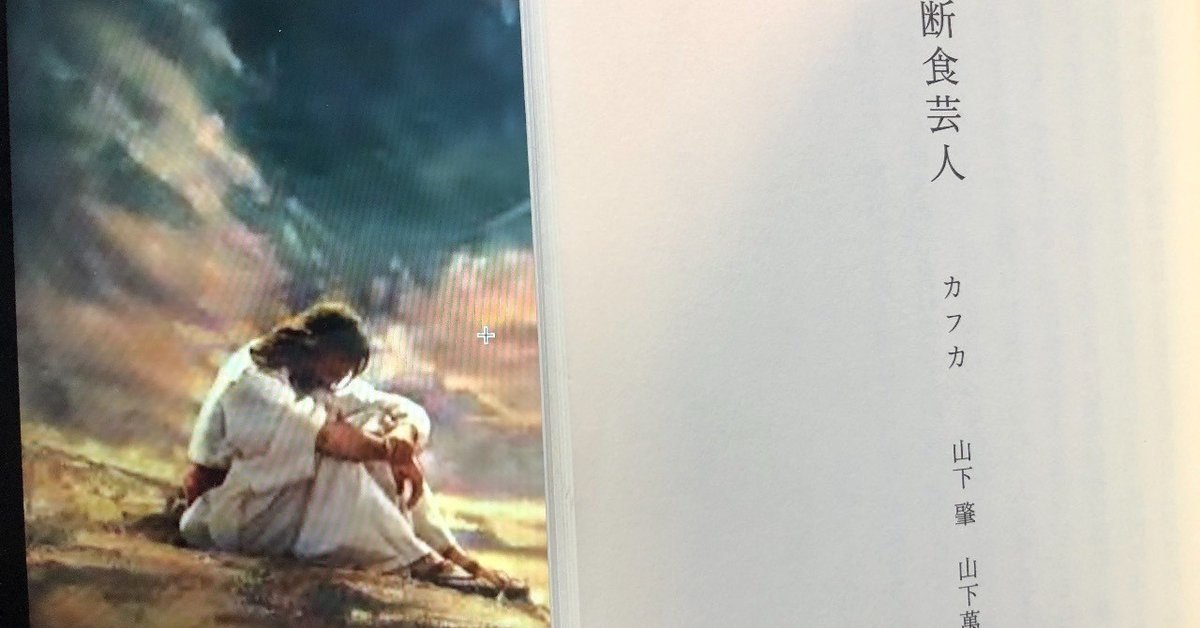
vol.34 カフカ「断食芸人」を読んで(山下萬里訳)
カフカ晩年の1922年ごろに書かれた作品。
断食芸って、例によってカフカの突飛な空想かなと思ったけど、19世紀末から20世紀初めのアメリカやヨーロッパで、サーカスや寄席や見世物小屋などで実際に演じられた芸らしい。
この小説でも「かつては、自前で断食興行を打つことがよい儲けになった」とある。
あらすじ
断食芸はかつては人気の芸だった。断食芸人は格子の付いた檻の中に入り、敷き詰めた藁の上に座ってじっとしている。断食芸人は時おり水で口を湿らす他は何も口にせず、また人目に隠れて物を食べないようにと常時見張りが付いている。興行は決められた日数である40日間続けられ、それが終われば音楽とともに人々の間に出迎えられる。しかし断食芸人は、40日で断食をやめなければならないことに不満であった。
断食芸の人気はすっかり衰え、断食芸人はサーカス一座と契約した。断食芸人の檻は動物小屋とともに並べられたが、誰も興味を示さない。そしてすっかり忘れられてしまう。ある日、監督が断食芸人の檻に気づき、藁屑を掻き出すと、断食芸人がまだ断食を続けていた。問いかける監督に対して、断食芸人は「自分にあった食べ物を見つけることができなかった」と述べ、息絶える。断食芸人が片付けられると、その折には生命力に溢れた豹が入れられた。(ウキペディアからの抜粋)
娯楽多様な現代からすると、断食は苦行で、芸と呼べるものじゃないと思う。これを芸とするのに違和感を感じた。強いて言えば、「大食い選手権」を思わせる無分別な戦いに通じる気がした。今あったら本当にイタイ「芸」だ。しかもこの小説では、人気がなくなっても「自分はまだまだ断食を続けられるんだ」と、観客はもう飽き飽きしているのに断食を続けている。これはもう、芸人じゃない。観客を無視した自己欺瞞だらけの行為だと思った。
さらに言い訳がましく、最後に断食芸人は「断食せずにはいられなかった。自分に合うべき食べ物さえ見つけていたら、みんなと同じようにたくさん食べていただろう」という趣旨の言葉を残して死んでしまう。そして、断食芸人が藁と一緒に片付けられた後に、檻の中に生き生きとして精悍な豹を入れる。この野獣はなんでも食べる。なんの欺瞞もない。いつしか、豹の檻の前には観客が群がっていた。
この展開に、カフカ的な、深く、暗く、魅力的な作品とならしめる仕掛けがあるなと思った。
もう一度読み直した。明らかにカフカは、断食という精神の行為を否定的に描いている。あるいは逆説的に描いていると思った。
そうするしか仕方のない、あるいは生き方がわからない人に対して、世間の理解が低すぎると訴えているのかもしれないと思った。
また、世間の関心は、断食という精神世界よりも、豹のような、なんでも食べる精悍でわかりやすい肉体にすぐに飛びついてしまう、無分別への警告なのかもしれない。
あるいは、断食芸人は、断食芸としての生き方に確固たる信念のもと死を迎えたことは、書くことでしか評価されないカフカの分身かもしれない。
はたまた、福音書にあるイエスの40日の断食で空腹を覚えたことからの引用かもしれない。
あるいは単なる拒食症の話か、自己陶酔の話か、疎外感の話か・・・。
とにかく、この作品、多様な解釈を楽しむことができると思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
