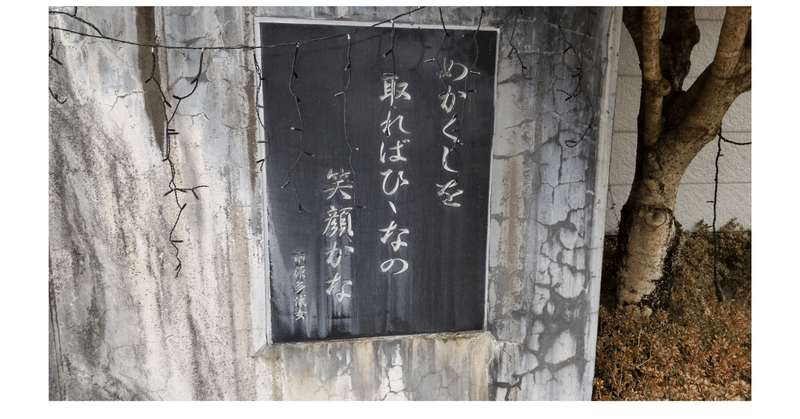
俳句にまつわる雑感
俳句の世界では仲春だというのに、相変わらず寒々しいみちのくです。

仲春というのは、春半ば、の意味。
日本列島は南北に細長いから、四季のずれがあって当然なのですけれど、もう葉桜の便りが聞こえてくる一方で、こちらはまだまだなのです。
さて、俳句のルールについてです。
基本は、575(17音)と、季語を入れる。
これのみのはずですが、「類想」「季重なり」「季語を立てる」など、深く突っ込むほどに、難しいルールが登場してきます。
さらには、ある程度の古典文法の知識もあると、望ましい。
この辺りで、「だぁー、メンドクセー!!」となる人も多いのでしょうね😅
ところが、noteで「俳句と関係のない人にも楽しんでもらおう」となると、ここでひと工夫必要になります。
類想句を避ける
詩情を残す
オリジナリティを出す
というのを前提とすると、句の生まれたバックボーンなどの説明も記載したほうが、俳句の知識がない人にも分かりやすい。
俳句本来の鑑賞方法からはあまり褒められないようですが(多分、鑑賞側の想像力を奪うからでしょう)、noteの発表分については、私は多少つけることが多いです。
桔槹吟社
俳句幼稚園に入園した頃に気になったのが、地元の句会の作品。
地元には、桔槹吟社という俳句結社があるのですけれど(私は未入会)、創刊千号の記念句会において、翠ケ丘公園にある妙見山で森川代表(当時)が詠まれた句が、こちら。
芝青くリポビタンD横たはり
「自分の弱さを俳句で出さないと、俳句は上達しない」というのが、森川氏の持論でした。
桔槹吟社は1922年に創設され、柳沼破籠子、矢部榾郎、道山草太郎らが原石鼎を招いたことが、結社のきっかけになったそうです。
そういえば、去年の春に牡丹園を訪れた際にも、彼らの句碑が建っていましたっけ。
牡丹園を訪問したときはまだ俳句を嗜んでいなかったので、その価値がよく分かっていなかったのですが、やはり$${^{*1}}$$柳沼氏の財力や人脈がなかったのならば、桔槹も誕生しなかったのかもしれません。
*1)柳沼破籠子は、須賀川牡丹園初代園主、柳沼源太郎氏の俳号。
多代女の主婦感覚
もう一人。
地元の俳人で私が参考にしたのが、市原多代女の「雛祭り」に関する句です。
あの小林一茶の「おらが春」にも彼女の句が載っているといいますから(老いたちの出る夜となれば朧月)、当時はよく知られた才女だったのでしょう。
ですが、私は今で言うならば「スーパー主婦」としての、多代女の感性に目を瞠ります。
をしい夜の更てちらつく雛哉
(おしいよのふけてちらつくひいなかな)
余所の雛見て来て親に不足哉
(よそのひなみてきておやにふそくかな)
棚の雛はつかたつ日のほこり哉
(たなのひなはつかたつひのほこりかな)
手奇麗な娵の料理や雛祭
(てぎれいなよめのりょうりやひなまつり)
献立も聞ゆる雛のひと間哉
(こんだてもきこゆるひなのひとまかな)
行燈に変えて更しぬ雛かな
(あんどんにかえてふけしぬひいなかな)
聞き分けて仕舞ふ四日の雛かな
(ききわけてしまうよっかのひいなかな)
めかくしを取ればひゝなの笑顔哉
(めかくしをとればひいなのえがおかな)
白酒は外から見えてひなのたな
(しろざけはそとからみえてひなのたな)
雛の間に居りて思ふむかし哉
(ひなのまにおりておもうむかしかな)
幾としも雛に倣ふむつみ哉
(いくとしもひなにならうむつみかな)
三ちとせを祝ふや代々に桃の酒
(みちとせをいわうやよよにもものさけ)
桃さくら雛見るこゝろとしよらず
(ももさくらひなみるこころとしよらず)
俳句ポストの「雛祭」の句も素敵なのですけれど、多代女の視線は、現代にも通じる感覚があるのではないでしょうか。
季語のある意味
そして、俳句に「季語」のあることの意味です。
散文との違いにも通じることですが、とあるサイトに、「日本人の共通認識である季語を使うことによって、読者に具体的なイメージを喚起させたり、様々な連想を広げたりして、思いを伝えることができる」とありました。
そういう意味では、現代の季語は、多代女の頃よりも増えすぎてしまったのかもしれません。
ですが、四季の移ろいを大切にする心は、日本だけでなく俳句を愛する人皆に通じるもの。
そう感じるのです。
©k_maru027.2022
#エッセイ
#俳句
#note俳句部
#俳句雑感
#福島
#須賀川
#俳人
#古典がすき
#ふるさとを語ろう
これまで数々のサポートをいただきまして、誠にありがとうございます。 いただきましたサポートは、書籍購入及び地元での取材費に充てさせていただいております。 皆様のご厚情に感謝するとともに、さらに精進していく所存でございます。
