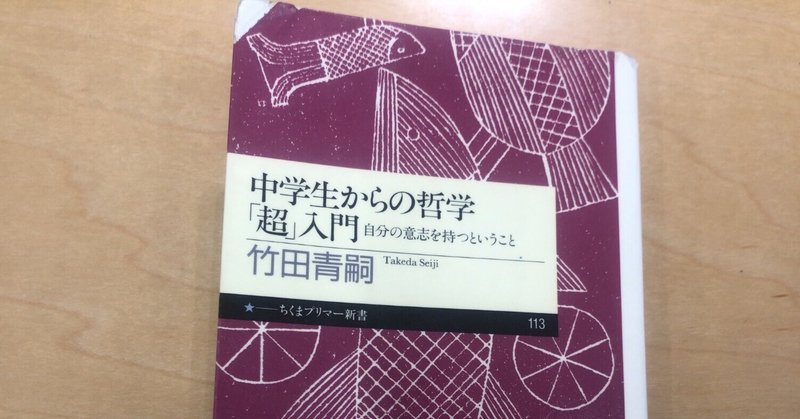
中学生からの哲学超入門
202404301
哲学は、人間や社会の「本質」を課題とし、
科学は、自然世界の「事実」を捉えようとする。
宗教の教義には絶対的な正しい教義というものは存在しない。なぜならそれはもともと「物語」だから、どれが絶対に正しいかを決められない。
人間の考えや価値観は、社会が進むほど多様になるので、これを一つにまとめることは不可能である。だから、どの教義が正しいかではなく、様々に現われる教義を、「一つだけ」にする、ということが宗教にとっては決定的に大事なことになる。
宗教の教義を時代ごとに解釈する。人間の考えや価値観が変化しても、時代を超えて、解釈可能な教義が受け継がれてきた。時代に関係なく人々に受け入れられてきた。それは、教義が、人間や社会の本質に根差しているからではないだろうか。
宗教は、物語によって統一的な世界説明をする。人間は特に、生死の問題や、自己の存在意義について、大きな不安を持つ生き物なので、世界や生の意味を示してくれる宗教は、重要な役割を果たす。
科学は、自然世界の認識については、宗教の世界説明では到底及ばない、高度な共通理解を浸透させた。
しかし、人間の生死の意味や自我の不安や人間関係の悩みといった問題については、まだ、この問題に長い経験をもつ宗教に優位がある。
科学は「事実」の学なので、人間の意味や価値の問題に迫る方法がない。
本質は真理とは異なる。
「ある事柄の一番大事なポイントをどんな言葉で呼べばよいか」というルールに従って、できるだけ大勢が納得できる言葉を探してゆく過程が、哲学である。ある事柄が原理であり、見つかった言葉が、本質である。
本質を見つけることは、共通理解を作り出していくことである。
真理とは、絶対的普遍であるから、社会や時代の影響も受けないし、人々の理解の必要がない。
仏教の空や無我を理解するのは、難しい。私たちは、体験によって世界を知覚するので、体験を伴わない思想を理解することは、難しいのだ。でも、私たちの理解に関わらず、真理は、存在している。
社会をゲームだと捉える。
何人かでゲームをはじめる。
いくつかのことをはじめの前提として認めあう必要がある。全員の合意でルールを決めること、全員が平等にルールに従うこと、ルールに従わないとゲームが成立しないので、違反したときには罰を科すことがあること、等々。
ルールのもとのプレーヤーの平等ということが前提で、これが守られなければ、ゲーム自体が成り立たない。だから各人がこの原則を守ろうという意志を持つ。そんなことをそれほど意識はしていないけれど、ゲームをするときには、そういう原則が必ず成立している。この原則を守らない人がいると、もうゲームは成り立たない。
ゲームが社会
ルールが法律
現代は資本主義なので、ゲームの勝者を決めるのは、金
ゲームの勝者を決めないのが、社会主義
とは言え、もちろん、社会は、自由で平等なゲームじゃない
私たちは、社会というゲームに生まれたときか
投げ入れられていて、気に入らないので自分は降りる、ということができない。ゲームを降りる自由、 あるいは出入りの自由がはじめから存在しない。
また、現実社会では、はじめから条件に大きな差があり、対等とは言えない。ある人は、お金持ちに生まれ、才能をもち、美人に生まれつく。そうでない人との差は歴然としている。だから、こんなゲームは不当だと感じている人が多く出てくる。その人たちにとっては、この社会がフェアなゲームと言えない。
社会 = ルールゲーム論へのもう一つの異議は、社会というものは、実際には、どこまでも実力のゲームであって、立てられているルールはいわば見せかけのものにすぎない。結局は、実力を持つものがルールの権限をうまく握り、社会を自分の思うように運んでゆく。
#日記
#エッセイ
#コラム
#ブログ
#人生
#生き方
#ライフスタイル
#日常
#とは
#スキしてみて
#哲学
#中学生からの哲学超入門
あなたの琴線に触れる文字を綴りたい。
