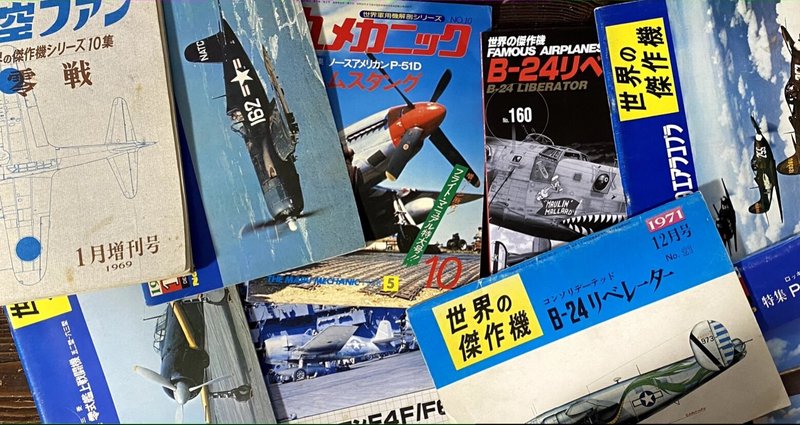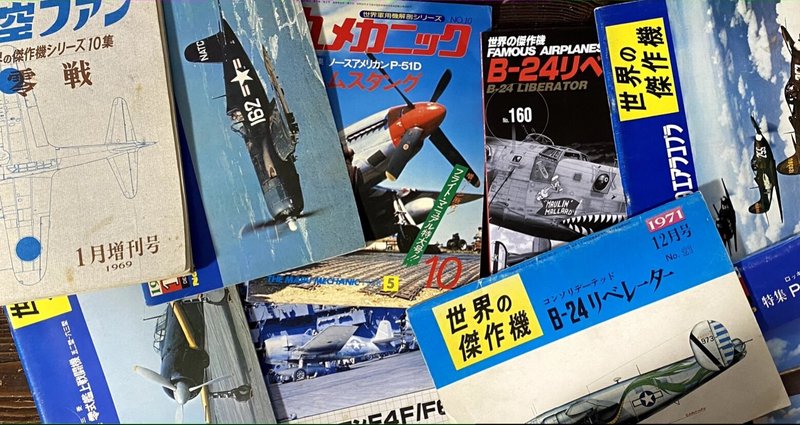川西 強風 N1K1 (1942)
第二次世界大戦前、アメリカから石油等の経済封鎖にあったことで東アジア方面への侵攻が日本にとって重要な戦略となった。東アジア方面の島嶼を基地として制空権を得ることが必要である。陸上基地に頼らない水上機で陸上機なみの戦闘機があったら・・・ということで海軍は他国には類のない水上戦闘機を構想した(水上機はたいがい偵察機であった)。構想されたのが十五試高速水上戦闘機の企画で、水上機を得意とした川西航空機が受託することになった。同時に零戦を生産していた中島飛行機にも、零戦を水上機化する