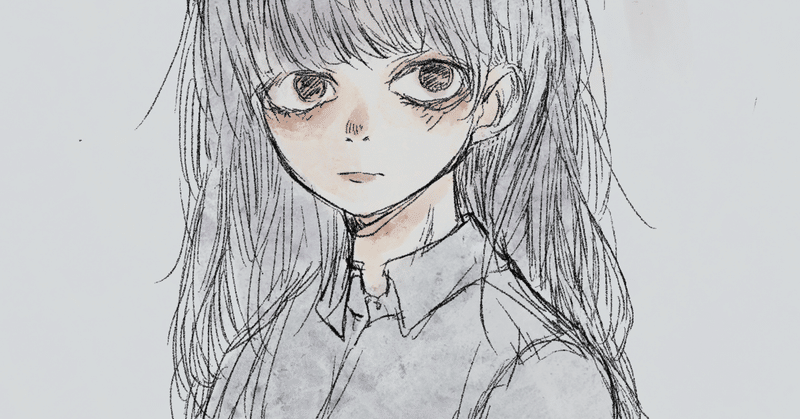
わたしはもう、サンドバッグから卒業する
「うつ病の人」
そういえばあの頃も、そんな名前で呼ばれていた。
本人は聞こえていないと思っているのか、それともわたしに聞こえるように言っていたのかはわからない。なんにしても「迷惑」をかけているのは自分なのだから、愚痴をこぼしてはいけない、弱音を吐いてはいけない。悪口なんて、以ての外だ。とにかく目の前の仕事をこなし、息をしなければならない。
パソコンを見ながら、悪夢を見ている。
臙脂色の瞳。内側から突き上げられるような恐怖と痙攣。力強く、繰り返し目を閉じていなければ、あふれる水滴を止められない。「後退」キーに小指を置き続け、奥歯を砕きながら生きている。
人との話し方なんて、わからない。
自分の発言すべてが間違っている気がする。誰のことも傷つけずに生きていけるはずがないのに、わたしは誰のことも傷つけたくなかった。
肉体が貫かれ、鈍い音を立てる。
自分が声を出す、それだけで周りが不幸になる気がした。失敗をしない。失敗をしても、自分ひとりでなんとかすればいいのだ。どうにも誤魔化せなくなったら、そのときは、辞めるしかない。さいていだ。さいていの仕事の仕方だ。でもそれが自分のできる、人を傷つけない"最善"だと思っていた。
◇
三年ほど前。わたしは住宅系の会社の事務として仕事をしていた。普通の会社員だ。収入は多くない、ただそんなことはどうでもよかった。
贅沢する気なんて微塵もない。おいしいごはんは食べられなくていい、楽しい場所に行けなくていい、趣味なんか必要ない。働いて、生きていけるお金が稼げればよかった。「自分にだってできる」。それを達成できるだけで、わたしは涙が出るほど嬉しかったのだ。
けれども、わたしは仕事ができなかった。
わからないことを中々人に聞けない。報連相がうまくできない。人を頼れない。それらすべての根底にあったのは、"人に迷惑をかけたくない"だった。
抱えこむ人が、最終的に人に迷惑をかける。それを頭の片隅で理解はしていたけれど、動かない。せめて丁寧な言葉遣い、丁寧な言葉選びを心がけていた。
その会社は転職をして、わたしの人生で二社目だった。「前と同じにならないようにしなくちゃ」と、唱えていられたのも、一瞬。誰とも上手に話せなかったわたしは、孤立する。ごちゃ混ぜになった感情を抱えきれなくなり、オフィスのど真ん中でパニック発作を起こし、倒れてしまった。
救急車で運ばれ、そこからあっという間にわたしの名前は「うつ病の人」になる。
.
.
「できそうか?」
後日、課長に呼び出され、面談をした。
できそうかどうかで聞かれたら、できない。けれど生きるためにやるしかなかった。わたしの人生は「嘘」で構成されている。涙しか、手をつないでくれる人がいない。自分も、涙としか手をつなごうとしない。
課長に言われたわけではないけれど、わたしはひとりひとり、部署の人に頭を下げ、謝った。ただでさえ仕事ができないのに、オフィスで倒れてしまった。もう、これは取り返しのつかない失敗。「がんばるから」なんて、まったくもって意味のない言葉。それでもやりたかった、生きたかった。
自分の席に戻る。
座り、それだけで臓器が飛び出してきそうだった。つま先から、髪の毛の先まで痺れてくる。人に話しかけられても、笑うことができない。なにもしていないのに、汗がサウナかなにかに入っているくらい出てくる。わたしが触った書類は、誰も触りたがらなかった。「ごめんなさい」と、繰り返し思う。周りの人は、親指と人差し指の先で、つまむ動き。
人に仕事を頼まれ、なんとかやりきる。
落ち着いてやれば、そんなに難しい仕事ではないはずだ。がんばれ、がんばってくれ自分——
「うつ病さん、これやっといて」
.
.
ああ、やっぱりだめだ。
隣の席の女の人。他の人とはいつだって楽しそうで、わたしが隣で、「ごめんなさい」。人を傷つけたくなかったのに、なにをしているのだろう。いるだけでわたしが迷惑になっている。性格は簡単に変わるものではない、それでも自分の性格を変えたかった。けれど繰り返し、聞こえてくる。
「うつ病の人が使えない」
「うつ病の人が今日も来た」
「うつ病、早く辞めないかな」
.
.
そうだよね。
そうだよね。
"できないわたし"が、わるいのだから。
被害者面なんてしない。でもわたし、がんばっているよ。"がんばっている"なんて、評価にならない。人の"かたち"をしたサンドバッグ。どこへ行ってもやっていけない。わたし、やっていけないよ。
◇
「おはよう」
小さなベッド。そこに隣同士、眠っている。鼻先と鼻先をくっつけ、キスをした。視線を絡ませ、愛が咲いている。やっと、わたしが「人生」と手をつなぎ始めていた。
いまのわたしは、恋人の彼と一つ屋根の下で暮らしている。失敗をしても、抱え込んでも、わたしの名前をそのまま呼んでくれる人がいる。ああ、だめだ。書いただけで瞳からは、涙が千切れるように落ちる。
会社を辞め、いまは飲食店で働いている。これが次にわたしの選んだ道だった。収入はさらに減った。ただそんなことはどうでもいい。贅沢する気なんて、微塵もないのだから。
「ここならやっていける」
そう思っていた。なにより、わたしの好きなお店だった。やさしい常連さんにも恵まれ、愛されていた。もうすぐここで働いて二年が経とうとしている。気づけば自分は副店長になり、皆に頼られる存在になっていた。わたしでもやれる。いける、いけるのだ。愛する彼もいる。わたしに合う仕事、環境があれば、生きていける。ここでならわたしが、わたしらしく笑顔で歩ける——
「ゲイの人、邪魔なんですけど」
.
.
ああ、やっぱりだめかもしれない。
二週間ほど前に、とある事情で恋人の彼が救急車で運ばれた。それを心配してお店を抜け出し、わたしは彼の元へ走っていた。後日、そのときの話が一瞬で従業員の間で広まる。それを加速させたのはきっと、わたしの言葉のせい。「彼女いたんですね」と聞かれたわたしは、自然にこぼしたつもりだった。
「いえ、男の恋人がいます」
当たり前に認めてくれると思っていた。そうでなくても、わたし以外には関係の薄いことだと思っていた。
愛する人がいる。
それを話しただけだ。「家族」が一大事だったから、お店を途中で抜けさせてもらった。あの頃と同じように、ひとりひとり頭を下げて回った。「迷惑をかけて申し訳ございません」と。
.
.
いつも通り仕事をしていても、聞こえてくる。
「ゲイが男の客と話してる」
「ゲイに好かれたら怖いね」
「ゲイだと思ったら、なんかキモチわるい」
聞こえていないと思っているのだろうか。
聞こえるように、言っているのだろう。
職場でそれが当たり前になって、一週間は経っている。わたしは孤立し、「笑われている人」、「ゲイの人」とレッテルを貼られてしまった。もともとわたしを玩具にする気のない人も、わたしに関わってしまったら、同じように口撃されてしまうかもしれない。人を傷つけたくなかったわたしは、自分から進んで孤立する。
「ゲイ」は「人」と同じくらい、愛される言葉のはずなのに。
それをお店の中で思ったところで意味のないことはわかっていた。考えれば考えるほど、涙がとめどなく溢れる。
「やっぱり女々しい」
「女みたい」
「男なのに泣くなよ」
今日、7月1日。
もう、遠慮がなくなってきた。限界だ。ここで辞めれば、誰も傷つけずに済む。そう考えたその瞬間、わたしは卒業を決意する——
「うっせえええ!!」
.
.
出したくなかった。
キッチンの中。お客さんにも聞こえてしまっただろう。わたしは野太い声で、叫んでいた。「女の子」でいたかった。「やさしい人」でいたかった。迷惑はかけた。でも、"わたし"は生きている。
サンドバッグではなく、わたしもひとりの意思を持った人間だ。
相手の表情は、一瞬で凍りついていた。
わたしは、初めて人を憎んだかもしれない。
こんな人になりたくなかった。でも、わたしを口撃したあなたを、わたしは許さない。許されたかったから、人を許して生きてきた。そんなわたしが、人を許さないという決断をした。
反撃をしてこないと思っていたからか、叫んでから、相手の声は止む。でも、わたしはまだ許していない。これからもっと、"正当に"あなたと闘う。これは、決意のnoteだ。
現実でも、SNSでも、同じ。
人が、心が生きている。
傷つけて、遊んでいられるのもいまのうち。
わたしは、弱くてやさしい人から、強くてやさしい人へ変わります。
書き続ける勇気になっています。
