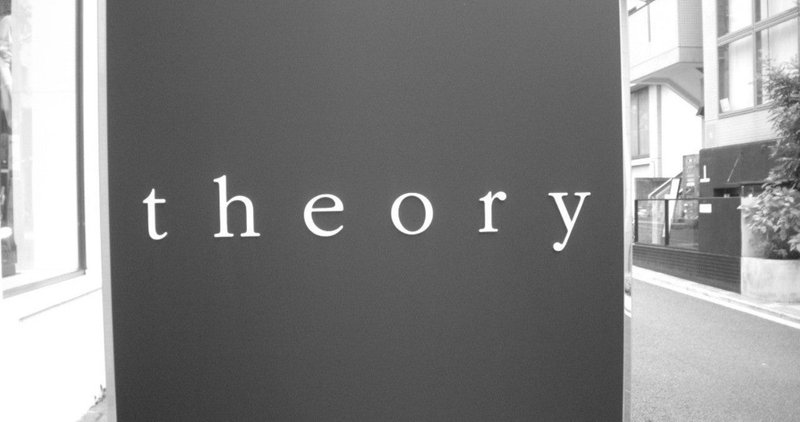
理論を使う面白さ〜現場至上主義に待ったをかける〜
「普遍的である」ことは、「完全である」こととイコールではないのです。
現場至上主義に思う
現場がすべてだ!
という意見ばかりに注目が集まりますが、私自身はそれと同じくらい理論の重要性を感じています。
なぜなら、理論はショートカットだから。
つまり、体で覚えていては何年もかかってしまうことを、理論を学ぶことで効率よく自分に取り入れられるということです。
理論化するというのは、つまり事例を一般化するということ。
一つ一つの小さな事例から、それらに存在する普遍性(≒共通点)を記録するということです。
だからこそ、
「この理論は現場に合わない。使えない」
とキレてしまう人もいますが、そもそも理論は各現場と100パーセント一致することはありません。
100パーセント一致するのであれば、それは理論が素晴らしいのではなく、奇跡が起きただけです。
「普遍的である」ことは、「完全である」こととイコールではないのです。
理論を使う意義
だからこそ、
「理論を現場に応用したらどのような成果が見込めるのか」
という予想を立てるときにこそ、理論は真の力を発揮するはずなのです。
理論を学ぶことによって、今まで見てきた現場をこれまでとは違った視点で見つめなおすことができるはずなのです。
現場に居続けるだけでは気づけない視点を理論から自分の中に取り込むことで、現場をブラッシュアップすることだってできます。
あなたがトマト農家なら
少しフワッとした話なので、ここで例え話を。
もしあなたがトマト農家で、大切なトマトが病害虫の被害にあっていたとして。
おそらく現場至上主義の人は、畑の一株一株をつぶさに観察し、その原因を探ることでしょう。
もちろんこれもとても大切です。
しかし、毎日現場に行って、原因が見つからなかったら、どうしますか?
諦めますか?たぶん、そうではないでしょう。
トマトがナス科の植物だと知っていれば。ナス農家の病害虫の倒し方を教えてもらいに行くかもしれません。ナス科ならピーマンやズッキーニなんかもあり得るでしょう。
つまり、「ナス理論」をトマトに応用したということですね。
とはいえ、それでも病害虫を根絶できなければどうしますか?
諦めますか?たぶん、そうではないでしょう。
もしかしたら全く関係なさそうな「マメ理論」や「コメ理論」を学び、それに基づいて病害虫と対峙してみるなんてこともあり得ます。
さてさて、理論を学び、実践する面白さはこのように問題解決を図るだけではありません。つまり、
「あれ、マメ理論で育てたトマト、何かいつものトマトよりおいしくない?」
が起こりうるということです。
事実、例えば、接ぎ木の苗は、キュウリを育てるために、かぼちゃの土台をお借りするという離れ業をやってのけています。
私はこれを知ったとき、「最初に思いついた奴、天才だな」と思いました。
きっとキュウリがうまく育たないと悩んだ人が、かぼちゃ理論を応用したんでしょう。
理論家ってどこかお堅くて一辺倒なイメージがあるかもしれませんが、案外、現場至上主義の人より変化や例外には柔軟だったりするように私は感じます。だからこそ、
理論が現場を変えていくということは大いに起こりうるのです。
理論に現場の成果を求めるのは筋違い
以上の議論を踏まえると、成果を大前提として、現場至上主義者が現場の成果を理論に求めるのは筋違いだと思うのです。
むしろ現場の成果を理論を反映させることで、次の予想がより精緻なものとなっていくはずです。
極端な話、現場の成果を出すのは現場の人間です。
なぜなら、理論家にとって「成果」とは、「理論をより素晴らしいものに更新すること」だからです。
理論家が現場を見て理論を更新し、それを現場の人が学んで自分たちで現場にフィードバックすることが理論と現場の連携が取れた状態だと私は考えます。
これができるのは理論が普遍的であっても完全でないからこそです。完全でないからこそ、理論を「自分たちなり」に応用していく余白を持つことができます。
理論と現場の融合を目指すのであれば、それぞれの特徴を理解して、理論が現場を、現場が理論を成長させていくという心がけが必要なんだと思います。
ーーー
私の大学院での研究はいわゆる「理論畑」でした。
そんな私が今は離島で鍬持って、農家民宿をやりたいという現場感?溢れる日々を送っています。
こんな私だからこそ、理論と現場はぜひ手を取り合ってほしいのです。
というわけで、本日はこれにて!
ご清読ありがとうございました!
いただいたサポート分、宿のお客様に缶コーヒーおごります!
