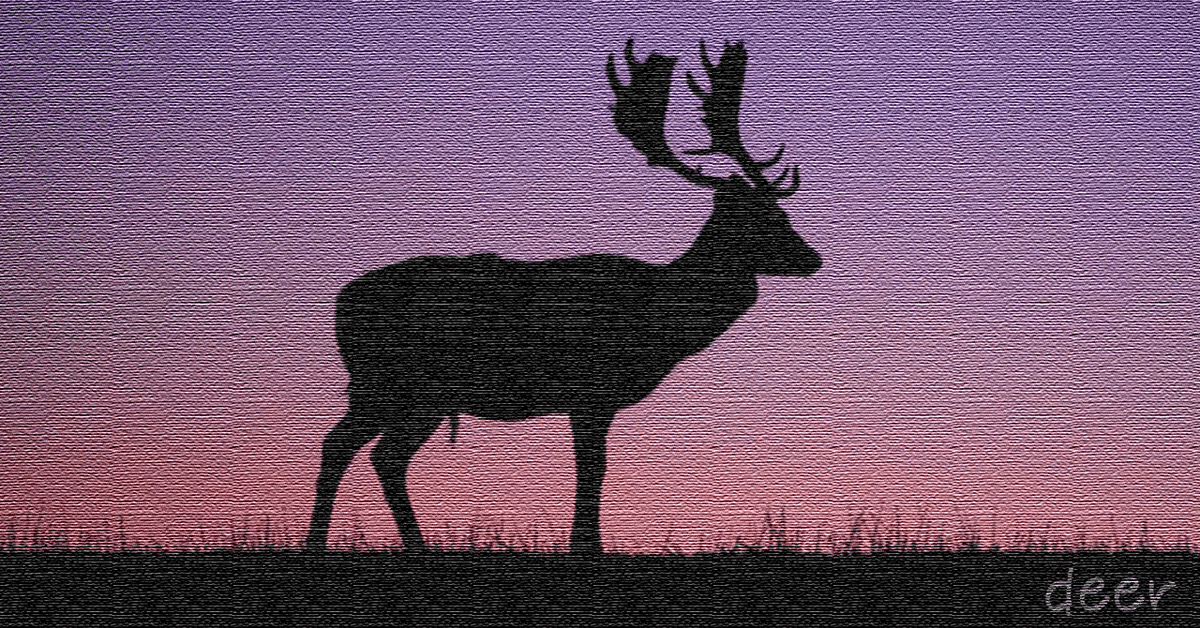
近世“ディア・ハンター”〜山本周五郎『樅ノ木は残った』(1958)
特に、山本周五郎のファンではなかった。ただ国民的作家ということもあり、若い頃に代表的な作品は数冊読んでいる。その後、久しく作品に接していなかったが、家内が『寝ぼけ署長』(1946〜1948)が面白いと言うので通読した。著者唯一の推理小説とのことながら、これは一種の勧善懲悪もの。主人公の警察署長のキャラクターがユニークで楽しめた。
驚異的とも言える数の作品群の中でも、代表作である『樅ノ木は残った』(1958、以下『樅ノ木〜』)は気になりつつ見逃してきた歴史小説。
この大作の映像版は、NHK大河ドラマ(1970年)としてご年配の方々には親しみがあると思う。50年以上前の放映であり、視聴経験者は現在の70歳以上の方々がメインと思われる。当方について言えば、両親が白黒テレビにかじりついていた記憶がおぼろげに。主人公・原田甲斐宗輔(以下「甲斐」)を演ずるは故・平幹二朗氏。平氏、30年ほど前に東京・渋谷の街角で、スタイリッシュなブーツ姿を見かけたことがある。
大河ドラマ放映は昭和45年。昭和30〜40年代は、21世紀の今より歴史ドラマ・時代劇が熱心に見られた時代であったと思う。テレビだけではない。司馬遼太郎氏を始めとする、歴史小説ブームもこの頃から。掘っ立て小屋のごとき我が家にも、山岡荘八『徳川家康』全26巻が棚に並べられていた。日本人は、ひたすら過去を振り返っていたのだ。
山本氏の本は、読むのに相応しい年齢があるような気がしていた。ツボを押さえた職人肌のストーリーテラーという印象。しかし当方の高校・大学時代、周りには大江健三郎、安部公房、高橋和巳、サルトル、カミュ、ドストエフスキーなどを愛読する学生が多く、この練達な作家に熱心な者は少数派だったと思う。
ところで、評論家かどなたかがすでに指摘しているかもしれないが、『樅ノ木〜』にはマイケル・チミノ監督の映画『ディア・ハンター』(1978)に酷似している箇所がある。
映画の方は、ロバート・デ・ニーロが鹿猟で大鹿を仕留めそこねるシーン。小説の方は、第二部の「くびじろ」の章になるが、弓弦(ゆみづる)が切れて甲斐が「くびじろ(大鹿の呼称)」猟に失敗する場面である。鉄砲と弓矢の違いはあるものの、とても似ているのである。
故・チミノ氏は1939年生まれだから、小説刊行時の1958年には20歳少し前。また、ドラマ放送の1970年には31歳になっているから、20歳代の10年間に、日米間という太平洋を挟む距離障壁はあるといえ、『樅ノ木〜』情報に文字または映像・音声を介して接した可能性がありはしないか。
それはともかく、容易に看取できるのは文学と映像の両氏が「生」と「死」の捉え方に力点を置いていることである。
甲斐は鹿猟を趣味としている。長年追い求めていた「くびじろ」を、もう少しのところで仕留めることに失敗する。それを悔やむ。
「もっとそばへやれ」
甲斐はそこへと、手で場所を示した。与五兵衛は云われるとおりにした。大鹿の死躰のそばへおちつくと、甲斐は「くびじろ」といって、その大鹿の頸へ手をやった。
「おれの手でやりたかった」と甲斐は云った。
(中略)
「おまえはとしよりになった、まもなく若い鹿に追いやられるか、どこかのつまらない猟師に殺されるかするだろう、おれはそうさせたくなかった」
山本氏は、甲斐に「死」のあり方を語らせている。若い者に追いやられるか、つまらない猟師の餌食になるくらいなら、甲斐自らが殺めた方がましだと考えている。大鹿はの甲斐の反映である。みじめな幕引きは見たくない、自分の始末は自分でしたい、と心情を吐露する。
上記悔恨の場面で有終の美への志向しながら、物語中盤になると甲斐は、主君のために死んだ塩沢丹三郎について一見矛盾するような言葉を吐く。
丹三郎は「自分の死は御役に立つであろう」と云った。主人のために身命を惜しまないのは侍の本分ではあるが、誰にでもそう容易に実践できることではない。甲斐は丹三郎を知っているし、彼の性質としてそういうことを口に出して云う以上、そのときが来れば死を怖れないだろう、ということもわかっていた。
―だがおれは好まない。
国のために、藩のため主人のため、また愛する者のために、自からすすんで死ぬ、ということは、侍の道徳としてだけつくられたものではなく、人間感情のもっとも純粋な燃焼の一つとして存在して来たし、今後も存在することだろう。―だがおれは好まない、甲斐はそっと頭を振った。
たとえそれに意味があったとしても、できることなら「死」は避けるほうがいい。そういう死には犠牲の壮烈と美しさがあるかもしれないが、それでもなお、生きぬいてゆくことには、はるかに及ばないだろう。
丹三郎の「死」を否定はしないが、「好まない」のである。
悪役として描かれる伊達兵部宗勝の暗殺に失敗し、捕縛・斬首された伊藤七十郎の「死」についても、甲斐は苦渋に満ちた様子でこう述べる。
「丹三郎はまずともかく、七十郎の死は誤っている、彼は侍の意地とか面目とか、本分などということで自分を唆(け)しかけた」甲斐はそう云いかけて、いかにもにがにがしげに顔をしかめた。そういうことを口にするのが、自分で恥ずかしく不愉快なのであろう、顔をしかめながら、いやな物でも吐き出すような調子で続けた、「―意地や面目を立てとおすことはいさましい、人の眼にも壮烈に見えるだろう、しかし、侍の本分というものは堪忍や辛抱の中にある、生きられる限り生きて御奉公をすることだ、これは侍に限らない、およそ人間の生きかたとはそういうものだ、いつの世でも、しんじつ国家を支え護立(もりた)てているのは、こういう堪忍や辛抱、―人の眼につかず名もあらわれないところに働いている力なのだ」
七十郎の「死」は自己中心的だと言いたいのだろう。しかし、利他・利己の違いがあるとはいえ、「死」は避ける方がいい、生きられるだけ生きた方がいい、という部分は同じである。
ところで丹三郎について述べた上記引用で、甲斐は「愛する者のために」死ぬことも「好まない」と言う。ここはちょっと引っ掛かった。第三部で、甲斐はこんな考えを示している。
人は誰でも、他人に理解されないものを持っている。もっとはっきり云えば、人間は決して他の人間に理解されることはないのだ。親と子、良人(おっと)と妻、どんなに親しい友達にでも、―人間はつねに独りだ。
けっこうなニヒリズムではないか。
山本氏は、空襲が激しさを増す昭和19年(1944年)12月19日の日記に、こうも書き記している。
生死の観念はまだ安定しない。つまり「死んでもよい」という覚悟がきまらないのである。「妻子のために生き残りたい」という感じだけは薄らいできた、是が最も独善的な欲望だったのである。先人たちが事を成す始めに「妻子を棄て」たことは、この独善感を克服するためだったのである、つき詰めたところ、妻は妻、子は子である、己の生死とは本来なんの関わりもないのだ。生死にかかわらずそれが妻子に及ぼすところは末節瑣事に属し、本質的には何ものをも与奪しないのである。 ―人間の為すところは常に外界に向かってであり、妻子のためにではない、そう思うのは毎も己の気力の弱っているときに限る。仏徒が俗縁を断つのも亦この意味から出たものと信じられる。肉親と離脱することを以て大悟への出発点とした、心理的解法は的確である。つまり妻子を否定することは「生命存続」の否定である、これが可能なら生死煩悩を脱却することは容易であろうから ― 。
「妻子を否定すること」が生死煩悩を脱却できるか否かの分かれ目である。こうは書くものの、上記日記の冒頭にある如く氏の生死に関する観念は安定しないのである。詰まるところ、「死んでもよい」という覚悟は定まらないのである。
戦中日記の昭和20年(1945)年2月3日には、日本人が持つ「死を『死』とせざる」観念について、次のように綴っている。
日本人にとって死が「滅亡」でないことは尊い、極楽とか地獄とか、或は天国などという概念を、すなおに受容れる者もあるが、概念として「そうか」と思うだけで、仏教国民や基督教国民の如く骨肉とは成らない、死に対する考方はかれらと根本的に違う、理論的に自覚するせぬの差はあっても、「死が祖先の系列に入る」ことだという信念は血となって全日本人を繋いでいる。日本人にとって死が恐怖(異邦人のようには)でないのは、この一点が先天的信念となっているからだ。 ― 或はこれを蒙昧とか云うかも知れない、しかし「生命」に就て科学的に検討し来った異邦人が、今なお宗教に頼らざるを得ないのはどうか。現世を「苦の世界」とし、死後に「安楽」ありとする思想は外来宗教の移入したもので、本来の日本人はそういう区別をもっていなかった。寧ろ現世と来世は相交流するものとさえ考えられていた。これは死に依って「氏族の系列に入る」つまり生命の一つの飛躍だという信念から発したものと解していいだろう。「不惜身命」は生活から生れたものではなく、日本人の生命がもっているものだ、死を「死」とせざる者でなくてはこの生き方はわからない、日本が万邦無比であることの根本はここにあるのだ。 ―まことに日本人の死に対する考え方は尊いものである。
一種、「死」の概念の否定と言うべきか、あるいは「死」に対する恐怖からの逃避と言うべきか。
戦火の中、ヒロポンを打ちながら執筆を続ける文士の姿が目に浮かぶ。この年5月、38歳で亡くなる妻の体調にも不吉な兆候が見え始めている時期のことである。
これらは戦中の心境である。戦後10年以上を経て世に出された『樅ノ木〜』では、上記の第二部(新潮文庫中巻161〜162頁)において甲斐に語らせたように、少なくとも国家のためとか、所属する組織ためとかいう意識は薄らいでいる。それでも、「死」からは、そして「死」の恐怖からは逃れられないのである。
では、どうすれば「死」を超越できるのか。
山本氏や甲斐の文脈では、「愛する者」を捨てることが関門である。それは『樅ノ木〜』の最期を読んでも伝わって来る。
『樅ノ木〜』の感想が長くなってしまった。映画『ディア・ハンター』についてはNoteに別稿があるので、そちらもご覧いただければありがたい。その駄文では確か、映画は「なぜ鹿狩りなのだろうか?」という疑問を呈した。この点は未だに腑に落ちていないが、『樅ノ木〜』を読んで、同じく戦争を背景にした『ディア・ハンター』が、これまた同様に「鹿狩り」といったイメージをもって、「死」そして「生」の感覚に迫ろうとしたことに偶然とは言えぬものを感じた。
祖国アメリカの山脈で鹿を逃したロバート・デ・ニーロ。彼は、ヴェトナムの戦争でゲリラに捕らえられても、友・クリストファー・ウォーケンの頽廃した姿を見ても、自らの「生」をあきらめない。「死」と隣り合わせだから生きたいと思う人間がいる。他方で死にたいと思う人間もいる。小説にも映画にも、すぐそばの「死」を通して自分自身の「生」の感覚をつかもうともがく人間像が描かれている。映画に出てくるロシアン・ルーレットは「死」を運に任せる手段である。これは小説の方の結末にも似ている。クリストファー・ウォーケンは、恐怖を乗り超える営みに埋没してしまった。デ・ニーロは友の死から何をつかんだのか?山本氏は、戦中・戦後を通じて、「死」の超越について何を感得したのであろうか?
文章でも映像でも、「愛する者たち」は置き去りにされた。非情な現実である。しかしながら、「死」の悲しみや本質はここにあるような気がする。
『樅ノ木〜』の読みどころは「生」や「死」だけではない。人間関係、派閥抗争、夫婦・家族、男女愛など多様な要素が盛り込んである。特に、女性の描き分け方がクリアでイメージを捉えやすい。全体を見渡すと細部が詰められていないところにも気づくが、そうした欠点をものともせず、最初から最期まで力強い筆致でグイグイ引っ張っていく紛れもない傑作である。
なお、山本氏が横浜磯子で散歩を楽しんだコースは、当方が1964年から1968年まで幼年時代を過ごした所に近いようだ。下校途中の坂下公園あたりで、着物姿の山本氏の視野に、背丈1メートルちょっとの当方が駆け回る姿が入っていたかもしれない。
