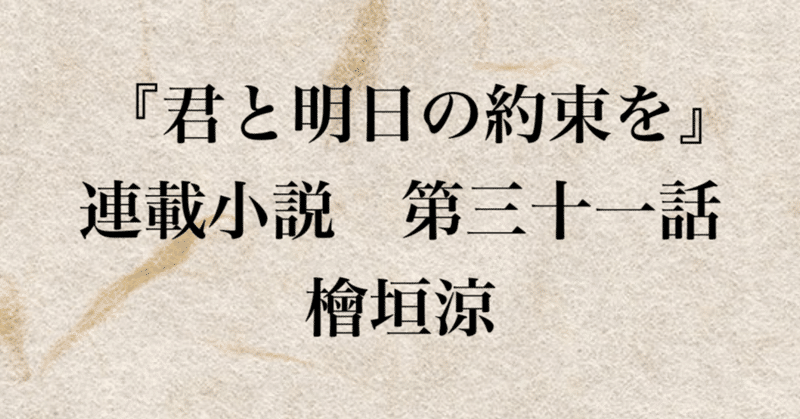
『君と明日の約束を』 連載小説 第三十一話 檜垣涼
檜垣涼(ひがきりょう)と申します。
小説を書いています。
よろしくお願いします!
毎日一話分ずつ、長編恋愛小説の連載を投稿しています💠
最後までいくと文庫本一冊分くらいになりますが、1つの投稿は数分でさくっと読めるようになっているので、よければ覗いてみてください!
一つ前のお話はこちらから読めます↓
午後の授業でも日織の様子は変わらなかった。六時間目に至っては、他の生徒も眠気を誘う地理の先生の影響か、慎一の二つ前の席でセーターに頭を預けたまま一時間を終えた。慎一は話を聞くふりをしながら問題集を解いていた。
その日の放課後、彼女から週末のバイトの確認をされ、二回目の手伝いが決定した。
朝家を出た時から降っていた雨がまだ止まないのだろう。キッチンの奥の曇りガラスはうすネズミ色に染まっていた。雨の日なのに忙しいキッチンの仕事を憂鬱な気分でこなし、注文が落ち着いた小休止、どうやら同じ気分で働いていた葵さんに話しかけられた。
「なんでこんなに人来るかな」
葵さんというのは同じアルバイトで僕より三つ年上の女子大生だ。と言ってもバイト自体は僕と同じ時期に始めたので、やっている仕事はだいたい同じようなものだった。
彼女とはシフト時間もよくかぶっていることもあって、休憩時間やご飯を食べている時によく話をしていた。
「雨の日くらい家でくつろいでくれたら良いのにね」と、オーナーかお客さんに聞かれてしまったら確実に反感を買うだろうこと――ただそれは今日のシフトに入っているバイト全員の代弁だけど――を言う。
僕は反感を買いたくないので相槌で済ます。
「つれないなあ」
彼女は鮮やかなピンク色の唇を歪ませる。
ここ一年ちょっとで彼女の性格はよくわかっていた。思ったことは遠慮せずに話すが、それが良いキャラとして働いていることと、気が向いたら年下をからかいたがること。
「私だったらこんな天気なら絶対大学休むけどなあ」
「それは葵さんだけです」
「そんなことないって。大学生なんてみんなそう。私だって高校の時は皆勤取ってたくらいなんだから」
「えっ、そうなんですか」
「本気で驚かないでよ! そうだよ。大学に入った時は頑張ろうとか思ってたけど、まあ三ヶ月経ったら面倒になるよね。ちゃんと全部の授業行ってるのは何か目標がある子くらいなんじゃないかな? 私はそういうのは無い。まあ、私の入っている学科が緩いだけなのかもしれないけど」
以前葵さんの所属している学科の話をちょっとだけ聞いたけど、楽ということしか分からなかったのであまり深くは聞かない。
「小坂くんも大学に入ったら分かるよこの気持ち」
「そんなこと……」
沈黙になりそうだったのを、進路に悩んでいる感じを葵さんに悟らせないために、僕はほぼ無意識に言葉を続ける。
「ないですよ、多分」
最後に「多分」と付け足すことで言葉の間にできた変な間を薄められたと思う。
幸い、追加の注文が一気に流れ込んできたので、そこで会話が途切れてくれた。
ーー第三十二話につづく
【2019年】恋愛小説、青春小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
