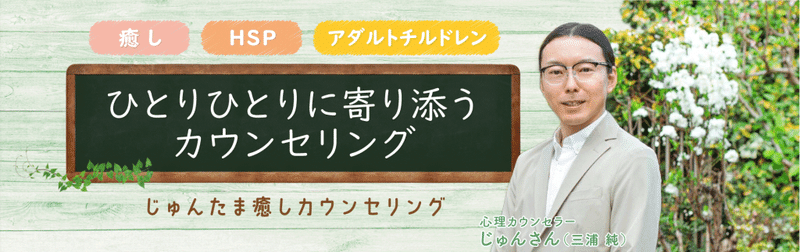快・痛みの原則
こんにちは心理カウンセラーのじゅんさんです。
いつも記事を読んでくださりありがとうございます(^-^)
今回は【快・痛みの原則】についてお話しさせていただきます。
1.NLPとは
NLPは1970年代にアメリカで開発された心理学的な手法です。
元々は創始者であるリチャード・バンドラーとジョン・グリンダーの二人がその当時天才と言われた3人のセラピストの研究からスタートしたと言われています。
彼ら3人の天才セラピスト達は並のセラピスト達が何年もかかって治療することができなかったクライアントすら短期間に治療したと言われています。
これは言語が人間にどんな影響を与えるかについての一連の研究からスタートしています。
NLP とは(ニューロ・リングウィスティック・プログラミング)の頭文字をとったもので、日本語では神経言語プログラミングと言われています。
N…神経を表していて五感などと捉えることが出来ます
L…言葉を指しています
P…プログラミングを意味しています
NLPは五感と言葉が脳のプログラムを作ったり起動させたりしているという風に考えることができます。
これは NLP の発祥の地アメリカでは脳の取扱説明書などと言われています
NLPは、脳に関する実践的な研究がされていて、応用範囲は人間の営みの大半に関わっていると考えることができます。
2.快・痛みの原則
人の脳は快を求めて痛みを避ける。
このことを【快・痛みの原則】と言っています。
今回は【快・痛みの原則】を三つに分けてお話ししていきたいと思います。
【快・痛みの原則】
①脳は快を求める時に最大限に働いてくれる
②脳は痛みを避ける時に最大限に働いてくれる
③人間は安全安心を求めている。
①【脳は快を求める時に最大限に働いてくれる】
「脳は快を求める時に最大限に働いてくれる」についてお話ししていきたいと思います。
ここで言う【快を求める】とはどんなことでしょうか?
「喜びを感じたい」
「楽しい時間を過ごしたい」
「気分転換をしたい」
「優しい気持ちでいたい」
こんな思考に繋がる行動を求めている状態が「快を求めている」という思考です。
ただ、人によって「快」というのはそれぞれ違いはありますよね。
今回は一部分を抜粋して、普段私が感じている「快」を中心にお話させていただくのでそのように読んでいただけるとうれしいです。
現在の私の生活状況で例えてお話していきますね。
私はステイホームの期間中、家の中で過ごす時間が増えました。
「外に出て気分転換したい」
「どこか遠くに外出してたい」
「自然に触れて癒されたい」
とよく考えるようになっていました。
これが私の今求めてる「快」です。

そこで私はこのステイホームの期間中に取り組んでいることが一つあります。
それは「1日1回ベランダに出て日光浴をする」ということです。
これは現在続けて2週間以上経った状態です。
実際に行うと、毎日継続するのはけっこう大変なんですね。
実行してみて気付く事って多いですよね。
【1日1回ベランダに出る】というこの行動は私が「快」を感じたいと思ったことから行動したことと考えることができます。
「外に出て気分転換したい」
「外出して外の自然に触れたい」
これらは私の本来求めている「快」の代替案ですよね。
私の脳は本来得れる「快」を得れなくて「不快」を感じなくて良いように「ベランダに出て快を感じようと働いている」とすることができます。
よって1日1回ベランダに出ることは、私にとっての「快」という思考と行動と私の脳は理解しているんですね。

またこの「快」「不快」はまったく同じ思考と行動でも、人によって感じ方はそれぞれ違いはあります。
「家の中で過ごす」という事に関して焦点を当てて少しお話ししていきたいと思います。
この「家の中で過ごす」という一つの、思考と行動をとっても。
これを「不快と感じる」人もいれば、家の中で過ごすことが「快」として感じている人もいますよね。
全く同じ時間、同じ場所で過ごしたとしても「不快」と「快」が存在しているということなんですよね。
これはとても大事な事だなって、私自身思っているんですね。
人によって瞬間瞬間に過ごす時間の感じ方や捉え方は人それぞれ違います。
「自由」だということなんですね。
そしてもう一つ。
「映画館で映画を見る」というこの思考と行動を例に挙げてお話させていただきます。
例えば、AさんとBさんがいて、同じ映画館で同じ時間を過ごしていたとイメージしてみてください。
Aさん…この薄暗い中で大きいスクリーンで映画を見れることが嬉しいし、 これが私の月一回の楽しみなんだなって思ってる人はこれはこの人にとって映画を観るは「快」ですよね。
Bさん… 映画館は暗くて。 怖いし隣に見ず知らずの人が近くにいて気になってしまって、そして息苦しい感じもする。こんな空間に二時間もいるなんてって思ってる人にとっては「不快」ですよね 。
このように「私」と「あなた」と別の人が同じ空間や時間を過ごしていたとしても、その後脳が判断する「快」「不快」はその人によって大分違いが出てきてますよね。
多分このような違いについて、普段の生活の中で皆さんもその違いに気づかれる瞬間があると思います。
これが一つ目の「脳は快を求める時に最大限に働いてくれる」というお話です。

②【脳は痛みを避けるときに最大限に働いてくれる】
そして2つ目の「脳は痛みを避けるときに最大限に働いてくれる」についてお話ししていきたいと思います。
ここでの「痛み」とは次のようなことを指します。
「悲しみを感じたくないなぁ」
「苦痛を感じたくないぁ」
「不快な思いをしたくないぁ」
「嫌な自分になりたくないぁ」
きっとこのような痛みを避けたいと感じる方が多いと思います。
ただ、この「痛み」の体験も人それぞれ感じる度合いや部分が違います。
痛みも人により、たくさんありますが、今回は私の体験を例にして、お話させていただきますね。
現在私はステイホームの期間があることによって、人と話したりする機会が減りました。
そのことで具体的に何が減ったのかというと、今まで私は朝コンビニに行ってレジにいる優しい店員さんに次のように声をかけてもらっていました。
「行ってらっしゃいませ」
と笑顔で毎日声をかけてもらっていました。
これはあたり前の習慣となっていたんですが、突然一切無くなったんですね。
またいつも、朝すれ違う途中に出会う犬を連れた散歩をされている方がいるんですけども、その方と犬とすれ違うときに交わしていた。
「おはようございます」
とかちょっとした挨拶や、犬と触れ合う機会が無くなりました。
このことによって私はさまざまなことを感じていきます。
寂しさ、人と関わりたいなどの欲求が出てきます。それが満たされないことでさらに次のような「痛み」を感じることになります。
「寂しい」
「悲しい」
「孤独を感じる」
これらを脳が認識して、これは私にとっての「不快」や「痛み」というように私の脳は認識しました。
私の脳はその不快や痛みを避けるためにどんな思考と行動をしたかといいますと次のような行動で不快や痛みを感じないように行動しました。
旧友とメールをする
noteに記事を書く
ラジオアプリのstand.fmで話をする
このように電話やSNSで人と繋がる時間が増えることになりました。

私にとっての何気ない朝のコンビニの店員さんの「いってらっしゃいませ」の声かけとか。
犬と散歩する近所の方との朝の「おはようございます」の挨拶とか。
当たり前となっていた、ちょっとした人や動物とのコミュニケーションです。
これは私にとっての「快」だったんですよね。
この様に私自身は普段気付いていないのですが、脳は「快」として捉えていたんですね。
なので私は、そういった快を失ってしまったことで、私の脳は不快に感じないために新しいことをしたりとか、このようにnoteに記事をきてみたり、ラジオで皆さんに語りかけ、聴いていただいたりしています。
もちろんこれらの目的は「快」を得るためだけではないですが。
脳の「快・痛みの原則」のお話に当てはめた場合はそのように私の行動は説明できますよね。
また最近ズーム飲み会とか流行っていますよね 。
これもまさに皆さんが「快」を失った方が多くて、痛みをさけることやそれを補う行動としてオンラインへの関心も高まっていきました。
これが2番目の【脳は痛みを避ける時に最大限に働いてくれる】というお話でした。

③【人間は安全安心を求めている】
「人間は安全安心を求めている」についてお話ししていきたいと思います 。
人間は危険を避けて、安全な場所、空間にいることを常に求めていますよね。
これは生存本能が私たちに備わっているので、私達人間は常に安全安心を求めています。
ここで一つ質問をさせていただきますね。
「あなたにとっての安全安心な場所とはどこでしょうか?」
そう。きっと次のような答えをイメージされた方も多いかと思います。
「家の中」
「自然の環境の中」
「誰もいない自分の部屋」
これも人それぞれの安全安心な場所があると思うんですよね。
ここで私の小さい時の体験をお話ししていきたいと思います。
私は小さい時に昔、東京タワーに行った事があるんですね。私のおばあちゃんとですね。
その際に上の階の方に展望台が設置された場所があった記憶があるんですね。
最近行ってないので今はどうなっているのかちょっとわからないですが。
東京タワーの上から地上を眺められるようになっている場所。
透明のガラス貼りの床があったんですよね。
私は興味本位を抱いてそのガラス貼りの床に立ってみたんですよね。
その時の感覚を生々しく覚えているんですね。
足がすくんで来て、膀胱あたりが縮み混んでくるような。
そんな感覚だったと思います。
そして私は次のように頭の中で声が聴こえます。
「危ないよ!落ちてしまうよ!」
恐怖を感じた私は、とっさにそのガラス貼りの床から離れておばあちゃんの手を握った思い出があります。
子供だった私にとっての不快や避ける痛みとして反応していました。
この私の思い出の世界には「危険を感じる場所」「安全安心を感じる場所」の両方が出てきますよね。
まず、「危険を感じた場所」は「ガラス貼りの床」ですよね。
そして「安全安心を感じた場所」はおばあちゃんの手を握っている瞬間ですよね。
またここではおばあちゃんの傍にいることで、「物理的な安全な場所」「心理的な安全、安心の場所」を確保できていました。
おばあちゃんの手の温もりを身体感覚で感じて、その行動から私の脳は「ここは安全・安心な場所だ」と感じて記憶していきます。
「物理的な安全な安心な場所」=「精神的な安全安心な場所」でもあります。
これが三つ目の【人間は安全安心を求める】というお話でした。
同じ出来事でも、それを体験する人によって。
それを。
【快】に結びつけて考えるか。
【痛み】に結びつけて考えるか。
その事で脳の働く機能の能力の度合いが変わってきます。
今回は脳の【快・痛みの原則】についてお話しさせていただきました。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました
それではまたお逢いしましょう(^-^)
私のNLPの入門におすすめな本です↓
3.じゅんさんのSNSやカウンセリングについて
◆心理カウンセリングをしています。お問い合わせ、お申し込みはホームページをご覧ください↓
◆Twitter・YouTube・ラジオ等でHSPについて配信しています↓
人に対して働く敏感(HSP)第六感(エンパス)とか無意識の部分。相手の個性にいち早く察知して慰めり。治そうとしたり。 ドキドキしたり。ハラハラしたり。そんな人のことかもしれませんよね。人は外部には敏感だけど自分には敏感ではないときがあります。アンテナの向きを調整することが大切なんですね。
— じゅんさん🌼心理カウンセラー (@ch87619600) June 5, 2020
いつもありがとうございます(^-^)いただいたサポートは記事を更新していく励みとなります。これからも記事を投稿していきますので読んでもらえると嬉しいです◎